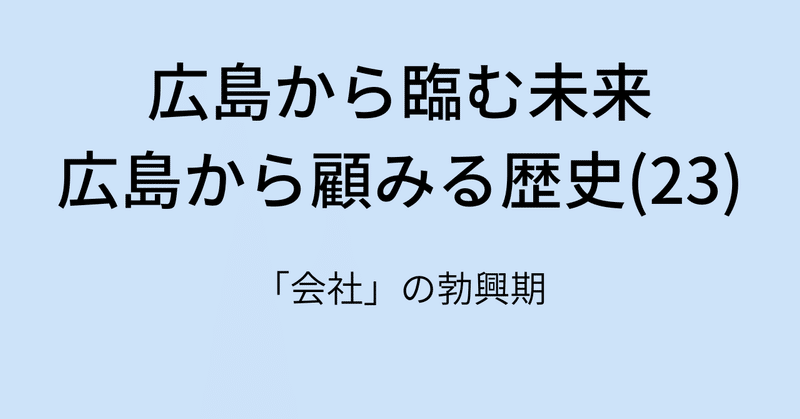
広島から臨む未来、広島から顧みる歴史(23)
「会社」の勃興期
引き続き『日本会社立法の歴史的展開』を見てゆきたい。第1章Ⅳ「会社」の流行 から要約と私見の続きを試みたい。
数字から見る第一次会社勃興時代
明治十(1877)年の西南戦争鎮定後に会社を名乗る企業が急増し、第一次の会社勃興時代が到来したという。掲載された表から見るに、まず、日本銀行条例が制定され、紙幣発行額がピークに達していたと見られる明治十五(1882)年に会社数は3655、見た目ではあるが金融業を除いても3000くらいの会社があったようだ。その後、紙幣整理に伴って、銀行類似会社は増加傾向を見せる中、一般の会社は急減した。明治十八(1885)年政府紙幣兌換の実施が布告されると、銀行類似会社などの金融会社はほぼ頭打ちになる一方で、一般の会社が少しずつ増加を始め、明治二十二(1889)年段階で会社総数は4456、金融業を除いても3500程度はありそうな、そのピークを迎えた。これは、アメリカが独立戦争後半世紀強で設立された金融業を含む会社数4000弱や、ドイツの1889年段階での概算2855よりも、数の上ではかなり優勢になっているとの指摘がなされているが、半世紀前のアメリカの企業数や、プロイセンがほとんどを占めていると見られるドイツの概算と比較するのはフェアとは言い難いようにも感じる。そして、後にも出てくる通り、明治十一年までは届出主義、その後も個人事業の会社組織化を含めた数字であり、実際的な意味があるようなものではなかったということは指摘されないといけないのであろう。
主務省がコロコロ変わる会社の管理
さて、明治政府による会社政策は、明治四(1871)年に大蔵省が『會社辨』と『立會略則』を官版として出版したことで初めて方向が示されたという。その後、廃藩置県後の縣治条例で、「諸会社ヲ許ス事」を、別に成規がない限り、地方官が処分の法案を作り、主務省に稟議し、許可の後施行すべき事項に掲げたという。主務省は、最初は全て大蔵省であるのが前提とされていたようだが、明治六年の政変で西郷派から実権を奪い取った大久保利通が、内務省を新設して殖産興業の拠点としたため、明治七(1874)年一月七日、「金券發行會社ヲ除ク外諸會社設立ノ准允」を与える権限は内務省に移されたという。明治九(1876)年には工部省が一定の事業につき主務省と認められ、内務省に残った権限については大久保の死後明治十一(1878)年再び大蔵省に移管され、明治十四(1881)年には新設の農商務省へ移管されたという。この段階では、主務省があるとは言え、地方官に主導権のある分権型の会社管理であったと言えそう。
内務省の動き
明治七(1874)年四月に会社政策に大きな転機があったという。この年は内務卿が大久保、木戸、大久保、伊藤、大久保と目まぐるしく変わった時期であり、四月は月末二十七日に木戸から大久保に変わっているので、この転機というのが一体何を意味しているのか、ということを追う必要がある。とにかくそれ以後内務省も大蔵省も、「人民相對ニ任セ候儀ト可心得候事」等と司令するようになったという。会社数が増えるに伴い、種々の不都合が生じてきたため、早急に会社条例を設けるものとし、それまでの経過措置としての指令だという。ただ、翌月には、これまで許可したようなものについては従前と同様に許可することが、内務省から太政官への伺いにより確認されているという。これはおそらく木戸が内務卿の時に前の指令が出て、大久保に変わって従前と同様、というようになったのだと思われる。この背景を、少し回り道しながら掘り下げてみたい。
官庁による思惑の違い
まず各省の会社法に対するアプローチであるが、内務省がイギリス法等を参考に、かつ相当に統制的な内容の会社条例を立案したのに対し、司法省は大陸法的な民法典・商法典編纂事業を主導権を握って進めようとし、会社法のみを単行法として制定することに抵抗、大蔵省は、せめて銀行に関してだけでも基準を示して監督行政に当たりたいと願っても、会社に関する法制が整うまで待つようにと言われ、そのほか様々な組織が関わることで立法が進まなかったためだという。
通商会社と為替会社の整理
このような状況で、会社法の制定を待つ状況になっていたようだが、それ以前の会社形態として存在した通商会社と為替会社は一体どうなったのだろうか。まず、それらを管轄した通商司に先立って置かれた、太政官札を用いた貸付のために設置された商法司について見てみたい。商法司は藩の専売体制の延長線上にあるような商法会所を通じた、いわば官による事業推進のような性質を持っていたようだ。
それに対して通商司は、藩の経済活動単位としての機能を奪って、商人たちの結社に担わせようとしたという。にもかかわらず、通商司は中央政府の後押しで会社の管理を行おうとしたので、最終的には大蔵省が介入を差し控える方針をとることとなった。
その後、明治四年の廃藩置県、明治五年の国立銀行条例の公布を受けて、藩の持っていた通商権を引き継いだ通商会社、そしてそこに貸付を行っていた為替会社の整理が必要になってきた。特に為替会社は、国立銀行条例の制定によって紙幣金券運用手形類の発行が許されなくなり、既発の金券等を直ちに金兌換で回収するように言われると、事業どころではなく、その整理の際に最終的な責任がどこへ行くのかが問題となる。
会社整理の混乱
国立銀行条例公布後、明けて明治六年になると、その問題が表面化しだした。これは、前回見た太政官札をどう処理するのかという話にも絡んで、大蔵省は為替会社の国立銀行への転業を期待してそのための条文も条例の中に設けたが、横浜為替会社以外はそれが叶わず、そのほかの為替会社の中でも身元金の損失にとどまった大津と敦賀以外のものは損失処理の必要が出てきた。政府から処理を委任された井上馨大蔵大輔は財政を注ぎ込んで会社処分を進めることにしたという。これは、責任についての規定が定められていなかった上に、会社という仕組みの紹介をした福沢諭吉の『西洋事情』に、手形を買えば利息と配当が得られ、官許を受けた商社は分散できず、もしそうする時には手形代金を政府が償う、という内容が書かれていたことに起因するようだ。
これはおそらく、
イギリス議会は、1858年8月2日、インド統治改善法を可決し、東インド会社が保有する全ての権限をイギリス国王に委譲させた。250年以上にわたり、活動を展開したイギリス東インド会社の歴史はこの時点で終わりを告げた。
だが、東インド会社はその後、1874年まで、小さいながらも会社組織は継続した。理由は、イギリス政府が株主に対して、1874年までの配当の支払いを約束していたからであり、残務整理が終了した1874年1月1日、正式に会社の歴史の幕を下ろした。
イギリス東インド会社のこの解散形態を見ての記述だと思われる。東インド会社が配当以外にも利子も約束していたかは寡聞にして知らないが、仮にそうであったとしても少なくとも有限責任についての記載があっても然るべきだが、それがないという時点で、福沢は株式の仕組みについては誤解していたと言えるのではないか。その後に手形を元金を払って買い戻しができ、それによって商売の株は全く商社の有になるとしていることから、融資と株式の区別があまりついていなかったか、あるいは日本的な座の株を意識して、それを複数で始めて最終的に自分のものにする手法か、とにかく独自の解釈が施されているようだ。
会社整理に伴う内務省を舞台にした暗闘
このような解釈が広がっていた中で、為替会社を所管していた大蔵省の大蔵卿大久保利通、大蔵大輔井上馨の体制下、とは言っても大久保は外遊中だったので、事実上大蔵大輔井上馨は独断で、特種の恩典を持って為替会社の救済を決めたようだ。井上は他にもいくつもの怪しい案件を抱えており、それに対して司法卿江藤新平は井上の関わったさまざまな事件を厳しく追求し、井上を辞任に追い込んだ。その後征韓論争を軸に政府は真っ二つに割れ、そして九月に岩倉使節団は帰国したものの、西郷らの辞任は避けられず、明治六年の政変につながって、それとともに江藤も下野した。大久保はその井上の政策から、通商会社だけでも引き離すということを大義名分として新設の内務省に移り、そこで会社政策を主導しようとしたのだと見られる。一方為替会社を所管する大蔵卿は政変後に大隈重信が就任した。一方大蔵省をさった井上馨は、大蔵省に誘った益田孝と一緒に、鉱山事業を主とし内外交易も行う会社として、翌明治七年(1874年)一月に商人の岡田平蔵らと共に岡田組を設立した。そんな動きの中、政変後帰郷した江藤は、二月に佐賀の乱を起こすが、その乱が起きる二日前に大久保は内務卿を木戸に譲り、佐賀の乱の処理に自ら赴き、これを鎮圧した。江藤は、弁論や釈明の機会も十分に与えないまま死刑を宣告され、その首はさらされるという、明治維新においても例を聞かない厳しい扱いを受けた。
なお、広島に関して言えば、明治六年一月に徴兵令が出て、その前日に広島に鎮台ができるという、軍都広島への第一歩を刻んだ時期となる。軍都でありながら、徴兵を嫌った広島の風土というのも大変興味深いが、今は話がずれてしまうので触れられない。ただ、この佐賀の乱は、徴兵された兵の腕試しのような側面があったと考えられ、その関わりは無視できない。
一方で、井上らとともに岡田組を立ち上げた岡田は設立間もなく銀座で変死し、井上と益田らは鉱山事業と岡田の出資分を岡田家に返し、残った商社機能をもって、同年三月に先収会社を発足させた。こういった流れの中で、この先収会社が勝手に認められるのは問題だとして大久保の政策をひっくり返したのが、四月の会社設立を人民相対に任せるとの指令だと見られ、そう考えるとそれはおそらく大久保に代わって内務卿になった木戸孝允のもとで出ただろうということは述べた。これは、費やされた整理費用のことを考えれば、せめて有限責任を定めた会社法がなければ、政府認可などはできようはずもない、ということだと考えられ、それは当然の立場であろう。
それが大久保派の反撃を喰らい、内務卿が再び大久保に戻るということになったと見られ、そして内務省から太政官への伺いで、これまで許可したような会社は従前と同様に許可するということが確認されたのだ。
会社の責任問題の推移
大蔵卿の大隈は七年にわたる長期在任となったが、その間明治九(1876)年、私立銀行第一号として三井銀行の創立が許された。もっとも、これは人民相対を以て営業、となり、さらに株主は無限責任を負うというものであった。これは、先の大蔵大輔井上が作った貿易商社先収会社を多額の負債と益田孝らの旧士族付で引き取ることの対価であったと言えるのかもしれない。これが三井物産となるが、それは無資本で上の三井銀行からの五万円の借越契約を元手に営業を始めたのだという。これによって為替会社の整理を一点に集め、そこへの融資を行うために三井銀行の創設を許したのだと言えそうだ。つまり、この相対とは三井銀行と三井物産との相対、ということを意味するのだと言えそう。
株式会社への展開
三井銀行を作る時、三井の三野村は株式会社の設立を願い出ていたが、それはどうも、株式市場を作ることを前提に動いていたようだ。
1874年(明治7年)10月13日 – 株式取引条例(太政官布告第107号)制定。
1878年(明治11年)
1月17日 - 東京株式取引所創立準備の為め第1回株式集会を開催し、東京府下第一大区十五小区兜町6番地を本所の位置と定め、同地の第一国立銀行の所有に係る家屋を購入しこれを営業所に充てるべきことと可決。
1月19日 - 当事者間で上記家屋の売買契約成立(以て、増築と修理を施した)。
5月4日 - 根拠法である株式取引所条例(太政官布告第8号)が制定。
5月10日 - 東京府経由で、渋沢栄一、木村正幹、益田孝、福地源一郎、三井武之助、三井養之助、三野村利助、深川亮蔵、小室信夫、小松彰、渋沢喜作を発起人とし、東京株式取引所の設立を出願。
5月15日 - 大蔵卿大隈重信から免許を受け、正式に成立。
6月1日 - 14時、仲買人76名、取引所職員14名によって営業が開始。
6月3日 - 定期取引、現場取引の売買が開始される。
7月15日 - 日本初の上場株式として東京株式取引所の売買が開始される。
9月 - 第一国立銀行(現みずほ銀行・旧第一勧業銀行)の株式が上場。
1878年(明治11年)5月22日に開業した時点において、上場銘柄 は旧公債(無利子)、新公債(年4%)、秩禄公債(年8%)の3種のみであり、上場企業は0であった。同年内には、金禄公債、起業公債が上場し、さらに初の上場企業として東京株式取引所が上場、東京蠣殻町米商会所、東京兜町米商会所、第一国立銀行が続いたが、依然として取引の中心は公債であった。また、開業初年に上場した4社は、東京株式取引所自身か設立発起人の渋沢栄一、田中平八が関与する企業であり、その後もしばらく新規上場は低調に推移した。
株式取引条例は、伊藤博文が四ヶ月弱だけ内務卿をしていた時に出されたもので、その前後は大久保利通が勤めていた。上で見た相対での会社承認の指令の後のこれまでに許可したものは従前の通り許可、という話は、内務省から太政官への伺いであり、すなわち大久保が内務卿に戻って会社承認をこれまでの通りにするように、ということを大蔵卿大隈重信の頭越しに太政官の許可を得て、無責任会社の乱立を主導しようとしたのに対し、伊藤が内務卿となって慌てて株式取引条例をまとめることで、株式取引をある場所に定まった取引所で行うことを定め、野放図な株式取引について歯止めをかけたと言える。この条例制定に関わり、株式だけでなく、これを米油相場会所にも適用しようという動きになり、その混乱に乗じて管轄庁が内務省に変わる、ということになったという。その後再び管轄が大蔵省に戻って年が明けての東京株式取引所に関わる動きとなってゆく。
東京株式取引所
その後上記のように明治九年に三井物産と三井銀行ができ、そして明治十一(1874)年の東京株式取引所設立への動きにつながる。五月四日に株式取引条例にかわって株式取引所条例が定められ、そして十四日に大久保利通が殺害されるという事件が起き、翌十五日に大蔵卿大隈重信から免許を受けて、東京株式取引所が正式に発足することになったという。
この混乱についてはさらに整理する必要がありそうだが、いずれにしてもそれで混乱がおさまったわけではなく、株主の責任が有限なのか無限なのかということも定まっておらず、それは会社の創立証書に明記されることになった。こうして一応は株式の取引の形が定まり、会社法制定以前にその実務だけは動き出すことになった。
会社法整備が遅れる一方、実務は先行してゆき、明治十一(1878)年七月二十五日、大久保が死んで二ヶ月後だが、府縣職制が出され、例規のある常務は地方長官の責任で処分し、のちに主務省に報告すれば良いという命令が出た。明治十三(1880)年には東京府が重要事業以外の会社設立は府知事に出願するには及ばず、郡区役所への届出をなせば良いとして会社設立を強く後押しした。中央政府は責任を取りきれない、とばかりに、地方政府に丸投げすることで、会社設立圧力から逃れたのだと言えそう。
この会社勃興期の混乱は、まだまだ整理すべき事項が多くありそうで、実態が明らかになるのにはもう少し時間がかかりそうだ。
誰かが読んで、評価をしてくれた、ということはとても大きな励みになります。サポート、本当にありがとうございます。
