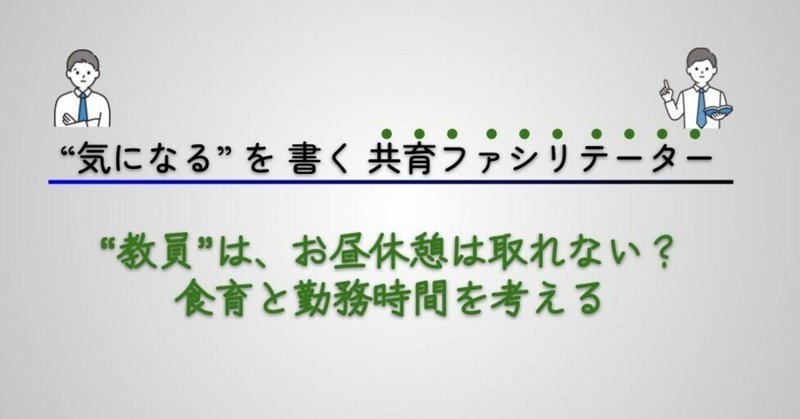
"休憩時間"は何をするか。
労働基準法第34条では
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩が必要とされている。
教職員の"休憩時間"って、難しい…。
ご覧いただき、ありがとうございます。
結構、教員関連のかたから「休憩時間」と「給食指導」について話を聞く機会があったので、ちょっと雑感を。
働き方の中で”休憩時間”の取扱いって本当に難しいですよね。
まず基本からおさらい。
いわゆる労働基準法では、
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
で、これは雇用形態に関わらずです。
つまり、正社員でも契約社員でも、パート・アルバイトでも一律です。
そしてその休憩時間の付与には、3つの原則があります。
・途中付与の原則
…休憩時間を付与するタイミングは労働時間の中である
・一斉付与の原則
…事業の特性による例外、労使協定による例外的な取り扱いを除き、基本 的に一斉単位で付与しなければならない
・自由利用の原則
…休憩時間を自由に利用させなければならない
ということなのです。本当に簡単にまとめると。
『働いている時間内に一斉に休憩時間を取るから、そこで自由に過ごしてね』ということなんです。※でも一斉に休んでしまうと、完全にストップしてしまう事業もあるから、それは例外で!
論点1:教員は、どういった立ち位置になるのか。
さてここからが、ややこしい話。
そして話を混ぜこぜにしない方がいい話。
上述した”労働基準法”が一部適用されないケースが”公務員”
国立学校に置かれる教諭は国家公務員、公立学校に置かれる教諭は地方公務員ですね。ただ私立の学校の場合、これは”公務員”には当てはまりません。
少しかなり外側の方からみた言い方をすれば
「”先生”と呼ばれる人は同じように見えるが、その所属しているところによっては、適用される法律・条例が異なるほど、立ち位置は違う。」
ということなのです。
これ実はその当人も理解していないケースが多い(というか多分教わっていない、教わる暇がない?)
第六条 任命権者は、勤務時間が六時間を超える場合は少なくとも四十五分、八時間を超える場合は少なくとも一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の場合において、任命権者は、第三条第二項に規定する職員(フレックスタイム制勤務職員を除く。)について、人事委員会の承認を得て、別に定めるところにより、休憩時間を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
4 前三項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
基本は”労働基準法”と似ていますが、詳細を書いてあるか否かで、やはり法解釈等は大きく異なります。
私の解釈で大きく異なるのは…
・”自由利用の原則”が記載されていないところ
・任命権者の定めるところによる、休憩時間の一斉付与をしないことが可能となる明記
※労働基準法では、ここについては例外を取り除いて、一斉付与が原則。
→ここが、日本語の難しいところです!
ということは、雑な言い方にはなりますが。
テーマの”給食指導”に照らし合わせると…
公務員の先生の”マインド”としては、
お昼休みの給食指導は当然”校務”、そして自身の休憩に関しても管理者側からすると、一斉の付与は出来ないので、自分の時間で取ることが求められる。けど、そんな休憩しているほど暇じゃないし、”自由利用の原則”がないから、休憩中であろうと何かあれば、直ぐに”校務”に戻らなければならない…。基本、休憩なんてないですよね?
私立の先生の”マインド”としては、
お昼休み時間なのだから、本来は生徒も先生も休憩時間。だからこそ休憩を取りたいが、実態はそうはいかない(給食指導・生徒看護)ので、後で時間を作ろう…と言いつつ、その時間がほとんどないという現実。心を決めて、今日は休憩時間をしっかりとるぞ!と決めて、外出し、外食をする。気楽ではなく、ある意味”決心”の上での行動。”自由利用”って結局何ですか?
基本、皆様本当に”真面目”なんです。
真面目がゆえに、そこに自身のウェルビーイングがないがしろにされてしまうケースが多いのです。
※私みたいに子どもたちと食べようが、食事をしなかろうが、そこに対して休憩をしたいとか思っていない例外も沢山”教職員業界”では多い気もします。でもそれはそれで、良くない部分も多いのですよね。
論点2:どうしたら”休憩時間”を取れる?
これは私がずーっと思っていたことなのですが、
素朴な疑問です。
小学校6年間は、担任・副担任?が全ての教科~日常生活まで、ほぼ張り付いて指導されますよね?(専科科目は異なるかもしれませんが)
中学校・高校・大学は、
担任はクラス運営、教科科目に関しては、科目担当のはずです。
ここに違和感を感じてたのですが、
小学校の先生も”分業化”ではないですか?
というか、全体的に教育の内容の”分業化”を進めたほうが良いですよね?
そこで出てくる”給食指導”
これは何のための時間なんでしょうか?
最上位目的を見つけると、そこに誰が入るのが正しいのかが見えるはず。
・本日の献立の内容で、どのような健康管理を行うのが良いのか、給食を通してアドバイスをするのであれば、栄養教諭や健康管理士、など専門家が入るのがよいでしょう。
・そもそもチームビルディングの一環として、食事の盛り付けを手伝う。机の配置を揃えるなど、クラス運営関わることを基軸とするならば、生活指導・生徒指導、または学生主体にするならば、生徒会などが主幹でもいいでしょう。
・食育という観点でも、一部異なった内容として、食事の際のマナー、世界の食糧事情に関する内容、などを学ばせたいなど副次的な要素を取り込みたいのであれば、マナー講師、道徳の観点も教員などもありでしょう。
ただ、単に食事を取らせるだけでも悪くないと思いますが、
リスクの管理さえできていれば、子どもたちの自主性に任せる。
その間は、しっかりと先生たちも”休憩時間”を取る。
もう一度”給食指導”という言葉を、考えてみる必要があると思います。
さて、もし教職員の皆さんは、休憩時間をもらえたらどうしますか?
これも独自調査ですけど、
・たまっていた資料を少しでも整理する
・保護者・生徒への連絡、渡す資料を作る
・授業準備
・やっぱり教室見に行くかも…
正直、私の周りだけかもしれませんが
みんな、まじめすぎ!!(笑)
でも、これが今の学校教育を支えて下さっている皆様なんです。
私はこの仕事に関しては、
「愛情」がなくなったら、終わりだよと先輩から言われ続けました。
「愛」と「情熱」で、愛情だそうです。
こうした「愛情」を持った人たちで出来上がる
”最高の教育機関”が出来上がれば、もっともっと教師の仕事の魅力が増すはずなのですが…
それを外側から変えていきたい。”教育”から”共育”へ
ご覧いただきありがとうございます。
読まれる楽しさを噛み締めながら、継続していきますね。
気軽にスキ・コメント・フォローしてみて下さい。
その一つ一つが本当に"有り難い"です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
