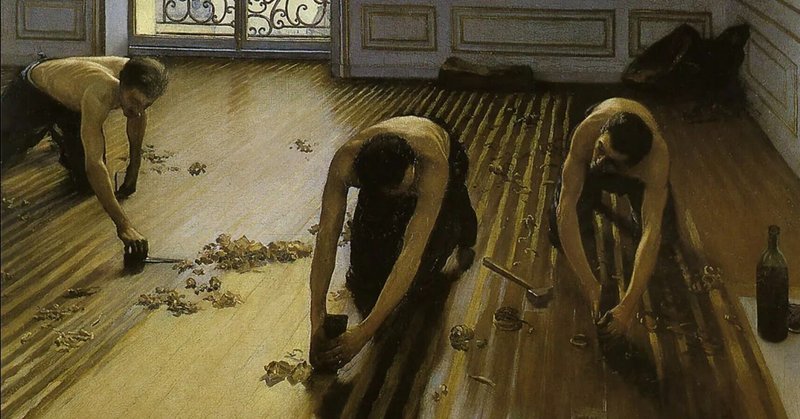
仮説を立てる力
今月の「絵を読み解く」は、カイユボットの「床削り」を扱いました。

なぜかオルセー美術館で、
この作品が日本人に大人気なのだそうで、
なんでなんだろう?
というあたりも含めて、みんなで分析しておりました。
こういうことに、「正解」なんてないので、
自分なりに仮説を立てる力が必要になってきます。
し、これからの時代、
自分なりに仮説を立てる力、
重要になってくると感じています。
(世界から「正解」が消えちゃった感)
いろんな意見が出て、楽しかったです✨
個人的には、
職人が働いている作品だからかなー
と思っていました。
日本人、職人の手の技大好きだし。
この作品、サロン・ド・パリ(政府主催の美術審査会)に出品されたときは、
「低俗」と評価されてしまったそうなのですが、
(モチーフが「都市の労働者」で、歴史画や肖像画などのヒエラルキー上位の作品ではなかったため)(モチーフによってヒエラルキーがあるらしいです)(イギリスなんかでは風景画のヒエラルキーが高いようなので、国によってヒエラルキー違うらしいですが)
この作品が、
欧米人(というか、キリスト教圏の人)にピンと来ず、
日本人に刺さるの、
キリスト教にとっては「労働」って、
アダムとイブが楽園追放されたときに、
神から人間に課せられた「罰」なのだけれど、
(だから、労働=辛いもの、苦しいもの、卑しいもの。はやく辞めたいもの。低俗なもの。昨今のFIREの思想も、根っこはキリスト教神話のここかも)
日本人にとって「労働」って、
なにせ古事記では神々も働くし、
(ニニギノミコトは稲穂を持って降臨するし)
ものすごく神聖で尊いこと。
だから、働いている人を見ると、勝手に尊さ、神聖さを感じてしまう。
ていう、日本人と西洋人の「労働」観の違いもありそうだなー、と思っています。
(FIREした人が賞賛される欧米と、「え、働いてないの?」って見られる日本の違い)(根っから働き者)
あとは、木の香りがしそうなところも日本人の好きポイントかも。
それと、西洋美術では、「光」って基本、「神の光」なんですよね。
その光が、名もなき労働者に当たっているの、いいなぁ、と思います。
ちなみに、ヨーロッパだと、
同じ国の中でも、
支配層・上流層は人種がドイツ系やオーストリア系、
銀行・学者・医者などはユダヤ系、
貴族のお手伝いや庭師などはスラブ系、
道路工事や新聞記事などはアラブ系なことが多いそうで、
肉体労働をしているこの職人さん達、
スラブ系なのかもしれません。
他人種に光を当てているところも、個人的に、いいなぁ、と思います。
4月は、ミュシャの「スラブ叙事詩」を扱います。

現在の戦争が、
スラブ民族同士の争いなので、
スラブ民族の統一を願って描かれた、
ミュシャ晩年の20枚の連作の1枚目を扱いたいと思います。
それぞれの国の思惑があると思いますが、
一日も早く戦争が終わりますように。
キツい状況になると、一番弱い人が真っ先に影響を受けるので。
(これは、戦争に限らないのですが)
講座にご興味がある方は、案内こちらになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
