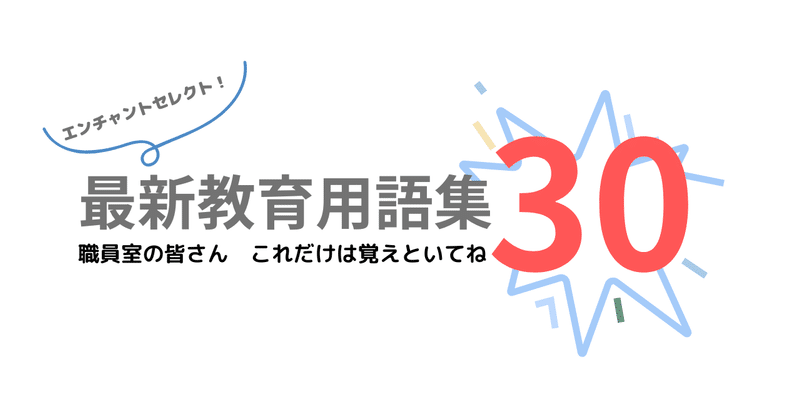
最新教育用語集30~職員室の皆さん、これだけは覚えといてね~ #129
「学びのきっかけになればいいなぁ。」
「共通言語があると、早い!」
と思い、作成します!
職員室向けに発信したものですので、簡単な言葉の紹介のみです。
ほとんど引用なので、「セレクトショップ」だと思ってください。
1.グリット
GRIT(グリット)とは「やり抜く力」のことで、アメリカの心理学者であり、ペンシルヴァニア大学のアンジェラ・リー・ダックワース教授が提唱した言葉です。
Guts(ガッツ):困難に立ち向かう「闘志」
Resilience(レジリエンス):失敗してもあきらめずに続ける「粘り強さ」
Initiative(イニシアチブ):自らが目標を定め取り組む「自発」
Tenacity(テナシティ):最後までやり遂げる「執念」
以上の4つの頭文字を取って、GRIT(グリット)と言われています。
「主体的に学習に取り組む態度」の一つ、
① 知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとしている側面と深く関連しているということができます。
2.レジリエンス
2020年に、打ち上げたアメリカの民間宇宙船クールドラゴンの機体を、搭乗した野口聡一宇宙飛行士らが「レジリエンス」と命名し話題となりました。これは、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の感染が終息し、再び世界全体が日常を取りもどすことを願ったからです。
レジリエンス(resilience)とは、復元力、回復力、弾力を意味する言葉です。精神医学や心理学では、「困難で脅威を与える状況にもかかわらず、うまく適応する過程や能力、および適応の結果のことで、精神的回復力」(最新心理学事典、平凡社)のことをいいます。今では、職務上のストレスで心身を病む従業員を出さないために、レジリエンスを向上させる企業研修も増加しています。「心が折れる」といいますが、レジリエンスはまさに「折れない心」を持つこととも言えます。
学校におけるレジリエンス
人間は誰でも満足した生活を送っている状態、ウェルビーイング(well-being)であることを望みます。ましてや発達段階にある子どもたちにとってそれはより必要なことです。また、学校は子どもたちにとって安全で安心できる居場所でなければなりません。しかし、子どもたちにとって危機的な状況となる要因があります。自然災害(地震、津波、豪雨など)、戦争、感染症などもあれば、子どもの自殺、学校活動における事故、あるいは個人的な疾病、両親の離婚や失業、転居などの要因もあります。
このような危機的な状況における 子どもたちの心の支援として、アメリカで考案されたモデルを踏まえ、日本の学校の実情に合わせた「予防」「準備」「対応」「回復」の4つの段階モデルが論じられています。とくに「予防段階」では、①ソーシャルスキルを育てる(対人関係のスキル、助けを求めるスキル、問題解決のスキル、感情をコントロールするスキル)、②自尊心を高める、③レジリエンスを育てる、④適切な時間的展望を獲得させる、といった点を高めることが求められます。(渡辺、2016)
また「回復段階」では、危機が発生した学校において安全・安心の回復、そして日常性の回復を支える支援が重要な役割となります。今後は、さらに学校の教育活動の中にどのようにレジリエンスを織り込むかを考案し、例えばカリキュラムの中に含めていくことや、学級経営に導入することなどの検討も喫緊の課題となっています。(小林、2021)
出典:「レジリエンス」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
3.エイジェンシー
これからの社会を生きる子どもたちに育成したい力について、OECD(経済協力開発機構)を中心として国際的な検討が活発に行われています。OECDは、「教育とスキルの未来2030プロジェクト」を進め、2019年5月に、「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)」を発表しました。
「エージェンシー」はその中心的な概念として、「変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力(the capacity to set a goal, reflect add act responsibly to effect change)」と定義されています。
出典:「エージェンシー」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
4.マインドセット
「マインドセット」とは、過去の経験や教育の内容、育ってきた社会、個人的な先入観などの、さまざまな要素によって形成される無意識の思考パターンや固定化された考え方をいいます。
ある状況に対する人の行動や受け止め方は、その人が持っているマインドセットの影響を受けるといわれています。
どのようなマインドセットを持っているかによって、チャンスと受け取るかピンチだと考えるか、また能動的に行動するか受動的な態度をとるかなどの行動が決まるため、その後の成果にも大きな影響を与えると考えられています。
また、マインドセットは生活してきた環境や経験などの、後天的な要素で変化することもあるとされています。
マインドセットがポジティブであるかどうかによって、個人のパフォーマンスや成長スピード、仕事の成果に影響があるといわれています。
出典:マインドセットとは?意味と重要性をわかりやすく解説 【中途採用ノウハウ】 | リクルートエージェント (r-agent.com)
5.パラダイムシフト
その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化することをいう。
現行の学習指導要領、GIGAスクール構想に基づく1人1台端末の整備により、令和の教育現場は大きなパラダイムシフトを求められている。
出典:池田 修×藤原友和 指導のパラダイムシフト【毎週木曜12時更新】 | みんなの教育技術 (sho.jp)
6.アクティブラーニング(なぜ消えた?)
「アクティブ・ラーニング」は「主体的・対話的で深い学び」に。
2月14日に出された学習指導要領改訂案にはそれまであった「アクティブ・ラーニング」という用語がすべてなくなっています。代わりに用いられているのは「主体的・対話的で深い学び」という言葉です。これには定義が曖昧な外来語は法令には適さないからという理由があります。
7.ティール組織
ティール組織(2014年 フレデリック・ラルー)
5つの組織モデルのことです。
それを学級にあてはめて書いてみました。
ティール組織~「あなたのクラス=あなた」はどのパラダイム?~|エンチャント先生@小学校 (note.com)
8.リフレクション
リフレクションは、日本語では「振り返り」と訳されます。「振り返り」は日常生活においてもさまざまな場面で行われていますが、学習指導の文脈で「振り返り」や「振り返り学習」が使われるようになったのは1990年代後半の「総合的な学習の時間」が登場してからです。2000年代になるとリフレクションと表現されるようにもなってきました。
その背景にはOECDの提言(2004年)でキー・コンピテンシーの中核としてリフレクティブネス(reflectiveness)が据えられたことや海外の諸文献からの引用として、リフレクションをそのまま用いるようになったことが考えられます。
こうした過程でリフレクションは主に体験的な学習において、体験を学びとして構築するための教育手法として定着してきました。現在では体験的な学習に留まらず、学習の多様な機会にリフレクションの機会が設けられています。
出典
「リフレクション」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
『先生たちのリフレクション』を読んで|エンチャント先生@小学校 (note.com)
9.フィードバック
フィードバック(feedback)とは、行動や成果物に対する現状(評価や感想など)を伝え、必要に応じて軌道修正を促しつつ、将来の行動指針を作ることを指します。
ビジネスの場だと従業員教育や目標達成を目的に、上司から部下に対してなど、主に社内で行われるフィードバックがよく知られています。多くのビジネスパーソンは、「今のまま進み続けていいのか、改善が必要なのか」日々考えながら職務に当たりますが、自分ひとりで考えるだけでは、現状を正しく認識することが難しく、他者からのフィードバックが欠かせないのです。また、ビジネス以外でも教育現場で生徒や子どもたちの力を引き出すために行われるフィードバックもあります。
これらはあくまでも例で、他にも多くの場面でフィードバックは行われています。ここでひとつ共通しているのが、フィードバックはあくまでも成長や成果の達成を願って、将来に向けた立て直しまで踏み込んで行われるものであるという点です。
フィードバックは、「レビュー(評価や感想のこと)」を伝えるだけではダメで、コーチが対話を通して、相手が自ら考え行動する能力を引き出す「コーチング」の側面や、時には経験豊富な人から、経験が浅い人へ自分の知識やノウハウを伝える「ティーチング」の側面も含んでいます。
出典:教育を効率化するフィードバックの方法とは?心理学的な観点からも解説! (shouin.io)
10.形成的評価
評価とは、生徒が何を学んでいるかを測定するために教師が使用する方法です。教育者は主に、形成的評価と総括的評価という2種類の評価を使用します。
形成的評価は学習活動中に生徒の学習を監視するために使用され、
総括的評価は学習活動の終了時に生徒の学習を評価するために使用されます。
形成的評価と総括的評価の主な違いは、形成的評価が学習プロセス中に行われるのに対し、総括的評価は学習ユニットの終了時に行われることです。
形成的評価とは、教育および学習活動を修正するために、学習過程において教師が行う公式および非公式な評価のことです。
その主な目的は、生徒の学習状況をモニターすることです。
形成的評価は生徒と教師の両方が学習プロセスを改善するのに役立ちます。一般的に評価は生徒に成績または点数を与えますが、形成的評価は生徒にフィードバックを与えます。したがって、それは生徒が自分の長所と短所を確認するのに役立ちます。
出典:形成的評価と総括的評価の違いとは?分かりやすく解説! | トーマスイッチ (toumaswitch.com)
11.メタ認知
メタ認知とは、知覚する、記憶する、思考する、判断するなどといった認知活動を客観的に理解し、それらの活動を評価したり制御したりする働きのことです。つまり、自分を客観的に認知する能力のことです。
「メタ(meta)」にはいろいろな意味がありますが、メタ認知の場合は、「上位の」という意味で用いられており、種々の認知活動の上位に位置づけられる認知ということになります。
学習の場においては、自分ができるようになったことを客観的に理解し、他の場面に活用できる力として最も大事な要素といえるでしょう。
なお、学習指導要領では、学力を「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」の3つに整理しています。そのうち、「学びに向かう力・人間性等」について、文部科学省は「主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態度等があり、自分の思考や行動を客観的に把握し認識する、いわゆる『メタ認知』に関わる力を含むもの」と説明しています。
メタ認知の育成は、児童生徒の「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、必要不可欠であるといえます。
出典:「メタ認知」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
12.自己調整能力
自己調整力とは、自分の学習状況や目標を把握し、適切な学習方法や方略を選択し、学習の経過や結果を評価し、必要に応じて修正する力です。自己調整学習の力を育成するには、「予見(見通し)」「遂行コントロール(学び深める)」「自己省察(振り返り)」の3つのステップを循環的に行うことが大切です。また、メタ認知、動機づけ、行動といった自己調整機能をうまく働かせることも重要です。
主体的に学習に取り組む態度を、(1)粘り強く学習に取り組む態度(粘り強さ)(2)自らの学習を調整しようという態度(自己調整力)……という二つの側面に分けています。
13.社会情動的スキル
近年、国内外で注目されている社会情動的スキル(非認知的スキル)とは、学力テストなどで計測できる認知的スキル以外の、数値化することが難しい心の動きのことです。
OECDは、2015年にこのスキルが、
目標の達成(がんばる力、自己抑制、目標への情熱)
感情のコントロール(自尊心、楽観性、自信)
他者との協働(社交性、敬意、思いやり)
の3つの要素で構成されると定義しています。
社会情動的スキルは、学校でも身に付けることができますが、日本の公教育ではカリキュラムの下では、あまり意識的に指導されていません。
14.コーチング
皆さまは「コーチング」という言葉をご存じでしょうか? コーチングとは、授業の内容を教える「ティーチング」と異なり、学習の進め方などに関して相談・アドバイスや確認を行うことです。コーチングは受験業界を中心に、現在の日本の教育業界に大きく広がりを見せています。
出典:生徒一人ひとりに寄り添い学習をサポートする「コーチング」で気をつけるべきポイント (1/2)|EdTechZine(エドテックジン)
15.サーバントリーダーシップ
組織の構成員をまとめる行為やそれに必要な資質をリーダーシップといい、一般に指導力、統率力などの資質を意味します。
専制型リーダーシップ
リーダーの意思を組織の構成員に「命令」として行動させるリーダーシップです。構成員は、常にリーダーの指示にしたがって行動する必要があります。メンバーが従う根拠としてはリーダーにカリスマ性があることや、リーダーが強い権力をもっていることなどが考えられます。メンバーの自律性は希薄ですが、災害時など緊急性を要する状況や、警察や消防など一貫した統率が必要な状況では有効です。
放任型リーダーシップ
リーダーが、組織の構成員に意思決定や状況判断のほとんどを任せるリーダーシップです。全員がリーダーのような状態になるので、構成員の能力が高い場合には有効です。一方、チームとしてのまとまりや一体感は薄まり、組織全体としての作業量も、ほかの2つのリーダーシップに比較して少なくなるといわれています。
民主型リーダーシップ
組織の意思決定にメンバーの意見や合意を反映させるリーダーシップです。メンバー一人ひとりの参画意識やモチベーションが高まるため、長期的に見ると全体の作業の質や量において有効であるとされています。一方、合意形成に時間がかかる、合意の過程で無難な結論に落ち着いてしまうといった欠点も指摘されています。
サーバントリーダーシップは、このうち、民主型リーダシップの類型に入るものといえるでしょう。近年、これまで主流であった「トップダウン型リーダーシップ」に替わり、「サーバントリーダーシップ」が注目を集めています。
出典:「サーバントリーダーシップ」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
16.フォロワーシップ
フォロワーシップとは、チームの成果を最大化させるために、「自律的かつ主体的にリーダーや他メンバーに働きかけ支援すること」です。
具体的には、リーダーの意思決定や行動に誤りがあると感じた場合は、臆することなく提言を行ったり、チームがより良い方向に進むようメンバーに働きかけたりと、自分の置かれたポジションだからこそできることを主体的に実行していくことを指します。
出典:フォロワーシップとは?リーダーシップとの違いや実践方法|グロービスキャリアノート (globis.ac.jp)
17.ゲーミフィケーション
ゲーミフィケーション(gamification)とは、ゲームの要素や仕組みをゲーム以外の分野に応用したアプローチです。
たとえば、
「課題をクリアして、ポイントや経験値を数値化、可視化しながらレベルをアップしていく」
「モチベーションを持続しながら、熱中していく」
こうしたゲームの仕組みを他の分野に応用して、業務の効率化や生産性アップ、課題解決へつなげていきます。
出典:ゲーミフィケーション×教育。授業で役立つ活用例と勉強アプリ紹介。 - ICT教育ラボ (kdc-ict.com)
18.EdTech(エドテック)
教育(エデュケーション)と技術(テクノロジー)の融合によって教育のあり方を変えていくことや、その技術、ビジネス市場を指す新しい言葉です。経済産業省は、学校での実証プロジェクトを通してEdTech導入を促進しようとしています。
出典:EdTechって何ですか?|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)
19.STEAM教育(スティームきょういく)
科学・技術・工学・芸術・数学の5つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)。芸術・リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。知る(探究)とつくる(創造)のサイクルを生み出す、分野横断的な学びです。
出典:STEAM教育って? | STEAM JAPAN (steam-japan.com)
20.ダイバーシティ
ダイバーシティ(Diversity)を日本語に直訳すると「多様性」。
他にも、「相違点」や「多種多様性」といった意味もあります。
21.イエナプラン
イエナプラン教育は、ドイツで始まりオランダで広がった、一人ひとりを尊重しながら自律と共生を学ぶオープンモデルの教育です。2019年には、長野県佐久穂町に日本初のイエナプラン校である、学校法人茂来学園しなのイエナプランスクール大日向小学校が開校した。2022年には、広島県福山市立常石小学校が、公立小として初めてイエナプランに基づいた学校教育を開始する予定である。その他の自治体でもイエナプランを参考にする動きが様々に見られ、日本における公教育改革へのイエナプランの影響は増してきている。
出典:日本イエナプラン教育協会 (japanjenaplan.org)
22.シンギュラリティ
シンギュラリティとはAI(人工知能)が人類の知能を超える技術的特異点(転換点)や、AIがもたらす世界の変化を示す言葉未来学上の概念のこと。特に近年はChatGPTをはじめとしたAI技術が一般にも普及したことを背景に、シンギュラリティやAIに対する関心が日に日に高まっています。
出典:シンギュラリティとは? もたらす影響、2045年問題など - カオナビ人事用語集 (kaonavi.jp)
23.ウェルビーイング
ウェルビーイング(Well-being)とは、「良好な状態」「心身ともに健康で、持続的に幸福な状態」という意味です。学校においては、子どもたちのウェルビーイングの実現をめざし、学習者が主体となる教育の転換が問われています。また、SDGsにおいてもウェルビーイングが重要です。
出典:「ウェルビーイング」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
24.教育DX(デジタルトランスフォーメーション)
DXは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語。デジタル技術の活用によって、社会や生活、ビジネスモデルなどをよりよいものに変革することを意味します。
経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」では、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義。近年、企業や行政など、さまざまな組織においてDX化が積極的に進められています。
教育DXは、それらと同様に、教育現場においてもデータやデジタル技術の活用によって、学校教育の在り方や教育手法の変革を行うこと。文部科学省のGIGAスクール構想も、そのための施策の一つです。
出典:「教育DX」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
25.エンパワーメント
近年、教育の世界でも「エンパワーメント」という用語をよく耳にするようになりました。この用語はもともと、社会的に弱い立場に置かれてきた人々(例えば、女性や人種的、民族的マイノリティなど)の権利を認め守ろうという社会運動のなかで使われ始めたとされています。そのため一般に、弱い立場に置かれた者に対して「権利を認める、権限を与える」という意味で用いられています。
ただ、学校という場の特徴を踏まえたとき、それとは少し異なる意味についても目を向けておく必要があるでしょう。それは、児童生徒が本来的に持つ潜在的な力や価値を引き出し、自分自身で人生を切り開いていくために必要なスキルや自信を身に付けさせるという意味です。エンパワーメントとは、主体性をはじめとする人間の内面にあるポジティブな力を育もうという志向性も持つ概念なのです。
出典:「エンパワーメント」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
26.ルーブリック
ルーブリックとは、パフォーマンス課題における学習の到達度を評価する際に使用する評価指標のことです。この評価指標は、学習活動を通して児童生徒に育成したい資質・能力について「評価観点」を設定し、それぞれの評価観点に対応する学習の到達度として「評価基準」を定めて表を作成し、児童生徒の学びの姿を文章で表現していきます。
出典:「ルーブリック」とは?【知っておきたい教育用語】|みんなの教育技術 (sho.jp)
27.PBL
PBLには、「プロブレム・ベースド・ラーニング」(問題解決学習)と、「プロジェクト・ベースド・ラーニング」(プロジェクト型学習)という異なる2つの意味があります。どちらも、高等教育をはじめとして初等・中等教育で推奨されている「アクティブ・ラーニング」を促す手法として注目されています。
28.生存バイアス
生存者バイアス(せいぞんしゃバイアス、英語: survivorship bias、survival bias)または生存バイアス(せいぞんバイアス)とは、何らかの選択過程を通過した人・物・事のみを基準として判断を行い、その結果には該当しない人・物・事が見えなくなることである。選択バイアスの一種である。
実績のあるコーチや監督が、たびたび体罰の有用性について主張することがあります。彼らの主張は、おおむね「実績のある選手はみな、体罰を受けて成長した」となります。しかしこの主張は、体罰が日常的だった時代の生き残りにしか目を向けていません。活躍できる才能を持った選手が、体罰によって芽を摘み取られてしまった可能性を無視しています。
これはまさに「生存者バイアス」に引っかかってしまっている例です。
出典:心理学用語「生存者バイアス」とは?意味と具体例を解説 – スッキリ (gimon-sukkiri.jp)
29.アンコンシャスバイアス
私たちは、何かを見たり、聞いたり、感じたりしたときに、「無意識に“こうだ”と思い込むこと」があります。これを、アンコンシャスバイアスといいます。日本語では、「無意識の思い込み」などとも表現されています。
出典:アンコンシャスバイアスとは?|一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所 (unconsciousbias-lab.org)
30.個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実
「個別最適な学び」について「指導の個別化」と「学習の個性化」に整理されており、児童生徒が自己調整しながら学習を進めていくことができるよう指導することの重要性が指摘されています。
探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよう、必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」を充実することも重要である。
実際の学校における授業づくりに当たっては、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の要素が組み合わさって実現されていくことが多いと考えられます。例えば授業の中で「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし、更にその成果を「個別最適な学び」に還元するなど、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実していくことが大切です。
出典:2.育成を目指す資質・能力と個別最適な学び・協働的な学び:文部科学省 (mext.go.jp)
以上、エンチャントでした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
