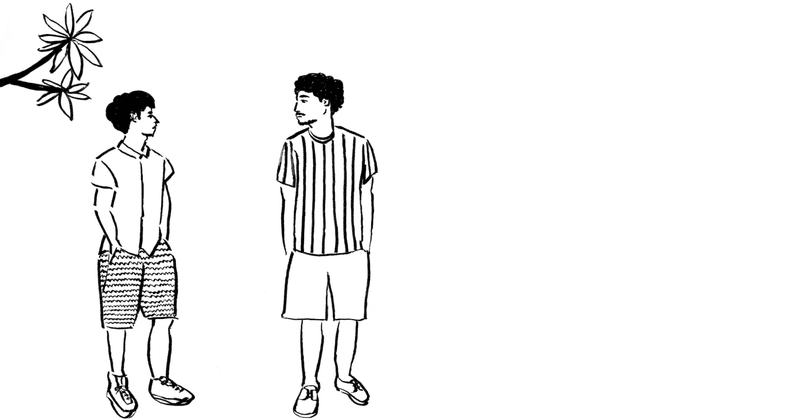
小説「黙過」
ほら、鉄を打つのが聴こえるだろう――
あれはノドの地から響き渡る
エデンの東を導く未来の響きだ――
二〇一五年一一月、Twitterでのナーデルの呟きより
――俺はノドの地にいる。
そう口にしてナーデルは口馴染みのよい温度の珈琲を啜った。喫茶店は休日の賑わいをみせて多言を語る者たちが集っていた。政治や恋愛、文学やスポーツ、漫画や映画の語らいが珈琲豆のようにミルされて、煙草に燻されたスモーキーな混信が交わされていた。その裡でも僕はナーデルの常套句を聴き逃さなかったし、その珈琲に濡れた唇の動きを見逃さなかった。そして、その常套句が普段とは違う声音で響いたことも――。
ナーデルはダックワーズを咀嚼してもう一度珈琲を飲んだ。僕はナーデルのその言葉を咀嚼しながら、腰かけるソファのベロア生地を撫ぜ、肘掛け付近の煙草の焼け跡をソファの臍のごとく慰撫した。
珈琲店に充満する音の中で僕らは瞬間、沈黙した。
――俺はノドの地にいる――これはレバノンから国際交流を目的の一環として留学してきたナーデルの口癖だった。その口癖は酒に酔った時や互いの腕と胸の中で眠る時の一つの冗談として口をつくことが常であった。つまりはある種の高揚感や恍惚、夜半の気がこんな常套句を冗談めかして言わせるのである。こんな夕暮れもまだ早い昼日中の池袋の喫茶店で言うことはこれが初めてだった。ましてやナーデルの声調が重く響き、僕は思わず身を強ばらせる――。
ナーデルと出逢ったのは大学の国際交流セミナー「バベルの塔」でのことだった。当時二年生だった僕は新入生である日本人の希望者と留学生の橋渡しとしてボランティア活動に従事し、自己紹介の後、各班に分かれて「バベルの塔」の活動などを紹介した。僕を含め五人の班は残念ながら継続して班を維持することができなかった。日本人学生二人は皆その一回きりで参加しなくなり、スペイン人の女性は別の班の女性に頼り切るようになった。それは仕方ないこととして、当時一年生のナーデルが僕に寄り添うようになった、というわけだ。
僕とナーデルは「バベルの塔」から延長してどちらともなく誘い合った食事処で親交を深めた。僕は英語と基礎的なアラビア語を修得していたし、ナーデルも日本語は留学に向け基礎を身につけていたから、言葉の障害は薄かったと言ってもいい。一ヶ月も経つとナーデルから積極的に僕との交際を匂わせてきた。ナーデルは出逢った当初から気づいていた、というが僕もナーデルも互いに性の趣が合致したために衣服の奥に隠された肌にも触れ合う関係になった。
僕たちは日常の付き合いの中でも、肩を寄せ合う。シーツの中でも個人的なことや国のこと、下らないことも民族としての慣習の違いを語り合った。ナーデルの家は代々イスラム教徒ではなく、マロン典礼派のキリスト教徒であり、教義においては同性愛を禁じられているといつか話してくれたことがある。僕が教えを破ることになるな、と軽口を叩くとナーデルは例のノドの地に関する冗談を返したのだ。
――俺はノドの地にいる。いて、こうしてクニオといる。
――ノドの地って、どこだ。
――ここさ。と冗談はさておき、知らないのかクニオ。教会で聖書を開いていたんだろう。
――過ぎた話だ。今は開いていない。
――ノドの地は、その嘘と罪咎の故にエデンの東を追われたカインが辿り着いた土地だよ。
――ああ、あの場所はノドというのか。
――ノドの地という。俺は追放された場所にいるから、埒外なんだよ。神様の見過ごす場所にいるんだ。
ナーデルはそう言った。その口調は素気なく何でもないように響いた。僕は蛇により楽園が失われ、楽園を見ることなくエデンの東をも追われたカインの後ろ姿を想像した。ノドの地は想像が追い付かず、ただ荒野に立ち尽くすカインが僕の脳裏にいた。
やがてカインが僕の描けなかったノドの地に向かうと、僕たちはシーツを人間二人分の大きな獣にして触れ合った。ナーデルは肩幅の広い巨躯だった。僕の黄色い掌が血色のよい唇が、ナーデルの浅黒の首元に匂い立つ一層黒い脇に厚い胸板に大きな乳首に臍に合わさる時、その巨躯は飼い慣らされた虎のように丸まり、高揚し静かな息を漏らす。大きな丸い山の谷間に温かな呼吸を挿入するとひくつく大いなる器に、僕が硬くそそり立つ一物を少しずつ(快感が永遠に続くようにと祈るように少しずつ)挿し込み、二匹合一の獣として汗ばんでじゃれ合い、やがて谷間にもたりとした乳を注ぐ――。
喫茶店の中は変わらず言葉が交錯していた。けれど、僕らは禁煙席(それでも煙は香ってきた。僕はこれを否定しない。これこそ正しい喫茶店だと思う)で窓際の隅にいて、右隣に座っていた男女は五分ほど前に店を出て行った。男女は疲れたように俯いて携帯電話の液晶画面を見つめていた。その男女が失せると、二十台後半の黒縁眼鏡をかけた男性が代わりに席に案内された。彼はコーヒーフロートとパンケーキを注文し、ゼンハウザーのヘッドフォンを頭に填め、MacBookで論文らしきものを書いていた。
ナーデルは今の雰囲気からどのように語るべきなのか言葉を探しているようだった。重要な話となれば、主にアラビア語で会話することになるだろう。そのことをナーデルも理解して真剣な顔で私にノドの地について語ったのだろう。僕たちは互いにコーヒーを啜り、ダックワーズを頬張った。
――なにか言いたいことがあるのなら、ナーデルの言葉で言えばいい。
ナーデルは少し決心を揺らがせるように唇を歪ませた。しかし、ついには言葉を紡ぎ出した。
――俺の家は敬虔なキリスト教徒だから食前食後・朝昼夜の祈祷は毎日欠かさず、安息日の礼拝には毎週家族で出かけていた。俺は小さな頃から聖典を携えていたし、聖歌だって多くを記憶している。頭の中で教会のオルガンはいつでも鳴り出し、いつでも俺は数多の聖歌を再生できる。
ある日の夕べの食卓についている時、父は俺に向けて、我が家に遠縁の子供を迎え入れると言った。俺はスフィーハ(挽肉のパイ)を野菜のシュールバ(スープ)で喉に流し込んで父の声を聞いた。母はその時、既に聞かされていたようで俺の顔をじっと見ていた。俺には決定権なんてなかった。当時まだ十二歳の俺には父の言葉に対して、きちんとスフィーハを胃に落としてから、うん、と頷くしかできなかった。
ひと月も経たない晴天の日に、その遠縁の子供は両親に手を繋がれて学校帰りの俺と対面した。名はジャマルと言い、二歳年下の十歳だった。
随分後になって聞いた話だがジャマルの両親は仕事の用事を終えた帰途で不幸な事故に遭い車内で圧し潰されて死んだと父は言った。ジャマルは友達の家で二人の帰りを待っていた。全く不幸な事故なんだ。ナーデル、優しい私の息子。分かるな、これから君は兄でジャマルは君の弟になるんだ。分かるな――。それに俺はきちんと本心から応えたよ。うん、父さん、と。弟ができるなんて嬉しい、と。
ジャマルは迎え入れられて、しばらくの間は俯いて過ごしていた。しかし、ジャマルは必死に前を向こうとしていた。俺の両親に心からの感謝は忘れなかったし、教会に行っては俺と聖歌を一緒に歌い、神父様とも何度も会い心を回復させていこうと必死になっていた。その姿は、我が家を安心させたし、母は何度もその懸命さに涙してジャマルを抱きしめた。
実際、ジャマルの硬くなっていた心は解かれ始めた。俺はジャマルを連れて友人たちを巻き込んで遊び、時には勉学にも励んだ。僕たちは本当に仲の良い兄弟だった。
けれど、本当のことを言ってしまうけれど、俺はジャマルと肉体を交わすことになる。あれは両親が出かけて俺とジャマルとで留守番をしていた時だ。俺は十三歳になり、ジャマルは十一歳だった。二人だけの小さな部屋は夕焼けの紅い陽が満ちて、俺たちの陰が重なり家具や玩具などあらゆる陰にひっついては離れてを繰り返した。じゃれ合ううちに俺はジャマルに組みふされたような形になって、腹の上にジャマルは跨った。俺はジャマルの幼い身体を見上げた。ジャマルの濃い色彩の顔は右半分が夕焼けに化粧されて左半分が陰に隠れて柔和な眼だけが光っていた。俺はそれまで男に愛を感じたことはなかった。本当の話だよ、俺は同じ学校に通っていたスハのことを好いていた。けれど、俺はジャマルによってその性的嗜好を決定的に変えられた。ジャマルは無邪気に折りたたんだ脚をバネのようにして腰を俺の腹に打ち付けながら跳ねた。俺はジャマルのまだ小さな身体を全身で感じた――。
もちろん始めにその性的衝動に対する葛藤があった。俺は努めてジャマルにも両親にも普段通りに接したけれど、数多の表情を見せ、俺を信頼するジャマルの美しさに俺は苦しんだ。
その苦しみに俺は勝てなかった。ジャマルに触れる俺の掌は舐るような手つきになり、次第に性を知らないジャマルに兄弟の誓いの名の元に、誰にも知られない密なる遊びを興じた。首元にキスをして、それは頬に口に至り、衣服の上から擦っていた下半身も次第に下着の中に入れるようになった。ジャマルはこの誓いを決して破らなかったし、女の子に目を向けることもしなかった。俺がさせなかった――と言ってもいい。俺の罪悪の感情は消えることはなかった。けれどジャマルが性に目覚め、この密なる遊びをしっかりと認識し、互いに兄弟でありながら愛する人になった頃にはその意識は水のように薄まり小さなことで流れてしまうようなものになった。
俺は十七歳になりジャマルが十五歳になった晴天のある少し汗ばむ日曜日だった。俺たちは敬虔なキリスト教徒だから家族揃って神を拝していた。しかし、俺とジャマルは密やかに罪ある我らをお許しくださいと舌を出して言い合いながら、手と手を取った。その日の午後、両親と別れた俺たちはファストフードのケバーブのピタサンドを食べ合って、通りを歩いてカフェに入った。そう今みたいに。俺たちは敬虔なキリスト教徒として教会に礼拝に毎週行くし、食前の祈りを捧げるわけだけれど、実際のところ背信の信者のような気分でいつづけた。分かるだろ、俺たちは地にオナンを垂らしているようなものだからさ……。
カフェで互いの顔を見たり、聖書や詩を読んだり、ニュースや愉快な動画を見て時は過ぎた。太陽が落ち始めて夕暮れ時が来た。俺たちの入ったカフェは人気が少なく、ハンチングを目深に被ってマックブックをいじる男性や、眠りの隙間を縫うように朝刊を読んでは気づけば目を閉じ、また同じ記事に目を通しているんだろう――捲られない新聞を持つ老人が目立つばかりで、カフェ全体は橙色に燃え上がってこの店の珈琲の色合いと相違ない暗闇が斜陽した。ジャマルは店主の目を盗むようにカップに隠れるように真っ白な角砂糖――といっても夕陽によって砂糖すら橙色に変じていたけれど――その角砂糖を積んでは崩してをしながら微笑んでいた。俺はその端正で柔和な顔つきを眺めて、何気なく本日の説教にあったカインとアベルの話の記された頁を撫ぜていた。
ジャマル、と俺は話しかけた。
始め、ジャマルは気づかないようにしたが、はっと顔を上げて角砂糖の壁を崩すと、何、兄さん、と応えた。
神は肉食主義者だったろうか――と冗談めかして俺は聞いたよ。何気ない冗句さ。カインの捧げた農作物を良しとされず、神はアベルの捧げた羊肉を良しとされた。神は野菜を嫌うのか? それなら随分不公平で不運な事件だ。
夕陽に刺青されたジャマルの顔は美しく、目は大きく見開かれ濡れて光っていた。
――どうだろう。兄さん。僕はアベルが美しく神の寵愛を受けていたように誤読して聖書を笑ってやるけどね。神父様は昼間の説教で言ったね。これは信心の問題だって。カインは不信を心に持ちながら自ら刈った農作物を神に捧げたから、神は拒否されたと。対してアベルは神を心から思い、羊の息を止めて――神に認められるほどの羊の息の止め方だったんだろうね。返り血なんか浴びなかったんじゃないかな。
ジャマルの吐く言葉と息は次第に熱を帯びてきた。
――ねえ、兄さんの言う通りだよ。こんな不公平なことがあるなんて。神の御業ほど傲慢で手抜きなこともないじゃないか。どうしてカインは不信を抱かねばならない。そしてたった一人の兄たるカインに殺害されなければならないアベルの悲しみは誰が救いとるんだ。カインはエデンの東を抜け最果てに行かなければならない。そしてアベルは、行き場のないアベルの魂は一体どこに行けばいいんだ。カインの殺害をどうして神は黙過したんだ。
ジャマルの目尻から涙が伝い頬を濡らしているのに気づいて俺はやっとジャマルの肩を揺すり、我に返ったようなジャマルにハンカチを差し出した。
なあ、クニオ。信じられるか。どうして、背信のキリスト教徒であるジャマルがカインとアベルの心情に涙しなければならないんだ。
なあ、クニオ。俺は全てに遅れを取っていた。
僕はナーデルの肩が内に内に丸まり、言葉をその巨躯の殻に閉じ込めてしまうように思えた。僕は子供の時、母の膝元で疲れて眠ってしまうほど泣き続けた時のような胸の苦しみを覚えていた。ナーデルの言葉はきっと彼が心に抱えている恐怖の大渦の中心にある事実なのだ。きっとその事実を知る者は少なく、真実を捉えているのはナーデルだけなのだ。その彼が珈琲の気配も失せ乾いた口で何とか話そうとしている。
僕がナーデルに対して吐く全ての言葉は大渦の中心には辿り着けないだろう。僕の唯一できることは、彼の吐くその真実を耳で聴くことだけだ。
「ジャマルは血を流して自らの足で遠くに行った」
ナーデルが精一杯吐いた言葉は僕の耳に残る。しかし珈琲店の喧騒として他にはその言葉は届かない。
「それで、ナーデルはどうした」
「俺より、父の話をしようか。父はジャマルの血の吐かれた身体を抱いた最初の人だった。父は激しく泣いていた。明らかにジャマルは自らの足で行ってしまったのに残された手紙は一切見つからなかった。両親も俺もジャマルが遠くに行くことで何を言おうとしているのか全く理解できなかった。ただ本当に愛された息子として、そして弟として、ジャマルが遠くに行ってしまったことを悲しんだ」
ナーデルはやっと緊張から少しづつ解放されたようだった。もう氷のすべて溶け出した水を口づけた。僕はウェイターを呼び、ブルーマウンテンを二杯、追加注文した。
「なあ、クニオ。俺が何よりクニオに話さなければならないのは未来の話だ。過去を背負って未来を話さなければいけない。だから今、本当に好きなクニオに話すんだ」
そうだ。過去を僕は聴くことしかできない。しかし、未来を話すならば僕もその大渦に身を浸さなければならない。大きな流れに抗いながら、ナーデルと手を取り合わなければならない。僕は頷いて、ナーデルの大きな手の甲に掌を添えた。
「俺はあくまで真実だと思われることを隠してしか話せない。絶対に大渦の中心を明解な言葉にすることはできない。俺のこうして話す母国語でも、拙い俺の日本語でも」
ウェイターが湯気と香ばしさが立ち昇るブルーマウンテンを運んできた。ナーデルは飲もうかどうか少し迷い、カップに手をかけたが、結局はその温度が舌馴染むのを待ち、未来の話を続けた。
「ジャマルは寵愛されたんだ。父にも俺にも。敬虔なキリスト教徒と背信のキリスト教徒に寵愛された。ジャマルは美しく、純粋だったから。多くの我が民族と同様に家族として迎え入れてくれた両親と俺に深く深く感謝しながら、その寵愛を受けた。結果、ジャマルはどこにも行けなくなってしまった。ジャマルは二つに引き裂かれるようにその行き場のない魂になって自らの足で遠くに行ってしまった。行き場のない魂がどこに行ってしまうのか、もう俺には決して分からない。俺は俺たち家族がその寵愛の故にジャマルを失ったと考えている。だから来たんだよ。ここへ。これはまだ両親に話していない問題だが、俺は手続きを取って、日本人国籍を取って日本に永住しようと思っている。近い将来の話だがな。ここで生きていくには、これから俺が過去を背負いながら歩いていくには日本でクニオが共にいて欲しいんだ」
ナーデルがここがノドの地だと言うのはそういうためか、と僕は確認した。ナーデルは頷いた。陽が沈み始めた。店内は広く、夕陽は珈琲店全体を染め上げはしないが、窓際の僕らを明るく染めた。
「ジャマルが遠くに行ってしまったこと――俺たち家族にその責任があるならば、エデンの東から追放されるのは俺なんだ。神に背信の心を持つ俺だ。だから、俺はもうノドの地でオナンを垂らしながら生きていかなきゃ」
ナーデルの告白は僕の未来にも過去にもなった。重いものを背負わなければならなくなった。そして、いずれきちんと僕もナーデルに告白しなければならない日が来る。
ナーデルにも僕の大渦を覗いてもらう日がいずれ来るだろう――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
