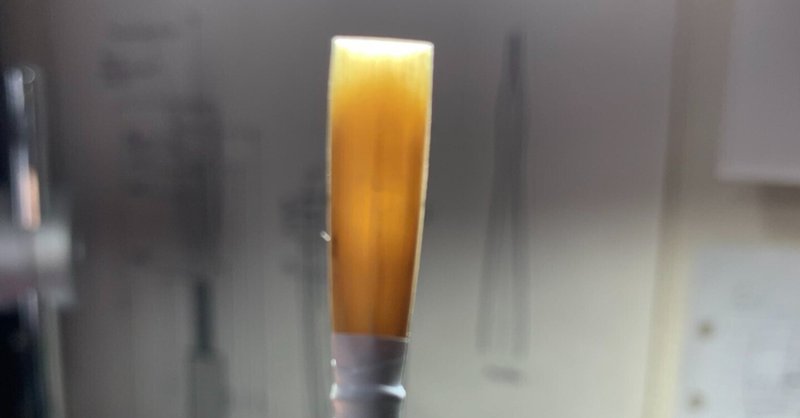
工具も手作りします~オーボエのリード製作、後編~
本日はオーボエのリード製作第2弾!
オーボエのSさんに組み立てたリードの削り方を見せていただきます。
※前回記事の続きとなります。前回記事はこちらから。
工具も手作りします~オーボエのリード製作、前編~|アンサンブルSAKURA #note
Q.組み立てた段階だと先端がまだ開いていません。ここからどのようにして先端を開いて、削りの工程に持っていくのでしょうか?
A.その前に、リードの削り方のスタイルについてお話しします。
リードの削った部分のことをスクレープと言うんですが、大きく分けてショートスクレープとロングスクレープの2種類があります。
ショートスクレープはリードの先端から三分の一から半分くらいまでのところを削ります。
ドイツやフランスなど、ヨーロッパの奏者のほとんどがこの削り方です。ドイツなどヨーロッパで勉強した人、その弟子が多い日本もこのスタイルが圧倒的に多いです。
一方ロングスクレープはリード全体を削ります。これはアメリカンスタイルとも呼ばれ、アメリカのオーケストラ奏者の多くがこのスタイルです。
私の先生がシカゴ響の故レイ・スティル先生の弟子なので、私もロングスクレープで削っています。
このスタイルの奏者は日本では少数派だと思います。
ちなみにSAKURAのもう一人のオーボエKさんはショートスクレープのリードを使っています。二人の音色の違いはリードの削り方の違いによるところが大きいと思います。
では、どのように削っていくのか簡単に説明します。
①糸巻きが終わったリード(先端はまだ閉じています)を全体に荒削りします。

②先端をカットします。

③先端(5ミリ程度)を薄く(0.1ミリくらいまで)し、それ以外のところも規定の厚みに整えて行きます。
④音を鳴らしながら表裏、左右が規定の同じ厚みになるように道具(ダイヤルキャリパー)で測りながら調整する。

⑤最先端を一番薄くして(0.05〜6ミリ)左右の端や中央(0.5ミリ)は基本的には厚くして、適度な抵抗感を持たせます。
自分なりに大体の厚みの基準はありますが、材料や季節(湿度)により調整します。
湿度が高い時期は1日でリードの状態が変わってしまいます。
演奏会の時など、午前中のリハーサルと本番でお客さんが入ることによりホールの湿度が上がってしまうとリードの状態が変わってしまうこともあります。その変化も見越してリードの準備する必要があります。
Q.オーボエのリードって、薄くて繊細なものだというのが良く分かりました。「手作りの工具」がこれまでいくつか登場しましたが、今後こういうものを作ってみたいという展望はありますか?
A.ひと通り道具は揃っていますので、もうないですね(笑)
ひたすら、より良いリードを作っていけるように頑張ります。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございます!!
【面白いと思って頂けましたら、画面下の♥を押下頂けると幸いです!】
【弦楽器団員募集中🎻お問い合わせは下記HP、Twitter、Facebook、noteからお願いいたします】

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬
アンサンブルSAKURA第40回定期演奏会
日時:2023/11/19(日)12:30開場13:00開演
⚠️開演時間が1時間前倒しとなってます⚠️
会場:浅草公会堂
指揮:高石治
入場料:1,000円
曲目:
グリーグ/ペールギュント 抜粋
シベリウス/フィンランディア
シベリウス/交響曲第1番
公式HPhttp://www.portwave.gr.jp/sakura/
公式note(毎月第2,4日曜の練習日更新)https://note.com/ensemblesakura
公式Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100057414580557
公式Twitterhttps://twitter.com/sakuraoke?t=xZ9PrGeCp4WgLrkQEBKgkA&s=09
♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬
