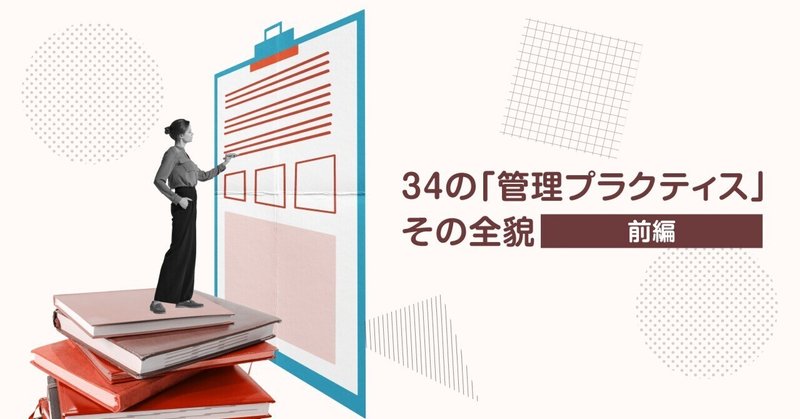
34の「管理プラクティス」、その全貌【前編】 ITサービスマネジメントを成功に導くノウハウが満載
「ITIL® 4」を構成する書籍には、まず「ファンデーション」「CDS」「DSV」「HVIT」「DPI」「DITS」の6冊があります。それだけではありません。これらのほかに、34冊の「プラクティスガイド」が存在します。
34冊……非常に多いように見えますが、一歩ずつ前進していきましょう。本記事がその導入になればと思います。
管理プラクティスは、サービスマネジメントに関する業務の遂行に必要な管理方法や実践方法を、目的別に34個に分類したものです。
「ITIL® 4」では、管理プラクティスを「業務遂行や達成目標を実現するための組織の一連のリソース」と定義していますが、要するにすぐに実践に応用できるようにまとめたものであるということです。
ちなみに「ファンデーション」「CDS」「DSV」「HVIT」「DPI」「DITS」の6冊の主要書籍は、紙媒体と電子媒体の両方で配布されています。一方で技術の変化や管理の考え方に関する新しいナレッジを迅速に反映できるよう、「プラクティスガイド」は電子媒体(月間または年間サブスクリプション契約)のみで提供されています。
全34テーマ「プラクティスガイド」を紐解く
それでは、34冊ある「プラクティスガイド」はどのようなラインアップになっているのでしょうか。各ガイドのタイトルをまとめると、以下になります。

「プラクティスガイド」は「一般的マネジメントプラクティス」「サービスマネジメントプラクティス」「技術的マネジメントプラクティス」という以下の3つのカテゴリーに分類されています。
●一般的マネジメントプラクティス:ITサービス領域に限らず、広く一般的な事業領域で実践されているプラクティスから取り入れられたもの。
●サービスマネジメントプラクティス:以前からサービスマネジメントで使われているプラクティス。
●技術的マネジメントプラクティス:ITの技術的な管理として培われたプラクティスから取り入れられたもの。
このように、「ITIL® 4」の管理プラクティスは伝統的なサービスマネジメント以外の分野からも取り入れられているため、サービスマネジメント以外のプラクティスと統合して活用することも意識されています。
また重要なこととしては、「プラクティスガイド」はいずれも、以下の構成になっていることが挙げられます。
1.ドキュメントの概要
2.プラクティスの目的や用語などの基本情報
3.バリューストリームとプロセス
4.組織と人材
5.情報と技術
6.パートナーとサプライヤ
7.注意事項
この内容を見て、「どこかで見覚えがある文字が並んでいるな」と思った方もいるでしょう。上記3~6の項目は「ITIL® 4」の実践の肝である「サービスマネジメントの4つの側面」に沿った記述になっています。特に各プラクティスがバリューストリームにどのように関わるのかという内容については以前の「ITIL®」では触れられていない部分であり、最新のITサービスマネジメントにモダナイズするときに大変参考になります。その他の側面も含めて「ITIL® 4」の管理プラクティスはとても洗練された内容にまとめられていますので、ぜひ実践に活かしてください。
※「4つの側面」と「CDS」の詳細な説明はこちら
現状、英語版のみの提供なので、日本人である私たちにとっては読破するのは正直、大変です。
しかし、実務に応用できるノウハウが満載な「ガイドブック」ですから、ITSMに携わる方にとっては避けて通れないことも事実です。
「後編」では、「ITIL® V3」にあった「管理プロセス」と、「ITIL® 4」における「プラクティスガイド」との違いについて、解説します。
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logoTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
