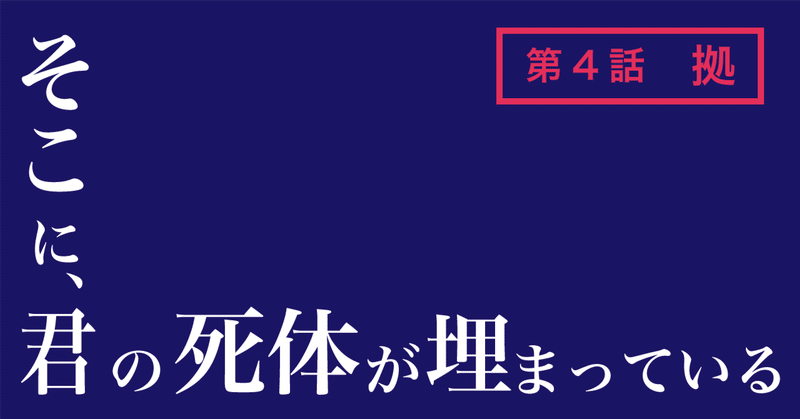
「そこに、君の死体が埋まっている」第4話 拠
堀龍起は、相変わらずあの大きな家に住んでいた。西洋風だったガーデンは六年前の白いテーブルと椅子がなくなって、アンティーク調のものに変わっていた。ピザ窯とコンロが増えているのは、料理研究家だという新しい母親の影響だろう。
部屋の位置は変わっていない。二階の南向きの窓がある部屋だ。朝は決まって、七時に起きてカーテンを開け、眠そうな表情でその日の天気を確認している。家を出るのは、七時五十分。学校までは徒歩で約二十分ほど。朝のホームルームが始まるのは八時二十分からだが、いつもゆっくり余裕を持って歩いていた。
部活はやっていないが、生徒会に入っている。父親と祖父が医者であることを考えれば、当然、卒業後は医学部のある大学に進学するつもりでいるのだろう。学校ではクラスメイトと過ごし、休憩時間は生徒会室か図書室にいることが多い。
相変わらずクラスの中心人物で、男子とも女子とも交流があった。特に仲がいいと言える奴はいない。みんな平等に広く接しているようで、誰かと付き合っている様子もなかった。
放課後は生徒会の活動を終えるとその足で家に帰り、月、水、金は家庭教師らしき男が訪ねてきていた。火と木は近所でピアノ教室をしている家に通っていた。
土日は家で過ごすことが多い。だが、たまに町にある無駄に駐車場の広い大型ショッピングモールに遊びに行ったり、新しくできた飲食店に行ったりもしている。それも五、六人の大人数でいくことが多かった。六年前の夏休みは、そのほとんどを俺と二人きりで過ごしていたのに……
今は、特定の誰かに対して、何か酷いことをしている様子はとくにない。
家族との関係も良好なようで、祖母が話していた噂の新しいお嫁さんとも本当の親子のように思えるくらい、一緒にいるのを見たが違和感は何もなかった。
堀龍起は、ごく普通の、どこにでもいる高校生だった。
俺は堀の行動パターン、行動範囲を全て把握。同じ教室で過ごしている————それも、席が真後であることから授業で関わることはあったが、当たり障りのない会話をして、日々をやり過ごしていた。
そうして考えた結果、やはり人目が多い校舎での殺害は難しい。誰もいない場所で、人知れず殺す。そうして、誰かにこの罪をなすりつける。
しかし、どうやって二人きりになればいいのか。殺意を隠したまま、自然にそういう状況を作るにはどうすべきか、あれこれ思案を巡らせていた頃昼休みに、堀が言った。
「理くん、来週の土曜日って暇?」
「え……?」
「ほら、理くんが戻ってきてから、まだ歓迎会をしていないだろう? 町外から来た奴は別として、小学生の時同じクラスだった奴何人かで、歓迎会をやろうって話になったんだ」
堀が提案した場所は駐車場が無駄に広い大型ショッピングモールの向かいにある、アミューズメント施設。カラオケやボーリング、ゲームセンターが一緒になったビルだった。堀と二人きりというわけではないが、機会はある。あの周辺、土日の治安はあまりよくない。町外から来たいわゆる暴走族が何度か問題を起こしている場所だ。数日前にもそこで暴行事件が起きたとかで少しニュースになっていた。そいつらにやられたことにして、殺してしまおうと考えた。
「ああ、別に、いいけど……」
ついに殺せる嬉しさで、口角が上がりそうになるのを必死にこらえて、快諾した。できるだけ自然に、別になんとも思っていないように。
「本当!? よかったぁ」
堀は能天気に嬉しそうに笑っていたが、俺は頭の中で何度も殺していた。
* * *
「————で、他の奴らは?」
「もうすぐ来るんじゃない? 先に入って待っていようよ」
現地集合ということで、俺は集合時間の五分前に着いた。だが、店の前にいたのは堀だけ。今日は女子も含めた十人で集まるはずだったのに、他の奴は誰一人来ていない。先に受付で部屋だけ確保しておいた方がいいと、会員証を持っている堀が受付も済ませていた。
「他のみんなが来たら受付で部屋の番号をいえばいいようにしておいたから、行こう?」
「ああ……」
仕方がなく堀についていくと、広いカラオケルーム。ここ数年の間にできた施設ということもあって、中はとても綺麗だった。隣の部屋からはどこかで聞いたアニソンを熱唱して盛り上がっている声が漏れて来ている。入る前に受付でもらった、飲み放題のソフトドリンク用の取っ手付きのガラスコップにコーラとメロンソーダをそれぞれ注いだものをテーブルの上に置く。荷物をソファの上に下ろして座ると、広い部屋だというのに堀は俺のすぐ隣に座った。
その距離の近さが、六年前に初めて堀の部屋に入った時と同じに思えて、反射的に俺は座る場所を堀の斜め前に座り直す。
「どうして逃げるの?」
「に、逃げてない」
それでも、堀は追って来た。またすぐ隣に座って————
「嘘だね。いつも僕のことつけてたくせに……」
「え?」
俺の手首を掴んで、放さなかった。
「は、放せよ!」
「嫌だ。僕が気づいていないとでも思った? 理くん、僕のことずっと見てたよね? ストーカーみたいに、学校でも、学校の外でも……どういうつもり?」
どういうつもりも何も、お前を殺すための計画を練っていた。そのために観察していただけだ。けれど、そんなこと口が裂けても言えるはずがない。
「ずっと待っていたんだよ? 理くんから話しかけてくれるの……」
「なんで……俺が……お前に話しかけなきゃならないんだよ」
「なんで? それはこっちが聞きたい。どうして、僕の前からいなくなったの? 僕たち、あんなに愛し合っていたのに」
「は……? 愛し……あっていた……?」
何を言っているのかわからなかった。
————愛し合っていた? 誰が? 誰と誰が?
「連絡の一つもよこさないで……僕はずっと、君が帰って来るのを待っていたんだよ? それなのにさ、やっと帰って来たと思ったら、素っ気なくて————これじゃぁ、まるで、僕たちの間に何もなかったみたいじゃない。少し傷ついたけど、でも、君は僕を見ているのがわかって…………すごく嬉しかった。君なりに何か考えがあるのかなって、ずっと我慢していたんだよ? どうして、何もしてこないの?」
「待てよ、ちょっと、待て……意味がわからない」
「わからない? 何が?」
「俺は、あの日、あの夏、お前を————」
殺そうとした。山の中に埋めた。自分を殺そうとしていた人間から、つけまわされて、どうして嬉しいんだ?
まさか、本当に————
「お前……本当に、覚えてないのか?」
「……あの夏? どの夏の話?」
堀は首を傾げている。覚えているようには見えない。演技をしているようには見えなかった。覚えていないなら、どうして……「相変わらず、可愛いね」なんて、言ったんだ?
「理くん。それって、もしかして俺が覚えていない時期の話? それなら、何も覚えていないんだ。でも、証拠はある————」
堀は自分のポケットからスマホを取り出すと、動画を再生して俺に見せる。あの時、消したはずの動画だった。
「この動画を見たんだ」
繋がったまま堀の命令で言わされたセリフを泣きながら喋っている、小学五年生の俺が映っている。
『……あいしてる。龍起くん』
「————ほら、僕たち愛し合っていたんでしょう?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

