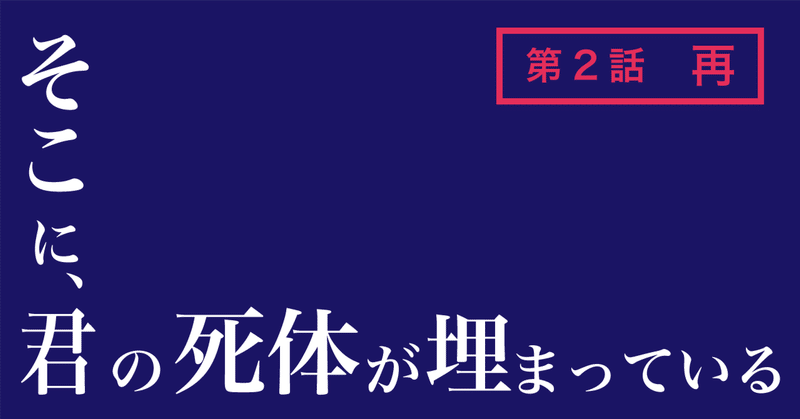
「そこに、君の死体が埋まっている」第2話 再
あの夏から六年。盆も正月も、一度もあの町には戻っていなかった。転校してすぐにバスケ部活に入り、部活を口実にして避け続けた。あの町で起きた出来事は思い出さないように、必死に部活に打ち込んで、部活を引退した後は、高校受験を口実にして……
全部、あの夏に置いてきた。
俺のところに、警察が訪ねてきたことは一度もない。
テレビやネットで山中で死体が発見されたというニュースを目にしたときは、彼のことじゃないかと何度も不安になったが、彼の死体は、まだ見つかってはいないようだった。例え見つかったとしても、俺が犯人だという証拠なんて、ないと思う。当日は大雨が降っていたし、あの裏山をわざわざ掘り返そうとするような奴もいないだろう。当時のクラスメイトとも一切連絡を取っていなかったし、あの町がどうなっているか、彼の死体が見つかっているか調べる勇気はなかった。
しかし、高校生になって初めて彼女ができて少し浮かれていた頃、突然予想もしなかった問題が起こる。両親が離婚した。原因は父の不倫によるもので、母は俺を連れて実家があるあの町に帰ると言い出した。父は不倫相手が取引相手の社長令嬢だったらしく、また職を失った。さらに妻子がいることを隠していたこともあり、多額の慰謝料を請求されている。俺には父を選ぶという選択肢は最初からない。母について行くしかなかった。二年だけ我慢して、大学か専門学校……進学が無理であったとしても、絶対に他の町に就職しようと決めた。
この六年、何も起こらなかったのだから、きっと大丈夫。そう思って、町で唯一の公立高校に二年生になった五月から母の旧姓である山中理として、戻ってくることになった。
クラスの八割があの当時、同じクラスメイトだった生徒で、残りの二割は他の高校を落ちて仕方なくこの町まで通っているらしい。「知り合いが多いんだから、きっとすぐに馴染めるでしょう」と母は言っていた。校舎は小学校のすぐ隣にあり、彼が埋まっているあの裏山からも近い。あの夏より身長もぐんと伸びたし、苗字も変わっているから、気づかれないことを願って教室に入った。
「転校生の山中理くんです」
担任の教師に紹介され、黒板の前に立つと教室全体が見渡せて、全員の顔がはっきりと見える。確かになんとなく、面影のある生徒が何人かいる。みんな成長したから、誰が誰かまではわからなかった。そもそも、当時のことは思い出さないようにしていたため、名前を聞いてもおそらく何一つ思い出せないだろうと思った。
ところが、窓側の後ろから二番目の席に座っていた男子生徒の顔を見て、俺の中で鮮明に、あの夏の記憶が蘇る。
「それじゃぁ、席は、堀の後ろの席————あそこを使ってね」
彼と同じ苗字で、彼と同じような顔をしたその男は、あの当時のように眩しい笑顔を俺に向けて、言った。
「久しぶりだね、理くん」
記憶の中にあった彼とは違う、低くなったこの男の声が、春だというのに、俺の指先から熱を奪っていく。
ど
う
し
て
生
き
て
い
る
喉の奥から出そうになったその言葉を飲み込んで、俺は笑い返した。
「ごめん、誰だっけ?」
精一杯強がって、何も覚えていないふりをした。
* * *
「なんも覚えてないとか、酷いなぁ。まぁ、僕も正直あまり覚えていないんだけど……」
彼は————堀龍起は、小学五年生の春から夏にかけての出来事を一切覚えていないと言った。夏休みに交通事故に遭い、その後遺症らしい。
「あの時は本当にびっくりしたよね。夏休みが終わっても龍起が全然学校に来なくてさ……秋になって戻ってきたよね」
「みんな心配してたんだよ。ひき逃げにあって、しかも記憶喪失なんてさ、なんか漫画とかドラマみたいな話だねって」
昼休み、当時同じクラスメイトで、特に堀と仲が良かった何人かが集まって、昔の話をした。残念ながら、誰一人として名前を聞いても思い出せなかったため、正直に「何も覚えていない」と話すと、なんとなくしか覚えていないようなどうでもいい思い出話を聞かされる羽目になった。
適当に相槌を打って、全部聞き流して、堀の様子を伺う。交通事故なわけがない。俺は確かに、あの時、この手で殺して、山の中に埋めた。
まだ小学生だったとはいえ、雨水で湿った重たい土を人一人埋めるのに十分なぐらいに掘って、自分より重たい人間を引きずり入れて、埋めたんだ。仮に実はまだ生きていたとしても、そうなると土地の中から自ら出てきたということになる。あの大雨の中、近くに誰か別の人間がいたとも思えない。
「でも、理くんが転校してきた日のことは覚えているよ。僕より背が低かったよね? 今、身長何センチ?」
「……百八十くらい」
「伸びたなぁ……僕より三センチは高いじゃん。でも顔はあまり変わってないね。そのまま大きくなったって感じ」
「お前だって、そのままじゃないか」と言いたかった。変声期を終えて、声も……当然身長だってあの頃とは違うのに、相変わらず眩しいくらいなんの邪心もなさそうな笑顔を浮かべているのが信じられない。俺はお前を忘れるために必死だったのに、こんな理不尽なことがあってたまるか。今でも夢にお前が出てくる度、悪夢にうなされる夜があるのに……
「こーら! いつまで喋ってるんだ! 授業始めるぞ!」
「げっ! やべっ!!」
午後の授業開始のチャイムが鳴って、みんな慌てて自分の席に着いた。俺の前の席に座っている堀はそのまま動く必要がなく、ただ前を向けばいい。当然そうするものだろうと思っていたが、その前に堀は俺にしか聞こえないくらいの小さい声で————
「相変わらず、可愛いね」
あの時と同じ笑顔で、そう言った。
その瞬間、走馬灯のようにあの夏の地獄が蘇る。
またこの男に、支配される絶望と恐怖で体が震えた。
もし、本当はあの日のことを覚えているなら、俺はあのことをネタに脅されるだろうし、覚えていなかったとしても、堀龍起という人間は、自分が欲しいと思ったものはなんでも手に入れる。そういう人間だ。
六年前と変わらず、堀はこの町の有力者の息子で、俺はただの家の息子。祖父はすでに定年退職して働いていないが、母は堀家の親族が経営している店で働いているし、祖母は婦人会の会員を続けているらしい。できることなら関わりたくはないが、この町で暮らしていく以上、避けては通れない。
ずっと蓋をしてごまかしていた感情と、この体に残っているあの気持ちの悪い味、むせ返るような悪臭、虫のように全身を這う感触が、また俺を地獄に引きずり込もうとする。同じ屈辱を味わう前に、どうにかしなければならない。今度こそ、確実に、俺は、堀龍起を殺さなければならない。
叩いて埋めるだけじゃ、ダメだったんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

