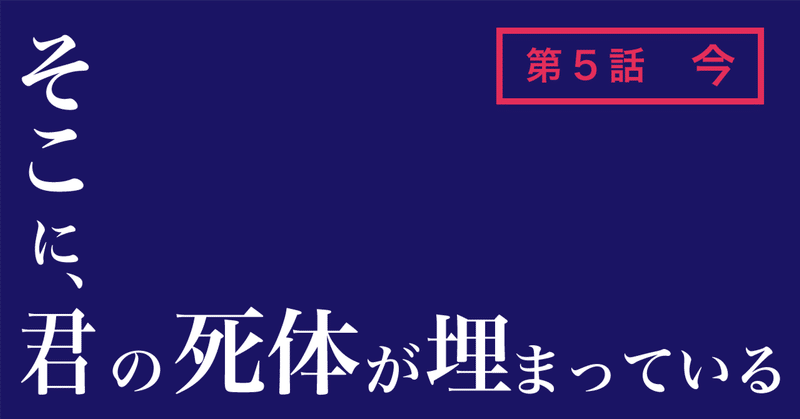
「そこに、君の死体が埋まっている」第5話 今
「僕は事故に遭う前の半年くらいの記憶がない。だから、君との間に何があったか、何も覚えていなんだ。君が四年生の秋に転校して来たことは知っている。でも、動画を見て僕たちのが愛し合っていたことがわかった」
堀の話によれば、事故の衝撃で記憶がないのは五年生の春頃から事故にあった夏休みの間と、意識不明で入院していた数日間。俺が最初にこの町に転校して来たのは四年生の秋頃で、その年の秋と冬の記憶はある。そもそも、記憶喪失であることが判明した時は、その記憶すらなかったらしい。自分が何者かもわからなかったが、家族やクラスメイトたちの協力で徐々に思い出した。それでも、春頃から事故にあった夏の記憶だけは未だにないのだと言った。
「君は僕が学校に戻った時にはもう、転校していなくなっていた。教室に君の姿はなかった。でも、どうしてかわからないけど、ずっと君のことが気にかかっている自分がいた。記憶がないのはとても怖いことだったよ。でもね、PCに日記と動画と画像が残っているのを見つけたんだ。ちょうど記憶がない春の終わり頃から、夏休みの終盤までほとんど毎日のように書いてあった」
堀が使っていたその日記は、スマホ用のアプリと同調できるものでありIDとパスワードさえ入力すれば、いつでもスマホから閲覧できるようになっている。スマホの方は俺が全部消去して川に捨てたため持っていなかったが、PCはログイン状態で保持されていた。俺に見せたのは、その日記の中にあった動画の一つだった。
堀のいう「愛し合っている」二人の様子が、堀の視点で歪曲されて書かれた気持ちの悪い文章が並んでいる。全て自分に都合がいいように、まるで、本当に「愛し合っていた」かのような書かれ方をしていた。俺からしたら苦痛でしかなかった出来事が、全て美化されて、読んだことはないが、官能小説のようなポエムのような————とにかく気持ちが悪い。
あの時、俺が全て削除したデータの一部がネット上にアップロードされていたと知って肝が冷える。個人用の鍵アカウントだが、何かの拍子に流出してもおかしくはない。
「僕は君のことが好きだった。多分、初恋だったんじゃないかな? それがいつからなのか正確にはわからないけど、でも、君を初めて見た時から……僕は理くんが好きだった」
「好き……? お前が、俺を……?」
信じられなかった。それなら、どうして、あんなに酷いことをしたのか、理解できない。ただただ気持ち悪かった。嫌だった。俺はお前なんて大嫌いだった。だから、お前から逃れるために、山の中に埋めたのに————殺したんだ。俺はお前を殺そうとした。それなのに、どうして……
「そうだよ。好きだから、愛していたから……だから、僕は理くんに会いたくて、会いたくて、毎日、この日記を見て耐えてきた。僕はあまり遠くに行けないから、理くんが夏休みや冬休みに帰ってきていないか、何度も君の家を見に行ったよ。お祖父さんの家だって聞いていたし、君に会えば、僕の失った記憶も、全部取り戻せるんじゃないかって————ねぇ、教えてよ、理くん。僕に一体何があたの? あの夏休み、僕たちは毎日のように会っていたんだよね?」
俺の思い出したくない記憶を、あの夏の話を聞かせろと、何も知らずに求める。今のこいつには、俺に対する罪悪感はない。もともとそんなものすらなかったようだが、なぜ殺されかけたのか、その理由もわかっていない。全部自分のいいように理解して、俺が話せば失ったその美化された記憶を取り戻せると思っている。
「ふざけんな……!! お前なんかに————」
話してやる義理はない。あんな悍ましいことを、俺の口から言葉にしたくない。自分のしたことも覚えていないこんな奴、今すぐこの場で殺してやろうと思った。
俺はいつでも殺せるように持っていたバタフライナイフが入っているカバンに手を伸ばした。その時だった。
「おお、ここか! 待たせたな!」
何も知らないクラスメイトが三人、部屋に入ってきた。
「え、なになに? なんかお前ら、距離近くね?」
「あれ? もしかして、邪魔だった?」
てっきりまた騙されて、誰も来ないのかと思っていた俺は拍子抜けする。それから続々と人が入ってきて、まったく嬉しくも楽しくもない歓迎会が始まった。
* * *
俺はしばらくは我慢して歌を聴いていたが、耐えきれずに一人でトイレに行った。カラオケなのだから歌えと言われて、仕方なく一曲だけ、流行りの曲を歌ってからだ。この町の高校生が遊ぶ場所はここくらいしかない。みんな歌い慣れているようで、それなりに点数も高く、俺は自分の点数の低さが高くも低くもないことが恥ずかしかった。
さらに、一人とてつもなく歌が上手い女子がいて、みんなその子が歌うと釘付けになっている。その隙に、いつの間にか俺の隣に陣取った堀が手を握ってきたのが気持ち悪かった。この場にいたくない。でも急に座る場所を変えるのは不審に思われる気がした。一度、トイレに外に出て、戻ってきたら堀から離れた場所に座れば不自然ではないだろうと、そう思った。
男子トイレには誰もいなかった。最近できた施設ということもあって、掃除が綺麗に行き届いている。前の町でもこういう施設を利用したことはあるが、そこは古くてトイレも汚い印象だった。用を足していると、誰かが入ってきた足音が俺の後ろで止まる。他が空いているのに、なぜか並ばれていることを不審に思った。妙なプレッシャーを感じて、早々に済ませて洗面台のほうへ行くと、鏡越しにその誰かの正体がわかる。
堀だ。
堀は用を足すわけでもなく、ただ俺の方をじっと見ていた。鏡の作りなのか、角度なのかわからないが、その顔はとても歪んでいるように見えて、気持ち悪い。気づかないふりをして、かざせば自動で出てくる水で手を洗っていると、堀は俺に後ろから覆いかぶさった。
「やめろ! 何するんだ」
「ごめん。でも、こうでもしないと、理くんは逃げるだろう?」
「放せよ……!!」
「嫌だ、ねぇ、教えてよ。さっきの続き」
肩に顎を乗せ、下半身を俺に押し当ててくる。それがあの夏の地獄を彷彿とさせて、俺は動けなかった。ただの非力な小さな子供だった頃とは、違うのに。身長だって、あの頃は俺の方がはるかに小さかったけど、今は逆だ。俺の方が少しだけど背が高い。部活で鍛えた筋力はそこまで衰えていない。抵抗できるはずだ。こんなの、簡単に振りほどけるはずなのに、恐怖の方が強かった。
「ずっとこうしたかった。理くんに触れたかった。きっと、僕と君の席が逆だったら、僕は耐えられなかったと思う。ずっとずっとずっと君とあの動画のように、触れ合いたかった」
「やめろ……俺は————」
あの頃とは違う、成長して骨ばった堀の手が、無理やり俺の顔を横向かせ、無理やりキスをされた。押し込まれた舌が気持ち悪い。虫のように蠢いて、逃げても逃げても、俺の舌を追いかけてくる。どうして、なんで、また、俺はこんな目に————
「んっ……ぅ」
一瞬であの夏に逆戻りした。あれから六年も経ったのに、俺はまた、何もできずにこの男に支配されてしまうのかと思ったその時、妙な違和感を感じる。違う。あの時と、違う。彼の舌は、こんな風じゃなかった。そんな気がした。さらに、彼の左目のまぶたの端には、小さな黒子がある。近くで見ないとわからないほど小さいが、変わった形をしているとぼんやり思ったのを思い出した。
今の堀には、それがない。
誰
だ
こ
れ
は
これは堀じゃない。
そう気づいた瞬間、体が動いて、俺は堀を————堀じゃない誰かをおもいきり突き飛ばしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

