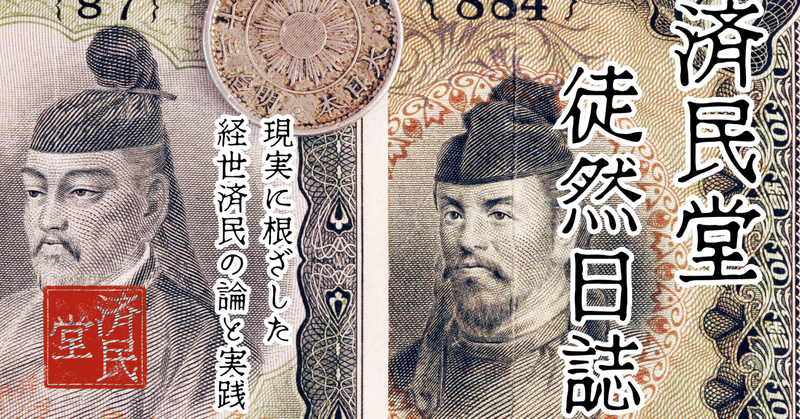
日本の歴史を考え直す その9 歴史を見る大きな視点
歴史や神話を勉強しようと思い立って関連する本を読み始めてみても、出来事や史料、固有名詞の羅列とそれに関する学説の展開が続き、なにが問題になっているのかよくわからないままに挫折してしまうことは多い。専門書と呼ばれる部類に入る本を選べばそういうことになるし、一般向けに出されている本ならいいかと言えば、今度は「昔の人も大変だったんですね」とか「こういう精神は守らなければなりません」みたいな教訓めいた、説教くさい話になりがちで、今後の世界や社会の動向を考察する土台となるような知見が得られるというようなものではない場合が多い。そうなると発展史観のようにすべてを理性の自己実現のためや階級闘争の物語として描くような、デウス・エクス・マキナな三文芝居のほうがまだわかりやすくて受け容れられやすいということになる。
とはいうものの、大きな枠組みとしての歴史観というものはやはり必要である。これがなければ歴史を語ることは本当にただの事例の羅列に陥ってしまうからであり、マルクス史観や皇国史観、あるいは「『万葉集』は日本古来の精神の発露!」みたいな安いナショナリズムの片棒担ぎでもないような枠組みがなければならない。
いまのところそういう大きな歴史の枠組みとして便利だろうと思うのは、歴史を「人々を定住させ、農耕(生産活動)に従事させてそこから税金を取るための仕組み作りと、その利権を巡る争い」をベースとして理解しようというものである。「それが階級闘争じゃないのか」「唯物史観そのものだ」と言われそうだが、そうではない。マルクス史観では下の階級が上の階級を倒すという図式だが、私は実際には世界の支配者層の血縁者同士の縄張り争いみたいなものだったと思っている。また生産手段に関する諸事情が歴史のすべてを決定するわけではないにしても、根源的な部分はやはり生産手段(とくに食料・燃料)が肝になることは間違いないだろう。なによりも私には人類が一方向に向かって「進歩」しているとはとうてい思えない。
さて、定住して体制に組み込まれる勢力と、体制からこぼれ落ちて下層民として扱われるものの、現実では力を持つ勢力というものも生まれてくる。「定住=体制派と流浪=アウトロー」の力学も、人類史を考える上で重要なファクターである。
いまの人類に最も近い形になったのが400万年前で、定住が始まったのが1万年前。最古の文字記録は5,000年前のシュメール人のくさび形文字であるから、有史はすべて定住後の世界を扱っているわけだが、実際には人々は人類に不向きな定住を強いられている。だから常に体制としては定住・農作を被支配民に強制し、被支配民はそこから逸脱しようとする力が働いている。
この枠組みで考えるとわかりやすい例として、仏教受容を考えてみる。701年に始まった律令体制というのは原始共産制のようなもので、それまで各豪族が私有していた土地と奴隷をすべて天皇家のものにして(公地公民)、その管理を各豪族に地方の国司・郡司の任命を通じて委託するという制度だ。律令体制のもとでは僧侶になるためには政府の許可が必要だった。なぜなら律令体制は土地に人をしばりつけ、そこで生産活動に従事させてその上前を税金として徴収する制度だから、勝手に土地を放り出して僧侶になるような人たち(これが優婆塞と呼ばれた)が増えては困るのである。これは体制の側から見ればそういう話だが、反体制側からみれば仏教を理論的な支柱にして、体制からはみ出る人たちを統率し、政権に対して圧力を加えることができる。仏教受容か否かという論争の本当のポイントはここにあったのではないか、ということだ。仏像だとか仏教の教義をいくらこねくり回してもいま一つわからなかったのはこういう構造だ。
現代に置き換えると、ちゃんと会社勤めをして、家と自動車をローンで買って結婚し子供を産むのがまっとうな社会人だが、そうではない人は落伍者ということになっている構造における「寝そべり族」と、律令制における優婆塞とは同じ位置づけになる。
この構造は古代ローマでも同様である。古代ローマはBC753年にロムルスによって建国されたとされ、AD395年に東西分裂、西ローマ帝国は476年に滅亡、東ローマ帝国は1453年に滅亡する。古代ローマこそ、西洋の文化の起点だとかローマ市民の誇りがどうだとかいろいろ言われ、事象の散発的な羅列で捉えどころがないように思えるが、「人々を定住させ、農耕(生産活動)に従事させてそこから税金を取るための仕組み作りと、その利権を巡る争い」があったことは日本と同じである。
たとえばBC367年に「リキニウス・セクスティウス法」が制定される。これは高校の世界史でも必ず習う法律だが、その意味するところは「土地の占有面積に上限を設ける」というものであった。ローマ市民は土地を賃借料を払って占有することができたが、ローマの拡大に伴って貧富の格差が生じたため、これを是正するために占有面積の上限を定めたのがリキニウス・セクスティウス法である。ところが実際には、貴族たちはこの法律を無視して大土地所有を続けていた。そこでBC133年から「グラックス兄弟の改革」が始まる。これはリキニウス・セクスティウス法で定められた上限の土地面積を遵守させ、上限を超えて占有されていた部分を無産市民に分配しようという試みであった。当然貴族たちの猛反発を受け、グラックス兄弟は兄も弟も暗殺されて改革は頓挫してしまった。
当時のローマ市民はみずから武装して兵士として戦うのが誇りでもあったから、無産市民が増えると、戦闘に従事する兵士の質が下がる。これはローマの国防上も問題なので対応が続けられ、BC107年にマリウスによって軍制改革が行われる。それまでは戦争のたびに散発的に軍を招集していたのをやめ、無産市民を常備軍として編成することにし、戦功を挙げた兵士には土地を割り当てることにした。
ローマはその後も勢力を広げていき、帝政に至る。BC27年にオクタヴィアヌスがはじめてアウグストゥスの称号を与えられるも、この時点では皇帝も「プリンケプス」つまり「ローマ市民の第一人者」であり、他の市民と平等であるという建前が取られていた。それがいつのまにか、皇帝はドミヌス(dominus)つまり市民に対する「主人」としての(dominantな)立場に変質していく。このプロセスも「属州の総督任命権がどのようにして皇帝に集まっていったか」という問題として研究されている。初の武家政権である鎌倉幕府も、その権力の根幹は守護・地頭の任命権を朝廷から勝ち取ったというところにある。
このように「人を定住させ管理するメカニズムとその管理権を巡る争いと、その枠組みから外れる人たち」という図式を大きな枠組みとして、関連する神話や逸話、思想や教義を位置づけてゆくというふうにすれば、自分なりの歴史観というものを形成しやすいだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
