
どうしても不登校を「克服?」したいなら
長男の2年生途中〜4年生になるくらいまでの不登校経験を元に、感情論と経験論だけで、不登校を克服?する方法を考えてみました。
?マークをつけたのは、学校に戻ることが克服かどうか自信がなかったからです。不登校をダメと思っているわけではありません。克服しなきゃダメだって思わないでください。それぞれのお子さんの特性があると思うので。
でも正直なところ、学校に行かなくても大丈夫、と思えても、実際は不安な大人は少なくない気がします。その方々へのアドバイスになって、結果的に親子で楽しくいきてほしいなぁ、と思っています。
1,学校から離れて過ごす時間を作る覚悟を親が持つ
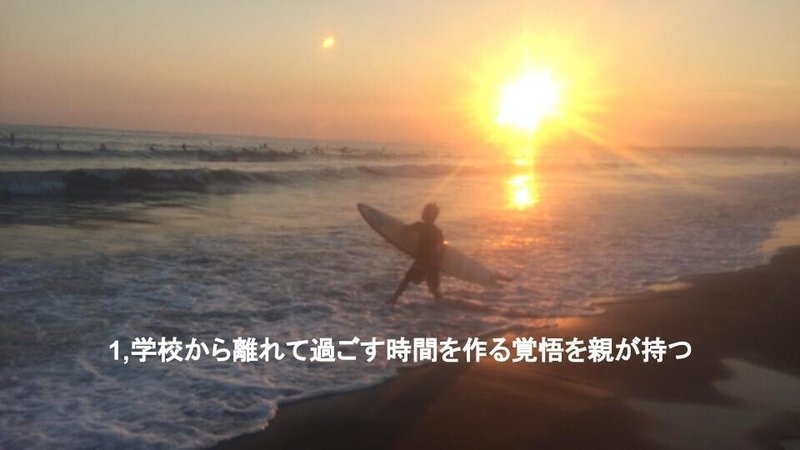
遅れたらどうしよう、友達がいなくなってしまう、先生に迷惑がかかる・・・正常な判断が親もできなくなり、これはなかなかできません。ただし、当事者の親は、そんな状況を受け止めるキャパを持ち合わせていません。冷静でいなければならない、冷静に努めるのだ、と勝手に思っています。あとで思い返したら、お恥ずかしい、冷静さのかけらもありませんでした。必死でした。
学校の先生に、「休んだ日の倍の日数が完全回復にかかる期間です。」と言われれ、最初は焦りました。が、これ、合ってました。
この「学校から離れることへの恐怖」の裏には、親に、潜在的な「比較」が存在していませんか。みんなより遅れる=この子は負け組だ=このまま遅れてしまったらこの子が困ってしまう・・・恥ずかしながら、私はこの状態に陥っていました。
2,親ではない誰かと過ごす時間を作る
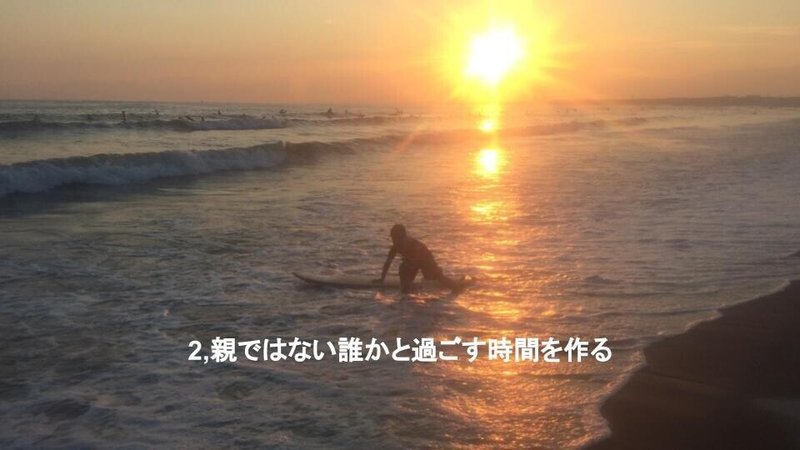
学校にいないと、親子で過ごす時間が増えます。良くも悪くも、です。ついつい、行かせようとする方向に話をしてみたり、いらぬ誘いを子どもにしてしまったりします。
我が家の場合は、親以外の大人がいっぱいいました。たくさん頼って、たくさん助けられて、楽しませてもらいました。
習っていたバスケットボールスクール。コーチは優しく声をかけてくれました。それから、周囲の友達も声をかけてくれたり、その保護者さん発案でBBQしたり。周囲の人が、子供だけでなく保護者である私たちにも普通に声をかけてくれること、特異な目でみないでくれたこと本当にうれしかったのです。よく考えてみると、学校の外だから、学校に行く行かない、は関係ないんですよね。言い方変えればそこにこだわっているのは親だけで、周囲は気にしていないんです。楽しそうに遊んでいました。
もうひとつは、学校に行かなくなって始めた、サーフィンスクールの先生でした。たくさん褒めてくださいました。自然の厳しさと同時に、必要なことも教えてくださいました。コミュニケーションとか信頼できる大人の姿を見せてくださいました。
学校だと「人にはきちんと挨拶しなさい。」というところを、サーフスクールの先生は、「同じ場所でサーフィンしてると、いつのまにか顔見知りになって仲良くなっていくんだよ、だから海に行く時にすれ違う人には挨拶するといいよ。」と教えてくれたそうです。
スクールの先生と海に行くときに一緒になって挨拶をしていました。それから、同じ時間帯のスクールには、まったく知らない人たちと一緒になります。私もスクールに行きましたけど、綺麗な女子大生のグループさんと一緒のときがありました。
息子からも、「今日は大人のおねえさんたちと一緒だった〜。」なんてうらやましい報告があるとちょっとうらやましかったりします。
「話とかするの?」「たくさんしゃべったよ〜。」
「何をしゃべるの?」「まぁ、いろいろ〜。」
↑しばらく行けてないのですが、親子でここの雰囲気が大好きでした。
3,親が変わる(しかない!)(のに、変われないことが多い。)
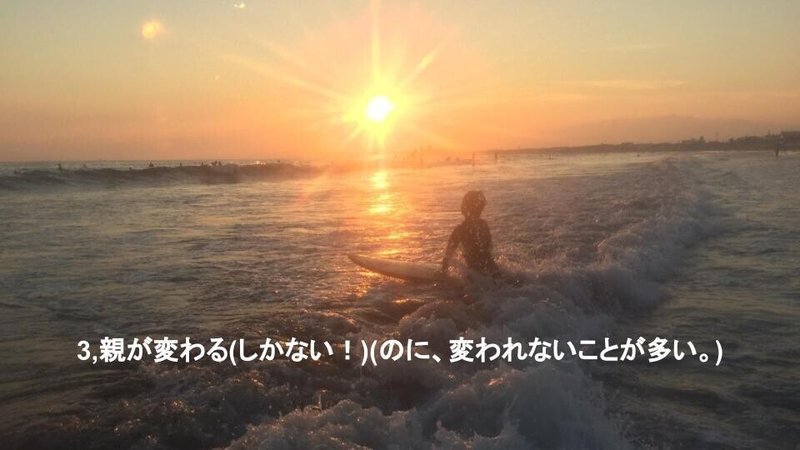
1,2,ができるようになった時は、3,は自動的にできていると思ってよい気がします。なぜなら、不登校のお子さんの保護者を見ていると、1,2,を提案しても受け入れない(受け入れられない)方が多いような気がします。そして、長引くケースほど、1,2,をせずに自分でなんとかしようと頑張ってしまったり、自分の考えや自分で教わった見地を元にどうにかしようとします。この「親の責任感」は、不登校の子にとってはさらに苦しめかねません。誰も悪くないので、親が解決しよう、と思わず周囲に頼ってよいのです。親も楽な時間を過ごしてもいいのです。
言い換えるなら、親がある程度「手放せるか」が大事になってくると思います。
以前、療育センターに私が行ったとき、冗談半分で先生が言っていました。もちろん、データとしてではなく、経験論として雑談レベルでおっしゃっていたことですが、
お父様が見えられる場合(夫婦一緒に、も含む)は、90%くらいの確率で不登校は解決すると思っています。不思議なんですけど、お父様が一緒になって動いてくれるかどうかはとても大きな力があるんですね〜。どうしても、お母様が一人で抱えていらっしゃる方も少なくないのですよ。
そして、「今日はよく、来てくださいましたね。」とおっしゃってくれたのです。この一言に、なんとなくほっとしたのを覚えています。
(番外)自然と過ごす
自然はいいですね。人間じゃ勝てません。子どもにも子どもなりのプライドってあると思うんですけど、びっくりするくらい気持ちよくそのプライドををぶっ壊してくれます。自然は怖い。でも優しい、ひたすらでかい。そして、楽しい。大人も子どもも関係なく、楽しい。
自分が感じたこと、我が子が感じたこと、それを学校の外で共有できたとき、学校というせまい組織の中で気にしていたことが、ちょっとだけ気にならない瞬間に出会えました。
言葉を交わして確認していないですけど、楽しい瞬間に合った目と目。そこには会話も確認も必要なかったのだと思います。
今回は、感情論と経験論「だけ」で不登校を考えてみました。
「行きたくないなら行かなくてもいいよ。」って思えました。でも、親は欲張りで、それでも息子には友達といっしょに楽しく学校生活を送ってほしいという思いを捨てられませんでした。学校に行かなくても大丈夫、ってもっと大きな声で言えたらいいのに、それが言えなかった、不登校経験者の親の勝手な意見です。
最後にこんなことを言うのはずるいのですが、何が「解決」「克服」か今もわかりません。とりあえず、彼は今日も楽しく生きているようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
