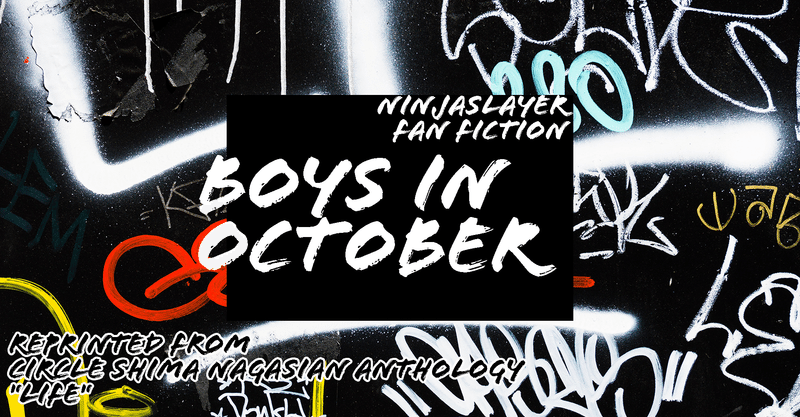
【ニンジャ二次創作】ボーイズ ・イン ・オクトーバー【アンソロジー再録】
これは2016年ニンジャ万博・ザ・ファイナルで頒布された、サークル・シマナガシアンソロジー「LIFE」へ参加した小説の再録です。2018年4月に再録可能になったのですがタイミング逃し続け今年の10月になったので今です。
【ボーイズ ・イン ・オクトーバー】
1
十月初頭、ニチョーム隔壁前。
ルイナーは、足元のビールケースから取り出したスプレー缶を、壁に吹き付けていた。ここに来てから、気が向いた時にそうしている。無機質な壁をそのままにしておくのは、何だか腹立たしかった。
やることもないから始めたことだったが、彼を遠巻きに見ていた周りのモータル達も、タギングやイラストを描き始め、黒い壁は今やキャンバスとなり、諧謔的なグラフィティだらけになってきた。
今ルイナーが仕上げているのは、黒い隔壁を夜空に見立てて、黄色い目をした棘のオバケが流星を叩き落としているデザインだ。要所が出来上がる度に、少し離れては全体を見ている。
そこに、ビール片手にやって来たのはスーサイドだ。
「よくこんなでかいの作れるな」
「昔、少しやってた。ガード下とか、シャッターとか、あるだろ」
スーサイドは答えず、コロナの栓を開ける。ルイナーが黙々と絵を仕上げていくのを、ビール片手に眺めるのが好きらしい。スーサイドが瓶をあおりだしたのをめざとく見つけ、ルイナーが右手を向けると、新たに栓を開けたコロナが渡される。
「学校っていうのは、絵とか描かないのか」
「あったけど、俺ヘタクソだったんだ」
右手でビールをチビチビ飲んでは、左手を動かし青色の上から手早く白い流星の尾を引いていく。本当は右手でやる方が上手く描けるが、細かい動作は負担が強い。
ビール瓶を持つ右の腕、その肩から肘は、今も鉄の茨で覆われている。先だってのイクサでちぎれかけたものを、アナイアレイターの鉄条網で繋ぎ止めたものだ。ニチョームには医者もいるが、ルイナーは右腕をそのままにしていた。
食い込む鉄の棘は動かす度に痛覚を苛む。それでもルイナーは顔には出さずにコロナを流し込んだ。
「……そうだ」
「あ?」
ルイナーは、グラフィティの真ん中に黒いスプレーを吹き付けながら、スーサイドに言う。
「……これ。あいつに『やれ』って言ったの、お前なんだってな」
振り向かないまま、ルイナーは自分の右腕を振る。スーサイドの返事はない。
「……アリガトな」
面と向かっても言えなかったろうし、周りに他の仲間がいたところでは余計に伝えられなかっただろう。
「何言ってんだよ。止せよ、ガラでもねえ。それ言ったらお前だって、その怪我であんだけの事やったじゃねえか。あれのおかげで俺達が助かったんだ」
ニチョームに駆け込む時のことだ。ルイナーは右腕の負傷を引きずりながらも単身囮となる事を選んだ。
「……あれは……ただのケンカだ。お前とヤモト=サンがデッドフェニックスにカチコミかけたのと同じだ。あの時帰ってきたお前ら、だいぶ酷かったぜ」
ニンジャになろうが、結局生きてきたようにしか生きられない。ルイナーは、ストリートギャングのやり方しか知らない。気に入らない相手にはケンカを売るし、売ったからには絶対に勝つ。自分がどうなろうが、勝つ瞬間にチームの頭目が立っていればいいのだ。あの時は、シマナガシを勝たせる賭けに乗ってくれたフィルギアや、フォレスト・サワタリのおかげで、命拾いした格好だ。
二度拾った命の使い道は、とうに考えている。
「俺は悪くないと思うぜ。あの娘」
わざと話を逸らすように茶化すと、スーサイドは簡単に引っかかった。
「その話すんのかよ!」
「ダメか」
「ダメだ!」
「そうか」
ルイナーは苦笑混じりに呟き、スプレーの噴き出し部から指を離して数メートル下がった。
仕上げた絵の中央に、シマナガシのグラフィティ文字が大きく描かれていた。ルイナーはスプレー缶をビールケースに放り込むと、悪くないと言いたげに頷いて、右手でコロナを飲み干した。
痛む右腕は、無差別に利己的に奪ってきたスーサイドやアナイアレイターが、救おうとした証だ。それを易々と捨てられるはずがなかった。
2
ゼン・トランス屋上。墓標のように立てかけられた狙撃銃の側で、スーサイドはコロナの瓶を弄んでいる。ニチョームのランドマークとも言えるこのビルは、ついこの間の戦争で酷い目に遭ったヤグラ337に比べれば軽傷で済んでいた。
シルバーキーというニンジャがここを『閉じて』からと言うもの、奇妙な夜がずっと続いている。01の星と立方体の月が沈まぬ常夜の世界。ガイオンのような人口太陽もないせいか、モータルたちの顔色は心なしか悪い。閉鎖空間でのストレスから小競り合いが起こり、ザクロが仲裁にかり出されることも増えてきたが、苛立っているのはスーサイドも同じだった。
このイクサで、己がいかにソウル・アブソープション・ジツに頼っていたかを思い知らされた。決して倒れずスターゲイザーを破ったアナイアレイターや、文字通りジャイアントキリングをやってのけたルイナー、遊撃と連絡に飛び回ったフィルギアに比べて、自分は何をした? そんな自問がスーサイドを責めている。
アマクダリの運用する機械兵器に対抗するにはカラテしかない。けれど自分には、それだけのカラテがない。短期集中カリキュラムで、何とか仕上がった程度のカラテだ。メンターとなるべき相手からも、クソッタレのニンジャネーム以外、ロクなものを受け取っていなかった。
――違う。受け取ろうとしなかったのは、ただ反抗するだけで満足していた自分だ。
「クソッ」
コンクリートがえぐれるほど、足元の床を蹴りつけた。
「……誰かいンのかい」
老人の声がし、スーサイドは振り返った。
「……爺さん」
その老爺をスーサイドは一方的に知っていた。スーサイドが手助けしたニチョームとアマクダリの戦い、そのどちらでも小太鼓を叩き歌を唸っていた、サイバーサングラスの老人だ。
「ジャマするよ」
片手に杖を携え小太鼓を脇に抱えた翁はするすると歩を進め、杖で辺りを叩いてからスーサイドの抉った瓦礫をどかし、アグラで座った。そこで初めて、スーサイドは彼が盲目であると悟った。
「この歳になっちまうと、若いののジャマになるからな。毎日決まった時間に、ここで歌うというわけよ」
時間の流れもへったくれもなくなったような空間で、この老爺だけが毎日を変わらず暮らしているようだった。
太鼓をアグラの前にすえ、翁は言う。
「今は随分静かになったもんだ。爺には何も見えんが、あの時の音は忘れん。イクサの音、鬨の声、若いの達の声もなァ」
翁は太鼓のバチでトントンと床を叩いた。
「よく、あんなイクサのアトモスフィアを生き残ったなァ。若いの」
「生き残っただけだよ。何もしちゃいない」
スーサイドの拗ねた物言いを翁は笑った。
「命がありゃあ、納得できる次の機会が来るモンさ。それまでに、何ができるのか知恵を絞りゃいいんだ。自分をくさすこたァない」
トトン、トトン。小太鼓の小気味良いリズム。
「……知恵が出なかったら」
「誰かの知恵を借りる。三人集まればナントカなる。ミヤモト・マサシの言葉だ」
三人。今、サークル・シマナガシは三人しかいない。体が半壊したデカブツと、無口な男と、苛立つ自分。ヘラヘラしながら煙に巻く四人目は、ヤモトと街の外だ。
フィルギアの不在は、スーサイドに微かな心細さをもたらしていた。あんな奴だが、シマナガシにとっては重要な緩衝材であり、様々な折衝を引き受けてきたネゴシエーターだった。
そのフィルギア抜きで、いつ明けるともしれない奇妙な夜を乗り切ること。まずはそれを考えないといけなかった。
スーサイドは、翁の知恵を受け取ることにした。出来ないことを数えるよりは、何か動いている方が気も紛れる。
「……アリガトゴザイマス」
「なんの、年寄りの説教さ」
スーサイドは首を振った。そして思いなおして言葉にした。
「いいや、助かった」
翁はゆっくり頷くと、「ハッ!」と小粋なかけ声を合図に歌い出した。
「ホロウ、ホロウ、ナッシン、エンター、サツバツ……」
翁のショッギョ・ムッジョの即興詩吟を聴きながら、スーサイドは考える。
せめて、居場所と仲間に、今できることはあるか?
「……あるじゃねえか」
何かに気づいたスーサイドは翁に深く一礼し、屋上から飛び降りた。
3
粋桃。シマナガシが間借りしている仮拠点のバーで、アナイアレイターは床に倒れ込んでいた。これで何度目か分からない失敗と失態だ。
「チクショウ!」
殴りつけたタイル床が砕け、下のコンクリートが覗く。
十月十日、アナイアレイターはスターゲイザーとの壮絶なチキンレースに勝った。けれどケンカに勝った爽快感はものの数日で消え失せ、半身を失ったブザマな自分だけが残っている。
それがアナイアレイターの癪にさわる。せめて自分のジツで車椅子から立ち上がれないか試みているものの、マトモに言う事を聞かない鉄条網が、無差別に枝を広げて収集が付かない。車椅子から転落しては、ルイナーやスーサイドが助けられる。
ブザマを仲間に晒すこと、自由のきかない体、自分に従わぬフマーのソウル。全てに腹が立っている。
「平気か」
「触ンな!」
いい加減我慢できなかった。差し出されたルイナーの手をアナイアレイターは払いのけ、獣のように唸る。ルイナーは肩をすくめ、壁際に身をもたせる。
「……焦るなよ」
「うるせェ!」
感情の波に呼応するように鉄条網がルイナーに向かう。それを巻き付かせるままにしている。ルイナーは根気よくアナイアレイターに付き合っていた。それが何故かはアナイアレイターには分からなかったが。
「お前、前に俺相手にやってくれたろ。あれが出来るなら、出来る」
荒い呼吸を繰り返すさなか、ルイナーが片腕を失いかけた夜を思い起こす。あの夜、自分の荒っぽすぎる処置でルイナーは命を繋いだ。半端な坊ちゃんだと思っていたスーサイドから叱責されなければ、ここにルイナーは居なかった。
あそこでルイナーを捨てていたら、スターゲイザーとのイクサで最後まで立っていられなかったかもしれない。今なら少し分かる。あの時自分は逃げようとした。その襟首を掴んだのがスーサイドの野郎だったのだ。癪だが。
深く息を吸い、吐き出す。自分が立ちあがることは、自分の体をコントロールする以外にも意味がある。
ザリザリと音を立て、野放図な蔦じみて広がっていた鉄条網が収束していく。肌を食い破り締め付ける。アナイアレイターの額にじっとり汗が浮かぶが、在るように在れと命じる。ざわめく硬質の蔓は、やがてボンヤリと形を取り始める。己の物ではないエゴを抑え付け、自分に従わせる。できなければ自分もシマナガシも実際死んでしまう。だから命をかけて意地を通す。
鉄条網は剪定されたように左腕の形を取り、カウンターのスツールに巻き付く。それで体を支え、アナイアレイターは立ち上がった。
「……どうだ、おら」
獰猛な笑みを浮かべてルイナーを睨む。ルイナーは壁から身を離し、かすかに頷いた。
そこに、どこかへ行っていたスーサイドが戻って来た。立ち上がるアナイアレイターを見て口角を釣り上げる。
「やったなお前」
そして、ルイナーと思わせぶりな目配せをした。
「これ、野郎が帰ってきたら取り立てだな」
ルイナーが頷く。アナイアレイターは舌打ちした。
「テメェらバクチしてやがったな?」
「……言い出したのはアイツだ」
「で、俺とコイツは、お前が早めに動ける方に賭けたってわけだ」
「ここから出たら、絶対サケ奢れよ」
「アイアイ」
どうにかスツールに腰を下ろしたアナイアレイターに、スーサイドが棒状の物を放った。
「……何だよ」
「あれば楽だろ。バシダ=サンとこから貰ってきた」
スーサイドはバシダ女医の所へ行っていたらしい。アナイアレイターに放ったのは、金属製の握り柄がついた歩行杖だった。
「お前が本調子じゃねえと、こっちも調子狂うんだよ」
アフロヘアーをかき回しながら、スーサイドはそっぽを向いた。こいつ、照れてやがる。
「へへ」
アナイアレイターはそれに答えるように、悪童めいて笑った。
4
曇天の夜空にネオンが反射し、薄ぼんやりとピンクがかった、ネオサイタマの夜。
なんとか、当座の寝床は確保した。寂れた廃マンションだが、雨露が凌げて眠れれば御の字だ。フィルギアは、開けた窓枠に腰掛ける。
「フィルギア=サンは、寝ないの?」
タタミ部屋で毛布をかぶったヤモト・コキが尋ねる。フィルギアは振り返り笑った。
「俺はもう少し起きてる。夜型だからね。女の子は早く寝なきゃダメだよ。お肌が荒れちまうぜ」
フィルギアのジョークにも、しかしヤモトは硬い表情のままだった。
「分かった。おやすみなさい」
「ハイ。おやすみ」
しばらくして少女の寝息が聞こえてきたのを確かめて、フィルギアは呟く。
「……サケが欲しいなァ」
正確には、サケを飲みながら、自分の下らない話をつまらなそうに聞いてくれる聞き手が。その点、シマナガシの三人は聞き手として最高だった。
フィルギアとヤモトが、シルバーキーから託された断片的な情報を元にウミノ・スドを探して数日経つ。焦燥を隠せないシ・ニンジャ――ヤモト・コキがあまりに危なっかしくて、置いて来た三人を心配するような余裕もない。
((……いや、そんなじゃないな))
実際、さほど彼らを憂う気持ちは少なかった。閉鎖空間でのフラストレーションが溜まることはあろうが、それをむやみに他人へ向けることはしないだろう。やるならアナイアレイターかスーサイドだろうが、アナイアレイターならスーサイドが抑え、スーサイドならばルイナーがうまくなだめる。ちょくちょく不在にしていたのが吉と出たのだろうか。
((大きくなったよねェ、あいつら))
本人達には死んでも言わないが、三人があんなタフになるとは思っていなかった。気の向くまま、苛立ちを消費するように振る舞っていた。それが、自分の怒りに指向性を与え、ケンカの相手をさだめ、三人なりのやり方で勝った。
若者は成長する。傷を厭わず、失うことを恐れず。
もしかしたら、自分はそれが見たかったのかもしれなかった。炎の細った炉に送り込む風を待っていたのかもしれなかった。
マグロツェッペリンの広告を漫然と眺めながら、フィルギアは笑う。
戦うことは恐ろしい。だが、もはや逃げぬ。ニンジャスレイヤーとの共闘を取り付けた時から研いできた覚悟だ。
「してやるとも、無茶でもなんでも」
なるべく早く戻って、アナイアレイターが再起したか知る必要がある。結構な額賭けてしまっていた。
「当面、あの子が根詰めすぎて倒れないようにしなきゃならないね」
若者を見守るのは年寄りの仕事だ。
フィルギアは湿った夜風に長い髪を揺らし、小さく笑った。
