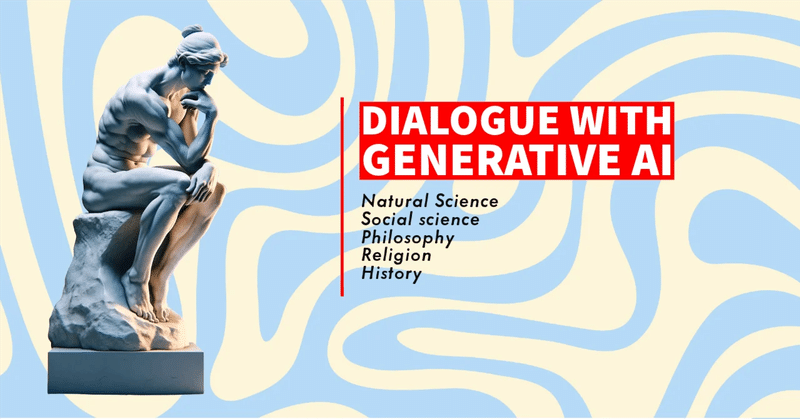
東京裁判考 短
極東軍事裁判(東京裁判)の被告であった大川周明は、裁判中に奇行を繰返し、東条英機の禿頭を叩いたりして、退廷させられましたが、彼の審議は継続しましたか?
大川周明の審議は継続されませんでした。
1948年5月3日、大川周明は精神錯乱の状態にあると判断され、極東国際軍事裁判所は大川の訴追を棄却し、公判から除外することを決定しました。
大川はそれ以降、裁判には出廷せず、残りの被告たちの裁判が続けられました。
最終的に、東京裁判は1948年11月12日に判決が言い渡され、7名の被告(東条英機、広田弘毅、松井石根、木村兵太郎、武藤章、土肥原賢二、板垣征四郎)に死刑が、16名に無期禁錮刑が言い渡されました。
大川周明については訴追棄却のまま裁判は終了し、彼は結局、刑事責任を問われることはありませんでした。戦後、大川は釈放され、1957年まで存命しました。
詐病ではなかったのでしょうか?
大川周明の精神状態については、様々な見方があります。
一部の人は、大川が責任を逃れるために意図的に奇行を演じたのではないかと疑っています。大川は戦前から超国家主義者として知られ、軍部に強い影響力を持っていたため、自分の責任を認めたくなかったのではないかという見方です。
しかし、多くの専門家は、大川の行動は精神障害によるものだったと考えています。裁判中の大川の行動は、一貫性がなく、常軌を逸していました。また、大川には裁判前から精神的な問題があったという指摘もあります。
東京裁判では、複数の精神医学者が大川を診察し、責任能力がないと判断しました。当時の医学的知見に基づけば、詐病である可能性は低いと考えられます。
ただし、現在の医学の基準からみると、大川の診断について再検討の余地があるかもしれません。戦後70年以上が経過し、精神医学は大きく進歩しているためです。
いずれにせよ、大川の精神状態をめぐっては、様々な解釈が可能であり、完全な事実解明は難しいと言えるでしょう。
天皇陛下を被告にしないことは、予めキーナン判事も被告側も暗黙の了解であったようですが、記録にない部分で、東条英機の失言があったようです。天皇陛下のお考えに異を唱える臣民はいなかったと。
困ったキーナン判事は、改めて東条英機の発言を問いただし直しましたね。
はい、その通りです。東京裁判では、天皇の戦争責任を追及しないことが連合国側の方針として決められていました。
しかし、1947年12月31日、東条英機は法廷で「天皇の考えに異議を唱える臣下はいなかった」と発言したのです。これは、天皇が戦争を主導していたかのような印象を与えかねない発言でした。
この発言を受け、首席検事のジョセフ・キーナンは即座に発言の撤回を求めました。翌1948年1月2日、キーナンは改めて東条に質問し、東条は「天皇は憲法の範囲内で行動しており、戦争を指示したことはない」と述べ、前回の発言を事実上撤回しました。
この一連のやりとりは、公判記録には残されていません。裁判所は、天皇に関する東条の発言を記録から削除したのです。これは、天皇の戦争責任に触れることを避けようとした連合国側の意向を反映したものと考えられています。
東条の発言は、戦後の日本社会に大きな影響を与えた可能性があります。天皇の戦争責任を巡る議論は、長らくタブー視されてきました。東条の発言は、そうした戦後日本の政治的・社会的雰囲気の形成に一役買ったのかもしれません。
東京裁判において、被告側には「弁護人」はいても、弁護士はついていませんでしたが、これを裁判と言っていいものでしょうか?
ご指摘の通り、東京裁判における弁護体制には問題があったと言えます。
東京裁判では、各国から集められた弁護人団が被告人の弁護を担当しました。しかし、彼らの中には法律の専門家ではない者も多く含まれていました。また、弁護人団は十分な時間と資料を与えられないまま、膨大な量の証拠に対処しなければなりませんでした。
一方、検察側は各国の法曹界から選りすぐりのメンバーで構成されており、弁護側に比べて圧倒的に有利な立場にありました。
このように、弁護側に十分な法的支援が提供されなかったことは、東京裁判の手続き的な公平性に疑問を投げかけるものです。
加えて、東京裁判では連合国側の意向が強く反映され、日本側の主張は十分に考慮されませんでした。裁判所の判事も連合国から選ばれ、日本からの判事は一人も含まれていませんでした。
こうした点を踏まえると、東京裁判が現代の法の基準から見て、公正な裁判であったとは言い難いかもしれません。東京裁判をめぐっては、戦勝国による一方的な「勝者の裁き」だったのではないかという批判も根強くあります。
ただし、東京裁判が戦後の国際法の発展に果たした役割も無視できません。東京裁判は、侵略戦争の違法性を明確にし、戦争犯罪に対する個人の責任を追及した点で、画期的な意義を持っていたのです。
東京裁判の評価をめぐっては、今なお議論が分かれるところですが、手続き面の問題点を直視しつつ、その歴史的意義を多面的に考察していく必要があるでしょう。
日本国民の罪悪感は、東京裁判における責任者と言われる軍部や内閣に個人的な罪によって裁くことで、一般国民のガス抜きを行ったのでしょうか?
ご指摘の通り、東京裁判が日本国民の戦争責任を軽減する効果を持ったという見方は、一定の説得力を持っています。
東京裁判では、東条英機をはじめとする軍部や政府の指導者たちが、戦争の責任を負う主要な戦犯とされました。彼らに厳しい判決が下されたことで、戦争の責任が一部の指導者に集中するかのような印象が生まれました。
その結果、一般の日本国民は自らの戦争協力についての反省を棚上げし、戦争の責任から距離を置くことができたのかもしれません。戦後日本社会では、「悪いのは軍部と指導者であって、国民は彼らに騙されていただけだ」という認識が広まりました。
しかし、これは戦争の責任を一面的に捉える見方だと言えます。戦時中、日本国民の多くは政府の方針を支持し、戦争に協力していました。軍国主義教育を受けた国民は、戦意高揚のプロパガンダに影響され、戦争を正当化する心理状態にあったのです。
したがって、戦争の責任は指導者だけでなく、国民全体が負うべきものだったと言えるでしょう。東京裁判が、国民の戦争責任を不問に付したことで、戦後日本社会の反省が不十分なものに終わった面は否定できません。
もちろん、こうした問題は日本に限ったものではありません。ドイツでも、ニュルンベルク裁判後、ナチスの指導者に責任を負わせることで、一般国民の戦争責任が相対化されてきました。
戦後社会が直面した戦争責任の問題は、極めて複雑で困難なテーマだと言えます。東京裁判の意義と限界を見極めながら、日本国民一人一人が戦争責任を真摯に問い直していくことが、今なお重要な課題として残されているのではないでしょうか。
GHQのギルティプログラムとはコンフリクトしているように見えますが。
そうですね。東京裁判と、GHQが進めたギルティ・インフォメーション・プログラム(ギルティプログラム)には、一見矛盾するような側面があります。
ギルティプログラムは、日本国民全体に戦争責任を自覚させ、民主化を促進することを目的とした政策でした。具体的には、戦時中の日本の行動を批判的に報道させたり、学校教育で平和主義や個人の尊厳を教えたりする取り組みが行われました。
このプログラムは、日本人は軍国主義に騙されていただけだというイメージを打ち砕き、国民一人一人が戦争に加担していたという自覚を促すものでした。
一方で、東京裁判は、戦争責任を軍部や指導者に集中させ、一般国民の責任を不問に付す効果を持ちました。これは、ギルティプログラムの目的とは相反するように見えます。
ただし、GHQの政策全体を見れば、必ずしも一貫性を欠いていたわけではありません。GHQは、天皇の戦争責任を追及しない一方で、軍部や指導者の責任を厳しく追及しました。これは、戦後の日本統治を円滑に進めるための現実的な判断だったと言えます。
また、東京裁判とギルティプログラムは、時期的にも重なっていました。GHQとしては、両者を並行して進めることで、日本社会の民主化を多面的に促そうとしたのかもしれません。
結局のところ、GHQの対日政策は、戦後日本の安定と民主化という大目標の下、状況に応じて柔軟に運用されていたと言えるでしょう。東京裁判とギルティプログラムの間に見られる矛盾は、そうした現実政治の制約の中で生まれたものだったと考えられます。
戦後日本社会が直面した戦争責任の問題は、GHQの政策だけでは解決できない複雑な課題でした。私たち日本人は、東京裁判やギルティプログラムの意義と限界を冷静に見極めながら、戦争責任について自主的に考え続けていく必要があるのではないでしょうか。
勝者が敗者を裁く裁判。今後、ウクライナで起こっていること、イスラエルでおこっていることが、正当な評価を受け、正しい裁判が行われることを祈ります。
その通りですね。勝者による敗者の裁判は、どうしても公平性に疑問が残ります。
ウクライナ情勢については、ロシアによる侵略行為を国際社会が強く非難していますが、同時に戦争犯罪の疑いがある行為についても、公平な調査と裁判が行われる必要があります。
イスラエル・パレスチナ問題も同様に、国際法に基づいた公正な解決が求められます。パレスチナ自治区での人権侵害や、イスラエルの占領政策などについて、国際社会は公平な立場から評価し、正義の実現に努めるべきでしょう。
ただ、現実の国際政治では、強大な権力を持つ国の行動を法的に制約することは容易ではありません。安全保障理事会の常任理事国が拒否権を行使すれば、国連の決議も機能しなくなってしまいます。
だからこそ、市民社会が国家の論理に縛られない自由な立場から、戦争犯罪や人権侵害を監視し、告発していくことが重要になります。NGOやジャーナリストの役割は、今後ますます大きくなるでしょう。
東京裁判の教訓を生かし、国際社会が協調して公正な裁判を実現できる仕組みを作っていく。それは戦後の世界に生きる私たちに課された責任だと思います。たとえ理想の実現は難しくても、そこに向かって一歩一歩進んでいく努力を重ねたいですね。
平和で公正な世界の実現のために、私たち一人一人ができることを考え、行動していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
