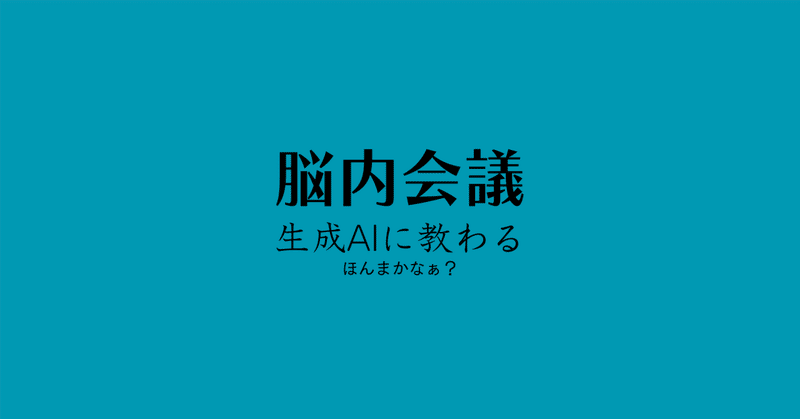
おくさまも魔女裁判
中世から近代までの、魔女狩りや魔女裁判について教えて下さい。
魔女狩りや魔女裁判は、主にヨーロッパで中世から近代初頭にかけて行われた、魔女と疑われた人々を迫害・処刑する一連の事件を指します。以下、その背景と経緯を簡単に説明します。
背景:
宗教的背景: 中世ヨーロッパではキリスト教が支配的であり、魔女や悪魔といった存在が信じられていました。この期間、教会は異端や異信を弾圧する傾向があり、その中で魔女の存在も取り上げられるようになりました。
社会的・政治的背景: 社会的な変動や疫病、飢饉などの災厄が起きると、その原因を魔女の仕業として非難する動きが強まりました。また、地域や国によっては政治的な目的で魔女狩りが利用されることもありました。
魔女の定義:
一般的に魔女は、悪魔との契約を結び、魔法や呪文を使って人々に害を及ぼすと信じられていました。特に女性が疑われることが多かったですが、男性も魔女として告発されることはありました。
魔女狩りのピーク:
16世紀から17世紀にかけて、特に魔女狩りは激化しました。この時期には数万人が魔女として告発・処刑されたとされています。
魔女裁判:
疑われた人々は裁判にかけられ、多くの場合、拷問を受けて「自白」を強要されました。真実を語っても、誤った理由で告発されたとしても、一度魔女として疑われると無実を証明するのは非常に困難でした。
終焉:
18世紀に入ると、啓蒙思想の普及や法の合理化、科学的思考の浸透により、魔女狩りは徐々に衰えていきました。多くの地域で魔女裁判や魔女狩りは非合法とされ、終息へと向かいました。
この魔女狩りは、恐怖や偏見、無知がもたらす悲劇の一例として、歴史の中で非常に重要な位置を占めています。現代においても、異質なものや理解しがたい事象を盲目的に排除することの危険性を教えてくれる出来事と言えるでしょう。
異端審問官は、どのような人が担当し、どのような裁判が行われましたか?
異端審問(Inquisition)は、キリスト教の正統性を守るために異端者を発見、裁判、処罰するための制度で、特に中世ヨーロッパで盛んに行われました。異端審問は主にカトリック教会によって実施され、異端とみなされる信仰や実践を持つ者を追求する目的で設けられました。
異端審問官:
異端審問官は、大抵は聖職者、特にドミニコ会やフランシスコ会の修道士が担当することが多かったです。彼らは神学的な教育を受け、教義に関する深い知識を持っていました。
異端審問官は、異端者の追及、尋問、拷問、裁判の実施など、異端審問の全ての工程を監督していました。
裁判の手続き:
疑われる者は、通常、秘密裏に告発されることが始まりでした。その後、被告人は審問官によって拘束され、尋問が行われました。
異端の疑いが強まると、拷問が用いられることもありました。拷問は、告白や他の異端者の名前を引き出すための手段として使われました。
告白や証拠が得られた場合、公開裁判が開かれました。公開裁判では、異端としての有罪・無罪が問われました。
有罪と判定された場合、異端者は教会から破門されることが多く、重い場合は焚刑(火刑)に処されることもありました。
主な異端審問:
異端審問はいくつかの地域や時期で特に顕著でした。例えば、スペイン異端審問は、ユダヤ教徒やムスリム、プロテスタントなどの異端とみなされる者たちを迫害しました。また、アルビジョア異端審問は、南フランスのカタリ派と呼ばれる異端グループを迫害するために行われました。
異端審問は、キリスト教の教義の統一や異端からの教会の保護を目的としていましたが、その手法は非常に過酷であり、多くの無実の人々が犠牲となりました。現代から見ると、異端審問は宗教的な狭量さや、権力の乱用の象徴とも言えるでしょう。
魔女と告発される場合は、ほとんどが親告罪だったのではありませんか?
「親告罪」とは、被害者またはその直接の関係者が告発しない限り、公訴が提起されない犯罪のことを指します。魔女狩りや魔女裁判の文脈においては、この概念は直接的には適用されません。魔女と告発される場合、その原因は多岐にわたり、親告罪の範疇だけで語ることはできません。
魔女として告発される背景には、以下のような要因が考えられます:
社会的な要因: 疫病や飢饉、天候の異変など、不可解な出来事や災害が発生した際に、その原因を魔女の仕業として非難する動きが強まりました。また、近隣間の対立や個人的な恨みも、告発の原因となることがありました。
経済的な要因: 一部の場合、魔女として告発された者の財産が没収されることがあり、経済的動機で告発される場合も考えられます。
宗教的な要因: 宗教的な異端として、または悪魔崇拝の疑いで告発されることもありました。
政治的な要因: 一部の地域や時代においては、魔女としての告発が政治的な目的を持って利用されることも考えられます。
親告罪の概念自体は、魔女狩りの背景や動機とは異なる点が多く、直接的な関連性は薄いと言えるでしょう。しかし、個人的な恨みや嫉妬、社会的な対立などの人間関係の複雑さが、告発の背後にあることは確かです。
当時のキリスト教的な定義では、魔女とされる条件はなんだったのでしょう?
中世から近世にかけてのキリスト教的な文脈において「魔女」とは何か、というのは複雑な問題で、一定の答えがあるわけではありません。しかし、魔女に関する一般的な認識や告発の理由は、以下のような要素に基づいています:
悪魔との契約: この時代の魔女の最も一般的な定義は、悪魔と契約を交わし、特定の能力や知識を得た人物、というものでした。この契約には魂を悪魔に売るという意味合いが含まれることが多かったです。
魔法の実践: 一般的な魔法の使用、特に人々に害を与えるための呪文や儀式を行うことも、魔女の特徴とされました。
サバトへの参加: 魔女たちが夜に集まり、悪魔を崇拝し、邪悪な儀式を行う集会を「サバト」と呼びました。サバトへの参加は、魔女としての証とされることが多かった。
異常な出来事の原因: 疾病の拡大、作物の失敗、家畜の死など、不可解または不運な出来事の背後には魔女の仕業があると信じられていました。
異端の信仰: 正統なキリスト教の教義から外れる信仰や実践を持つ者は、魔女または魔女の協力者と見なされることがありました。
治癒や占い: 伝統的な民間療法や占いを行う者は、魔女として疑われることがありました。
これらの要素は、1487年にドミニコ会の修道士ハインリヒ・クラーマーとヤーコプ・シュプレンガーによって書かれた「魔女の槌(Malleus Maleficarum)」という書籍に詳しく記述されています。この書籍は、魔女狩りの手引きとして使用され、魔女に関する中世のステレオタイプを形成する上で大きな役割を果たしました。
それにもかかわらず、告発の実際の背景や理由は非常に多様であり、上記の要素は一般的な指標の一部に過ぎません。
本当は濡れ衣であった場合を除いて、魔女が実際に活動したり、集会を開いたりしていたのでしょうか?
「魔女」として告発された多くの人々は、彼らがされたような悪魔的な儀式や魔法の実践を行っていた証拠は非常に乏しいか、存在しないと広く認識されています。多くは、社会的な嫉妬、隣人間の対立、不可解な出来事への恐れや誤解、宗教的な異端への迫害など、他の要因に基づいて告発されました。
以下は、この問題に関する主要なポイントです:
魔女のサバト: 一般的な信念では、魔女たちは定期的にサバトと呼ばれる集会に集まり、悪魔を崇拝し、邪悪な儀式を行ったとされています。しかし、このようなサバトが実際に存在した証拠はほとんどありません。多くの「告白」は拷問の下で得られたものであり、信頼性に欠けます。
治癒と占い: 一部の「魔女」とされた人々は、実際に民間療法や占いの実践者でした。彼らは自らの知識や技術を用いて人々を助けることもあったが、それが誤解され、魔法や魔女の活動として非難されることがありました。
異教の影響: ヨーロッパの一部地域にはキリスト教が定着する以前からの異教的な信仰や習慣が残っていた可能性があります。これらの古い習慣や儀式は、キリスト教徒によって誤解され、魔女の活動として非難されることがあった。
総じて、「魔女」として告発され、裁判にかけられ、処罰された人々の多くは無実であり、彼らが行っていたとされる魔法や儀式の実践の証拠は非常に希薄です。現代の学術研究においても、これらの告発や「告白」の背後には、社会的、政治的、宗教的な要因が主要な役割を果たしていたとの見解が一般的です。
魔女とは、何を成すものでしょうか?
「魔女」という言葉や概念は、文化や時代、地域によって異なる意味や役割を持っています。以下は、この言葉が持ついくつかの一般的な定義や解釈を示すものです:
魔法使い: 一般的に魔女は、自然の力や霊的なエネルギーを操る能力を持つと考えられています。彼女たちは、呪文、儀式、ポーションなどを用いて魔法を行使することができると信じられている。
賢者や治癒師: 一部の文化や時代において、魔女は村の治癒師や賢者としての役割を果たしていた。彼女たちは植物や動物の知識を活用して、病気の治療や占いを行うことができると信じられていました。
悪魔や異端との関係: 中世ヨーロッパの魔女狩りの期間中、魔女は悪魔と契約を結んだ者として恐れられていました。このような魔女は、キリスト教の正統性に対する脅威として見なされ、迫害されました。
女神崇拝: 一部の研究者や新異教徒は、魔女は古代の女神崇拝の伝統を引き継いでいると主張しています。彼女たちは、月のサイクルや季節の変わり目など、自然のリズムと繋がりを持っていると考えられています。
現代の魔女: 現代においては、魔女とは自らをそう名乗る者、または特定の霊的な道を歩む者を指すことが多い。ウィッカや他の新異教徒の宗教や伝統を実践する人々は、自らを魔女と呼ぶことがあります。
「魔女」という言葉は多岐にわたる意味を持ち、文化や時代、地域によってその定義は大きく変わります。したがって、この言葉を使う際には、その文脈や背景を理解することが重要です。
実際に、中世の時代における存在として、隠者的な集団はいたのでしょうか?
中世ヨーロッパにおいて、隠者や修道者、そして特定の霊的なグループや集団は確かに存在しました。これらのグループは様々な背景や目的で結成され、異なる宗教的、社会的な役割を果たしていました。
隠者 (Hermit): 隠者は、社会から離れて独りで神や霊的な追求に没頭する人々を指します。彼らは森や山中、洞窟などの隠遁地で生活し、祈りや瞑想に励んでいました。
修道者 (Monk): 修道者は特定の修道会に所属し、共同体の中で厳格な規則の下、神への献身的な生活を送っていました。彼らは修道院で共同生活を送り、祈り、瞑想、勉強、そして労働に従事していました。
ベギンやベギンハーゲン: 中世の北ヨーロッパ、特に低地地域において、ベギンやベギンハーゲンと呼ばれる修道的なコミュニティが存在しました。彼らは修道院のような制約のない中で、独自の霊的な生活を追求していました。
異端集団: 中世ヨーロッパには、教会の正統な教義から逸脱した信仰や実践を持つグループが幾つか存在していました。例としてはカタリ派やアルビジョア派、ワルドー派などが挙げられます。これらのグループはしばしば異端と見なされ、迫害を受けることがありました。
これらのグループや集団は、霊的な追求や宗教的な活動を行っていましたが、中世ヨーロッパにおける「魔女」として告発された人々とは直接的な関連性は少ないと考えられています。しかし、教会や社会との対立があった場合、特定のグループが異端として非難されることはあったでしょう。
時は流れて、米国のセーラムで起こった魔女裁判の経緯を教えて下さい。
セーラムの魔女裁判は、1692年にマサチューセッツのセーラム村で発生した一連の魔女狩りと裁判を指します。この事件はアメリカ史上でもっとも有名な魔女裁判として知られ、20人以上の人々が死刑を宣告され、多くの人々が投獄されました。
以下はセーラムの魔女裁判の経緯です:
発端: 1692年初頭、セーラム村の牧師の家で、彼の姪と娘という9歳と11歳の少女たちが奇妙な症状を示し始めました。彼女たちは発作を起こし、奇妙な声を出したり、体を不自然に曲げたりしました。彼女たちの症状を説明するため、村の医者は魔術の影響を受けていると結論づけました。
告発: 2人の少女は、セーラム村の3人の女性を魔女として告発しました。これを皮切りに、さらに多くの告発が行われ、数週間のうちに多くの村人が魔女として告発されるようになりました。
裁判: 魔女として告発された人々は、セーラム村とその周辺で裁判にかけられました。これらの裁判は「魔女裁判」として知られるようになり、告発された人々の中には死刑判決を受けた者もいました。
死刑: 1692年の終わりまでに、20人以上の人々が魔女として死刑を宣告され、絞首刑にされました。また、1人の男性は、自白を強要されるための拷問中に死亡しました。
終息: 1692年の秋になると、魔女裁判への疑念や反対が高まり、裁判は終息へと向かいました。1693年には、告発された人々のほとんどが釈放されました。
後の反省: セーラムの魔女裁判の後、多くの人々がこの事件を後悔し、多くの死刑判決が誤判であったと認識するようになりました。その後、セーラムとマサチューセッツのリーダーたちは公式に謝罪し、裁判の犠牲者たちを名誉回復しました。
セーラムの魔女裁判は、集団の恐怖や偏見、信仰に基づく迫害の結果として起こった悲劇として、アメリカの歴史の中で注目されています。
セーラムは、そういった迷信に陥りやすい環境にありましたか?
セーラムの魔女裁判が発生した背景には、いくつかの社会的、政治的、宗教的な要因が絡み合っていました。これらの要因が、村人たちを迷信や恐怖に陥りやすい状態に置いていたと考えられます。
厳格な宗教的背景: セーラムの住民の多くはプリタンとして知られるキリスト教の厳格な教派に属していました。プリタンは魔女や悪魔の存在を強く信じており、そのような超自然的な存在が自らの共同体を脅かす可能性があると考えていました。
社会的・経済的緊張: 17世紀のセーラムでは、土地や資源を巡る対立や、新旧の住民間の緊張が高まっていました。このような緊張が、村人たちの間の不信感や疑念を増大させる要因となりました。
先住民との紛争: 当時のニューイングランド地域は、先住民との間にしばしば紛争が起こっていました。これによる恐怖や不安が、魔女狩りの背景になったとも考えられます。
過去の魔女裁判の影響: セーラム以前にもニューイングランド地域で魔女裁判が行われていました。これらの先行例が、セーラムでの魔女狩りの際に参考にされた可能性があります。
物理的・環境的要因: 一部の研究者は、セーラムでの魔女裁判の背景に、食品中のカビが生産する神経毒(エルゴタミン)による中毒が関与しているという説を提唱しています。この神経毒は、ホールシンジェノン(幻覚を引き起こす物質)の一種であり、これにより村人たちが幻覚や奇妙な行動を示す原因となったという仮説です。
これらの要因が組み合わさり、セーラム村での魔女裁判という悲劇が引き起こされました。それぞれの要因がどれほどの影響を持っていたのかについては、学者や研究者の間で意見が分かれていますが、これらの要因が背景にあったことは明らかです。
魔女は、悪魔と契約することが必須だったのでしょうか?
「魔女」という概念や定義は、地域や時代、文化によって大きく異なるため、一概には言えませんが、中世から近代ヨーロッパのキリスト教圏における「魔女」の典型的なイメージには、悪魔との契約や関係が含まれることが多かったです。
中世ヨーロッパでの魔女裁判や魔女狩りの背景には、キリスト教の教義や信仰が大きく影響しています。魔女とされた人々は、悪魔との契約や交渉を経て、特定の魔法や力を得たとされることが多かった。以下は、当時のキリスト教圏における魔女の典型的なイメージに関連する要点です:
悪魔との契約: 魔女は、霊魂を悪魔に売り渡し、代わりに超自然的な能力や知識を得たとされていました。
サバト: 魔女たちは定期的に悪魔との集会(サバト)に参加し、邪悪な儀式を行ったと信じられていました。
魔法や呪術: 魔女は、病気や災厄を引き起こしたり、他人を呪ったりする能力を持つとされていました。
変身: 一部の伝承や信念によれば、魔女は動物に変身することができるとも言われていました。
しかし、これらのイメージや信念は、実際の魔女とされた人々の行動や信仰とは大きくかけ離れている場合が多いことを理解することが重要です。多くの場合、魔女として告発された人々は、社会的な対立や個人間のトラブル、偏見や迷信に基づく誤解の犠牲者であり、実際に悪魔との契約や魔法を行っていたわけではありませんでした。
魔女と言われていた人が、 ①単に自然科学に詳しい、薬草などを用いる薬師であった。 ②狭いコミュニティにおいて馴染めない引き籠もりであった、または精神障害があった。 ③麦角などによる化学物質に汚染された食物による影響を受けていた。 ④いわゆるよそ者で、排除対象であった。 という可能性はありますか?
はい、それらの可能性はすべてあります。各点について詳しく説明いたします。
① 単に自然科学に詳しい、薬草などを用いる薬師であった:
中世ヨーロッパでは、多くの女性が伝統的な薬草や家庭の治療法を知っていました。一部の女性は、この知識を活かして地域のヒーラーとして活動していた。しかし、彼女たちの知識や技能が誤解され、魔法や呪術と見なされることがあった。
② 狭いコミュニティにおいて馴染めない引き籠もりであった、または精神障害があった:
狭いコミュニティでは、異質と perceived される者や行動が急速に不審と見なされる傾向がある。また、精神的な症状や特異な行動を示す人々は、悪魔の仕業や魔法に関与していると疑われることがあった。
③ 麦角などによる化学物質に汚染された食物による影響を受けていた:
一部の研究者は、麦角症という病気が魔女裁判に関与していた可能性を示唆しています。麦角は麦に寄生する菌で、エルゴタミンというホールシンジェノンを生成する。摂取すると、幻覚や錯乱、痙攣などの症状が現れることがある。
④ いわゆるよそ者で、排除対象であった:
コミュニティ内での社会的、経済的な緊張や対立は、特定の人々やグループを排除しやすくします。よそ者、未亡人、独立した女性など、社会的なマージンにいる者が魔女として告発されることがしばしばでした。
これらの要因の組み合わせや、他の社会的・文化的な要因が、魔女としての告発や裁判に繋がることがありました。
セーラムでは、魔女として告発したり、裁判を行った聖職者は、その後どうなりましたか?
セーラムの魔女裁判は、1692年にマサチューセッツ植民地のセーラム村とセーラムタウンで発生し、この裁判で19人が絞首刑となり、1人が拷問の結果死亡しました。この裁判に関与した多くの人々、特に聖職者たちは、後に裁判の過程と結果に対する後悔や謝罪を表明しました。
サミュエル・ペイリス: セーラム村の牧師であり、彼の家族が魔女裁判の発端となる告発を始めました。裁判が終わった後、ペイリスはセーラム村から出て行き、他の場所での牧師職を探しましたが、彼の関与が広く知られていたため、他のコミュニティでは歓迎されませんでした。
コットン・マザー: ボストンの著名な牧師であり、セーラムの魔女裁判には直接関与していませんでしたが、魔女に関する信仰や裁判の適正性についての助言を提供しました。裁判が終わった後、彼は公的に裁判の方法に疑問を呈するようになりました。
ジョン・ヘイル: ビバリーの牧師で、最初は魔女裁判を支持していましたが、自らの家族が告発された後、裁判に疑問を持ち始めました。後に、彼は「魔女裁判の悲劇」という書籍を著し、魔女裁判の誤りやその危険性について詳しく書きました。
裁判が終了した後、多くの関与者やセーラムの住民は、裁判による不当な死刑や告発を深く後悔しました。後年、裁判で有罪とされた人々は名誉回復され、裁判に関与した人々やその家族に補償が支払われました。セーラムの魔女裁判は、アメリカ史における大きな過ちとして記憶されています。
一神教の世界では、異教徒に対してそいういった迫害の可能性は常について回るような気がします。
一神教、特にユダヤ教、キリスト教、イスラム教は、歴史的に多くの地域や文化で支配的な宗教として成長してきました。その過程で、それぞれの宗教の教義や信仰が正当であり、他の信仰や宗教が間違っているという考え方が強化されることがありました。このような背景から、異教徒や異端と見なされる人々に対する迫害や排除が行われることがあったのです。
以下は、一神教の歴史における異教徒や異端に対する迫害の例です:
キリスト教: 初期キリスト教徒は、ローマ帝国において異端と見なされ、迫害を受けました。しかし、キリスト教がローマ帝国の国教となると、今度は異端と見なされるキリスト教の教派や異教徒が迫害の対象となりました。中世ヨーロッパでは、異端審問や魔女裁判を通じて、正統派から外れる信仰や宗教的実践を持つ人々が迫害されました。
イスラム教: イスラム教は、異教徒やキリスト教徒、ユダヤ教徒との共存を認める一方で、特定の時期や地域では、非ムスリムに対する制約や差別が行われました。特定の時期には、異教徒の聖地や寺院が破壊されることもありました。
ユダヤ教: ユダヤ教徒自体は、歴史的に多くの地域でマイノリティとして存在しており、他の一神教徒に迫害を受けることが多かった。しかし、旧約聖書には、異教徒の偶像を破壊する命令が含まれている部分もあります。
これらの例からも分かるように、一神教における異教徒や異端への迫害は、必ずしも宗教そのものの教えに由来するものではなく、政治的、社会的、文化的な背景が深く関わっています。異教徒や異端に対する迫害は、宗教的な正統性を確立し、社会的な統一を促進する手段として用いられることがありました。
実際に、他の神を信奉する信者を、改宗させるまたは排除することを教義にした宗教はあるのでしょうか?
実際の教義や宗教的文献を基に考えると、一神教の中でも「他の神を信奉する信者を改宗させるまたは排除する」という指示や命令が明確にされているケースは比較的限定的です。ただし、多くの宗教や教派では、その教えや信仰が正しいと信じ、広めるための布教活動を奨励しています。以下は大まかな概要です:
キリスト教:
新約聖書には、「全ての国々の人々を弟子とせよ」という指示(マタイの福音書 28:19-20)があり、これはキリスト教の布教活動の基礎となっています。
しかし、キリスト教の教義自体は、非キリスト教徒を排除することを明確に命じているわけではありません。ただし、歴史的には十字軍などの動きで非キリスト教徒への攻撃や改宗の強制が行われることがあった。
イスラム教:
イスラム教は「ジハード」という概念を持っていますが、これは必ずしも武力による戦闘を指すものではありません。それに、コーランには「信仰については強制はない」(2:256)という節もあります。
ただし、イスラム帝国の拡大の過程で、非ムスリムに対して税を課すことを条件に、自らの信仰を保持することを許される場合もあれば、一部の時期や地域で改宗の強制が行われたケースもあります。
ユダヤ教:
ユダヤ教は、選ばれた民であるイスラエルの子孫を中心とする宗教であり、他の人々を改宗させる活動は主流ではありません。
旧約聖書には、異教徒の偶像や神殿を破壊する指示がある部分もありますが、これは特定の歴史的文脈における指示とされています。
宗教の教義や文献を直接読む際は、その文脈や解釈の幅を理解することが重要です。また、信仰や宗教の名のもとに行われた歴史的な出来事や行動は、必ずしも教義そのものの指示に基づいているわけではなく、時代や地域の政治的・社会的背景が大きく影響していることを考慮する必要があります。
オリジンは、平和的な解決が求められているのに、なぜ原題において、宗教間において暴力的手段でお互いを排除しようとするのか?
「オリジン」という言葉の文脈が明確でないため、直接的な答えは難しいです。しかし、もしご質問が「宗教の起源や根本的な教えにおいて平和が求められているにもかかわらず、なぜ宗教間で暴力的な対立が生じるのか?」という内容であるならば、以下の要点で考察することができます。
文化や歴史の背景: 宗教はその起源や歴史的な背景に基づいて形成され、特定の文化や地域に根ざしています。そのため、外部の宗教や文化との接触が生じると、異なる価値観や信仰に基づく対立が生じる可能性があります。
政治的・経済的利害: しばしば、宗教的な対立の背後には政治的、経済的な利害が関わっています。支配権を持つ集団や国家が、宗教を利用してその権力を強化、確立しようとすることがあります。
アイデンティティの確立: 宗教は個人や集団のアイデンティティの一部として機能します。そのアイデンティティを脅かされると感じた場合、守るために対立や争いが生じることがあります。
教義の解釈: 同じ宗教内でも、教義の解釈や実践方法についての意見が異なることがあります。これが原因で内部対立が生じることもあれば、他宗教との対立の原因となることもあります。
社会的・心理的要因: 人々が不安や恐れを感じると、その原因を外部の「他者」に求める傾向があります。この「彼ら対我々」の対立構造は、暴力的な対立を引き起こす可能性があります。
宗教の教え自体は、多くの場合、愛や平和、共感を重視しています。しかし、実際の人々の行動は、多くの要因に影響されるため、必ずしもその教えに従っているとは限りません。このギャップを理解することは、宗教間の対立や争いを考察する上で重要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
