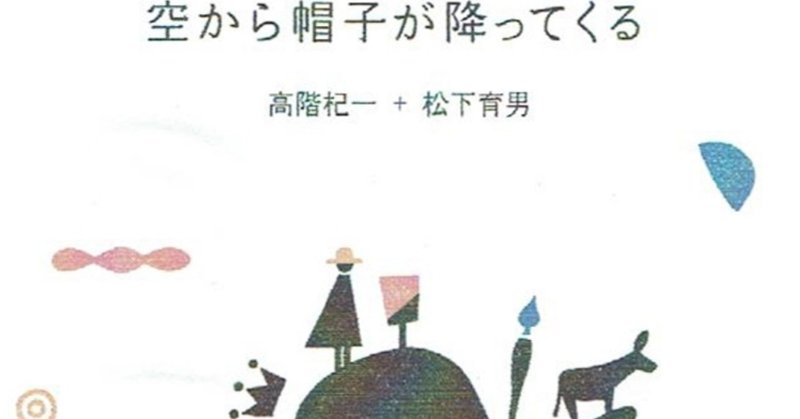
高階杞一 + 松下育男 『共詩・空から帽子が降ってくる』
高階さんから「新しい詩集を送るよ」とメールがあって、楽しみに待っていたら、届いた詩集には高階さんの他に、松下さんの名前もあった。しかもそのふたつが「+」で繋がれていて、題名には「共詩」と謳われている。おまけに帯には「ライト兄弟」(!)とあるではないか。
共同で書く詩と言えば、昔は連歌や連句、最近では連詩がある。連詩でもふたりだけで行う場合は「対詩」と呼んだりする。僕も小池昌代さんや田口犬男さん(今ごろどこで何をしているのだろう?)と、一年以上の時間をかけて詩をやり取りしたことがあった。
だがこの詩集はそれとも違う。ふたりの詩人がそれぞれの詩を交換し合うのではなく、ふたりで一篇の詩を書き上げてゆくのだ。つまり「合作」に近いのだが、相談しながら書いているわけではない。あくまでも交代で書き継ぐというスタイルで、そこには明らかに連歌・連詩・対詩に通じる「付合(つけあい)」の要素があるだろう。けれどもその交代の間隔が数行刻みであり、かつ誰が何を書いたという記録を残さないので、出来上がったときには二人の境目が溶け消えて、一篇の詩だけが残されることになる。
なんだ、そういう手があったのか!コロンバスの卵、というか、僕は自分の不明に恥じ入る思いだった。というのも、いわゆる連詩には、やっている当人は愉しいけれど、後でそれを読まされる方は読んでも流れがよく分からない、だからつまらない、つまりはreadabilityが低いという弱点があると、以前から不満に思っていたのだ。それを解消する手立てとして、共通するテーマを設定したり、物語性を導入するなど試行錯誤を行ってきたのだが、こんなやり方があるとは気づかなかった。
具体的に見てみよう。
冒頭に置かれた表題作。2010年に作られた最初の共詩だそうだ。そう言われれば、いかにも新鮮なワクワク感が漂っている。
空から帽子が降ってくる
でかける用事があったのに
もう降り出してきたのかと
にわかに暗くなってきた空を
頬杖ついて見上げてた
これが最初の一連だ。共詩というアイデアを仕掛けたのは高階さんだそうだから、一行目も彼が書いたに違いない。では二行目も彼だろうか。そこで寸止めして、三行目を松下さんに託したのか。だとすれば凄技だな……そんなふうに想像して読むのが愉しい。
こちらは4連目。
空から帽子が降ってくる
どんな治世の王様だったか
水の言葉は禁じられ
ロバは困る
ご主人が狂ったように笑うので
この連の五行はどれも相当に飛んでいる。どこから「治世の王様」とか「水の言葉」なんていう発想がやって来たのか。おまけにロジックも捻じ曲げられている。「水の言葉が禁じられ/ロバは困る」と読むと、なんとなく水飲み場でしょぼくれているロバの姿が浮かぶけれど、次の行を読むと、彼が困っている理由は主人の笑いの方にあるのだと分かる。でもその歪みのどこまでが、ひとりの詩人の手によるもので、どこからが交代したことの結果なのか。
こうして読んでみると、共詩は、連詩よりも連歌に近いと思う。この一連を一句に見立てるならば、連歌同様にふたりで上の句と下の句を組み合わせているとも読めるからだ。
僕が特に胸を打たれたのは「サカナの泳ぐ日」と「川沿いの道」の二篇だ。どちらも男と女の物語。失われた愛の話だ。初めのうちはふたりの詩人の掛け合いを楽しみ、その技や癖を読み取ろうとして読んでゆくのだが、いつの間にか物語のなかに引きずり込まれてしまう。そして読み終わったときは、作者の存在や制作のプロセスのことをすっかり忘れているのだ。あとには無名の、つまり普遍的な、魂の悲しみだけが残っている。そしてその点はひとりで書いた詩であっても、優れた詩には常に言えることではあるまいか。作品だけを残して、作者が消える。詩における「作者」、言い換えれば「書く主体」って一体何なのだろうと考えてしまう。
この詩集は二人の詩人による共詩だけれど、これを四人くらいでやってみても面白いかもしれない。その場合は一行ずつぐるぐる回してゆくことになるのかな。あ、「びーぐる」の編集同人でやってみたらどうだろう?山田兼士さんも、細見和之さんもそれぞれ作風が違うから、相当奇妙キテレツなものが出来上がるはずだ。どうでしょう、高階さん?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
