
『ベリー・ベスト・オブ・TOP~ワーナー・イヤーズ』 タワー・オブ・パワー
いつもの曲がり角を右に曲がると、そこから乾いたドラムの音が聞こえる。そしていつも窓を開けっぱなしにして、上半身裸の男がせわしなく16ビートを刻んでいる。
自転車で通学していた僕は、いつもその曲がり角に近づくとちょっとだけ胸が高鳴った。
そのビートは非常に黒いものに聞こえたが、実はタワー・オブ・パワーのリズムをその男は叩いていたのだ。なぜなら友達を連れて、男の部屋を覗きに行った時、友達はすぐに『ヴァンプ・シティ』(1972)の「You’re still a young man」と『タワー・オブ・パワー』(1973)の「What is HIP」という曲のリズムだ、と断定したからだ。その後、友達の家に行き、彼の部屋でタワー・オブ・パワーを初めて聴いた時、その特徴的なリズムが聞こえ、なんともいえない高揚感が僕を襲った。
僕はそれまで、よしだたくろうや陽水、海外ではビートルズ、フリーといった比較的わかりやすい音楽を好んで聴いていたが、ブラスの効いたセンスのある重厚なロックを初めて聴いた時、ちょっとだけ大人のロックを体験した気がした。特にその頃の僕はドラムを始めたばかりだったので、当時人気のジョン・ボーナムやイアン・ペイスのレコードを何回も聴くより、間近で見る上半身裸の男のリズムの方がためになった。見て憶えることは早い。特に音階の無い楽器なので、筋肉の動きや手首の返しなど、とにかく見よう見まねである。16ビートを刻みながら、スネアを連打する。パラディドルを憶えたのもその上半身裸の男のおかげだ。そして、いつしか好きなドラマーにタワー・オブ・パワーのデビッド・ガリバルディが加わった(本当は上半身裸の男なんだけど・・・)。
タワー・オブ・パワーはシカゴやブラッド・スェット&ティアーズと並ぶブラスロックの雄で、サンフランシスコを中心に活動し、フィルモアなどの有名なライヴハウスにも出演していた。そして、あのジミヘンの前座も務めた事があるという。
セカンドアルバム『ヴァンプ・シティ』(エンジニアはスティーブ・クロッパー)発表後は、舞台を全米、そして全世界へと活動範囲を広げていった。
総勢10名に及ぶメンバーでブラスロックにファンクとソウルを融合させ、はじけまくる。ロックのオーケストレーションが体験できるバンドである。
ヴォーカルが弱いという風評もあったが、そんなことよりも、彼らの出すグルーヴは白人離れしたノリの良さだ。
しかし、70年代も後半に差し掛かる頃、ディスコ・ミュージックの波に押され、音楽性が微妙に変化していった。レコード会社もワーナーからコロンビアへ、そして80年代に入るとエピックへと移籍。同時にメンバーも大きく替わっていった。
この状況は、彼らが白人のグループだったことが大きく起因している。ディスコ・ミュージックへの音楽地図に対応しきれなかったことが彼らを劣勢にさせた。もし、彼らが黒人であったら、ソフトロックへの変更(クール&ザ・ギャング)やギラギラのダンスミュージックへの変更(アース・ウィンド&ファイヤー)が出来ただろう。しかし、白人がやってもサマにならず、すぐに誰かの真似と揶揄されるだけだったかもしれない。
そんな彼らは新たな音楽を求め、ホーンセクションを切り離しながら、様々なアーティストのバッキングをつとめた。リトル・フィートやヒューイ・ルイス&ザ・ニュースなど・・・。そして日本のアーティストのバッキングにも参加している。RCサクセションの70年代の名盤『シングルマン』(1976)もタワー・オブ・パワーのホーンセクションだ・・・。これは買い。
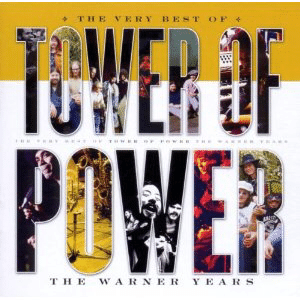
『ベリー・ベスト・オブ・タワー・オブ・パワー ワーナー・イヤーズ』(2001)は、タワーの一番美味しいところを収録したベスト盤である。『ヴァンプ・シティ』も名盤だが、ワーナーの頃のタワーは全て聴いてもらいたいので、あえてベスト盤をお勧めする。
2006年8月17日
花形
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
