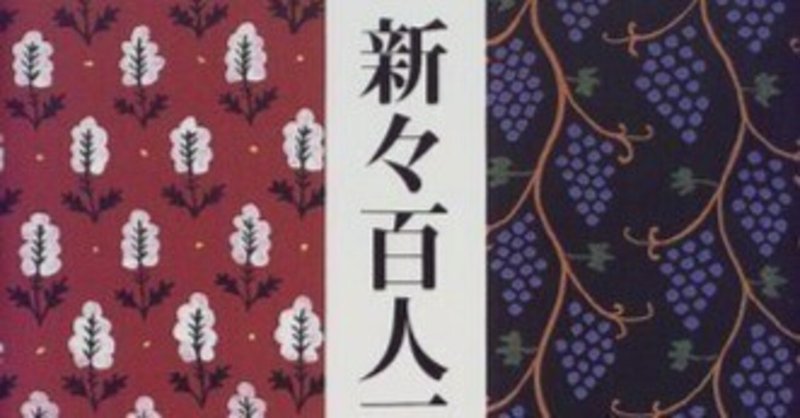
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)『新々百人一首』新潮社 1999.6 丸谷才一・大岡信(1931.2.16-2017.4.5)「詞華集と日本文学の伝統」『新潮』 1999年8月号

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『新々百人一首』
新潮社 1999年6月刊
2009年7月21日読了
2018年10月19日購入 アマゾン中古352円
https://www.amazon.co.jp/dp/4103206071
「王朝和歌の世界が絢爛と甦る歴代の名手から新たに選ばれた不朽の秀歌百首。藤原定家の「小倉百人一首」、源義尚の「新百人一首」に続く秀歌集。定家と義尚の選んだ二百人を敬遠せず、両人の取った二百首との重複は避け、厳選した百首に長短繁簡とりどりの注釈を付す。王朝和歌の絢爛たる世界が甦る。」
669ページもある分厚く重たい本で、
7世紀の舒明天皇から、15世紀の連歌師肖柏までの
百人が詠んだ和歌を観賞するアンソロジー。
『新古今和歌集』の部立(ぶだて)通り、
春・夏・秋・冬・賀・哀傷・旅・離別・恋・雑・釈教・神祇
の順に構成されていますが、
もしこの分厚い本を再読することがあれば、
次回は、今回読んだ部立順ではなく、巻末の
「新々百人一首時代順目次」
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/100i/sinsin100.html
に従って読んでみようと思います。
「藤原良経 昔たれかかる桜の花を植ゑて吉野を春の山となしけん
……
一首は屏風歌として詠まれたものではないが、明らかにその伝統につらなつてゐる。第二句「かかる桜の」で画面を具体的に指示し説明する気配もさうだが、それよりも、様式性と装飾性と慶賀の意によつて屏風歌に近いのである。
屏風絵と屏風歌の儀式性の底には、古代的な呪術性が厳然と控へてゐた。屏風歌は本質的に呪歌だつたのである。屏風歌が王朝和歌の様式を支配したといふ形勢の根本には、もともと王朝和歌が、四季歌だらうと恋歌だらうと呪術的な性格のものだつたといふ事情がある。
それは呪文が、呪文としての体質を改めないまま挨拶になり、やがて、呪文の雰囲気をとどめながら藝術に変じたものなのである。」
p.95「春・藤原良経」『海』1979年7月号「千本桜」
「宮内卿 片枝さすをふの浦梨初秋になりもならずも風ぞ身にしむ
女は才智の限りを盡して気のきいたことを言ふときに最も美しい。彼ら[王朝の人々]はさう思つてゐたし、その風俗的信念が極点に達したとき、後鳥羽院の宮廷における宮内卿の高い位置が生じた。
福田百合子
[1928- 山口女子大学教授、山口県立大学名誉教授、中原中也記念館 館長]
https://yamaguchi-kp.tumblr.com/
がすでに指摘したやうに、
[「宮内卿の世界」日本文藝研究 17 1965-10 関西学院大学
かな? 未見]
https://cir.nii.ac.jp/crid/1520853832604559872
勅撰集の巻一のはじめの配列はすこぶる儀式的なものだが、『新古今和歌集』巻第一春歌上は、摂政太政大臣良経、後鳥羽院、式子内親王、宮内卿とつづく。その意味では、彼女は後鳥羽院の歌道の師、藤原俊成よりも重要な歌人だったのである。」
p.193「夏・宮内卿」『草月』1978年6月号
「能因 さらしなや姨捨山に旅寝して今宵の月をむかし見しかな
歌枕とは和歌によく詠まれた名所のことで、基本的には、地理的概念であるよりもさきに様式美の装置であつた。
京を離れることが極めて稀で、たまたま旅をしても、宇治とか熊野とかごく限られたところへしかゆかない王朝貴族にとつて、諸国名所はまづ屏風絵の画材だつたのである。
彼らは屏風絵を眺めて、あるいは天の橋立を心に思ひ描き、あるいは武蔵野を夢見た。極度に意匠化された(絵師たち自身も現地を見たことがない)風景画に助けられなければ、想像力は働くことができなかつたらう。
屏風絵の画材であるよりもさきに、喚起性の強い名詞だつたと言ふほうが正しいかもしれない。歌人たちは地名を語源俗解ふうに分析し、こぢつけ、そして詩情のきつかけとしたわけである。
しかし屏風絵よりも、地名からの単純な連想よりも、その歌枕をあしらつた先行する名歌が大きく作用した。
歌人たちはさういふ古歌に促されて歌枕を詠みこんだ。しかもその際、先行する名歌は共通の記憶となつてゐるゆゑ、新しく詠まれた和歌の、いはば地となつて見えがくれにゆらめき、意味と色彩を増幅することになる。
もともと王朝和歌は文学の伝統を大がかりに利用する古典主義的な文学形式だつたが(もしさういふことがなければわづか三十一音のなかに複雑な内容を盛ることはむづかしい)、その古典主義の仕掛けの一つが歌枕といふ約束事であつた。」
p.264「秋・能因」『ウーマン』1978年10月号
「後鳥羽院 わたつうみの波の花をば染めかねて八十島(やそしま)とほく雲ぞしぐるる
後鳥羽院は俊成の弟子で、すなはち定家とは相弟子になるわけだが、彼らの方法は充分に重んじながら、つまり六条家の旧套は捨てて御子左家の新風に就きながら、しかも俊成父子との資質の差を痛感してゐた。
二人があくまでも職業歌人として和歌に対し、和歌を藝術に仕立てようとしてゐることが不満だつたのである。この不満は、人格円満な俊成に対しては抑へられてゐたが、温厚篤実とは決して言ひにくい、そして父よりも藝術家的意識がいつそうあらはな定家との関係において、はつきりと意識されることになつた。
逆に言へば、後鳥羽院は定家によつて自己を確認できたので、これはおそらく定家にとつてもまた事情は変わらなかつたらう。その対立によつて後鳥羽院が明確に意識した自己とは、宮廷といふ具体的な詩の場に所属する者、あるいはそれを主催する者としての自己にほかならない。(定家はその詩の場を失つて詩人の孤独のなかにとぢこもらうとするゆゑ、誤りを犯してゐるのである。)
その宮廷においては、和歌は、かつて遠い昔に呪文であつたと同じやうに、いま、呪術の気配をほのかにとどめながら、基本的には礼儀と社交の具でなければならない。(定家はそれを純粋な藝術に変じようとするゆゑ危険である。)
すなはち和歌はめでたく詠み捨てるのが本来の姿である。(定家の場合はその詠み捨ての趣を嫌つて、一首の出来栄えにうるさく拘泥する。)和歌のかういふ古代的なあり方を根本のところで保持してゆきたいといふのが後鳥羽院の願ひであつた。(しかるに定家は近代の純粋詩を求めた。)
俊成、定家の彫心鏤骨の詠み口にあきたらない彼にとつて、職業歌人と対立する型の者は誰だつたか。まづ西行である。」
p.318「冬・後鳥羽院」
『岩波講座文学 3 言語』岩波書店 1976年2月刊「言葉で作る世界」
一首一首の注釈は短かったり長かったり色々ですが、
この後鳥羽院の分は20ページ以上あって、読み応え十分で、
『新古今集』に興味があれば、とても面白い文章でした。
「和泉式部 黒髪のみだれもしらず打伏せばまづかきやりし人ぞ恋しき
和泉式部のこの絶唱によつて「黒髪」は歌語として定着した。そして、
藤原定家 かきやりしその黒髪のすぢごとに打伏すほどは面影ぞ立つ
は明らかにこの一首を本歌とする。一代の名匠が和泉式部に張合って詠んだ傑作で、彼女とは逆に男の側から歌つてゐる。
かうして一人、横になつてゐると、共寝した夜、わたしがかきやつたあの黒髪の一本一本がはつきりと心に浮かぶ、といふほどの意味だらうが、眼目は第三句の「すぢごとに」で、女の髪の冷やかな感触を伝えて間然するところがない。さながら死んだ女をしのぶかのように。
そして、王朝和歌の基本的な技法の一つである本歌どりとは、単なる模倣では決してなく、継承であり、展開であり、唱和であり、それゆゑ一つの批評のあり方なのだから、われわれは定家の本歌どりを手がかりにして、逆に、もつと詳しく本歌の意味を探ることができるかもしれない。
さう考へて和泉式部の一首を読み返すとき、われわれは、これは死んだ男ないし遠くに旅している男を虚しくなつかしんでゐる歌なのだと思ひいたるのではなからうか。すくなくとも、わたしはそんな気がする。」
p.479「恋・和泉式部」『いんなあトリップ』1975年1月号
「わが恋は知る人もなし堰(せ)く床(とこ)の涙もらすなつげのを枕
式子内親王
百首歌の中に忍恋を 新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1036
正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。
枕をあしらつた恋歌のうち最も有名なものは、
和泉式部 枕だに知らねばいはじ見しままに君かたるなよ春の夜の夢
で、これは、恋を知る枕といふ伝承を背景において、ただしその枕さへしないでの(する暇のないくらゐゆとりのない)情事でしたから、枕は見てゐないはず、知らないはず、といふこころを、濃厚な色調で歌ひあげた絶唱である。
和泉式部ならではの率直な、なりふり構わぬ詠ひぶりに辟易して、これはいささか品が悪いと感ずる人もゐるかもしれない。
その点、式子内親王の忍ぶる恋の一首はまことに清婉でしかも繊細な趣で、同じく枕を詠んでもこれほど対蹠的になるものかと驚くほどである。わたしにとつてはいづれも極めておもしろく、これもまた傑作と呼んで差支へない気がする。
隠岐本でも除かれてゐないゆゑ、隠岐に流された後鳥羽院が評価を改めなかつたことがわかるし、さらに藤原定家もまた『定家八代抄』に選んでゐる。」
p.494「恋・式子内親王」『ウーマン』1977年10月号

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
大岡信(1931.2.16-2017.4.5)
「詞華集と日本文学の伝統」
『新潮』 1999年8月号
2021年6月4日読了
大岡信『おもひ草』世界文化社 2000.2 p.140-181
「丸谷 [『新々百人一首』新潮社 1999.6 で]
ぼくが考えたのは、王朝和歌の歴史全体を示すことをしたい。
具体的にいうと、
古代の帝から中世の連歌師、応仁の乱のころの連歌師までで終わる。
応仁の乱以後、俳諧が生まれてからはもう和歌は滅んでいるという史観を示すこと。
大岡 読者は単に『百人一首』を読むだけでなくて、『百人一首』についてどのようなところまで問題意識を広げていけるかということをも同時に読み込むことができる。
丸谷 一つの面でいうと、「アララギ」中心の和歌史に対する批判。
別の面でいうと、東大国文中心の国文学研究の方法に対する批判。
十九世紀西洋の文学観を、日本の古代・中世文学に適用する素朴な方法に対して、あれこれと異議を唱えてる。
和歌を論じてはいるけれども、実は近代日本文学を支配している自然主義と私小説中心の文学観に対するぼくの反論提起を、和歌のアンソロジーという形でやっている。
大岡 連歌師たちは和歌を、ある意味でいうと非常に自覚的に守った。守ると同時に、五七五七七の和歌形式は、連歌が崩壊させた。連歌師の頭にあった和歌というものと、藤原定家の頭にあった和歌とは全然違うでしょう。
丸谷 ぼくは、厳密にいえば正徹[1381-1459]のところで滅んだと思うし、ひょっとすると正徹も、あれも次の文学形態、連歌とか誹諧とかの準備なのかもしれないという気さえする。」p.157-163
正徹の名前を知ったのは、
明治大学生田校舎図書館でアルバイトしていた、
明治大学文学部卒業・聖心女子大学図書館就職、直前の
1978年2月25日に明大生田生協で購入した、
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『梨のつぶて』晶文社 1966.10
「吉野山はいづくぞ」p.110-118
『展望』1965年3月号
https://note.com/fe1955/n/n49dc2860af81
でした。
もう四十年以上も経ってしまったんだなぁ。
「「よしの山はいづくぞと、人たづね侍らば、ただ花にはよし野、もみじにはたつたをよむことと思ひ侍りてよむばかりにて、伊勢やらん、日向やらんしらずと答ふべきなり。いづれの国と才覚はおぼえて用なし、おぼえんとせねども、おのづからおぼえらるれば、よしのは山としるなり。」
吉野を詠んだ古歌を正確に読みさえすれば、吉野が山であることは自然に判るし、またそれだけで十分だと彼は述べている。
……
ほとんど激越とさえ言って差し支えないほどの、伝統尊重の態度である。
彼にとっては吉野山は、大和の国にも伊勢にも日向にもなく、『古今集』から『源氏物語』と[藤原]定家を経て自分じしんへと到る伝統のなかだけにあった。
西行が詠み定家が選んだ吉野の歌の数々がある以上、吉野山はどこにもなくても一向かまわないと彼は考えていたのである。」
『梨のつぶて』p.115
読書メーター 丸谷才一の本棚(登録冊数175冊 刊行年月順)
https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091201
エクセルファイル
"発表年月日順・丸谷才一作品目録.xls"
作成中 現在3018行


https://note.com/fe1955/n/ncecbb5720ade
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『日本文学史早わかり』講談社 1978.4
『無地のネクタイ』岩波書店 2013.2
池澤夏樹(1945.7.7- )
「メイキング・オブ・文学全集」
『池澤夏樹、文学全集を編む』河出書房新社 2017.9

https://note.com/fe1955/n/n49dc2860af81
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『梨のつぶて 文芸評論集』晶文社 1966.10
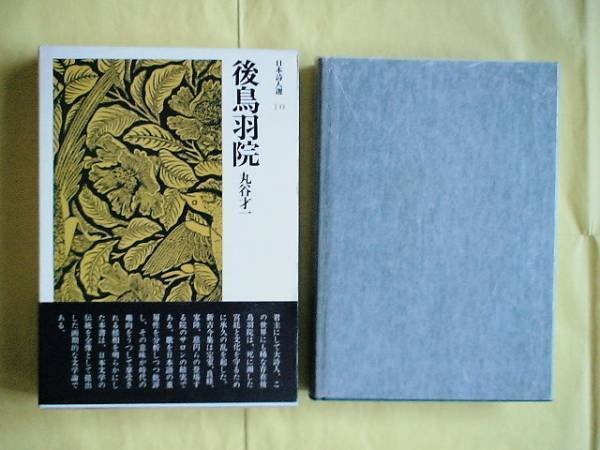
https://note.com/fe1955/n/n3c66be4eafe5
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『日本詩人選 10 後鳥羽院』筑摩書房 1973.6

https://note.com/fe1955/n/n56fdad7f55bb
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『樹液そして果実』集英社 2011.7
『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9
『恋と女の日本文学』講談社 1996.8

https://note.com/fe1955/n/na3ae02ec7a01
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
「昭和が発見したもの」
『一千年目の源氏物語(シリーズ古典再生)』
伊井春樹編 思文閣出版 2008.6
「むらさきの色こき時」
『樹液そして果実』集英社 2011.7

https://note.com/fe1955/n/n2b8658079955
林望『源氏物語の楽しみかた(祥伝社新書)』祥伝社 2020.12
『謹訳 源氏物語 私抄 味わいつくす十三の視点』祥伝社 2014.4
『謹訳 源氏物語 四』祥伝社 2010.11
『謹訳 源氏物語 五』祥伝社 2011.2
丸谷才一「舟のかよひ路」
『梨のつぶて 文芸評論集』晶文社 1966.10

https://note.com/fe1955/n/n1998cbebf2ac
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『挨拶はむづかしい』朝日新聞社 1985.9

https://note.com/fe1955/n/nd41726da27bb
丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)
『快楽としてのミステリー(ちくま文庫)』
筑摩書房 2012.11

https://note.com/fe1955/n/nf236daad7399
福永武彦・中村真一郎・丸谷才一
『決定版 深夜の散歩 ミステリの愉しみ』講談社 1978.6

https://note.com/fe1955/n/n26e000989c48
福永武彦・中村真一郎・丸谷才一
『深夜の散歩 ミステリの愉しみ(創元推理文庫)』東京創元社 2019.10
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
