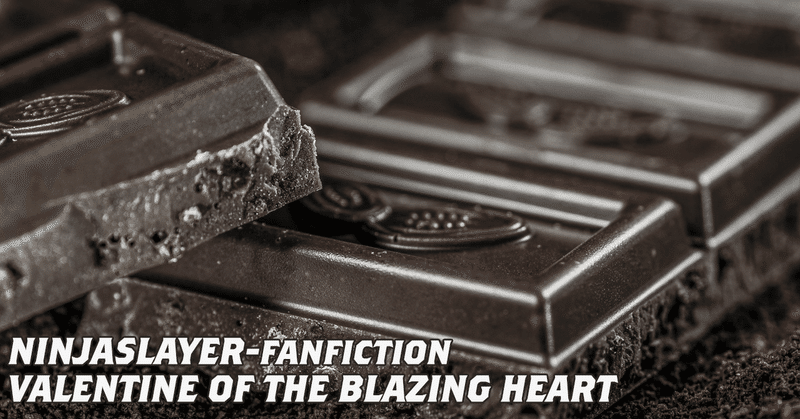
ニンジャスレイヤー二次創作:バレンタイン・オブ・ザ・ブレイジング・ハート
2月14日。バレンタイン・デイ。恋人たちが愛を誓い合い、語り合い、感謝を告げ、祝い合う、神聖なる祭事。……しかしそれも今は昔の話だ。こと現代日本・ネオサイタマにおいては、割拠する暗黒メガコーポの思惑により、市民の消費を促すための様々なイベントが企画され、日本的価値観と巧みにミクスチャーされた一つの独自文化を形成するに至っていた。チョコレートの贈呈は、その最も代表的な形式である。
ありとあらゆる場所へと商業的キャンペーンの手は伸び尽くし、恋人のみならず、日頃世話になっている人間、友人・同僚・クラスメイトなど、対象が限りなく無差別化されたアリガト・チョコ文化はその極みである。そして獲得したチョコの数や質でコミュニティ内の男子ヒエラルキーは決定づけられ、一ヶ月後のホワイト・デイにはいかに高価なものを返礼として送れるかでさらにその真価が問われるのだ。
贈られたチョコと同額程度の代物であればたちまち周囲の嘲笑を買うだろう。返礼そのものを忘れたり、拒否しようとすれば事態はさらに深刻となり、社会的地位の低下は免れず、場合によってはムラハチすら十分にありえる。このような背景から、否が応でも市民は無慈悲な過剰消費を強いられるのだ。
ある者はメガコーポの巧みな宣伝誘導にはまり、ある者はコミュニティ内での地位のために、等しくカネを吸い上げられてゆく。なんたる伝統とモラルを食い物とする暗黒商業主義の末路か。
……しかし、そのような世間の流れに与しようとしない者も珍しくはない。ことアウトローの坩堝たる、このネオサイタマにおいては。
「……しょーもねぇことやってんなァ、毎度毎度」
騒がしいストリートの中で、アシンメトリーの赤い髪と「地獄お」レタリングのマフラーをなびかせて歩くパンクス女が一人。彼女の名はイグナイト。この地でけして真っ当とは言えぬ稼業を営む……ニンジャである。
「高級な」「とてもカカオです」「千利休」などの購買意欲を煽るノボリが乱立し、肌寒い空気を物ともしない活気に包まれている様を、彼女は冷ややかに見やる。元よりこのような熱狂に興味など抱かぬ。企業の操る欺瞞まみれのキャンペーンが、パンク精神と相容れる道理はないのだから。
今日の仕事も終わった。後は帰るだけだ……と、ぼんやりと思考しながら歩いていると、ふとコンビニの側で足が止まる。イグナイトは何事か考えて自動ドア越しに店内を眺め、しばらくの間立ち止まっていたかと思うと……ゆっくりと入店した。
◆
とあるアパートの廊下。扉の前でがちゃりと鍵を開け、彼女は室内へとエントリーする。
「お、オカエリ。メシできてるぞ」
「……タダイマ」
……奥からのそのそと現れた男はシルバーキー。本名カタオキ・シンイチ。彼もまたニンジャであり……今現在のイグナイトの同居人である。自分も仕事の後だろうに律儀に出迎えてくる彼に少し呆れつつも、悪くはない気分を抗わず受け入れた。
「……ン」「……ン?」
イグナイトは表情を変えることなく、シルバーキーへと手に持ったコンビニの袋を突きつける。
「今日」「今日……ああ!」
シルバーキーの表情が、すぐに驚きと喜びの混じったものへと変わる。
「そうか……いや、なんだ。ありがとうな」「イイよ別に。ただのきまぐれだし」
はにかむような仕草を見せながら、シルバーキーはゆっくりとオジギをしてみせた。安チョコ一個で大袈裟なと思いつつも、それがこの男の長所であることを、イグナイトは知っている。
「そうか……えっと、いや、実はさ」「アン?」
そそくさと奥に引っ込んでは、何かを持ってくる。その手にあるは……然り! チョコレートである! それもイグナイトのものよりも明らかに大きく、高級な!
「いや、俺の方もこういうものをな……」
「ハァ!? お前、エッ……ナンデ!?」驚きに目と口を大きく開くイグナイト!
「日頃世話ンなってるし……テレビでもやってたけど、最近は男の方からあげるってのもアリらしいぜ」
「お前なァ、そんなのチョコ売りたい連中のクソみたいな方便に決まってんだろォ……」
どこまで人が良いのか。と思わず全身の力が抜けそうになる。
「それはわかってるけどさ……結局こういうのは、あげたいヤツが買うもんでしかないわけで……そこで変に意地張ってもしょうがねぇかなッて」
「アー……」
その論理はわからなくもなかった。実際自分とて安チョコとは言え買ってきてしまったのだから。頭を掻きながらイグナイトはシルバーキーの手からチョコを無造作に取る。一抹の気恥ずかしさも、手に伝わる重量感への妙な敗北感も表には出すことなく、奥ゆかしく軽く頭を下げた。
「ま……一応例は言ッとく。ドーモ」「おう」
「……メシの前にシャワーな」「おう」
◆
……とびきり熱いシャワーを全身に浴びながら、イグナイトは胸中で一人ごちる。まったくもって、パンクスが聞いて呆れる安穏生活ぶりだ。数年前の自分が見たら、果たしてどんな顔をするものだろうか。だが、それでいい。イグナイトは自分の行いを否定しない。彼女は常にしたいと思ったことをしているのだ。でなければ、最初からあの男と同棲などしていないだろう。
「……シンイチ」
その名をぼそりと口にして、くっくっと笑いが漏れた。あのいかにも人畜無害そうで頼りなさそうな男が、時折こうやって自分を驚かせてくるのが、どうにもムカついて愉快でたまらない。今まで自分が経験した中でもっとも不思議な感覚であり、しかし嫌いではなかった。
いつまで続くか? などと考えることもあるが、本来であれば、自分とは最も遠い世界にいるはずの男だ。何かの拍子で……それこそ明日に終わる関係でもおかしくはないのだ。信頼と執着は別のものだと、イグナイトは知っている。ましてや、彼女はもうティーンエイジャーではないのだから。
だが、とりあえずはあと一ヶ月。それまでは多少の何かがあっても我慢してやるかと、それだけがたった今、彼女の中で決まった。どうせ向こうはまた何かを用意してくるのだろうから、それを超える何かを。やられっぱなしでは終われない。そんなことを考えながら、勢いよく吹き出していたシャワーを止め、イグナイトは誰にも見られることなく、少女のように笑った。
【バレンタイン・オブ・ザ・ブレイジング・ハート】終わり
スシが供給されます。
