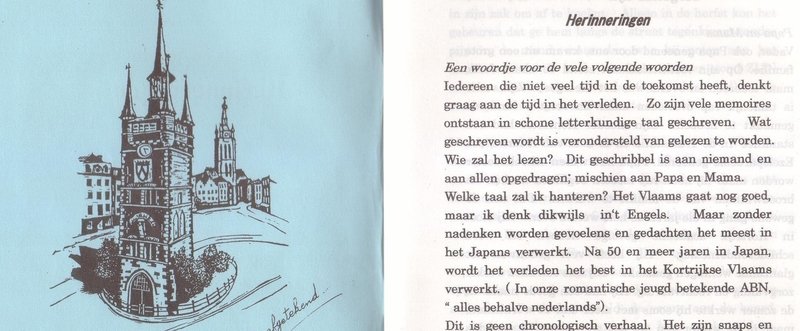
「御手の中で〜とある老司祭の生涯」‥1
〈まず最初に。誕生日の3月1日にnoteを始めたので、もうすぐ3カ月。昨日、ようやくですが、100人を超える方がフォロワーになってくださいました。なので、ここで、本来、わたしがこのnoteでみなさんにいちばん読んでいただきたかった小説「御手(みて)の中で」を更新していきたいと思います。わたしが幼児洗礼の(生後何カ月かで洗礼を受けた)カトリック信徒であることは何度も書きました。そして小さい時から気がつけばそこにいてくれた神父さまが(ベルギー人ですが、戦後の日本に宣教に来られ、日本人に帰化までして日本の文化に溶け込もうとされてきた方です。一人の神父であるのみならず、宗教家の枠を越え、リノリウム(木版画)を手掛ける芸術家であり、一般の女子大生や非行に走った少年らに指導者であり一人の教師として、時には父親のように慕われる、人間としてとてもチャーミングな方でした。
しかし2011年3月の終わり。あの未曾有の大震災から半月ほど経ったとき、彼はたった一人、誰に看取られることもなく、家の玄関で亡くなっているのが発見されました。たくさんの友人知人を持ち、決して孤独な人生ではなかったにもかかわらず。。83歳でした。残された彼の部屋には9冊にも及ぶ、母国語であるフラマン語で綴られ、自身で描いたリノリウムの挿絵がところどころに入った「Herinneringen」と題された人生の記録が残されていました。「Herinneringen」とは、日本語で、「楽しかったこと、そしてそのほかの想い出---回想録」といったような意味合いであり、この小説「御手の中で」は、一人の実在した司祭としての彼、そして、その彼の残した人生の記録を基に、著者自身の想いを重ね、想像とフィクションを巡らせて文字を紡いだ文章です。初回は無料、2回目からは有料マガジンか何かに設定させていただき、読みたいと思ってくださった方に読んでいただきたいと思っています。ではここから本編に入ります=なお挿入する画像は、Herinneringenの中に出てくる本物の挿絵を使っています〉
‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥ ‥‥‥‥
「御手の中で 〜とある老司祭の生涯〜」
プロローグ 静寂の時
いつからこうしているのだろう。気がつけば、じーっという音が聞こえ続けていた。静まりかえった部屋に一人でいると、頭の芯から響いてくる、あの鈍く、重い音だ。誰もがいちどはそのような音を聞いたことがあるのではないか。ZとTがいり混じったような、一直線に長く伸び続ける音。矛盾しているようだが、静寂の中でこそ、聞こえてくる音がある。少なくとも私は、人生において幾度もの場面で、その音にじっと耳を澄ませてきた。気がつけば、じーっという音が聞こえ続けていた。静まりかえった部屋に一人でいると、頭の芯から響いてくる、あの鈍く、重い音だ。誰もがいちどはそのような音を聞いたことがあるのではないか。
Z‥‥T‥‥zzztttt‥‥‥‥zzztttttzzzz ‥‥ZZZZ‥‥TTTT‥‥TTTTZZZZZZZ‥‥
黙想ということをどこまで真面目にやってきたか自信がないのだが、この音はそう、黙想するときにはいつも必ずそこにあった。祈りとは切り離せない音だ。これまで毎朝毎晩わたしは祈りを続けてきたが、その祈りにどれほど意味があったのか正直なところ分からない。神はわたしの生涯の祈りにどれほど耳を傾けてくださっただろうか。。そんな自問をしたのかどうか。いや頭を掠めたのは確かだ。もっとも、この時鳴り続けていた音は、これまでに聞いたどの音とも違う、初めて聞いた音だった。ZZZ‥‥TT‥‥と、ただどこまでも長く伸びていくのではなく、辺り一面に張り付いてそこで止まっている感じ。音とともに時間の流れが、急速にしてゆっくりとテンポを落としていくような感覚を覚えた。
これが黙想なら随分と長い黙想だ。なんとも言えない不思議な静寂。決して不快ではない。夢をみているのだろうか。。そうこうしている間に私の意識は、今さっきまであった現実の世界を離れ、70年も前の、遠い少年の日に帰っていた。気が付けば年老いた自分は忘れ、あのころ、第一次世界大戦の余波もまだ残っているうちに、次の第二次大戦の足音が近付いて来ていたあのころ、ベルギー・フランダース地方の田舎町に暮らす、当時のあの地方にしてはごくごく一般的な子沢山の家の次男坊だった自分に。ちょうど、父の背に馬乗りになって狭い部屋の中を這い回って遊んだり、母がバニラプリンを作るのをすぐ傍でじっと待って、できあがるのと同時に指を突っ込んでペロッと舐めるのが楽しみだった、そんな、ほんのりと甘い時代が終わりを告げ、幼いながらにも、この世の中に『不条理』が満ち満ちていることが分かり始めたころの僕に。
夢ではない。その瞬間、時空を超えて、僕は確かにそこにいた。80をとうに過ぎた僕ではなく、無邪気なフランダースの少年、弟と一緒に泥んこになって叢に這いつくばる14歳の僕が。そして、つい今しがたまで聞こえ続けていた、あの静寂の音は消えてなくなってしまっていた。
++司祭の回想1 少年の見た戦争

「兄さん、来た、来たよ!」
「本当だ。ジャック、さあ早く隠れるんだ」
村いちばんの幹線道路、といっても、もちろん舗装などされていようはずはなく土埃の舞う田舎道。そのすぐ脇の叢で、僕とジャックは、じっと身を潜めていた。遥か彼方からドイツ軍が刻々と迫って来ている。その「不気味なほどに大きい」と聞かされていた戦車を、純粋な好奇心から見てみたかった。子ども心にも、いや子どもだからこそ植え付けられていた愛国心から来る敵国への憎しみ(といってもまだまだ可愛らしいと言える程度の憎しみ)と少年ならではのイタズラ心を持て余していた僕らは、その日、早朝から無数の画鋲を道にばら撒き、巨大な戦車がその上を通るのを待ち受けていたのだ。第2次大戦が始まったばかり。僕は、物心つく前からずっと一つ布団で寝ていた2つ違いの弟と、当時、既に15歳近くになっていたというのに、何をするにも一緒の毎日を送っていたのだった。
大戦前、僕は12歳で、生まれ育ったフランダース地方の片田舎から、遠く離れた大きな町の神学校に入学することとなり、大家族を離れて一人、慣れない寄宿舎生活に入った。ところが1940年5月8日、ベルギーに最初の独軍侵攻がなされたことにより、あらゆる学校は勉強どころではなくなった。僕の通っていた神学校でもすぐさま帰郷命令が出され、今思えば恥ずかしいほど幼稚だった僕はよく訳も分からないまま、まだ始まったばかりだった学生生活のすべてを中断し、不安に駆られて列車に乗るたくさんの人々に紛れて一人大きなバッグを大事に抱えてそっと車両の片隅に座り、長い時間をかけて、再び故郷の田舎町に戻った。むしろそのことを喜び、弟と2人、世の中を大きく包み初めていた不穏な空気をものともせず、日一日と10人家族の暮らしが困窮していくのを感じながらも、なんとも無邪気に日々を過ごしていたのだ。
その朝の行動は、そう、僕らのささやかなレジスタンスと言ってよかった。叢の中にかがみ込んで地面に耳をあて、その巨大な戦車の足音を聞きつけるやいなや、すぐに逃げ出せるよう態勢を整え、どきどきしながら、その時を忍耐強く待っていた。もっとも僕は内心、それほどの戦車の頑丈なタイヤが画鋲ごときにやられるものか、と高を括っていた。しかし! 結果は違った。なんと僕らが画鋲を撒いたその場所で「バーン!」と何かが破裂するような大きな音がした。巨大な戦車の頑丈なはずのタイヤは、小さな画鋲の塊にあっけなく破られ、パンクしたのだ。
「お兄ちゃん!」
「しっ! ジャック。喋るな」
緊張の一瞬。僕らは叢に這いつくばって身を隠し、そっと辺りを窺った。戦車は僕らの3㍍ほど先で止まり、数人のドイツ兵が降りてきたかと思うと、すぐに賑やかな声が聞こえてきた。
「ワハハハ」
「ヒュー。やられたぜ」
彼らは笑っていた。ほっとした瞬間、冷や汗が流れた。つられて笑い出しそうになっているジャックの口を素早く押さえ、そのままじりじりと後ずさりした。そして彼らが視界から消えた時点で思いっきり走って逃げた。
レイユ川のほとりまで来て寝転がった。まだ息が弾んでいる。
「あー、お兄ちゃん、面白かったね」
ジャックがにこにこして言った。
「うん。ジャック。でも今日だけだ。もうやらないぞ」
顔は引きつれ、心臓の動悸がなかなかおさまらなかった。僕は生まれながらの小心者なのだ。2歳しか違わないのに、勇敢で物怖じしない弟。その小さな手をぎゅっと握りしめると、その手もまた汗でじっとりとぬるんでいた。
そんな幼いころの映像がなぜ今、急に脳裏に浮かんだのだろう。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
そう思った時、またもや、あの静寂の音が鳴り始めた。そして、ふいに、私は、ほんのりと温かく、なめらかな白い手が私に向かって差し延べられるのを感じた。その手は老いさらばえた私の手を静かに取った。
何一つ思い煩うことはない。この手に委ねよう。そう自然に思うと同時に、鉛のように重いはずの私の体躯は、軽やかに空中へと引き上げられたように感じた。もはや何の音もしなかった。
「主よ、やっといま、あなたの御(み)もとにゆけるのですね」
天を仰いでそう口に出したが、声にはなっていなかったかもしれない。答えはないままに、私の躯は真っ白な、いや透明な光の中を流れていくようだった。手を引いてくれているのが、生涯、慕い続けてきた、その方だということだけははっきりと分かった。

聖母マリア。しかし、私は60年もの間、カトリックの司祭として生きてきながら、ここで正直に明かせば、神の子が聖母の胎内に汚れなく宿られたということに対する疑いをぬぐいきれないでいた。だが、それ故に、ある種の親近感を持って、自分の母のように、彼女を常に身近に感じてきた。「崇拝」の対象としてではなく。それはやはり司祭として正しい信心のありようではなかっただろう。それにもかかわらず、主はいま、聖母を通して私を御もとへと、既にこの世を去った家族や、数多くの友らと同じように、緩やかにカーブを描く水平線の向こう側へと、導いてくださっているのだ。そこには最愛の弟にして永遠の友、ジャックもいる。
〈死はなんら怖れるものではない〉
これまでの人生の中で、もちろんそう確信していたが、そのときがこんなにも安楽に満ちていたとは。神の前にあって人間は、生まれる時も死ぬ時も、何の心配をせずともよいのだ。そう、心の底から幼子のように、聖母に躯をあずけるだけで。
感謝の気持ちに包まれて、私の肉体は安らかに眠りに落ちていった。
→→‥‥2に続く
#小説 #御手の中で #老司祭 #カトリック #宣教 #リノリウム #Herinneringen #ベルギー #フランダース #第一次世界大戦 #第二次世界大戦 #バニラプリン #聖母マリア
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
