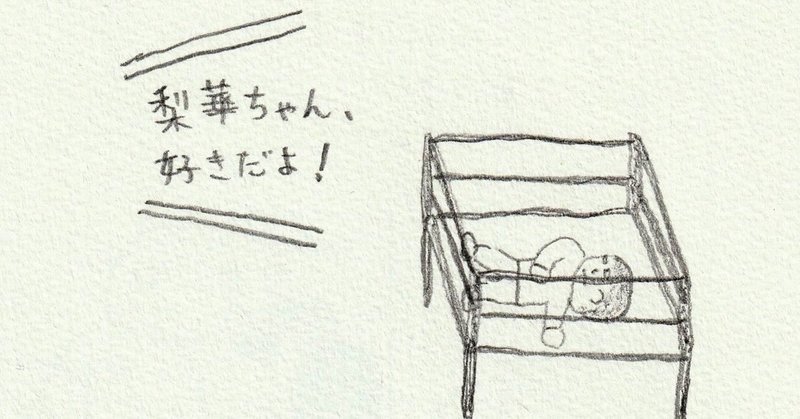
私のパパは、石川梨華の旦那さん
まえがき
この原稿用紙5枚ちょっとの短い妄想小説は、梨華ちゃんがプロ野球選手と結婚してしまう10年くらい前に書きました。だからやたら希望にあふれています。その頃の僕は、よもや梨華ちゃんがプロ野球選手が好きだなんて思っていなかった。よもやよもやだ。僕がそれとは真逆の存在と言っていい小説家になって、梨華ちゃんと結婚したという設定の、今となっては哀し過ぎる小説です。僕と梨華ちゃんとの間に生まれた娘の視点から書きました。最近やっと、梨華ちゃんの結婚による悲しみを乗り越えたので、この哀し過ぎる妄想小説を読み返すことができました。書き直すところはほとんどなかった。すぐ読み終わるので、よかったらお読みください。
私のパパは、石川梨華の旦那さん
私のパパは本当にしょうがない人。ママのことが好きすぎるのよね。きっと私のことより好きなんだわ、いやな人。ママが玄関で靴をはいている。私をだっこしながらパパはそれを切なげに眺めている。ママが「じゃ、行ってくるね」と言うと、パパはママにしがみついた。
「行かないで梨華ちゃん。さみしいよ。好きだよ!」
「もう、ふっち君たら、甘ったれなんだから。じゃあ仕事行ってくるからね」
「そうだ梨華ちゃん、いいこと考えたよ。僕も一緒に行っていい?」
「だめよそんなの、恥ずかしいじゃないの。あなたは家でやることがあるでしょう」
「さみしいな……」
「りながいるから、さみしくないでしょう」
「そうだね……。ねえ、梨華ちゃん」
「なあに」
「好きだよ!」
「もう……わたしも好きよ」
「うわお、梨華ちゃん!」
そして二人は熱いキスを交わす。私はママの化粧が取れないか心配になる。ママが出て行って玄関のドアが閉まると、パパは泣きそうな顔になって、「梨華ちゃん……早く帰ってきてね。うえーん」と言った。ああ、これが30歳を過ぎた男だなんて、信じられないわ。情けないったらありゃしないわ。
それからパパは私を背負いながら掃除をした。洗濯物を干した。そのあいだずっと、「梨華ちゃん……好きだよ」だとか呟いていた。なんて貧弱なボキャブラリーなのかしら。好きか、愛してるか、それに「超」をつけるか、それくらいしか言わない。とても小説家とは思えないわ。
お昼ごはんを食べたあと、パパは私をベビーベッドに優しく置いて、殊勝にも机に向かう。しばらくすると、「あーだめだ。梨華ちゃんがいないとだめだ。書けないよお」という悲痛な声が聞こえてきた。「パパったら、ママがいたらもっと書けないくせに」と思って、笑っちゃった。そしてパパが髪をかきむしる音を聞きながら、私はいつのまにか眠ってしまった。
目を覚ますと、部屋には赤い夕焼けの光がさしこんでいた。パパは机に突っ伏して寝息を立てている。まったくしょうがないんだから。少しは書けたのかしら。お股がひんやりしていて、お漏らししたことに気付いた私は、大声で泣いた。びええええん。ガタンと音がし、パパがやってきて私のことをベビーベッドから優しく抱き上げる。
「どうしたのりなちゃん。あら、おしっこしたのかな。これはこれは。おむつを取り替えないとね。『とっかえっ娘。』って知ってる? 映画なんだけど。梨華ちゃんがね、出てたんだよ、それがかわいくてさ、まあいつもかわいいんだけど……」
いいから早くとりかえてよ、という気持ちで、私はさっきより大きな声で泣く。
「あらごめんよ悪かった、りなちゃん。いますぐやるからね」
パパは紙おむつをもってきて、濡れたものを取り外す。新しいのを丁寧につけながら私に語りかける。
「りなちゃんも、ママみたいな女性になるかなあ。なってほしいなあ。綺麗で優しくて、かわいくてお茶目で、まじめで清純で、そんな女性に。きっと大丈夫だね。だって梨華ちゃんの娘なんだもんね」
そこで私は思った、だけどパパの娘でもあるからなあ、あんまり大丈夫じゃなさそうだなあ。
それからパパは私を背負ってスーパーに行く。ボンカレーと玉ねぎとお肉と人参を買う。
「お肉スキスキ、カレーすきすき、梨華ちゃん好き好き」とパパが唄いながらの帰り道、携帯がなった。「梨華ちゃん、元気!? そうか、よかった。元気であることが何よりだよ。安心した。お仕事おつかれさま。……好きだよ。え、だから、好きだよって言ったの。なんだよ、つれないなあ、照れないでおくれ。もう帰ってくるの? ほんとに? わーい。早く会いたいなあ。それじゃ、気をつけて帰ってきてね。何かあったら電話してね。助けにいくから。へへへ。なに、それほどでも。うんわかった、梨華ちゃん、好きだよ! へへへ。それじゃまたね。ちゅ〜」
私はパパの頼りない背中に揺られて、そのうちに眠ってしまった。
目を覚ますと、パパの声が聞こえた。カレーのいい匂いがする。
「ねえ梨華ちゃん、おいしいかい。愛情たっぷりボンカレーだよ。おいしい?」
「うん、おいしい。なんか、いつもごめんね、家のことやってもらっちゃって」
「なにをおっしゃるお嬢さん、いいんだよ、梨華ちゃんにはお仕事があるんだから」
「でも、ふっち君もお仕事あるでしょ」
「そうだけどさ、家事の合間にやるからいいんだよ、大丈夫。そんなことより、今日のお仕事はどうだったの」
「うーん、まあいつも通りかな」
「そっか、いつも通りなのが一番だよね。……梨華ちゃん、あのね、好きだよ」
「なによ、嬉しいわね、ありがとう」
「へへへ、梨華ちゃんはかわいいなあ」
「んもう、困っちゃうわ。そんなに見つめられたら食べにくいじゃない」
「あら、ごめんね。つい見つめ過ぎちゃった。梨華ちゃんがかわいいから。むふふ、大好きだよ」
「わかったから、ほら、ふっち君も食べなさい」
「うん、そうだね。よーし、食べるぞ!」
二人はボンカレーを平らげた。それから私は離乳食を食べて、お風呂に入り、ベビーベッドに寝かされた。灯りが消える。暗闇の中から、とびきり甘い語らいが流れてくる。仲がいいのね。妬けちゃうわ。聞いているだけで糖尿病になりそう。そのうち私は桃色の眠気に誘われて目を閉じる。そして思う、明日もきっと同じような一日になるんだろうなあ。明日もあさってもずっと。やれやれ、まいっちゃうなあ。
お忙しいところ、最後まで読んでくださってありがとうございます。もし「いいね!」と思ったら、愛の手を差し伸べて頂けるととても嬉しいです。noteやYouTubeの製作費に使わせていただきます。
