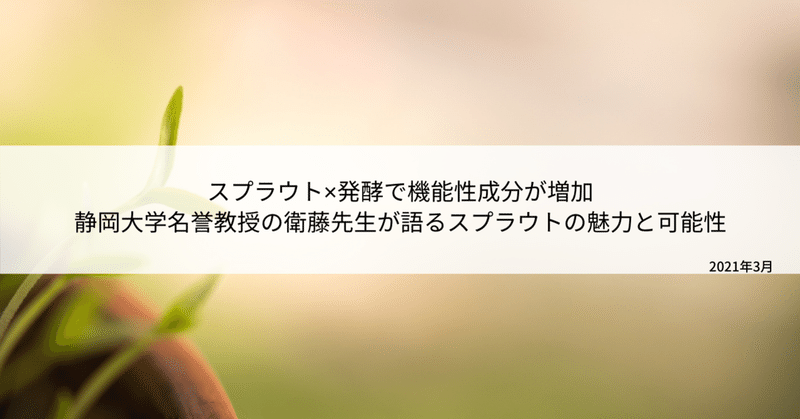
スプラウト×発酵で機能性成分が増加 静岡大学名誉教授の衛藤先生が語るスプラウトの魅力と可能性
静岡大学名誉教授の衛藤英男先生は、農産物や海産物の機能性を研究しています。『科学・技術研究』という学術雑誌に「野菜スプラウトの機能性の最近の進展─発酵ソバスプラストを中心に─」という論文を発表したばかりの衛藤先生に、機能性成分が豊富に含まれるスプラウトの魅力と可能性について解説していただきました。
スルフォラファンの抗ガン作用で注目されたスプラウト
静岡大学の衛藤英男です。農学部応用生物化学科の教授を務めてきた私は、茶・ワサビ・トマト・サクラエビなど、静岡県産の農産物や海産物をはじめとする全国の地域資源の機能性研究に長年携わってきました。近年、「食と健康」の関係があらためて注目されています。実際に、特定保健用食品や機能性表示食品は増加しており、以前よりも身近なものとなっています。背景にあるのは、生活習慣病の増加や消費者の健康志向の高まりです。
味や彩りといった従来の食事の楽しみに加えて、不足しがちな栄養成分を取り入れる──。超高齢社会を迎える日本では、食による病気の予防・改善はますます重要になっていくでしょう。そんな中で私が注目している食品の一つが、「野菜スプラウトの機能性の最近の進展─発酵ソバスプラストを中心に─」でもご紹介した新芽野菜「スプラウト」です。サラダやみそ汁などにスプラウトを加えるだけで、新芽に含まれている豊富な栄養素を手軽に摂取することができます。
リンク:野菜スプラウトの機能性の最近の進展─発酵ソバスプラストを中心に─
健康のイメージが定着しているスプラウトには、ブロッコリースプラウトや発芽玄米などが挙げられます。ブロッコリースプラウトに含まれている機能性成分は、スルフォラファンです。1997年、ジョンズ・ホプキンス大学教授のポール・タラレー博士が抗ガン作用を報告したことで、ブロッコリースプラウトは一躍脚光を浴びる存在になりました。
一方の発芽玄米には、血圧の正常化、コレステロール・中性脂肪の増加抑制、腎臓・肝臓・膵臓の働きの活性化、血糖値の上昇抑制、不安障害の解消などの効果が期待されるGABAが豊富に含まれています。発芽させることでGABAの量は玄米の10倍以上に増加することが明らかになっており、信州大学の茅原紘先生らが行なった実験では、神経伝達物質を抑制することによって睡眠障害が改善する可能性も示唆されています。
スプラウト×発酵で機能性成分が増加
発芽によって機能性成分が増えること、つまり、スプラウトそのものが健康食品であることはすでに認知されていますが、スプラウトを発酵させることで機能性成分がさらに増加することはご存じでしょうか。「野菜スプラウトの機能性の最近の進展─発酵ソバスプラストを中心に─」では、私も研究に携わってきた「発酵ソバスプラウト(発芽そば発酵エキス)」の実例を取り上げています。
ソバスプラウトは現在、静岡県富士宮市にある不二工芸製作所の自社農場「不二バイオファーム」で水耕栽培されています。2008年、当時、信州大学の修士過程に在籍していた前島靖勲常務から共同研究の依頼を受けました。これが発芽そば発酵エキスとの出合いです。地元である静岡の企業の研究を応援したいという気持ちがあって快諾したわけですが、“ソバスプラウトを発酵させる”という着想に対する好奇心・興味もありました。
まずは、ソバスプラウトの特性を簡単にご紹介しましょう。ソバスプラウトには、血圧降下作用のあるルチンが豊富に含まれています。発芽6日目で含有量はピークを迎え、ルチンはソバ(ソバの実)の10倍以上になることが確認されています。そのほか、抗酸化物質であるアントシアニン、メラニンの生成に関与しているチロシナーゼという酵素の活性を抑制して美白効果を発揮するシス・ウンベル酸などが、ソバスプラウトには含まれています。

ソバスプラウトの青汁
ソバスプラウトを乳酸発酵させると、発酵の過程で新しい機能性物質が生成されることがわかっています。厳密には、ソバスプラウトの青汁を乳酸発酵させているのですが、アントシアニンの一種で発酵ソバスプラウトに赤色をもたらしているケラシアニンのほか、アミノ酸、アスパラギン酸、リジン、メチオニンなどは2〜5倍、GABAについては約20倍に増加していました。

発酵ソバスプラウト
その後、抗酸化物質を分析したところ、ケルセチン、インドール-3-エタノールを確認することができました。インドール-3-エタノールはソバスプラウトの青汁には含まれていない成分で、ケルセチンについては発酵によって大幅に量が増加しています。私たちの実験では、これらの成分による抗酸化活性はソバスプラウトの3〜4倍、アスコルビン酸という抗酸化剤の2倍であることが明らかになっています。
そのほか、血圧の上昇にかかわる「アンジオテンシン(ACE)II」の生成阻害物質を調べた結果、ニコチアナミン、2”-ヒドロキシニコチアナミンという物質を確認。含有量はそれぞれ、青汁の2.7倍、3.3倍に増加していることがわかりました。実際に、高血圧の改善に直結するACE阻害活性を調べると、発酵ソバスプラウトの活性はソバスプラウトの4倍に増大していることが明らかになりました。乳酸発酵の過程でたんぱく質が分解してできた3種類のペプチドが新たに確認されており、実験ではそれらの関与も示唆されています。
発酵のメリットは、ご紹介してきた機能性成分の増加だけにとどまりません。ソバスプラウトを乳酸発酵することで、ソバアレルギーを引き起こすたんぱく質がほとんど分解されることもわかっています。さらに、ソバスプラウトの青汁は、肥満細胞からのヒスタミンなどの化学伝達物質放出に関わり、アレルギー症状を引き起こすヒアルロニダーゼという酵素の阻害活性を示しますが、乳酸発酵により阻害活性が約7倍増強されることから、発酵ソバスプラウトは抗アレルギー作用も期待されます。
今回発表した論文では発酵ソバスプラウトを中心に最近の研究情報をご紹介してきましたが、今後、ネギやニラ、モロヘイヤやカイランなどのスプラウトや、それらの発酵エキスが新たに出てくるかもしれません。サプリメントなどの形状でしか摂取できないものもありますが、スプラウトはふだんの料理に加えるだけで無理なく手軽に食べることができておすすめです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
