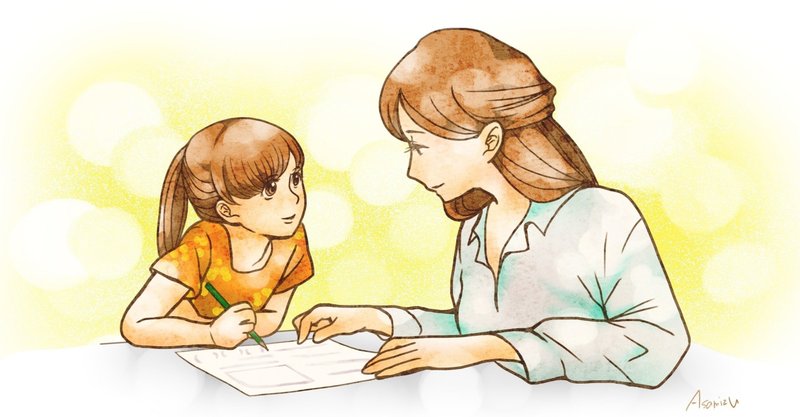
井出進学塾からの問題提起-小学生の保護者様へ!新学習指導要領がはじまりました。
こんにちは、井出進学塾です。
コロナによる休校が長引き、新しく始まる大学入試制度との関連などが話題になっています。
これらに比べると、どうしても影が薄くなってしまいますが、今年度より小学校で新しい指導要領のスタートです。
本来、社会でもっとかんかんがくがくと議論されてしかるべきなのですが、これもまたコロナによる弊害の一つと言えるでしょう。
もっとも、「プログラミング」をはじめとするICT教育、また、主権者教育、消費者教育など、確かに早期からとりくんだ方がよいにはよいので、文句のつけようがありません。現場の先生たちの負担はかなりのものでしょうが、それも別の問題として、おいておきましょう。(おいとけない問題かも、しれませんが・・・)

ここで扱うのは、もっとせまく学問的なカリキュラムの問題です。視野が狭いと、ご批判を受けるかもしれませんが、これこそ大切な問題ですし、私が取り扱える話題でもあります。
それでは、みていきましょう。まずは、
小学6年生からです。
学校再開のおりも、まずは中学3年生と小学6年生・1年生から、という案が示されていました。これは、小学校内容も中学校内容も今学年度で終わらせたい、という文科省の意向でしょう。
ただし、小学6年生については、カリキュラム的にそれほどあわてる必要はないと考えます。「ゆとり」の反動で、学習内容が増えた結果、小学6年で新しく学習する計算技術はほとんどなく(後でくわしく述べます)、他の単元も中学で学習する内容をちょっとずつ予習するような内容です。(もっとも、それはそれで大切なのですが、中には中途半端にやらない方がいいだろう、と思えるところもあるくらいです。)
問題なのはむしろ小学1年生の方ですね。保育園あるいは幼稚園に通っていないお子さんですと、ひらがなでも自分の名前しか書けない、あるいは自分の名前すら書けない、というお子さんはいくらでもいます。結果、2か月余りの小学校がはじまるのが遅くなりましたが、成長期のこの2か月はかなりの損失といえます。小学1年生を先に学校をはじめさせるというのは、唐山の方針ですし、6年生は1年生の世話をする役割も担っているので、そのような方針になったのでしょう。
では、カリキュラム的な問題をみていきましょう。
実はすでに移行措置はとられているので、今年に入ってどうこう、ということはありません。
現小学6年生にとっては、今まで6年で勉強することになっていた「速さ」の単元をすでに5年生のときに学習し、今まで5年で勉強した「分数×整数、分数÷整数」の単元が6年にまわされることになりました。現小学6年生は、令和2年の5月の段階で、「分数×整数、分数÷整数」のやりかたを、まだ知らないということです。
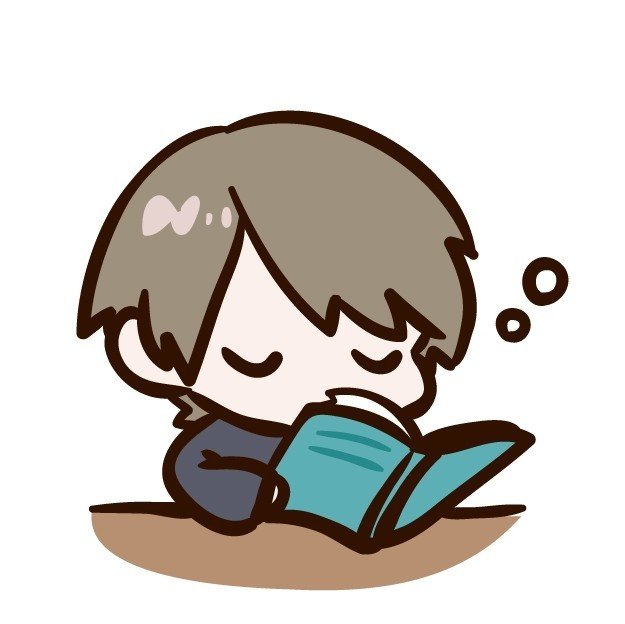
ここで誤解される方が多いのですが、「分数のかけ算・わり算が、5年生内容から6年生内容に変わった」という認識では、まちがいです。
今までのカリキュラムでは、
5年生の2学期に、①「分数×整数、分数÷整数」の単元を学習し、
6年生で、②「分数×分数、分数÷分数」を学習することになっていました。
今までは、①「×整数(÷整数)」の段階を経てから、②「×分数(÷分数)」を学習していたのが、今回の改定で実質①と②は、同時に扱うことになります。
ここから、私の主張に入ります。
日本の教育カリキュラムは、旧来、ひじょうにすぐれたものでありました。
特に、どこらへんが、すぐれていたかというと・・・
時間的熟成を、大事にしていた点にあります。
今までのカリキュラムでしたら、①と②の間に、冬休み・春休みのワーク、日々の宿題などが、はさまります。
その過程で、例えば「(3分の1)×6」は、(3分の1)は3つで1になるので、6つあれば確かに2になるのだけど、それが約分で求められる不思議さなど。また、わり算でいうと「(3分の2)÷2」の計算で、(3分の2)は(3分の1)が2つ分なので、2でわったら確かに(3分の1)ですし、「(3分の1)÷2」でしたら、分母を2倍することによって求める答えになる、しくみ。
こういうものを、もちろん個人差はありますが、1人1人の中で熟成していき、「×分数」や「÷分数」の計算の理解につながっていきます。
もちろん、一般の親御さんからすると、そこまでは覚えていないでしょう。
塾のバイトスタッフ講師にも、ここらへんはしっかり指導しないと、いきなり逆数を使って指導しようとしてしまいます。しかし覚えていないだけで、そういう過程を経て分数の計算の理解につなっがてきた、というのは事実です。

私が今指摘している問題は、今回の改定ではじまったことではなく、いこう措置、あるいは前回の改定からのことかもしれません。
近年、学校の先生が①の「÷整数」を最初から逆数で教え、そのくせ②「÷分数」では、分数のわり算はなぜ逆数をかけるのか?にこだわり、あまり有益ではない途中式を書かせる事例を多くみかけました。
当初は、困った先生がいるものだな、と思いましたが、どうやらこれが文科省の方針のようです。
私の指摘した①と②の間の熟成が必要、という問題に対する文科省の対処が「分数のわり算は、なぜ逆数をかけるのか?について、しっかりと扱う」・・・ということでしょう。
それが効果的なことなのか、はなはだ疑問ですが、こうなってしまっては、仕方ありません。我々のような民間塾は、それに合わせて最善を尽くしていくだけです。(ここらへんを問題視する、教育の専門家さんとかが、もっと声をあげてほしいですけどね・・・)
私の印象としては、文科省は世論や
私立中学受験専門塾 を、気にしすぎです。
指導の効率性など、それは、はたからみればこういうところの方がすごそうにみえてしまうかもしれませんが、けっして公が気にするべきところではありません。もっと、従来のカリキュラムに誇りを持つべきでしょう。(もっとも、「ゆとり教育」のときは、もっとボロボロでしたが・・・)

私は、気にせずに今までの方針で行くべき、と考えていますが、目立たない所でもけっこうな、変化があります。
例えば、今までは「対頂角の性質」や「三角形の内角と外角の関係」は、中学2年生になって、『定理』という考えとともに、はじめて使ってよい、ということになっていました。ところが、今では小学算数でも使用可です。
塾などで、裏技のように教えるから、学校側もそう対応せざるをえなくなったということでしょう。
(これに関しては、早めに教えられるものなら早めに教えればいいだろう、という意見を持たれる方も多いでしょうが、私は時間的「熟成」を重視する立場です。もっとも、こうなってしまった以上、それに合わせるしかないでしょう。)
私が、もっとも困ったことだな、と思っているのが、小学6年算数内容の
分数・小数の混合計算問題 です。
都会の名門私立中学受験塾ではそうでもないかもしれませんが、地方の私立中学受験塾に通われていた生徒さんは、私からみて、実によくない計算のクセをつけているな、と思うことがよくありました。
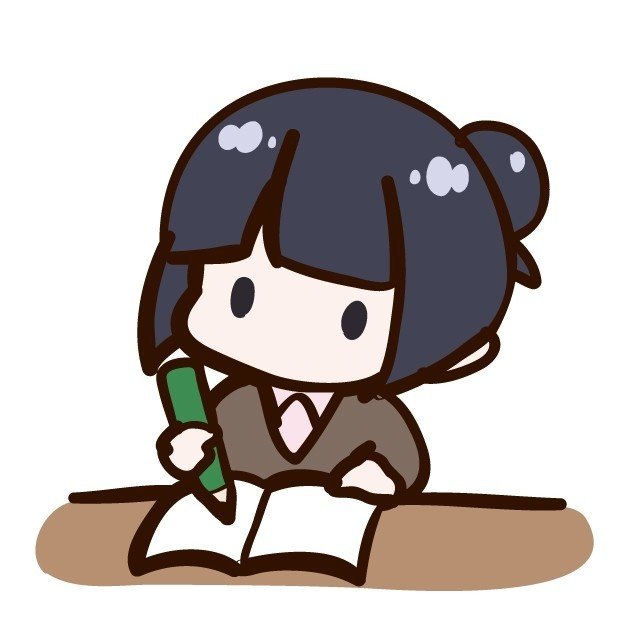
中学では、それほど問題にならないでしょうが(分数・小数混合計算は、あまり出てこない、というか、使いこなせる人が少ない、と言った方が正確でしょう)、高校生になって化学や物理に取り組むとき、こんなクセがついていたら、とうてい対応できないだろう、というクセです。計算力をいたずらに下げる、悪いクセです。
そのような計算が、な、な、なんと・・・
小学6年算数でも、扱われるようになっています
前回の改定からです。
確かにそういう塾でそういう計算法を教えられると、すごそうにみえるのは、わかります。しかし、それを公立の小学校の児童に強いる、というのは、いかがなものかと思います。文科省は、計算力を伸ばそうという意図でしょうが、まったくの逆効果です。
これに関しては、なんとかやめさせたいですね。
しかし、私がやめさせたいと思っても、どうこうなるものではなく、やはり対処法を提供していくしかできないでしょう。
このような計算をさせられるようになったのは、現中学3年生からです。
来年、高校の化学や物理の先生方は、びっくりするのでは、と思います。
やはり、ここらへんは、私にできる範囲の注意喚起や、対処法の提供をしていかなければと、感じています。
以上です。
ご意見・ご感想、お待ちしています。
文 井出進学塾(富士宮教材開発) 井出真歩
ツイッターはじめました。
よかったら、フォローお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
