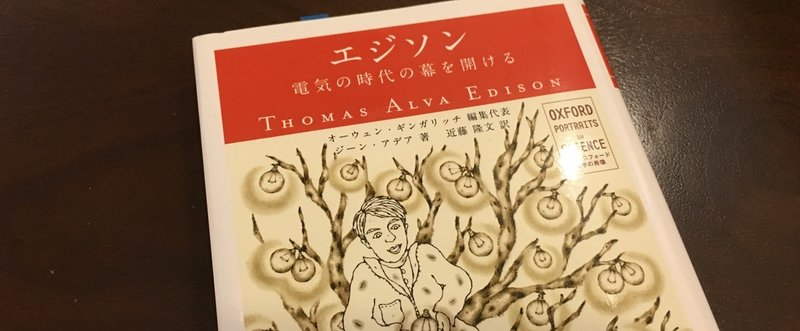
めざせ発明王。
小学3年生くらいのひどく暑い夏。クラスの友だち数名のあいだで、ある遊びが大流行したことがあった。
屋根のない、野ざらしの駐車場に停められた自動車の鍵を、誰かが親から借りてくる。炎天下の、シートに触れるだけで火傷しそうになるような車のなかにみんなできゃあきゃあ言いながら入る。急いでドアを閉め、熱気が外に漏れ出すのを食い止める。「うおおお」とか「ひえええ」とか思い思いに叫びつつ、あるいはじっとこらえつつ、時が過ぎるのを待つ。
玉のような汗が噴き出してくる。頬が、手が、半ズボンからむきだしになった太腿が、ピンク色に染まり表面がちりちり熱を帯びてくる。
存分に苦しみ抜いた末、誰かが「もうダメだっ!」とドアを開け、外に飛び出す。あわせてみんな、転げるように外に飛び出す。
と、さっきまで暑かった外気の、なんと涼しいことか。頬をすり抜ける風の、なんとさわやかなことか。目を閉じた男児たちは両の手を広げ、天を仰ぎ、その清涼を全身で味わいながら、きゃははと笑う。ふたたび車内に熱気がこもるまで、ふたたび車内に飛び込むまで、日陰を探すこともせず、水を飲みに行くことさえもせず、吹き出た汗が乾くのを待つ。
ぼくらのあいだでサウナ遊びと呼ばれていたそれは、自分も含むいまの大人から見れば、熱中症や脱水症状寸前の、危険きわまりない遊びに映るのかもしれない。けれどもぼくらはあの涼しさを、大発明だと思っていた。涼しさそのものよりも、大発明であること自体が、たまらなくたのしかった。
きょう、うんざりするような炎天下の東京を歩きながら気がついた。
子どものころの遊びとは、すべて「発明するもの」だったんだ。だからあんなにたのしかったんだ。
仕事もたぶん、どこかに「発明」を加えれば抜群におもしろくなる。もしも、いまやってる仕事がつまんないとすれば、それは「発明」をサボっているからだ。いま抱えているあの本、この本、あのお仕事も、ぜーんぶ「発明」が必要だし、そうすれば勝手におもしろくなっていくんだよなあ。
めざせ発明王、ですよ。
