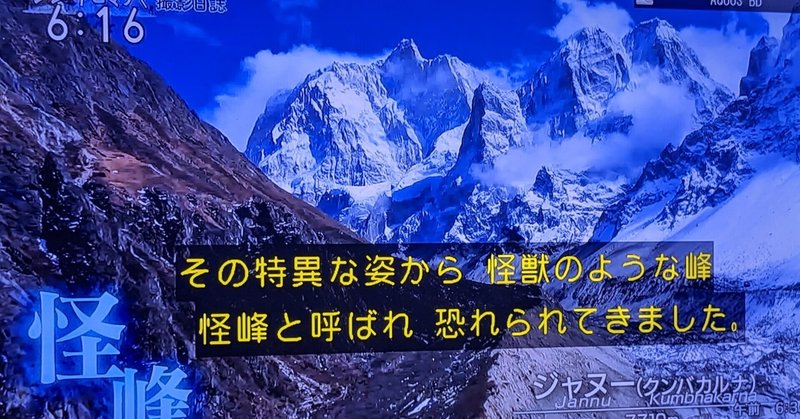
流々転々
原理はほぼ全て分かった。 Buddizm(諦観中心に心穏やかにする技術)の教えも、真逆のICHIGOの悪魔性も エントロピー増大原理も、時間の正体も、暗黒物質の正体も、世界の成り立ちも理解して 理解した上で悩みの対処法も構築したが結局頭でっかち 理性で感性をコントロールすることは不可能。その不可能だという諦観もまた 結論の一つに違いないが、それすら何の意味もない。 これまで構築した屁理屈は冷凍保存した上でしかしそれに囚われることなくリセットして 新たなる閃きに従い理論を紡ぐ必要がある。過去の遺物をたまに懐かしむのはリフレッシュには 最適だが、それにしがみつき思想大全をこしらえるという本業に立ち向かうべきではない。 参考程度にしてもいかん。一か所に留まることは腐敗し澱んだ沼となるゆえ ネコは日々リセットしている。過去をひきづらない。
以下過去の遺物 ↓
9日間の夏休みのうち、3日間は仕事の付き合いや臨時現場フォローで潰れた。 さてそれ以外の6日間のうち4日間は登山。 ① 7/24(日)乗鞍岳剣ヶ峰(3026m)【百名山】 ② 7/29(金)北八ヶ岳(麦草峠2120m~白駒池2115m~にゅう2352m~中山展望台2480m~高見石2270m) ③ 7/30(土)北八ヶ岳最高峰天狗岳(唐沢鉱泉1870m~西天狗岳2626m~東天狗岳2640m) ④ 8/ 1(月)みずがき山荘1520m~瑞牆山2230m【百名山】 どれも素晴らしかった。③、④は天候に気を揉んだが、④は15時には雷雨くるとい予報のもと 13時前には下山するため6時台早い時間に登山開始(遠州方向からの身内との集合は須玉IC近くに5:30) ちなみに①~⓷はソロクライミングだが、行き先々でほぼ道中を共にする登山家との交流も実にハートフル。 ② ③の連荘の翌日の中休みの7/31(日)はマッサージチェアで体をほぐし(体組成計も購入)、睡眠も多めにとって整えたが 8/1(月)は3時起きで前日21時頃には床につくも睡眠は浅く寝不足感は否めず、8/1(月)は2200m の山頂や森の中は涼しいとは言え、登山口辺りは38℃近い酷暑で暑さにもやられてグロッキー。 増冨の湯(ラジウム温泉)のぬるいお湯に長く浸かり、清里の小作で豚肉ほうとう(1500円)を食して体力は 回復。QPコーワのゼリーを小海豊里のツルハ薬局で購入し滋養強壮。 7/27(水)は息子の高校の三者面談(夏期講習も一緒に選び、8/6に河合塾の面談に付き合う) 8/2(火)~は仕事に戻り昼はカリウム補うためカットすいかと銀座デリーの3辛のカシミールカレー(シャバシャバのスープカレーのよう) 辛さを喩えると蒙古タンメン中本くらいの辛さ(北極に近い) そういえば7/18~2週間実施した塩分6㎎/日以内食事プロジェクトの後半に夏期休暇は辺り、食事メニュー(会社負担)はすべてそれで済ませた。 朝起床後と夕食後にナトリウムカリウム値測定は毎日実施。 ■■10月7日 すっかり秋ですなぁ、錦秋 明後日は涸沢カール日帰りピストン計画 しかしやること、やりたいこと多数 山行は北アルプス、八ヶ岳などの峰は高峰はすでに雪。 そろそろ、中山しか厳しくなる。 よって涸沢カールは秋の北アルプス納めとしては最適中の最適。 英語検定(英検やTOEICではない、簡易テスト)もあり対策も数日必要。 オミクロン接種券きたから予定組んで予約も。 BSの山番組やヒューマニエンス、コズミックフロント、各種名画はかなり溜まっている。 途中の書籍も多い。 完全に欲張り過ぎですな。 そぎ落とさないと楽しみのはずの事項がストレス源となる。 核心部のみに絞り、欲張らずスリム化が必要。 雑務や気がかりなタームは大分片付いた。 欲張り過ぎ休日を楽しみたい。 以上じゃ 行きは5時台~河童橋~明神(標準タイム60分のところ40分(3KM)) 明神~徳沢(3.4KM約40分)、徳沢~横尾(4.6KM50分)2時間10分で到着 横尾~涸沢の登山道も最初は平地的で緩いが、本谷橋からが本番。なかなかの急登続き。 下りの大渋滞に遭遇し登りはまあまあ進むが遅い先頭を途中で抜いて青ガレ(大崩落地帯)、Sガレくらいまで かなり早いペースで進む。カール見えてからヒュッテまでも結構登った。 絶景を約30分目に焼き付けたのち11時にカールを後にして 下りは本谷橋のせせらぎまでかなり走るようなハイペース(ハイペースな夫婦と後ろの赤いオッサンの間で) 飛ばし過ぎて距離もすでに26KMとかになり横尾で太腿の付け根の筋肉疲労が半端ない。 つるまでいかないが、既に筋肉痛の酷い状態に。横尾から徳沢はほんとに長い。途中河原から森に入る辺りで雨も降ってきて 徳沢に着くころにはかなり強い振りに。 徳沢着くまでが筋肉疲労による脳のドクターストップが低くていわゆるメンタルがやられた状態に。 足の疲れ以上に体が動かない。へたばったというやる。プロテインバーやナッツ、レーズンバターロールなど行動食は少しづつ摂取していたが 徳沢園で山小屋のカレー(1000円)を食してエネルギー―チャージ。心に作用して徳沢~明神まではメンタル復活してまた速いペースんい戻った。しかるに明神から梨平キャンプ場までは足(太腿の筋肉)疲労も限界に近い。 「ラオウの【心地よい痛みというべきか】」や「我は覇者なり、なんのこれしき」という念や 最後は足を庇いポールで漕ぐ腕や背中も疲労を起こしていたが「宮本武蔵の肖像画の脱力のポーズで力を抜き」 「後ろから抜く人などにも全く気にせずこちらのペースで歩く(抜かせるためにペース落とすなどをしない)」 それら思考法で脳の錯覚を払拭してなんとか完走(37KM、5万歩) 車に乗ってから足の疲労は酷く、家についてもびっこ引き、しかし一晩経ってかなり回復した。それでも今日に山行は不可 ストラトのNEW ALBUM 『Survive』実に北欧メタル然とした良盤ですな。 北欧メタルといえば、ヨーロッパ、シルバーマウンテン、ビスカヤ、プライド、ユニバース、タロット、マスカレード、プリティメイズなど 透明感がありクラシカルな旋律が煌めく初期のイングヴェイ・J・マルムスティーンにも通じる世界観(バッハの楽曲からの引用多し) ドイツにもクラシカルな楽曲を得意とするバンドも多い(アクセプト、アクシス、ボンファイアなど) ウルフ・ホフマンの「ムソルグスキーの禿山の一夜の一夜」も骨太で痺れます。まるで槍ヶ岳のような重厚さ。 ストラトの7年ぶりの新譜『Survive』からは#2「Demand」,#3「Broken」#7「World on Fire」#10「Before the Fall」 が特にスパークしているように3回くらい通しで聴いて思った。 今回はAlbum全体で歌心あるというか、しばらく心に染み入り良い後味がずっと残るテイストである。 山行の歩みは人生の歩みそのもの なんのために歩むのか?過程を楽しむため?やはり最大の目的は山嶺に到り、眼下を見下ろし遠方の高峰(劔、槍、穂高など)を眺めるためであろう。 人生における山嶺とは?死の直前がピークか?それとも40~50の体力的知的ピークを指すのか? 体力的知的peakが山嶺なら残りの人生は下り登山だ。死が絶頂なら下りは心肺停止もしくは脳死から完全に灰になるまでの時間を指すのか? 昨日の山行はピークを踏まなかった。峠はあったがそれは決して山嶺ではなかった。青木村の霊峰・子檀嶺岳(こまゆみだだけ)を目指すも 登山口を間違えて外輪山を登ってしまった。時間が時間で昨日は子檀嶺岳は諦めた。マイナーな信州百名山は登山口が分かりづらい。発見はしたが めんどくさいも科学した。億劫感の正体は脳のディスオーダーと嫌いなヤローなどの嫌悪感で扁桃体が嫌になっていると億劫感とめんどくさい感情となる。 それは生体反応、反射神経と捉えあまりやる気論、精神衛生論に持ち込まない方がよい。単純に行動を無心ですべきと、心に余裕があると余計なことを考えるから 余裕をなくして逆転の発想にて荒治療すべきマターだ。目をつむり片足で30秒立つと無心になり脳がすっきりする。 物を探すのを宝さがし、物を拾うのをスクワット、無為に見える単純作業もゲームと捉え、セカセカ時間に焦ることを止める。時間が迫る気が焦るは恐ろしい。 あらゆることは山行か?放物線カーブの放物線はまた円の見えるらしい。以上 億劫(面倒)とは義務感、急き立てられ感、そして圧により身体がこわばる物理的苦痛。呼吸も止まっている。 「時間急き立て」などに屈せず、自分のペースで堂々と歩けばこわばりは解ける。呼吸もゆったりに。 面倒の正体はそういう苦痛。 他人のグズに寛容でない人。自己中。そんな奴はいずれ自滅するからほっとけ。自分のペース。TO DO整理。順番付 他人のイライラに影響されない。イライラはその人のもの、ほっとけ。 書類作成は変に焦ったり急ぐから苦痛、億劫になるが、焦らず、音楽でも聴きながら楽しむ。 苦痛を愉悦に変えたとき人生はカラフルになる。 時間は上から下に一方向にしかも決まった速度で流れるものでない(重力が低いとこでは時間が早く流れる。宇宙空間の1年が地球でいう20年に当たるなど)。 スカイツリー(634Mの展望台(約450m)と地上での時間の進み方の差の実験(光格子時計を使った)で結果は上が0.00000000000005秒速く進んでいると) では上から下だけでなく下から上(また概念で捉えづらいが横とか斜めに)時間は流れるのか?下から上はリバースですね。低エントロピー状態では時間は反転するという映画 テネットの描写。 エントロピーとは理系的数式を極力排して説明すると「無秩序な状態の度合い(=乱雑さ)を定量的に表す概念」で無秩序なほど高い値となる。 気体の拡散に例でいくとエントロピーが増加した状態(無秩序、乱雑)は拡散しているので温度は下がる(冷める)。そして自然と元に戻ることはない。 人為など外圧がないと元の熱々な状態にコーヒーは戻らない。コーヒーを加熱するとはエントロピーを下げるということとやや近いか? あと部屋が散らかることも整理整頓するとエントロピーが下がる。 人間は普遍性(不変性=不老不死)の願望があるからエントロピーを下げようとする本能が働く。 テネットにおいては単純に加熱したらエントロピーが下がった(閾値を超えると時間が反転し出す)わけではなかった。 難しいですね。温めるということはエントロピーを下げる十分条件ではない。それは直観的に分かる。 ブラックホールは凄まじい重力のかかるところ。つまり時間の進み方が極端に遅い。それは相対的に反転したように見えることもあるのでは? 人為的にブラックホールに近い重力をかけると物の成長(変化)は極端にに遅くなり外部と比較すると逆方向に進んでいるように見えるとか。 絶対零度ではないが重力マックスではエントピーは限りなくゼロに近づき、ゼロを超ええるとマイナス方向に進み時間も反転する。 それがテネットで描かれたイメージ。 時間が斜めに進むとは?それは4次元の中に生きるモノにしか感覚的に捉えることは出来ない。反転ではなくマルチバース的にまたちがった状態へと反転的に進むことか? しかしそれすら3次元的な捉え方なので違うかも知れない。 エンとろぴーは下げた方が良いのか?自然のままにしてどんどん増大し放題がいいのか?適度がいいのか?ま、適度が良いのは当たり前ですよね。だって適度だから。 例えば清潔に関する潔癖度合いは高すぎると神経症になる。低く過ぎると感染症になる。 部屋の混乱は?断捨離して物がなにもないとエントロピーは低い。一冊の本が凄い重量となる。 ゴミ屋敷みたいな部屋はエントロピーが高い。 適度に片づけて適度に物がある状態が良い。 中国ではそれを中庸の精神と呼んだ。 得てして人間は両極端に走り勝ち。 月並みながら、部屋の片づけも、清潔感も人間関係も富も幸せ度数も適切が良い。 エントロピーの綱引き、またはカーリングですな。 以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
