
松本人志的な笑いはどこから来てどこへ行くのか
いいね・リツイートはこちらから▶️
松本人志的な笑いはどこから来てどこへ行くのか|西端 two-outs-butter @spring_rain_out #note https://t.co/Nlr9L2xIjM
— 西端 two-outs-butter (@spring_rain_out) January 9, 2024
1.はじめに
昨年末に週刊文春が松本人志の性加害疑惑
(《参加女性が続々告発》「全裸の松本人志がいきなりキスしてきて…」「俺の子ども産めや!」1泊30万円の超高級ホテルで行われた「恐怖のゲーム」 | 文春オンライン (bunshun.jp))
を報じてからというもの、松本からの性被害を訴えていたネット上の書き込みが発掘されたり過去のラジオや著書での発言がふたたび注目集めたりしたことも相まって、世間はいっそう反松本の色を濃くしている。その流れの延長として、松本的な笑い、ダウンタウン的な笑い、ひいては吉本興業的な笑いというものが批判され始め、ラディカルな批判者は吉本興業の解体を唱え始めた。
反松本人志の流れにやや遅れるようにして松本擁護論が姿を見せ始めるが、その多くが「証拠がないのに断ずるな」とか「なぜ司法ではなくメディアにタレコミを入れるのか」といったような事件そのものを懐疑する立場に留まっており、便乗するように俄か湧き始めた「松本の笑いは有害か」といった芸能の議論には踏み込まない。沈黙するか、せいぜい「当時の価値観をいまの価値観で裁くことはよくない」といった穏健な反論に留まる。つまり特別な愛着から松本を擁護しているというよりは、ここ数年強く浸透したといわれるキャンセル・カルチャーへの抵抗の一形態と見受けられる。
さて、2014年春ごろに「ダウンタウンのごっつええ感じ DVD発売記念スペシャル」を見て以来、世代でもないのに松本人志の熱烈なファンとなった私からしてみると(つまりダウンタウンについての「彼らの笑いは90年代で止まっている、いまの若い子は好んでいない」とかいう言説に違和感がある私からしてみると)、この件は性加害疑惑というより松本的なお笑いがキャンセルされそうになっている現実の方に興味が向く。性加害疑惑については、たとえ「やってた」としても彼の笑いを否定はし得ない気分であるので、正直どちらでも結論はさして変わらぬというのが本音である。
私は、松本が司法的にどう裁かれるかということについて、強い関心がない。私の関心事は、もっぱら、松本的笑いがキャンセルされるか否か。司法の世界での裁きよりも芸能の世界での裁きの方が重大だと思っている。松本が有罪になってもその笑いがキャンセルされなければ御の字だし、無罪になったとしても笑いがキャンセルされて引退なんてことになれば残念だ。(追記:松本人志は芸能活動を休止したようだ。悪い予感がする)
ワイドナショー出演は休業前のファンの皆さん(いないかもしれんが💦)へのご挨拶のため。顔見せ程度ですよ。
— 松本人志 (@matsu_bouzu) January 9, 2024
では、松本人志的笑いとはなんだろう。
2.ダウンタウン的な、松本人志的な
(1)ダウンタウン的な
松本人志的な笑いを考える前にダウンタウン的な笑いを考える。ダウンタウンの特徴として、第一にNSC(大阪)1期生というのが挙げられる。NSCとは吉本興業が創設したお笑い学校である。学校制度が師匠制度を破壊し、そのうえで、「お前は何期?」「大阪の22期です」「同期は?」「キングコングとかダイアンとかNON STYLEとか…結構売れてますよ」などのやりとりに代表される、学校的(体育会系的)上下関係の形成を促したことは多く指摘されていることである。すなわち、師匠~弟子的上下関係から先輩~後輩的上下関係への移行。ダウンタウンはその1期生であり、師匠制度をよしとする上の世代からの厳しい目に晒されて、それに対する反骨のエネルギーが今度は自分たちを一番の先輩とする新たな上下関係の構築に向かったことは想像に難くない。いま、関東ではダウンタウンが、関西の一部では同じくNSC1期生のトミーズがテレビバラエティにおいて大きな位置を占めていることは、先に述べた移行が達成されたことを示しているように思われる。
第二の特徴として、デリカシーのなさがある。ナンシー関が「地肩」「庶民感覚の欠落」と呼ぶそれは、すなわち裸の王様に「裸だ」と言える能力のことだが、ダウンタウンはそれがずば抜けて高いという。私に言わせれば、ダウンタウンは裸でもない人に裸だと言うこともしばしばある。2017年、快進撃を続ける将棋界のルーキー・藤井聡太を「ワイドナショー」で取り扱った際、コメンテーターを務めていた松本人志は「彼が童貞じゃなくなったときにどうなるんだろうっていう」と発言した。藤井が当時中学生だったこともあるが、極めてカジュアルに彼を童貞と決めつけていることに松本の強みがあると言える。当然、この発言は炎上することとなる。

無謬そうなヒーローに毒を吐くことは、やはり特別な「やけっぱち」的信条のようなものがないとできないのだろうと思う。なんというか、タレントとして無益だからだ。羽生結弦をホモと言い放ったビートたけし、澤穂希の容姿を弄ったナイツの塙宣之なども含め、どこか自暴自棄、逸脱者の気配がある。政治家を弄ることより遥かにハードルが高いことをやっている。相方の浜田雅功もいまだに女性芸人(これは先ほどとは違い「無謬そうなヒーロー」ではない)に対して「ブタ」と罵倒するが、それを受けての非難を含めて楽しんでいるようにも見える。「なぜそんな発言を?」と思うかもしれないが、それは彼らの中になにか欲求不満があるからだろう。人生に満足しきっていれば、わざわざ罵倒などしないのだ。そしてそれが、ダウンタウンの強みである。
※芸人として売れに売れたのち、松本人志がわざわざ「人志松本のゆるせない話」という企画を立ち上げ、クレームじみた話までも展開してみせたことはひとつの象徴である。金を得ても地位を得てもなお怒りが湧いてくるために、怒りを笑いに昇華する必要があったわけだ。「なぜ売れている芸人がクレーム話をテレビでやるのか」という問いの答えは、「芸人とは売れても売れても怒りが消えない生き物だから」ということになるだろうか。
おおまかに言ってこれら二つの特徴がダウンタウンと言えよう。
(2)松本人志的な
松本人志は、先の二つの特徴に加えて笑いと軍団づくりへのこだわりを持つ。
松本人志の笑いへの強い関心について、ダイノジの大谷ノブ彦は、「大阪でマルクス兄弟の上映会をやった際に吉本芸人で松本人志だけが来ていた」という宮沢章夫の証言や、シティボーイズのライブに松本がよく足を運んでいたということを踏まえ、「吉本の土着的なベタをわかった上で、東京の、あの当時のサブカルチャー的なものを研究して研究してしっかりパッケージをしたと思う」と発言している。松本は相方と比較して「語りたがり、分析したがり」の人である。全国区で売れてやや落ち着きを見せ始めた30代後半に始まったラジオ「放送室」や、50代のキャリアとほぼぴったり重なるワイドショー番組「ワイドナショー」などでは、笑いに限らず幅広い時事ネタについて持論を展開している。そして、その発展形としての笑い至上主義的側面(後述)が、多くの芸人たちに影響を与えることとなる。
軍団づくりへのこだわりというのは、これは今回の性加害疑惑で問題視されることとなったホモソーシャル云々とも絡んでくるかもしれない。相方である浜田も軍団をつくっていることはよく知られるが、それは15-20年近く芸歴の離れた後輩ばかりで構成されており、「オヤジ」願望の発露であろう。松本は「オヤジ」というよりは「アニキ」であり、「ごっつええ感じ」や「ガキの使い」等の年齢の近いレギュラー芸人のほぼ全てが「浜田軍団」でなしに「松本軍団」にカテゴライズされていたことはよく知られている(現時点でどの程度の付き合いがあるのかは不明)。この違いは、高校時代に、極端な管理教育がおこなわれた日生学園でサバイバルした浜田と、近畿で有名な不良ばかりが集うとされていた(松本談)尼崎工業高校でサバイバルした松本の違いではなかろうか。管理教育における教師は「オヤジ」的であり、不良高校における先輩や番長は「アニキ」的なのだ。
先輩~後輩的な上下関係と(アグレッシブな)デリカシーのなさを基軸としつつ、洞察に裏づけられた笑いが提供される。「ごっつええ感じ」における「キャシー塚本」、コントアルバム「VISUALBUM」における「ゲッタマン」などはその一つの極として捉えられよう。


デリカシーのなさが垣間見られるのは多くの場合アドリブであり偶発であり、その意味で「ごっつええ感じ」のコントのほぼ全てがアドリブだったことや出演者が笑っても続行されたということも頷ける。
松本人志が2016年にネット番組として満を持して開始したプロジェクト「ドキュメンタル」(amazon prime video)についても触れておきたい。この番組は密室に芸人10人を集めて自由に笑わせ合いをするというものだが、テレビに比べてコンプライアンスの緩いネット番組であるだけに、着地点は大抵が下ネタと暴力と突拍子もない叫び・ギャグである。その一つの到達点がシーズン2のラストの、バイきんぐ小峠英二とジャングルポケット斉藤慎二の攻防である。これを松本は大いに笑う。これが仮に松本がやりたいことだとしたら、松本が求めているものは要は「ショー」ではなく「仲間内の遊び」ということになる。仲間内の遊び、男子学生が休み時間に教室の隅っこでワイワイガヤガヤと騒ぎながらやる遊びに、「ドキュメンタル」はよく似ている(というかそれをもっとハードにしたものだ)。そしてそこが批判される。しかし、むしろ「それ」が面白いんだという態度が松本には見受けられる。きっとそれは、ラジオ「放送室」でたびたび触れられていた「中2のときの仲間との遊び」の思い出が、今でも強く残っているからかもしれない。ちなみにこのグループは同級生の男子数名からなっており、松本と浜田、高須光聖(現・放送作家)などが様々な「遊び」をしていた。言ってみれば「ごっつええ感じ」や「ガキの使い」は後輩を仲間に見立ててその再現をしているという見方もできよう。後輩を仲間に見立てるが後輩は後輩であるので、同級生内では「弄り」に済んでいたものが「イジメ」に拡大されて見える可能性は十分にあり、それが世間の「ダウンタウンはイジメをテレビに持ち込んだ」言説を生んだのかもしれない。…もちろん、別段そのような企画・コントばかりをやっていたわけでないことには留意されたい。ただ、ダウンタウン的な笑いの特殊性がそこにあるということである。(そしてそのような先輩~後輩的、あるいは同級生グループ的笑いは一部Youtuberにも受け継がれる。Youtuberの企画にガキの使いのパクリ企画がしばしば見られるのも、そのような事情が関係している)

松本人志的な笑いを、先輩~後輩的笑い、デリカシーのなさ、笑いへのストイックな態度(その発展形としてのお笑い至上主義)の3つだと規定したとして、現代において批判されているもの、消え去られようとしているものはなんなのか?
現代においては、松本的笑いの第一項と第三項はそのままに、第二項のデリカシーのなさの内実が変容している。
第一項については言うに及ばず、いまだNSCをはじめとするお笑い学校ビジネスは繁盛し続けているし、「軍団」「界隈」的なものは続々と作られている。また、芸人数組がユニットを組んでライブを開催するという文化も継続中だ。
ex.千鳥軍団、ハリウッド軍団、ニューヨーク軍団、高円寺芸人界隈、学生お笑い界隈、大喜利界隈、粗品ギャンブル四兄弟、ユニット「アキナ牛シュタイン」、ユニット「漫才ブーム」、ユニット「漫才工房」、ユニット「チョコンヌ」、●●no寄席(ダイヤモンドno寄席、マヂカルラブリーno寄席…)など
第三項についても、「お笑い研究家的芸人」「笑いを語りたがるタイプの芸人」は年を追うごとに増している。テレビにyoutubeにサブスクにDVDにと、お笑いを見る手段そのものが増加したためにお笑いに「ハマる」下地はできているのだ。かつてはラジオや書籍のみに留まっていたお笑い語り(バラエティ語りともまた違う)が、ここ10年でどっとテレビやネットの世界にも流れ込む。
ex.あちこちオードリー、しくじり先生お笑い研究部、お笑い実力刃、ジンギス談、やすとものいたって真剣です、スピードワゴンの月曜THE NIGHT、ゴッドタン(の一部企画)、アメトーク(の一部企画)
ここに書ききれないが、Youtubeではもっと多くのお笑い語りが氾濫している。M-1の季節を思い返そう。
では、第二項の変容とはなにか。デリカシーのなさの変容とはなにを指すか。そのためにも、まずは「王様」になる前のダウンタウンに思いを巡らせなければならない。
3.松本人志的でない笑い―あるいは代替的差別―
(1)松本人志は「どこの」権力者なのか?
バラエティにおける松本人志及びダウンタウンの攻撃対象はまず後輩であったが、次第にそれは先輩にも他業種にも向かう。「ガキの使い」でゲームと称して野坂昭如を殴ること、「ダウンタウンDX」で志村けんや和田アキ子をツッコミと言いながら叩くこと、「一人ごっつ」のお笑い共通一次試験という大喜利企画で、かつてはセンス・エリート兼時代の寵児だった糸井重里の答案に低得点をつけること、「HEYHEYHEY」や「JUNK SPORTS」でミュージシャンやスポーツ選手に毒を吐くこと、それらすべてがダウンタウンの攻撃である。
松本人志の根っこには、笑い以外の様々なものに対するコンプレックスがあったのかもしれない。それらを笑いで覆うことが、彼の勝利の手段であった。以下の画像は、単独ライブ「寸止め海峡」のエンディングで流れた松本のメッセージである。

スポーツができる、賢い、腕っぷしがある、モテ、裕福、それらは昔からずっと人生に這い回るようについてくるステータスである。お笑い至上主義を敷くことにより、それらすべての価値を無効化する。そんな松本の強いカウンター的気概が感じられる。そしてそれが、バラエティでの、言ってみれば「リスペクトのない」態度に繋がる。浜田雅功も似たようなもので、彼がしばしば石橋貴明と比較して「アスリートに対する謙虚さがない」と評されるのも無理のない話である。そもそも、浜田は石橋と違って野球に打ち込めるような環境ではなかったのだから。最近ようやく浸透しつつあるが、そもそもスポーツ(や勉強や音楽)に打ち込めるか否かは環境に左右されるのだ。
さて、最近のダウンタウンは権力側に回りもはやカウンターではないという意見がある。では、松本人志が権力となったとはどういうことなのか。ここで、中田敦彦が指摘した「松本人志帝国化するお笑い界」の話を挙げておきたい。
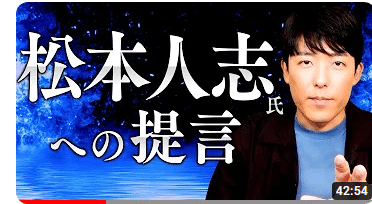
彼が指摘したのは、芸人同士がその能力でもってバトルするような企画の多くに松本人志が君臨していることである。たとえばM-1、キングオブコント、THE SECOND、IPPONグランプリ、ドキュメンタル、すべらない話…ここまで多くの、それも豪華な企画に関与する芸人は松本以外にいない。爆笑問題、東野幸治、千原ジュニア、ナインティナイン、有吉弘行、バカリズム、サンドウィッチマン、千鳥…といった大物芸人の顔を浮かべても、松本ほどの規模感でお笑いのバトル的な企画に君臨(参加ではない)する芸人はいない。
松本自身の活躍、松本軍団なるもの、そしてNSCビジネスの大きな成功が松本の権力を次第に強くする。1990年代にダウンタウンのライバルと目されたビートたけしやとんねるず、明石家さんまとの違いはそこであった。たけし、とんねるず、さんまと比して、ダウンタウンは自身を頂点とするピラミッドを作ることが容易だったし、更にそこに意欲的だった。特に、たけしがおこなわなかった漫才の復興を松本が島田紳助と共にM-1という形で実現させたことや、さんまがおこなわなかった「笑いのアーカイブ化(=自分たちのネタや企画を後世の人間が見られるようにする)」を積極的におこなったことは特筆に値する。
たまにダウンタウンは1995年に天下をとったといわれるが、私としてはその時期は群雄割拠の時代に映る。ほんとうの天下はもっと先ではないだろうか。「笑ってはいけない」と「水曜日のダウンタウン」の人気が定着し、たけしが映画監督としての色を濃くし、さんまが「そのタイミングで引退する」とかねがね言っていた還暦を迎え、紳助が引退し、タモリが「いいとも」から身を引き、とんねるずの「みなさん」が終わり、ナイナイの「めちゃイケ」が終わり…それがすべて訪れた2018年頃、ようやくダウンタウンの天下が訪れたと私は見る。長いサバイバルに成功したとも言える。
正月に行われる「ドリーム東西ネタ合戦」なる番組には、毎年30組あるいはそれ以上の有名芸人が出演しネタを披露する。エンディングでダウンタウンが「今年もよいお年を」という挨拶をし、共演芸人がにこやかに拍手する姿を見るにつけ、ダウンタウンがその天下を揺るぎないものにしていることを再確認させられる。
※ちなみに、お笑いファンがよく言う「天下」の意味が、たぶん私の解釈と異なる。私は、お笑い界という次元ならば天下など同時代に多くて二つだと思っている。もちろん、ゼロの時代もある。

※しかし、ダウンタウン枠のようなものがテレビ局にあり、それがダウンタウンを持続させていたのでは? という推測も囁かれている。たとえば、フジ系「アカン警察」が2013年9月に終わると、1ヶ月ほど空いて「教訓のススメ」(13年11月~15年3月)が始まり、これが終わるとすぐに「ダウンタウンなう」(15年4月~21年3月)が始まり、そしてこれが終わると「酒のつまみになる話」(21年4月~)が始まるのだ。また、TBS系でも「リンカーン」(-13年9月)から「100秒博士アカデミー」(13年10月~14年3月)、そして「水曜日のダウンタウン」(14年4月~)とキレイに繋がるのだ。それもひとつの政治力ということか。
※バッファロー吾郎が発案・プロデュースした「ダイナマイト関西」(1999年~)なる大喜利ライブイベントで活躍した芸人のうち少なからざる人数がIPPONグランプリ(2009年~)に輸出された流れなども書きたいが、あえて書かない。

(2)差別への逆襲としての差別と、逆襲に対する逆襲としての差別
なるほど、松本人志はたしかに権力である。しかし私が改めて確認しておきたいことは、これは「お笑い業界」の権力者となったに過ぎず、別段、芸能界のトップに君臨したわけでもなければ日本のトップに君臨したわけでもないということである。ここを履き違えてほしくないと思っている。松本及びダウンタウンが展開していた「お笑いvs非お笑い」という戦いは貫徹されていない。ただ、その戦いの過程で彼らはお笑い界のトップに到達しただけの話だ。
その証拠にというべきか、世間のダウンタウンへのdisを見てみるがよい。「育ちが悪い」「教養がない」「下品」「低学歴」「文化への理解がない」…ダウンタウンは世間を笑いで覆うことにまだまだ成功してはいないのだ! どころか、差別的disにも晒されている。
私は思う、ダウンタウン(特に松本)がおこなってきたヤンキー的差別、ヤンキー的ノンデリカシーのお笑いとは、エリート層がおこなってきたインテリ的差別、インテリ的ノンデリカシーへの逆襲なのではないかと。差別への逆襲の限りにおいて、また異なる差別の笑いは認められるのではないかと。文化人・知識人で、それなりに年を重ねてきた人がダウンタウンを指して「なんであんなものが人気に…日本の品位も堕ちたものだ」とか言うのを見かけるにつけ、「ダウンタウン人気などお前らの〝文化的なるものの〟の押しつけからの反発じゃないか」と思っちゃうのである。
…とここまで書くと、あたかもダウンタウンは文化人嫌悪であり維新的でありネオリベ的であり…という「よくある」論調に突入しかねない。しかし私はそれも否定する。
松本は確かに政治(政党政治ではない)と競争を好むが、しかし「勝ち組」「負け組」とかそういったものの基準にわざわざ「笑い」を持ち込み更にその存在感を高めようとした人間であり、いわば既存の「勝ち・負け競争」のルール内で争うエリートや、彼らを信奉する一部大衆とは色が異なる。
松本人志が執筆した「遺書」「松本」などを呼んでも、そこに自己啓発の色合いは薄い。アジテーションである。自分の信ずる笑いというものの価値を、必死に煽り立てている。そしてそれに感化された若者たちが次々と芸人になることを志す。彼らは松本に説得されたのではなく、啓蒙されたのでもなく、駆り立てられたのだろう。
そんな中、松本人志的なもの、ダウンタウン的なものを〝漂白〟することがほんとうに良いのか? ということは、繰り返し問うていかなければならない。
松本人志がキャンセルされたらヤンキー的お笑いからエリート的お笑い(飄々・俯瞰的・楽しげ・満足げ・軽やか・変に俗っぽい)への移行が起きるのだろう。すでにネット一部では「そういう連中」が固まり始めている。
— 西端 two-outs-butter (@spring_rain_out) December 30, 2023
でも私はあんまりそういうのが好きじゃないから困っている。
ヤンキーによる差別のお笑いを排除したって、エリーティズム溢るる差別のお笑いが立ち現れてくる
— 西端 two-outs-butter (@spring_rain_out) December 30, 2023
エリーティズムへの逆襲としての松本の笑いが去り行けば、エリーティズム溢るる差別のお笑いが、〝逆襲の逆襲〟として到来する。「できないヤツ」から「できるヤツ」の時代へ。この流れにおいて、お笑い一本で生きていこうとすることはほぼ不可能になりつつある。そしてそれは、個人が個人の様々の側面を切り売りすることで人気を搔き集めるSNS・Youtubeの時代とオーヴァーラップする。「お笑いの就活化」現象とも言えようか。個人の、お笑いネタ以外の特性…すなわち学歴であったり副業であったりスポーツや音楽の特技であったり…別にネタに使うわけでもないそれらの特性が、その芸人の「幅」として許容され始める。むしろその特性の方が重視されることもしばしばである。その延長線上に、元東大だの元CIAだの元パイロットという経歴のおかげでテレビに出られる「経歴芸人」(と私は呼んでいる)が現れてくる。「アメトーク」に出るために習い事や副業を始める芸人などもいたそうだが、それはそのような時代状況を鑑みてのことだろうし、Youtubeでやたらと芸人の半生やこれまでの芸能生活についてネタにするのもその流れだろう。
これは言ってみれば「非お笑い」への、媚びに似たアプローチである。「芸人なのに賢い、すごい」「芸人なのに楽器が弾ける、すごい」…これらは芸人を下に見ることで成立するやりとりであり、ダウンタウン的なお笑い至上主義と相反する。しかしこの時代はもう来つつある。そして芸人は、また芸能界の下層へと自らを追いやるのだ。
つまり、松本人志的な笑いがキャンセルされることは、ただの新陳代謝とかいうレベルで語られるような話ではない。たとえハッタリだとしても、お笑い至上主義を唱えていた芸人が消えることの重大性は認識されるべきである。
※そういえば昔、ロザンの宇治原史規は「勉強はできるがつまらない」みたいなキャラでテレビに出ており、たけしからイジメられていたように思う。しかし7年ほど前に同じくクイズキャラとして登場したカズレーザーは飄々と淡々とこなしており、しかも時折笑いをとる。時代の移り変わりを感じる。
※明石家さんまと爆笑問題というのは、この意味でやや語りにくい芸人である。松本のようにお笑いを上に「見させる」ことは嫌うが、しかしプロフェッショナル意識を持っている。彼らが好んで使っていた「ドブ芸人」というのは、おそらく自称するのはOKだが、他人が使うのはNGだろう。「見下される奴等」という仮面を被りながらしっかりと笑いを取りカネを稼ぐのが彼らの美学なのだろう。それはそれでカッコいい。

4.おわりに
今後は水面下で、徐々に徐々に、暴力と性の臭いのない、しかしインテリ的な差別は残るお笑いが、浸透してゆくこととなるだろう。いまの若手芸人のYoutubeなどをちょっと見ればその気配はある。「凄いヤツ(これは、お笑い的な凄さとは別である)」を見たときにフツーに持て囃す笑いが流行り始めている。飄々・俯瞰的・楽しげ・満足げ・軽やか・変に俗っぽい。そんな笑いである。私はそういったものを疑っている(そういえば、ここ1,2年の間お笑いファンがこぞって永野を絶賛しているのは、うっすらと共有されているそのような疑いを笑いに昇華しているからではないか)。
松本人志的笑いと松本人志的でない笑い。その両取りをできる芸人が今後の天下取りレースに名を挙げることになるのだろうか。いま、パッと、東野幸治と太田光の顔が浮かんできた。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
