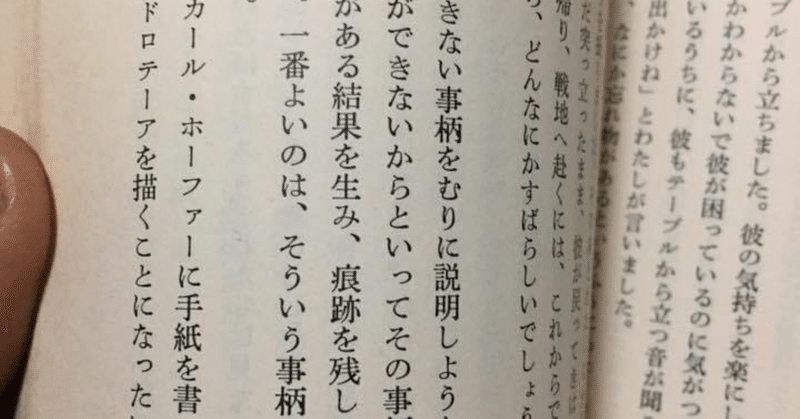
"ドロテーア"(2018.1.24の日記)
西岸良平の三丁目の夕日のコンビニ本を読んでいたらひとめぼれという話があった。
ある若い警官が美衣子という女性と知り合いすぐにプロポーズする。実は警官が幼少期にこっそりと猫を飼っていてそれが親に見つかり捨てられてしまったという過去があった。その猫=ミーコは美衣子にそっくりで可愛がっていた猫に似ているという理由で一目惚れをしたのだ。
一方美衣子の方も両親が美衣子の幼少期の写真を見ていてそこには一匹の犬の姿が。美衣子がすごく可愛がっていた犬が警官にそっくりだなと両親は微笑んで終わるというオチ。
はて、これと似た話どっかで読んだことがあるなと思い出してみる。それはドイツの作家ノサックのドロテーアという小説だったと気づく。
ノサックはハンブルク空襲など第二次大戦下のドイツの苦難をテーマにした作家でドロテーアもその内の一つだ。
戦後直後ドイツである一枚の女性が描かれた絵画に感銘を受けた男がその絵にそっくりな女性を街中で見つける。男はその女性に絵のモデルになったことがあるかと尋ねるがそんなことはしたことがないと答える。
逆に女性=ドロテーアは男にあなたには弟がいて軍人か?と訊ねる。しかし男は弟はいるがドイツにはいないし軍人でもないと答える。なぜドロテーアはそんなことを聞くのか?
1943年のハンブルク空襲の際ドロテーアはある1人の軍人に命を救われ食糧も世話してもらったのだ。その軍人は何処もなく消えてしまうのだが軍人が男に生き写しだと言う。もちろん男は軍人でもない。同じくハンブルク空襲下で生き延びたのは共通する。ドロテーアと男は話し合うといろいろ奇妙に一致する点があるのだがそれでもドロテーアは絵のモデルになってないし男はドロテーアを助けた覚えもない。しかしこれをご存知?と女性が差し出した古い雑誌を見ると男がむかし書いた詩が掲載された号だった。その雑誌は軍人が持っていた雑誌で彼は彼女にこの詩を教えたのだという。
この事について終盤、とても印象的な文が書かれている。
〜大きな激動の時代には、われわれはみんな互いに似かよってくるのだろうか。あるいは、こういう時代には、個々の人のもつ考えが壊れた境界線を踏み越えて、共通の場へ出ていくのだろうか。そしてそこで、遅かれ早かれ、同様にひどい目にあったほかの人から生まれた考えと出会う。こうして共通の運命を体験したことを確認しあう。
しかし、それが、われわれが死と呼んでいるもののあとになって起こるとしたらどうなるであろうか。そうだ、だれかが自分について、「そこからここまでがわたしだ」というようなことが言えるのだろうか。そんなことをしたら人間の頭のなかに出入りする観念のほうがその人間に対して苦情を申し入れてくることになる、「なぜわれわれの存在を認めないのか」と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
