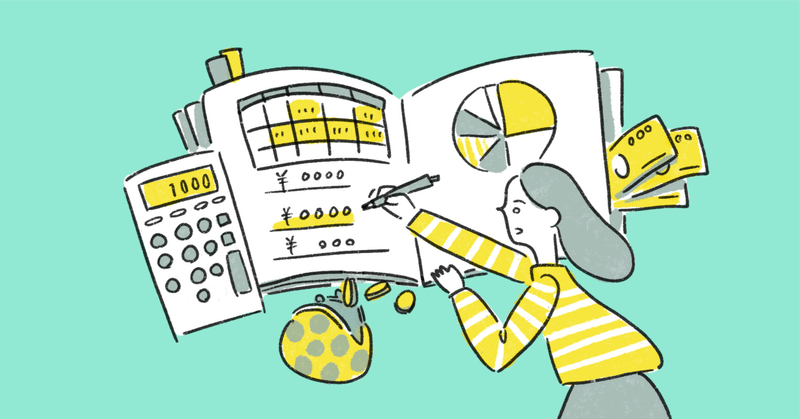
お金の管理ツール
こんにちは。しみっく(@simik_gay)です。
いきなりですが、みなさんどうやってお金の管理してますか?
私の管理方法を紹介しますので、ご参考になれば幸いです。
私の場合、以下の2つを使っています。
2つ使っている目的、それぞれの使い分けについても説明しますね!
メイン:表計算ソフト(Mac なので標準でついているNumbers)
サブ:マネーフォワード for 住信SBIネット銀行(無料版)
お金の管理で大事な3つの観点
お金の管理で大事なのは、過去・現在・未来の3つの観点を持つことだと思います。私たちにとって一番大事なのはこれから、つまり未来です。ただ、過去・現在のことは調べればわかりますが、未来のことは誰にもわかりません。
過去・現在の情報を整理し、未来を予測するしかないのです。
過去にどれだけお金を使ったかはわかっているはずのことなので、調べて、わかりやすく整理しておけば今までの経験と重ね合わせて今後どのくらい使うだろうかという予測ができます。
次に、現在がどうなのかというのは、意外と簡単ではありません。
私が一つの銀行口座しか持っておらず、クレジットカードや投資、確定拠出年金もしていないのであれば、今手元にあるお金と銀行口座のお金が全てです。その場合は管理は簡単です。
でも、実際はそうではありませんので、簡単にリアルタイムで資産状況を把握するための手立てが必要になります。この資産状況の把握が、過去データの蓄積につながっていきます。
未来についてはもちろん過去・現在からの延長ではあるのですが、まだ起こっていないことなので当然、様々な要素で未来は変動します。例えば何年後にマイホームを買うとか、資産運用の年利を何%に設定するとか、収入はどの程度の変化を想定するのか、支出はどのくらいを見積もるのか、などなど。
様々な起こりうる事象を想定し、状況の変化に合わせて臨機応変に見積もりも変える必要があります。
これらの過去・現在・未来の観点で資産状況を整理していくために私は最初にお伝えした2つのツールを使っています。
マネーフォワード for 住信SBIネット銀行について
上記の観点でいうと、私が現在の資産状況の把握に使っているのが「マネーフォワード for 住信SBIネット銀行」です。
マネーフォワードは銀行や証券会社、クレジットカード、ポイントサービス、確定拠出年金などを登録しておくと1つのアプリで資産状況をまとめて管理できるというとても便利なアプリです。
基本的な機能は無料版で使えますが、有料版(ひと月あたり441円〜500円程度)にすると、登録できるサービスの上限が無料版は10個までなのが無制限になったり、資産のデータが直近1年分しか見られないのが無制限で見られるようになったり、資産状況をサービスごとに手動更新しなくても一括更新できるようになる、資産推移などをCSVで取得できる、などなど良いところがたくさんあります。
ですが、私は無料で十分かなと思っています。
銀行口座、証券会社、確定拠出年金などのストックとしての資産については片手に収まりますし、クレジットカードやポイントなどはあくまでフローなのでそこまですべてをマネーフォワードで管理する必要性がありません。なので、10個で十分です。あと、あくまでマネーフォワードは私にとって資産管理のサブツールでしかなく、あくまでメインは表計算ソフトなので、過去の資産データも1年見られれば十分です。
私はお金を表計算ソフトで管理するのが好きなので時間が多少かかってもいいのですが、そうでない方は時間を買うためにも有料版を使われるのもいいと思います。
無印版と金融機関提携版との違い
ちなみに少し話が逸れますが、マネーフォワードには特に金融機関と提携していないもの(無印版とします)に加えて、金融機関と提携したもの(金融機関提携版)が10以上あります。私が使用しているものは住信SBIネット銀行と提携している「マネーフォワード for 住信SBIネット銀行」です。
金融機関提携版は無印版に比べて使えない機能がいくつかあるようなのですが、私は気にならなかったのと、住信SBIネット銀行提携版では2点良いことがあります。
1点は提携金融機関については10個の制限の対象外となりますので、私の場合、住信SBIネット銀行に加えて他に10個の金融サービスを登録できることになります。特にSBI証券を利用されている方は自動的に住信SBIネット銀行も契約されていると思うので、無駄にならないかと思います。
もう1点良いことは広告が表示されないことです。
無印版と住信SBIネット銀行版の二つを使って比べてみたのですが、無印版に出てきたやや目障りな広告が住信SBIネット銀行版ではありませんでした。(2022/9/23現在)
今後はこの差は無くなる可能性がありますが、もしかすると住信SBIネット銀行の宣伝になっているからその分を銀行側が負担してくれているのかもしれませんね。他の金融機関提携版がどうなっているかはわかりませんが、最初に使い比べてみる価値はあるかと思います。
表計算ソフトでの資産管理
というわけでマネーフォワードはすごくいいサービスだと思いますし、ありがたく利用させてもらっています。ですが、あくまでサブとして利用し、メインの資産管理は自分で表計算ソフトで行なっています。
表計算ソフトで資産管理を行う主なメリットは以下の3つです。
メリット①:過去のデータが管理できる
マネーフォワードは契約時点からのデータは収集、蓄積してくれますが、過去のデータについては限度があります。
どこまで遡れるのかは私も知りませんが、私が使用している金融機関では自分で調べられる過去の取引の履歴は10年ほどが限界でした。(有料だったらいけるところもあったかもしれません)
私は可能な限りいろんなデータを管理したい人間なので、ちょっと物足りません。就職してからの給与明細は全て残しているので、これらのデータも全てまとめて管理したいとなったときにマネーフォワードでは難しいかなと感じました。
ちなみに以前はCSV、Excelによるデータのアップロード機能があったようですが、2022/09/23 現在は提供されていないようです。
メリット②:特定のサービスに依存しないので乗り換えやすい
マネーフォワードは良いサービスだと思いますが、いつまでも素晴らしいサービスであり続けるかはわかりません。サービスを終了する日が来るかも知れませんし、もっと競合が良いサービスを出してくることも考えられます。
そのときにマネーフォワードにどっぷり浸かったマニアックな使いこなしをしていては困ると思うのです。なので私は表計算ソフトなどで自分の分かる範囲内で管理したいです。
もちろん今でもマネーフォワードで(プレミアムサービスを利用すれば)CSVデータ出力はできるようですし、他のサービスに移行できるような手段も登場する可能性もあるかと思います。
とはいえ、非常に重要なデータですし、なるべく自分で管理しやすい状態においておきたいというのが本音です。
メリット③:未来の予測(妄想)して楽しんだり、自由度が高い
自分で表計算ソフトを用いて計算するので自分の資産状況に応じて項目を追加したり削除したりできます。
例えば私の場合は(1) 月単位の投資に限定したシート、(2) 月単位の資産全体を把握できる家計簿的なシート、(3)年単位のキャッシュフロー表を作成・管理しています。
(1) 月単位の投資に限定したシートでは銘柄単位で月の投資額、投資総額、評価損益などを記載しています。自分の投資ポートフォリオでバランスが適正かなどを見られるようにしています。
(2) 月単位の資産全体を把握できる家計簿的なシートではもっと大枠での資産管理をしています。月の収入、支出、全体の投資額、全体の評価損益などを把握します。自分のモチベーション向上のためにも月当たりの利回りや年当たりの利回りなどを自動算出できるようにしています。
(3) 年単位のキャッシュフロー表では過去・現在・未来全部を記載しています。人生100年になる可能性を見越して就職してからの資産推移を全て記載し、直近3年の支出をベースに今後の支出予測を記載、資産の運用利回りもパラメータで簡単に調整できるようにしています。
特に年単位のキャッシュフロー表をもとに今後の資産推移を妄想するのは楽しいですね。今のペースで貯蓄・投資をした場合利回り5%想定で2034年に資産1億円突破し、60歳まで勤め上げたら1.7億円、その後70歳までは収入なしで資産運用だけで過ごしても1.9億円、そこから年金をもらい始めたら資産はどんどん増えて80歳時点で2.6億円に・・・なんていう妄想ができます。
もちろん実際は様々なリスク要因がありますのでそのまま鵜呑みにはできませんが、それは生活しながら適宜修正していけばいいと思っています。
表計算ソフトでの資産管理のデメリット
もちろん表計算ソフトでの資産管理にデメリットもあります。
表計算ソフトの扱いになれていないと難しい
難しい関数は一切使用していませんが、さすがに計算式ぐらいは入力できないと難しいです数式を間違うことがある
表計算ソフトでいろいろなデータをみたくて数式をいじっているといつの間にか実態と合っていない予測になってしまうことがあります。人生プランに大きく影響するので念入りに検算されることをお勧めします手動なので時間がかかる
細かい資産推移などは全て手入力なので時間がかかります。マネーフォワード プレミアムのCSV出力サービスなどをうまく活用すれば省力化できるかもしれませんね。クラウドサービスに比べたら個人の管理なのでバックアップはより気をつけないといけない
ローカルPCのHDDに置いているだけだとHDDがクラッシュしたら終わりなので別のHDDやクラウドなどにバックアップが必須です。
というわけで表計算ソフトでの管理は誰にでもおすすめできるというわけではありませんが、早期の経済的自立を目指す一助になれば幸いです。
みなさんも過去・現在・未来の観点で資産管理されているかと思うのですが、良い方法があったら教えてもらえたら幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
