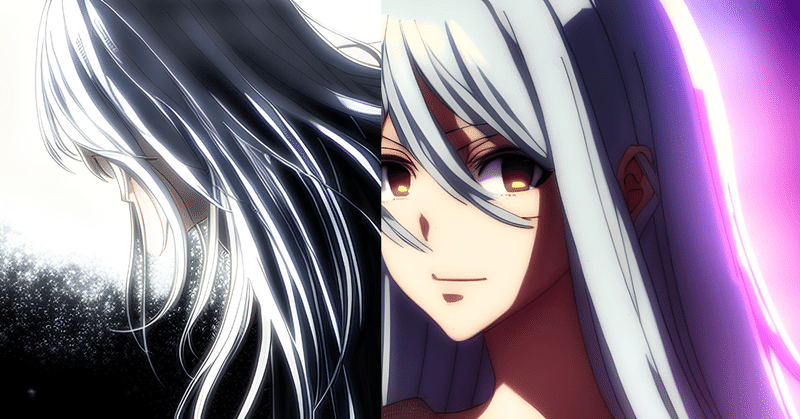
『魔女の遺伝子』第九話「普通の女の子」
既出の登場人物
エリザベス・アヴェリー:愛称リサ。本作の主人公。やや背が高い銀髪の女子高生(ヴィジュアルはヘッダー画像右)。政府の少子化対策の一環として作られたクローン人間の一人。本人も彼女の友人もそのことは知っている。
ナタリー・ホワイト:愛称ナターシャ。500年前に迫害を受けていた能力者を束ね、国家転覆を企てた少女。国に甚大な被害をもたらすも、最終的に捕らえられ処刑された。リサのクローン元。
クリストファー・ブライアント:愛称クリス。長身、短い金髪の美男子。ヴァネッサの仲間と思われたが、彼女を騙してリサと一緒に逃走を図る。物体を加速または減速させる能力を持つ。クローン元になった同名の人物がナターシャの切断された左手を盗み出し保存していた。
(作者注:第八話に引き続きクリスの回想から)
次の日、俺が見回りでナターシャの房を横切るたび、あいつはそっぽを向いて顔を合わせないようにしていた。まあ、おおかた嫌われたのだろうと思って、俺も何も言わないようにした。
そしてその晩、いつものようにパンと水を持って行ったときのことだった。
「食事だ。置いておくぞ。水が飲みたくなったら俺が通りがかったときに言え。いいな」
両手がないナターシャに対しても王国は厳しく、飲めないとわかっていて、普通のコップに水を入れて出すよう指示を出していた。お上の酷い仕打ちと、能力者でありながら迫害を免れた自分自身の負い目が、俺に妙な情を抱かせたのかもしれない。
しばらく様子を見たが、ナターシャはずっとそっぽを向いたままだったから、俺は諦めて戻ろうとした。
「待って」
そのときあいつは、気のない声で俺を呼び止めた。返事を期待していなかったから、正直驚いたよ。
「食べる」
あいつはそう一言だけ言って、パンと水の乗った盆に近付いて地べたに座った。俺もその場で胡坐をかいた。
「パンも口に運ぶか?」
「いい。あっち向いてて」
介助されるみたいで嫌だったんだろうな。それに両手が無いから食べ方も不格好になると思ったんだろう。食べているところは見せたくないみたいだった。俺は言われた通り他所を向いたよ。
静かな夜の牢獄に、ナターシャがパンを食べる音だけがしていた。
「水」
「はいはい」
「あっち向いて」
「……はい」
俺はあいつに言われた通り、明後日の方向を向いたまま、コップを持って少しずつ傾けて水を飲ませた。看守と囚人なのに、立場が逆転していた。
そんなこんなでナターシャはパンを食べ終えた。
「少しは腹の足しになったか?」
「……」
あいつはしばらく黙ってから、そのまま何も言わず寝床に戻っていった。まあ、食事を口にしただけでも大きな成果だと思って、その日もそれ以上は踏み込まなかった。
翌朝、俺は早番だったんだが、朝の巡回のとき、何の気まぐれかナターシャは自分から俺に声をかけてきた。
「ねえ」
「どうした? 話したいことがあるなら、大声を出さないよう注意して話せ」
「大声なんか出さない」
そのとき俺はちょっと違和感を感じたんだ。あいつは暗く沈んだ瞳をしていたが、それ以外は普通の十代の娘って感じだった。収監された日とは印象が違った。
看守としてあるまじき考えだが、俺はそのとき、あいつが万単位の人間を殺したのが、まるで嘘のように感じられたんだ。
あいつは迫害してきた人間を虐殺し、王国の正規軍に挑んで甚大な被害を与えた。それは紛れもない事実だ。しかしそれは迫害によって追い詰められ、心が歪んでしまったためではないのか。そんな考えが頭を過った。
「ねえ、聞いてる?」
「あ……。ああ、すまん。少しぼうっとしていた」
俺は意識が別の方に向いているところを引き戻された。
「何か言いたいことでもあるのか?」
「そうじゃない。あなた、普通の人間として生きてきたんでしょ?」
「ああ」
「なら、私ぐらいの歳の女の子が、どういう生活をしているのか、当然知ってるのよね?」
「そりゃまあ。お前ぐらいの歳ってことは、十ぐらい下か。この仕事に就いてから関りがめっきり減ったから、あんまり具体的な話はできないが」
「聞かせてよ。普通の女の子って、普段何をしているの?」
あいつは興味津々だった。知識ぐらいはあっただろうが、能力者は伝染病が蔓延しはじめる前、すでに社会から距離を置かれていたからな。実態をよく知らなかったんだろう。
「だいたいお前が聞いてきた通りだろうが、まあいいか」
それから俺は、年頃の娘の生活についてかいつまんで話した。
「昔は文化的な生活を送れるのは富裕層だけだったらしいが、今は行商が盛んに商売できるようになって経済が潤って、庶民にも様々な娯楽が広まってきたんだ。それで若い女のすることと言えば、友人と一緒にマルシェで買い物をしたり、カフェでお喋りをしたり、男たちがスポーツをするのを観戦したり。伝染病が流行りだす前、豚の膀胱で作ったボールを蹴り合ってチームで得点を競うゲームが流行りだして、その人気選手の話題なんかでよく盛り上がってたみたいだな」
ナターシャは俺の話を熱心に聞いていた。そういう生活に憧れを抱いていて、伝聞の真相を知りたかったのかもしれない。
「それから、能力者の家系は教育熱心だからお前も俺も読み書きができるが、ここ二世代ぐらいで、普通の庶民の識字率もだいぶ上がってきた。そのおかげで、多くの人が本を読み、演劇を楽しめるようになったんだ。大劇場はまだ安くないから、庶民の多くは小さな芝居小屋で劇を楽しんでる。若い女に人気の演目は、だいたい恋愛ものだな。俺は演劇に疎いからよく知らないが、最近は有名な舞台作家が書いた、恋愛悲劇が大人気らしい」
そこまで話して、俺は巡回の時間が残り少ないことに気付いた。
「そろそろ時間だ。期待していた内容と違ったら悪かったな」
「いいえ、満足よ。ありがとう」
一瞬、ナターシャが微笑んだ気がした。それにちゃんと礼も言った。数日前の刺々しさはもう感じられなかった。
六日目の朝、ナターシャは明日が死刑執行の日だというのに、前日以上に平然としていた。そして俺が巡回に来ると、またあいつの方から声をかけてきた。
「ねえ」
「なんだ?」
「そういえば、まだあなたの名前を聞いてなかったわ。聞いてもいい?」
あいつは俺の名前を知りたがった。普通、看守が囚人に対して名を名乗ることはないが、もう最後だからいいかと、俺は素直に答えた。
「……クリスだ。クリストファー・ブライアント」
「そう、クリスね。私はナタリー・ホワイト。ご存じだと思うけれど」
「ああ。存じ上げてる」
ナターシャはくすりと笑った。そのときは、はっきりと。
かと思うと、今度は思いつめたような顔で俺の眼を見た。
「クリス」
「ん?」
「私が死ぬまでにあと何回話せる? あなたの言う通り、ここで私の話を真剣に聞いてくれるのはあなたしかいない。だから悔いが残らないように、最後に話を聞いてほしいの」
あいつの真剣な眼差しを見て俺は、ここでこいつの願いを聞き入れないと一生後悔するだろうと思った。
「……二回だ。今日の俺の巡回は残り二回。お前と話せるのはその二回だけだ」
「……わかったわ」
「長話はできないぞ」
「うん」
俺はそのとき、何か覚悟のようなものを決めたつもりになっていた。この不幸にも道を誤ってしまった少女の、最期の願いを聞き届けるのは、俺の使命であり責任なのだと。
だが今思えばそれは覚悟ではなく、情に流され軸を失った愚かな男の、短絡的で浅はかな思い込みでしかなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
