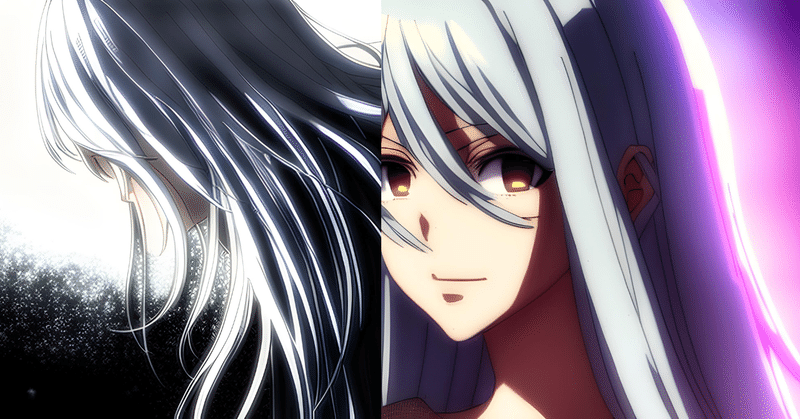
『魔女の遺伝子』第八話「五百年前の出来事」
既出の登場人物
エリザベス・アヴェリー:愛称リサ。本作の主人公。やや背が高い銀髪の女子高生(ヴィジュアルはヘッダー画像右)。政府の少子化対策の一環として作られたクローン人間の一人。本人も彼女の友人もそのことは知っている。
ヴァネッサ・ハートリー:誘拐されたリサの前に現れた白衣を着た赤毛のグラマーな女性。肘から先を自在に変形する能力を持つ。
ナタリー・ホワイト:愛称ナターシャ。500年前に迫害を受けていた能力者を束ね、国家転覆を企てた少女。国に甚大な被害をもたらすも、最終的に捕らえられ処刑された。リサのクローン元。
クリストファー・ブライアント:愛称クリス。長身、短い金髪の美男子。ヴァネッサの仲間と思われたが、彼女を騙してリサと一緒に逃走を図る。物体を加速または減速させる能力を持つ。
リサの能力によって大木に頭を打ち付けたヴァネッサは、その場でしばらく気を失っていた。そして気が付いたころにはもう、クリスたちは姿を消していた。
「……してやられたわ」
彼女は歯噛みし、クリスに裏切られた理由を探したが、思い当たる節は何もなかった。ただ一つだけはっきりしていることがあった。
(あいつが何を考えているのかはわからないけど、私の敵であることだけは間違いないわ)
ナターシャのクローンであり依り代でもあるリサを、クリスは連れ去った。そこにどんな意図があろうとも、ナターシャを復活させ、社会に復讐しようと企てるヴァネッサにとって、彼は紛れもない敵となった。
しかしクリスに裏切られ、リサを取り逃がしたにもかかわらず、ヴァネッサは先ほどよりずっと冷静だった。というのも、リサの中にいるナターシャの人格を蘇らせる、別の手立てを思い出したからだ。
(さっきあの娘が使った能力は紛れもなくナタリー様のもの。能力者のクローンは能力の覚醒度合に比例して元の人格が蘇る傾向がある。なら刺客を送り込んで戦わせれば、あの娘は自然と能力を使い、ナタリー様の人格を蘇らせることになるはず)
これはクリスや他のクローンで実験済みだった。あくまでゆるい相関だが、能力の発現と元の人格の復元に関連があることを、ヴァネッサはすでにつきとめていた。
組織にはすでに能力者の子孫と、社会に恨みを抱く能力者のクローンたちが何人もいる。彼らを使ってクリスを始末するとともに、少々手荒な方法で、リサの中にいるナターシャの人格を蘇らせようというわけだ。
「あの娘が自分の能力に気付いたのなら、それを存分に使わせればいい。ついでに世の中の汚さを嫌と言うほど聞かせてやれば、あの娘自身も気が変わるでしょう」
ヴァネッサは不敵な笑みを浮かべながら研究所へと戻って行った。
そのころクリスたちは樹海の半ばまで到達していた。
「もう完全に撒いたな。さあ、あと少しだ。ここを下れば大幅に時間短縮できる」
クリスはリサを抱えたまま、落差二十メートルほどの崖を前にそう言った。
「ここを下るって、どこを?」
「ここさ。この崖だ」
「え?」
彼はそのまま崖から飛び降りようとした。
「え!! 待って!! いや!!」
リサは驚いて声を上げたが、すでに二人は空中にいた。彼女は今日一番の恐怖で、目をつむり全身をガチガチに硬直させた。
このまま自分は崖から落下して死ぬ。そう思った瞬間、リサは心地よい夜風を受けながらゆっくりと下降していた。
「え? え?」
恐る恐る目を開けたリサは、状況が飲み込めずにきょろきょろと辺りを見回した。まるでパラシュートでも付けているかのようだった。
「言っただろう。俺の能力は物体を加速または減速させる能力。こんな風に服の落下速度を落としてゆっくり下降することもできる」
リサはあっけにとられてしばらく何も言えなかった。
クリスは無事、崖の下に着地した。
「さあ、もうあとは自力で歩けるだろう。下すぞ」
そう言って彼はリサを下した。リサはそこでやっと我に返った。
「もう! 飛び降りる前にちゃんと説明してよ! 死ぬかと思ったんだから!」
夢でも見ているかのような非現実的な出来事が立て続けに起こったためか、普段はおっとりしているリサもちょっとピリピリしていた。
「ああ、すまなかった。腕が限界に近かったんだ。担いでいられる間に降りないと面倒だと思ってな」
クリスは率直に謝罪し、弁明した。それを見たリサは大切なことを思い出した。
「あ……ごめんなさい。私、あなたに助けてもらったのに、文句なんか言って……」
「気にするな。いきなりさらわれて、突飛なことを言われて、おっかない女に追い回されて……。不安だっただろう?」
クリスはリサの気持ちを汲むように、優しく微笑んだ。
「でも……」
「それより、まずこの森を抜けよう。話は道中でゆっくりすればいい」
彼はそう言ってポケットからペンライトを取り出し、進行方向を照らした。よく見ると木々の並びが少し整ったところがあり、それがぼんやりとした道になっていた。
リサは黙って頷いて、クリスと一緒に歩きだした。
リサには気になることがたくさんあった。しかし何から聞けばいいかわからなかったので、思いついた順に尋ねることにした。
「ねえ」
「なんだ?」
「なんで私のことを助けたの? あなたはヴァネッサの仲間じゃないの?」
クリスは一瞬間を置いて答えた。
「仲間じゃない……というより君の味方だ。君とナターシャの味方。何から話せばいいか……。いや、正直に言おう。リサ。ナターシャのクローンである君が生まれた原因は俺にある」
「?」
「正確には、俺のクローン元である五百年前のクリストファー・ブライアントが原因だ。最後の戦いでナターシャは両手を切り落とされた。そしてナターシャが刑死したあと、その切断された左手を盗み出して保存したのが、五百年前の俺だ」
リサは立ち止まり、クリスの方を見た。
「どういうこと?」
彼女がそう尋ねると、クリスも立ち止まった。その背中はどこか物悲しげに見えた。
「順を追って話そう。俺は能力者であることを隠し、死刑囚を収監する監獄の看守として、当時の王朝に遣えていた。そこでナターシャを収監し、最期の七日間、毎日顔を合わせていた」
彼は再びゆっくりと歩きだした。リサも黙って彼について行った。
「初めて会った日、あいつは酷く荒れていた。俺は他の看守と一緒に、やっとの思いでナターシャを独房に入れた。その後は大人しかったよ。なんというか、すべてを諦めたような、途方もない虚しさがにじみ出ていた」
淡々と話すクリス。リサは自分のクローン元であるナターシャの話に不思議な感覚を抱いていた。
「翌週には死ぬさだめだからか、出された食事にも一切手を付けない。それでも決まりだったから、俺はナターシャの独房に水とパンを運んだ。そして三日目の晩。俺はほんの気の迷いから、個人的にあいつに話しかけたんだ」
==========
「おい。いくら死刑が決まったからって、飲まず食わずじゃ苦しいだけだぞ」
ナターシャは俺の方をちらっと見ただけで、またぼうっと何もない空間を眺めだした。そのとき、なんでだろうな、同情からか、また別の感情からかはわからないが、俺はあいつに、自分が能力者であることを打ち明けたんだ。
「聞け。俺もお前と同じ能力者だ。素性を隠して生きている」
するとナターシャは俺の方を見たあと、ゆっくり立ち上がってこちらに近付いてきた。
「これから刑死する人間をからかって楽しい? 私はもう疲れたの。食事もいらない。絞首刑でも飢え死にでもなんでもいいから、死ぬまで独りでいたいの」
あいつは怒りと悲しみが入り混じった表情で俺を睨みつけた。まあ、からかっていると思われても仕方がない。俺は自分が能力者であることを証明するために、持っていた銅貨を取り出して、その場で落としてみせた。減速の能力を使って。
ゆっくりと落下する銅貨を見て、ナターシャは目の色を変えた。そして、なんで? って顔で俺を見たんだ。
「すまない。本来なら俺もそちら側の人間だ。三代前からずっと隠してきたおかげで迫害を免れた」
ナターシャは悔しそうな顔をして俯いた。
「やっぱり、からかってるじゃない。自分たちは上手くやりおおして迫害を免れたって、自慢したいわけ? あっち行ってよ。お願いだから……」
いたぶるつもりはなかった。だが俺もどうしたらいいかわからなかった。
「俺が気に入らないなら、俺の能力のことを他の看守にばらせばいい。それで気が晴れるならな。だが俺なら聞いてやれる話もある。死刑になったのは仕方がないが、死ぬ前に吐き出したい膿もあるだろう。能力者でない人間はお前の話に耳を貸さない。それはお前が一番よく知っているはずだ」
あいつをどうにかして救ってやりたい。そう思って絞り出した言葉がそれだった。今思えばただの思い上がりだがな。
「……知らないわよ」
ナターシャがそう言って寝床に戻ったから、俺もその晩はそれ以上は踏み込まず、大人しく引き下がることにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
