
フランク・ノリス『マクティーグ サンフランシスコの物語』訳者解題(text by 高野泰志)
2019年9月24日、幻戯書房は海外古典文学の新しい翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の三冊目、フランク・ノリス『マクティーグ』を刊行いたします。
本書はもともと1899年に刊行され、エリッヒ・フォン・シュトロハイム監督に映画『グリード』(1924。淀川長治も生涯ベスト・ワンの一つに挙げた一本)を作らせたノワール文学の先駆的作品。日本ではかつて1957年に『死の谷』の邦題で岩波文庫上下二冊で訳されたこともありますが、長らく絶版。今回は完全新訳にして、当時の地図や新聞記事など、資料や附録も豊富に収録したニュー・ヴァージョンです。
以下に公開するのは、訳者・高野泰志さんによる「訳者解題」です。アメリカ自然主義(ナチュラリズム)による最高の「宿命小説」とは? どうぞご覧ください。
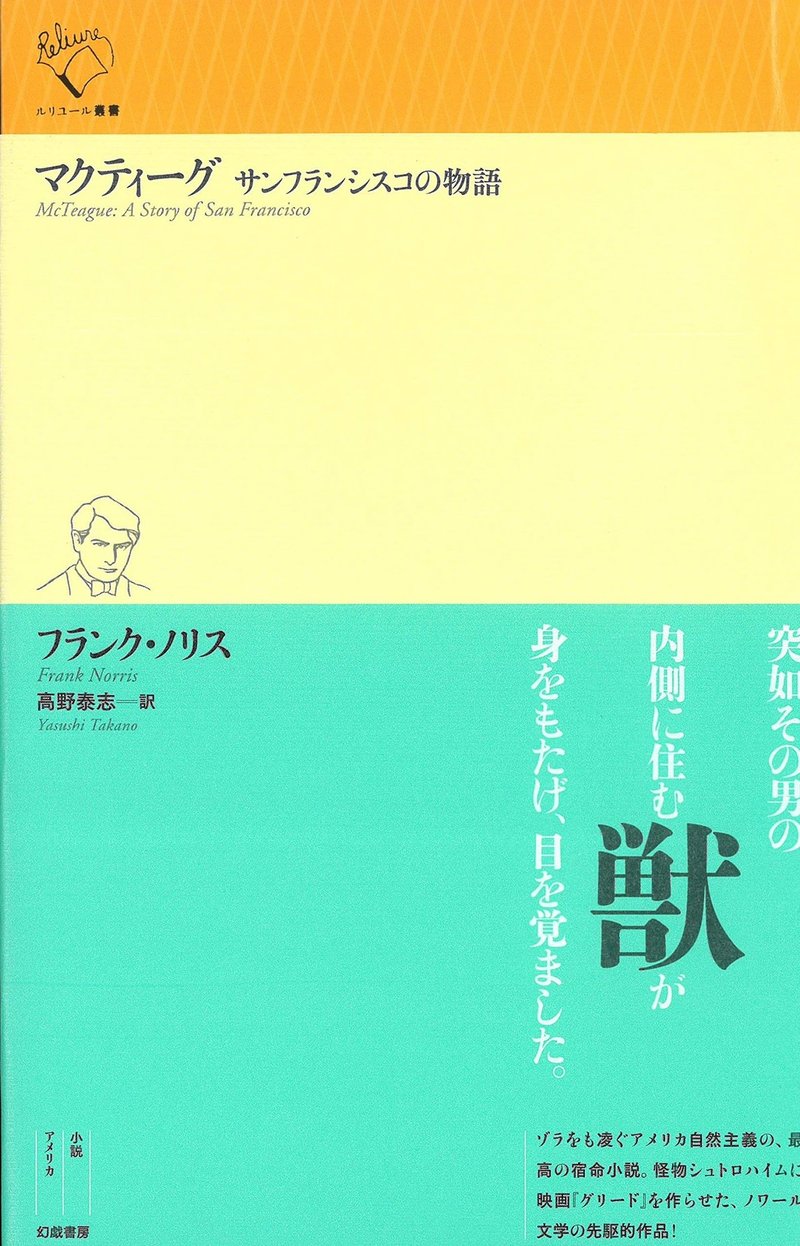
人物
19世紀から20世紀へと移り変わる過渡期、フランスの影響を受けてアメリカ文学においてもナチュラリズムの運動が盛んになった。しかしほかのナチュラリズムの作家、シオドア・ドライサー(『シスター・キャリー』『アメリカの悲劇』)、スティーヴン・クレイン(『街の女マギー』『赤い武功章』)、ジャック・ロンドン(『荒野の呼び声』『白い牙』)などと比べると、日本におけるフランク・ノリスの知名度はかなり低いと言えるだろう。しかしその文学的価値はほかのナチュラリズムの作家と比べて決して劣ることはない。とりわけ『マクティーグ McTeague : A Story of San Francisco』は多くの論者によって、この時代を代表する傑作とみなされ、文学史でもきわめて重要視されている。とりわけストーリーテリングのおもしろさという点について言えば、本書はあらゆるアメリカ文学作品の中でも群を抜いており、まさに巻をおく能わずというべき作品である。
まずは読者に恐らくあまり馴染みのない、作者フランク・ノリスに関して、簡単に説明しておこう。ノリスは1870年にシカゴで生まれた。父親はミシガンの農場で生まれながらも、宝石の卸売業で財をなした立身出世の人であり、ノリスはかなり裕福な家庭に育ったことになる。息子をベンジャミン・フランクリン・ノリス・ジュニアと名付けたのは、もちろん息子にも自分と同じように、成功者になってもらいたかったからだろう。もちろん言うまでもなくベンジャミン・フランクリンはアメリカを代表する立身出世の人である。母親はもともと教師をしていた女性で、イギリスのロマンスを好み、子供たちに幼い頃からそういった作品を読んで聞かせていた。1年間、一家でヨーロッパに滞在した後、ノリスはシカゴの私立学校に入学するが、ノリスにとっては母親の読んで聞かせてくれるイギリス小説の方がよほど大きな影響を与えたようである。
その後1884年にカリフォルニア州オークランドに移住し、85年にはサンフランシスコに落ち着く。父親は息子に自分のような実業家になってほしかったようだが、ノリスは高校の授業に興味をもてず、絵を学びたいと言って高校を退学し、絵画クラスに入る。87年には一家はイギリスに旅行し、その後すぐにフランスに移り住む。ノリスはパリのアトリエで絵の勉強を始め、両親がサンフランシスコに帰った後もフランスに残った。ところがこのフランス滞在中にフランス文学に興味をもち始め、小説を書きたいと思うようになるのである。父親はノリスを宝石商の跡継ぎにする予定だったので、このような息子の興味を知り、慌ててアメリカに連れ戻したのである。
その後カリフォルニア大学バークレー校に入学するが、そこでフランスのナチュラリズムの作家ゾラに出会い、熱中することになる。またバークレーでのもうひとつの重要な影響は、ジョセフ・ルコントの進化論の授業であった。この授業で得た知識が、後のノリスの文学的基盤となったのである。
ただ、英文学の授業は昔ながらの修辞学研究であったため、創作を目指していたノリスには興味のもてるものではなかった。また必修であった数学の単位が取れず、結局バークレーを中退することになるのである。その同じ年、両親が離婚する。その結果、ノリスは本格的に作家として自立することを考え始めるのである。
バークレーを去った後、ノリスはハーヴァード大学の創作科に入学する。ここでルイス・E・ゲイツ教授(Lewis Edwards Gates 1860‐1924)に小説の創作技法を学ぶ。現代のアメリカでは非常に多くの大学で創作科が開設されており、多くの作家を輩出しているが、おそらくノリスはアメリカ文学史上最初の創作科出身の作家であると言えるだろう。そしてこの創作科時代の課題作文として、後の代表作となる『マクティーグ』の断片を書き始めるのである。また生前は出版されず、死後出版となった『ヴァンドーヴァーと野獣 Vandover and the Brute』を完成させたのもこの時期である。
大学を出た後、ノリスは1895年、「サンフランシスコ・クロニクル」紙と契約し、ジャーナリストとして南アフリカに行き、ボーア戦争を取材するが、翌九六年に病に侵され、あまり芳しい結果は残せなかった。帰国後は「サンフランシスコ・ウェイヴ」誌の編集スタッフとなり、以後2年間にわたり、エッセイや短編小説を発表する。そして最初に読者受けのする保守的なロマンス作品をいくつか発表しながら、1898年に当時の文壇の大御所ウィリアム・ディーン・ハウエルズ(William Dean Howells 1837‐1920)と知り合い、『マクティーグ』の原稿を読んでもらうという幸運に恵まれる。
その後、米西戦争の取材でキューバに行ったときには、同じくジャーナリストとしてその場に居合わせたもうひとりのナチュラリストの作家スティーヴン・クレイン(Stephen Crane 1871‐1900)と知り合うことになる。しかしこのときも発熱のため、ノリスはすぐにサンフランシスコに戻らざるを得なかった。そしてその翌年の1899年についに『マクティーグ』を出版したのである。この作品はそれまでのお上品な伝統のアメリカで大きな物議を醸し、厳しい批判にさらされたが、ハウエルズには好意的な評価を寄せられた。
一方でノリスは次の作品として「小麦の叙事詩」と名付けた三部作を構想し、三部作の第一作『オクトパス The Octopus』に取りかかる。1900年にはダブルデイ・ペイジ社に就職し、ジャネット・ブラックと結婚する。また、後のナチュラリズムの大御所シオドア・ドライサー(Theodore Dreiser 1871‐1945)が『シスター・キャリー Sister Carrie』の原稿をダブルデイ・ペイジ社に持ち込んだのもこの頃であった。ノリスはこの作品を絶賛し、同社から出版されることになる。翌年に『オクトパス』を出版すると、三部作の第二作『取引所 The Pit』創作に取りかかり、完成させる。その直後に一家はヨーロッパ旅行の計画を立てるが、まずはジャネットが虫垂炎の手術を受け、その後ノリスも急性虫垂炎にかかってしまう。医者に行くのを遅らせたために悪化し、壊疽と腹膜炎を併発した結果、わずか32歳の生涯を閉じるのである。
時代と作品
ノリスがすごした短い生涯は、アメリカの都市化がもっとも加速していた時期であり、大陸横断鉄道の完成とフロンティアの消滅にともない、それまでは東部の一部と、交通の要所シカゴなどにしかなかった大都市が、アメリカ中に飛び地のようにして広まった。今日の我々に非常に興味深いのは、生まれたばかりの西部の都市、サンフランシスコが非常に生き生きと描かれていることである。本書をお読みになった方は、マクティーグが歯科医院を開くポーク・ストリートの活気あふれる街並みを、轟音を立てて通りすぎるケーブルカーの様子を、また今も多くの観光客を集めるプレシディオの情景や、サンフランシスコ湾を渡った対岸にあるBストリート(オークランドの外れに位置する)が一気に鄙びてわびしげな様相を呈しているのをご記憶のことと思う。これらはノリスの正確かつ詳細な描写によって、当時の時代風俗の貴重な証言となっているのである(その後、ここに描かれた時代から十年とたたないうちに、サンフランシスコは1906年の大地震によっていったん壊滅的な打撃を受けてしまう)。ノリスがいかに正確にサンフランシスコの街並みを描いていたかを確認するためにも、附録の地図(前付掲載の「『マクティーグ』要図」)で登場人物たちの足取りをたどってもらいたい。そうすると、マクティーグとマーカスのふたりの散歩ルートがどれほどの長距離にいたっているか多少は実感できるのではないだろうか。
またこの作品にはきわめて多彩な人種が登場する。マクティーグの人種に関しては特に書かれていないが、名前からすると、おそらくはアイルランド系の移民であろう。19世紀半ばにアイルランドでいわゆるジャガイモ飢饉が起こった結果、大量のアイルランド移民がアメリカに押し寄せることになった。とりわけ1848年にカリフォルニアで金鉱が発見されると、翌49年にはこのゴールドラッシュは海外からの移民も惹きつけることになった。アイルランド移民を含むこれらの移民はフォーティナイナーズと呼ばれ、アメリカ大陸を横断して西部へとやってきたのである。1855年までに少なくとも30万人の採掘者が訪れたが、この中にはアメリカ人のほかにヨーロッパや南アメリカ、中国人などが入り混じっていたという。鉱山で働いていたマクティーグの父親も、おそらくはこのゴールドラッシュの流れに乗ってカリフォルニアに住み着いたのであろう。
トリナ・ジーペやマーカス、あるいは彼らの親戚たちはドイツ系スイス人の移民であると書かれている。これも19世紀中葉のアメリカでは、ヨーロッパでの1848年革命の影響で、おびただしい数のヨーロッパ系移民が渡米していたことと関連している可能性がある。これら革命の影響で訪れた移民はフォーティエイターズと呼ばれるが、中でもドイツからの移民は圧倒的多数に及んでいた。トリナの両親がドイツ語交じりの片言の英語を話しているのは移民一世であるからで、二世であるトリナやマーカスの世代がもう普通の英語を話しているのも、細かい描写ではあるが当時の実態を反映しているのであろう。
他にもメキシコ系のマリア・マカパやポーランド系ユダヤ人のザーコフなど、また背景にひっそりとではあるが所どころに中国系移民の姿も垣間見られる。彼らはアメリカ大陸に遅れて移民してきたという意味で、一般に新移民と呼ばれるが、旧移民の中心をなすアングロサクソン系の登場人物はグラニス爺さんとミス・ベイカーのみである。彼らだけが作中で唯一ハッピーエンドを迎えるのは、当然深い意味があり、その点に関しては後ほど、簡単に触れたい。
また、作中で特に触れられることはないが、この時代で忘れてはならないのが、1890年代から第一次世界大戦までの間、アメリカ合衆国がいわゆる帝国主義時代と呼ばれ、領土拡大を図っていた時代であったことである。『マクティーグ』が出版される前年の1898年にはハワイ王国を準州として併合した。またこの年にはノリスも新聞記者として取材した米西戦争が起こっている。この戦争の結果、カリブ海に浮かぶスペイン植民地であったキューバが、アメリカ軍の管理下で独立を果たす。しかし独立とはいっても事実上はアメリカの支配下にあった。アメリカでは先住民の掃討が終わり、フロンティアの消滅が宣言されたのが1890年である。アメリカがいよいよ国外へと目を向け始めた時代、『マクティーグ』はかつてのフロンティアの到達点である最西端の都市で繰り広げられる物語なのである。このことは表面的には小説とはなんの関係もないことのように思えるかもしれないが、後で詳しく述べるように、当時の人々の心性に強い影響を及ぼしていたのである。
開拓時代のアメリカ西部はとりわけ作品後半で綿密に描かれるが、マクティーグの逃亡ルートであるオーバーランド鉄道およびカーソン‐コロラド鉄道線沿いの情景も非常に興味深い。特に物語とはなんの関係もないものの、線路脇に無言で立ち尽くす先住民の姿など、非常に印象的である。これらの風景は、大掛かりな金鉱の掘削機などの描写やデス・ヴァレーでの試掘の様子も含め、すべてノリスが現地に行って綿密な調査を行った成果である。これらの位置関係も、ぜひ附録の「『マクティーグ』要図」で確認していただきたい。
また『マクティーグ』はたんに背景として当時の時代を描きこんだだけではない。ノリスはこの作品を実在の事件に基づいて着想しているのである。本書巻末には1893年10月10日と14日の「サンフランシスコ・イグザミナー」紙に掲載された新聞記事を「附録」として収録しているが、この記事が扱っているのがパトリック・コリンズというアイルランド系移民の起こした殺人事件である。詳しい内容については記事を読んでいただくとして、この貧民街で起こった悲惨な殺人事件を、ノリスは時代を映し出す事件として取り上げたのだ。作品に改変する中で大きく変更が加わっていることは言うまでもないが、幼稚園という殺人事件の舞台などが共通しているだけでなく、記事がコリンズの殺人の原因を「遺伝」に求め、文明社会に生まれた「野蛮人」の振る舞いとして描いているところも興味深い。この遺伝の問題は後程詳しく触れるが、まずは人間の行動が「遺伝」によって決定されるというのが当時の一般的な考え方であったことを確認しておいてもらいたい。このことは文学的状況にも大きな影響を及ぼしているのである。
文学的状況とノリスのナチュラリズム
では当時のアメリカにおける文学的状況を概観したい。当時はウィリアム・ディーン・ハウエルズや、マーク・トウェイン(Mark Twain 1835‐1910)、ヘンリー・ジェイムズ(Henry James 1843‐1916)らのリアリズム文学が発展するとともに、フランス文学のエミール・ゾラ(Émile Zola 1840‐1902)の影響を受けたナチュラリズムの文学が一気に花開いた時期であった。リアリズム文学とナチュラリズム文学の違いをごく簡単に説明しておくと、前者が主人公に自我を与え、社会の中でのその選択と行動を描くものである一方、ナチュラリズムはダーウィンの進化論に基づいており、遺伝と環境の支配を受けた登場人物に行動選択の自由はない。作家はただ実験室で顕微鏡をのぞくようにして、特定の遺伝子をもった登場人物を特定の環境に置いて、その様子を観察するのである。
このナチュラリズムの文学運動は、アメリカでは世紀転換期のほんの一時期にはやっただけで短命に終わったが、同じ文学運動に取り組む作家の中でも遺伝と環境に対する考え方や小説執筆にあたって重視する度合いも異なっていた。そんな中でも、スティーヴン・クレインやノリスは、かなり理論的にこの文学理論に取り組んでいたと言えるだろう。とりわけノリスはアメリカ文学独自のナチュラリズムを作り上げようとしたのであり、雑誌などでかなりの数のナチュラリズム小説論を書いたのである。ではノリス独特のナチュラリズムがどのようなものなのか、概観してみたい。
まずはノリスが小説家としてデビューする前に書かれたゾラ論を見てみよう。「ロマンス作家としてのゾラ “Zola as a Romantic Writer”」というエッセイで、ノリスはゾラやナチュラリズムの作品がこれまでリアリズムの発展形として捉えられてきたことに対して反論している。ノリスの言うナチュラリズム観によれば、ナチュラリズムとはむしろロマンスの一分野なのである。当時リアリズムの大御所であったハウエルズの作品を引き合いに出しながら、登場人物や物語に蓋然性があり、突飛な事態が起こったりしないのがリアリズムである、とノリスは主張する。一方ナチュラリズムは表面的な描写の正確さ、綿密さにはこだわるが、そこがポイントなのではなく、描かれる事件が我々の身のまわりで起こりそうなことではない。つまり日常に起こり得るかどうかという蓋然性がリアリズムとロマンスを分ける境界線であると考えるのだ。「〔リアリズム文学が描くのは〕日常生活のほんの小さな細部であり、昼食と夕食の間に起こりそうな出来事であり、ささやかな恋愛、抑制された感動であり、応接間のドラマ、午後の訪問の悲劇、ティーカップをめぐる危機なのである」という有名な一節は、ノリスのリアリズム観を非常に的確に表していると言えるだろう。当時アメリカのリアリズム文学はいわゆる「お上品な伝統」と呼ばれ、過激なテーマや醜悪なモチーフを描くことを避ける傾向にあったが、ノリスはそういった伝統に反発を感じていたのである。
それに対してロマンスとは、非日常の世界であり、我々の周囲にいる人物やありきたりの事物を描くものではない。「〔ロマンスは〕我々の世界ではない。それは我々の社会的地位が異なっているからではない。我々が平凡だからだ。ゾラ氏の注意を惹きたければ、庶民たることをやめ、日々前進する世の中の先頭に立つか、あるいは道端に倒れるかしなければならない。大衆から孤立しなければならない。個性的で唯一無二の存在にならなければならないのだ。ナチュラリズムの作家は平凡な庶民など顧みないのだ。利害関係や生活、考えが平凡で、ありきたりである限り、見向きもしないのだ」確かに『マクティーグ』の登場人物たちは、一見どこにでもいるような取るに足りない平凡な人物のようだが、社会的に転落し始めたときに見せる主人公の暴力性と狡猾さ、トリナの病的なばかりの金銭への執着など、「ティーカップをめぐる危機」を大きく逸脱していると言えるだろう。
『マクティーグ』を書いた後、1901年に書かれた「ロマンス小説の主張 “A Plea for Romantic Fiction”」をみてみると、この主張がさらに過激になって、公然とリアリズム批判をするようになる。リアリズムは物事の表面しか見ず、また「見えるところしか見ていない」というのだ。「リアリズムは微細なものを描く。壊れたティーカップのドラマであり、1ブロック先まで歩くことの悲劇であり、午後の訪問の刺激であり、夕食に招待することの冒険なのである。近所の家への訪問、それも形式的な訪問なのであり、そこからはなんの結論も引き出せない。隣人や友人を――ひどく、そう、とてつもなくひどく当たり前の人を――目にすることになるが、それだけのことだ。リアリズムはドアマットの上でお辞儀をし、立ち去り、そして歩道で腕を組みながらこう語りかけてくる。「これが人生だ」と。わたしは違うと言いたい。そんなものが人生でないのは、ロマンスを片手に隣人を訪ねてみれば、すぐにわかるだろう」
ノリスに言わせると、ロマンスは玄関先でとどまることはなく、住人とともに家の中に入り、ベッドルームや居間に入り込んでクローゼットの中まで覗き回るのである。そしてそうしないまま物事の表面だけを描き、奥に隠されたものを暴き出そうとしないリアリズムを批判しているのである。もちろんリアリズム小説もまた、すぐれた作品であれば表面的な描写の背後に隠された真実を描き出すはずであり、必ずしもノリスの批判が当たっているわけではないが、ナチュラリズムの文学がしばしば貧困や売春、汚職や不平等など、お上品な伝統から隠された社会の暗部を暴き出そうとする傾向をもっていたことをうまく説明していると言えるだろう。
19世紀後半以降、今日にいたるまで、ロマンスということばが空想的な内容を含むものをすべて引き受けさせられる結果になり、遠い過去や馴染みのない異国を舞台にした突飛な物語であるとみなされがちになっているが、ノリスの主張によれば、真のロマンスは中世の時代やどこか遠くを舞台にするだけではなく、スラムや酒場の喧騒を舞台にしてもよいのだという。つまり下層階級の犯罪を描くロマンスこそが、ノリス流のナチュラリズムなのである。リアリズム小説や、大衆受けする空想ロマンスのような、お上品な題材だけでなく、我々の身のまわりには見られない汚いものをあえて暴き出し、それを遠慮することなく内側まで入り込んで描くことこそがノリスの目指していた小説なのである。このエッセイでノリスは「ロマンスに属するのは、この世の中の多岐にわたる様々なもの、計り知れない人間の心の内奥、セックスの神秘、人生の難題、人間の魂のいまだ分け入られたことのない深奥なのである」と高らかに宣言している。
ちなみにウィリアム・ディーン・ハウエルズは当時、お上品な伝統を代表するようなリアリズム文学の大御所として知られていたが、先にも触れたようにノリスには非常に好意的であった。『マクティーグ』に寄せた書評でのハウエルズの主張によると、そもそもヨーロッパ文学は大人の読み物であり、女性読者を想定せずに男性向けに書かれているのに対して、アメリカでは文学作品は伝統的に男女ともにあらゆる年代の読者にも受け入れられるように書かれてきたという。そしてそのようなお上品な伝統を捨ててヨーロッパの基準に合わせるべきだという問題を突きつけたのが『マクティーグ』であると主張するのである。そして以下のように述べている。「〔お上品な伝統を捨てるかどうかという点〕こそ、我々が考えるべき問題である。今我々はモンロー主義(ヨーロッパに干渉しないとするアメリカの孤立主義外交)が決して適用されることのない領域〔つまり文学のこと〕において帝国主義的拡張政策を始めたところなのである。我々がヨーロッパを侵略し、支配する時代がついに訪れたのかもしれない」文学を帝国主義的侵略の比喩を用いて表現していることからも、国外へと向けて領土拡張を目指していた当時のアメリカの時代風潮が見てとれる。そしてここでハウエルズはノリスの文学をヨーロッパの(ゾラの)方法論で書かれた作品とみなし、『マクティーグ』に文学的帝国主義の先兵となることを期待していたのだと言えるだろう。
『マクティーグ』とナチュラリズム
では、このノリスのナチュラリズム論は『マクティーグ』にどのように反映されているだろうか。以下作品のあらすじを振り返ってみたい【※作品の結末に触れているので未読の方はご注意を】。
物語は実在の事件に着想を得たもので、ノリスがハーヴァード大学の創作コースに在学していたときから書き続けていた題材である。主人公のマクティーグは鈍重なおとなしい大男で、サンフランシスコで歯科医業を営んでいる。そこへ同じアパートに住む友人マーカス・シューラーがいとこで恋人のトリナを連れてくる。トリナの治療を通じて次第に彼女に惹かれていくマクティーグは、マーカスに譲歩してもらい、ついにトリナと結婚することに成功する。しかしまだマーカスとつきあっていたときに買った富くじが当たったために、トリナは5、000ドルという大金を手に入れ、そのことがきっかけとなってマクティーグとマーカスの仲は次第に険悪なものになっていく。マーカスがその賞金の一部を手に入れる権利を主張し始めたのである。分け前をせしめることに失敗したマーカスは、マクティーグの歯科業が実は無許可営業であることを告発し、マクティーグは歯科医を続けられなくなる。それ以後マクティーグ家はどんどん落ちぶれていき、常習的に飲酒を始めたマクティーグは、病的なほど吝嗇になった妻に暴力を振るうようになる。やがてついにトリナを殺害したマクティーグは逃亡を企てるが、逃亡先のデス・ヴァレーで今は保安官になっているマーカスに追いつめられ、格闘の末にマーカスを殺害する。しかし死の間際にマーカスは自分とマクティーグを手錠でつなぎ、砂漠の真ん中で動けなくなったマクティーグもまた、そのまま死ぬしかないことを暗示しながら物語は終わる。
先ほど見たようなノリスのナチュラリズム論だけを読むと、いかに突飛な登場人物が出てくるのかと身構えるかもしれないが、実際に作品を読み進めると、それぞれの登場人物は非常に生き生きとした現実感をもっており、それほど大きく蓋然性を逸脱しているように思えないかもしれない。とりわけ脇役であるマリア・マカパやハイゼ、ミス・ベイカーやグラニス爺さんなど、いかにも我々の身近にいそうな錯覚を抱くのではないだろうか。一般的にリアリズム文学は社会の一部を切り取ることで現実感を生み出そうとするが、ロマンスは、たとえば「臆病な老人」とか「強欲で騒がしいアパート管理人」とか、典型的な人物を作り出してその役割を固定する。リアリズム文学の登場人物であれば、その人物が次にどのような行動に出るかは、その都度その人物が判断して動くのに対し、ロマンスでは、大概の登場人物が出来事に対してどのように対応するかは大半の読者に予想がついてしまう。ジーペ氏はいつもオーガスト(アウグーステ)を張り倒しているし、マリア・マカパはいつだってマクティーグの診察室から金目の物をくすねている。つまりロマンスとは人物を典型として扱うことに特徴があるのである。そしてノリスの主張に従うならば、リアリズムが個別の事実を例示するしかないのに対して、ロマンス的傾向をもつナチュラリズムは、人物の典型を観察することによって、より深い人間性の真実を見出すことができるのである。
このことと、ノリスが大学生時代に学んだ遺伝に関する生物学は、実は非常に深くかかわっている。『マクティーグ』が始まって間もない場面からひとつ引用してみよう。マクティーグが歯の治療でトリナに麻酔をかけた後の場面である。
マクティーグはまるで避難場所を求めるかのように作業に戻った。しかしトリナにもう一度近づくと、無防備で無力なその魅力がまた新たに押し寄せた。それは押しとどまろうとする決意に逆らう最後の異議申し立てであった。やおらマクティーグはトリナに覆いかぶさり、キスをした。乱暴に、真正面から口にべったりと。自分でも気づかないうちにそうしていたのだ。自分は強いのだと思い込んでいたその瞬間にこんなにも弱かったことを知って怯え、必死に力を振り絞ってもう一度作業に戻った。歯にゴムのシートを貼りつけているときまでには、ふたたび自分を抑えていられた。狼狽し、身震いが止まらず、運命の瞬間に感じた苦悩でいまだわなないていたが、それでも自分が優位に立っていた。獣は倒され、少なくとも今は服従しているのだ。
しかしにもかかわらず野獣はまだそこにいた。長いあいだ眠っていたが、今ついによみがえり、目を覚ましたのだ。これ以降は常にその存在を意識することになるだろう。鎖を引っ張り、機会を窺っているのを感じることになるだろう。なんと哀れなことか! なぜずっと純粋に、潔癖に彼女を愛せないのか? 彼の内側で息づき、肉に編み込まれた、この邪悪で不埒なものの正体はなんなのか?
マクティーグの内なる善良さすべてを形作る立派な素材の背後には、先祖代々受け継いできた邪悪が、下水のように脈々と流れているのだ。父親の、そのまた父親の、そして三代、四代、五百代の世代の犯してきた悪徳と罪悪が、その血を汚していたのだ。ひとつの人種全体の悪徳が、その血管を流れていた。なぜそんなことになるのか? マクティーグはそんなことなど求めていなかったのに。この男に非があるというのか?(本書42‐43ページ)
ここでマクティーグは、トリナに麻酔をかけたことをきっかけにし、突如眠っていた性的欲望を、トリナを襲いたいという獣のような欲望を抱く。マクティーグは最終的には殺人事件を起こすような犯罪者になってしまうわけだが、こういったマクティーグの振る舞いは彼自身にあるわけではなく、「五百代の世代の犯してきた悪徳と罪悪」がその血に流れているからなのである。この遺伝が、特定の環境に置かれたとき、どうなるかを観察するのがナチュラリズムの文学の作劇法なのである。
少し考えれば誰にでもわかることであろうが、このような考え方は、とりわけ性や人種に関して容易に偏見に陥りやすい。実際にダーウィンの進化論は当時、安易に人間社会に適用されて「社会進化論」という思想を生み出した。人間の身体を計測することで優等な人種と劣等な人種とを比較しようとしたり、遺伝的に優秀な種を残すことを検討したり、いわゆる優生思想につながっていくのである。言うまでもなくその最悪の結実がナチス・ドイツのホロコーストであったわけである。またこの社会進化論の副産物として生まれたのが、フランシス・ゴルトンの発見した指紋の個別性であり、またチェザーレ・ロンブローゾの始めた犯罪人類学である。前者は黒人が白人よりも劣っていることを「計測」しようとした試みのひとつであり、後者は犯罪者に典型的な顔つきや身体的特徴を遺伝的に分類することを目指したのである。
当然ノリスはこの時代に生きた人間として、当時のこの人種差別的な思想の影響を受けていた。先ほど軽く触れたように、この物語に登場するほとんどの登場人物は新移民であり、そのほとんどが不幸な結末を迎えていることもその表れである。唯一ミス・ベイカーとグラニス爺さんだけが幸せな結末にいたるのは、おそらくは彼らがアングロサクソンだからである。このようなアングロサクソン中心主義は、当時のアメリカの領土拡張政策と無縁ではない。キューバやフィリピンなどに確実に勢力を拡大する一方で、国内に入り混じる雑多な新移民を下位に分類し、アングロサクソンの集団と区別する必要が生じていたからである。
また、ジェンダーに対する偏見も非常に強く表れていることは、現代の読者であれば誰もが気にかかるところであろう。先ほどのアングロサクソンのふたりも、マクティーグ夫妻の家財道具のオークションの場面を見れば明らかなように、男性であるグラニス爺さんの方がわずかに道徳的に優れているように描かれているのにお気づきだろうか。
しかし『マクティーグ』がこのような人種やジェンダーに関して強い偏見のもとで書かれているにもかかわらず、登場人物たちがそれを超えて生き生きとした魅力をもっていることも事実である。自らの偏見に無自覚なままステレオタイプな人物を登場させているはずの『マクティーグ』が、いったいなぜこのような魅力をもっているのか。それはおそらくノリス自身が、自分で主張しているこの「普遍の真理」に、どこかで疑いを抱いているからではないだろうか。今回何度も繰り返し読んでいたこの作品を訳していて、あらためて気づかされたのは、先ほど引用した部分でもはっきりと表れているように、ノリスが普遍の真理と考えていたものを描くところで、急におびただしい数の疑問文が登場することである。もうひとつ、マクティーグがトリナにキスをする場面を引用してみたい。
列車の通過はふたりをひどく驚かせた。トリナはもがいてマクティーグから身を引き離した。「ねえ、やめて! お願いよ!」ほとんど泣きそうになりながらトリナはそう訴えた。マクティーグは離してやったが、その瞬間、わずかに、ほんのかすかにしかわからない程度だが、それまでの感情が方向を変え始めた。トリナが身を明け渡した途端に、キスを許した途端に、マクティーグの方は前ほどにはトリナのことを思わなくなった。結局さほどものにしたいわけでもないのだ。しかしこの反動はあまりにもかすか、あまりにも微細、あまりにも漠然としており、次の瞬間にはそんなことが生じたとは信じられなかった。しかししばらくたつとまた蘇ってくるのだ。今のトリナから何かが失われてしまわなかっただろうか。自分がずっとしたいと思ってきたことなのに、やっとやり遂げたと思ったら、そのせいでトリナに失望してしまったのではないか? 従順でおとなしく、手に入れることのできるトリナだって、何も変わらないはずではないか? 手に入らないトリナと同じくらい品位があって愛らしいはずではないか? おそらくマクティーグにはぼんやりとわかっていたのだ、これは仕方のないことなのだと。変わらぬ世の常なのだと。―男は女が自らを譲り渡そうとしないからこそ女を求めるのだ。女は自分が男に明け渡したもののために男を崇拝するのだ。譲歩を勝ち取るごとに男の欲望は冷めていく。身を明け渡すごとに女の崇拝はいや増すのだ。しかしなぜそうでなければならないのか?(本書100‐101ページ)
「変わらぬ世の常」だと言いながら、ここでノリスはそのことに疑問を抱いているように見えてこないだろうか。「なぜそうでなければならないのか?」この問いはノリスが自分に向けて問いかけた問いではなかったろうか。結局はノリス自身の中に浮かんでくるこの疑問のせいで、そして自分の説に対して抱いている疑いのせいで、たんなるステレオタイプが予想通りの行動を起こす小説とは違い、それぞれの人物の行動に陰影が生まれてくるのである。ノリスのもつ自己矛盾に関してもう少し詳細に知りたい読者は、拙著『下半身から読むアメリカ文学』(松籟社)に『マクティーグ』を論じた章があるので参照されたい。
『マクティーグ』への反応
『マクティーグ』は1899年に出版されたが、当時はお上品な伝統の支配する時代であり、この作品は大きな衝撃をもって受け止められた。読者もクライマックス近くの陰惨な殺人の場面などは強く印象に残っているのではないだろうか。しかし興味深いことに、当時の読者からもっとも強い批判を受けたのは、殺人の暴力的な場面ではなく、もう少し違った場面であった。本書のどの部分に当時の読者が眉をしかめたのか、おわかりだろうか。
あまりに強く批判を受けたために、第2版を出版する際に一部の文章を差し替えざるを得なくなったのは、実は第8章のヴァラエティ・ショーを見に行く場面である。ここでオーガストが尿意をこらえ切れずにお漏らしをしてしまうことが描かれるが、これが当時の読者からは許しがたい描写であった。たとえ血みどろの殺人を描くことは許されても、排泄を描くことは許されなかったのである。19世紀のアメリカでは人間の生殖や排泄は、ないもののように扱われ、決して触れてはならなかったのである。よく引き合いに出されるエピソードであるが、19世紀半ばごろ、アメリカではピアノの脚にまで布を巻いて隠す習慣があったという。これはもちろん人間の脚を連想させるから、そして脚は性器と隣り合わせにあるから、という理由であり、あまりにも行きすぎた身体性への拒否感があったのである。したがってたとえオーガストのような子どもであっても、排泄を描くなどもってのほかだったのである。第2版ではオーガストの尿意は眠気にとってかわられ、お漏らしのかわりにマクティーグが帽子をなくすことになる。
またこれと同様の問題として、差し替えこそされることはなかったが、麻酔から覚めたトリナの感じる吐き気も排泄に類する問題として非難を浴びたという。もっともトリナに関して言えば、吐き気以上に物議をかもしたのは、はっきりとは描かれないものの、トリナが性欲をもっているらしいことが匂わされている点である。お上品な伝統においては女性は性欲を感じないものというのが当時の常識であり、男性のこの「思い込み」は20世紀前半までも支配し続けることになる。ノリスはこのような刺激的な作品を出版するために、『マクティーグ』と並行して、当時のお上品な伝統に完全に従った娯楽的なロマンスをいくつか書いて、出版社を説得したのだった。
なお、拙訳ではオーガストのおもらしの場面も、初版の状態のまま訳してある。
映画について
『マクティーグ』はその後、ハリウッドで1924年に映画化されている。オーストリア生まれのエーリッヒ・フォン・シュトロハイムという怪物的なまでに完全主義者の手にかかって作られた作品は『グリード Greed』というタイトルをつけられるが、この作品の公開には現在にいたるまで語り継がれる逸話が残っている。フォン・シュトロハイムはノリスのこの作品にあまりに心酔し、持ち前の完全主義で完璧な形で映画化しようと試みた。当時はスタジオ撮影が常識であったが、フォン・シュトロハイムはすべてをロケーションで撮影した。1906年の大地震で崩壊する以前のサンフランシスコの街並みを実際に再現させ、俳優たちをそこで寝泊まりさせて登場人物になりきるよう指導した。また作品最終部の舞台であるビッグ・ディッパー鉱山は、現地に赴き、すでに操業されていなかった設備を再稼働させた。きわめつけはデス・ヴァレーの場面で、夏の盛りに実際にアルカリ砂漠のデス・ヴァレーで撮影を行ったため、撮影スタッフの中には死者まで出たという。
フォン・シュトロハイムは『マクティーグ』に描かれた内容を一字一句まですべて撮影することを目指し、膨大な脚本に基づいて撮影を行った。七か月の撮影期間が終わると、フィルムの全長は44、104フィートにおよび、最初の試写の段階でおよそ9時間あったという。その後映画会社の指示により、自ら約半分の長さにカットすることを余儀なくされるが、それでも上映するには膨大すぎた。紆余曲折を経たのち、『グリード』はフォン・シュトロハイムの思惑を無視する形で最終的に130分弱にまで削られた。今日われわれが目にすることのできるのはこのバージョンである。
フォン・シュトロハイムはサイレント映画時代の三大巨匠のひとりと言われ、現在でも熱狂的なファンが多い映画監督である。彼はノリスの創作姿勢をほとんど自分のもののように感じるほど熱烈に信奉しており、その結果が『グリード』製作に向けた執念につながったのだろう。映画会社に無残に切り刻まれる以前の失われたフィルムは、いまだに時折発見されたといううわさが生じるが、今のところそのすべては虚報であることが判明している。いずれ完全版のネガが発見されるようなことがあるかどうかはわからないが、短いバージョンに関してはDVDが発売されているので現在でも鑑賞は可能である。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。本篇はぜひ、書籍『マクティーグ サンフランシスコの物語』で御覧ください。
