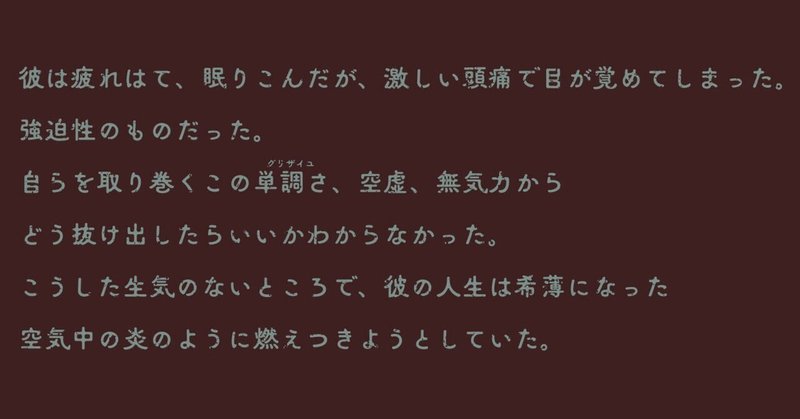
ジョルジュ・シムノン『運河の家 人殺し』訳者あとがき(text by 森井良)
2022年4月25日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第21回配本として、ジョルジュ・シムノン『運河の家 人殺し』を刊行いたします(本書で30冊目の刊行を迎えました)。ジョルジュ・シムノン(Georges Simenon 1903-89)はベルギーのリエージュ生まれ、フランス語圏の作家。〈メグレ警視〉シリーズでも世界的に有名なミステリー小説家として知られています。
本書の2作『運河の家』『人殺し』は、そんな〈メグレ警視〉シリーズと並行して書かれた、純文学志向の〈硬い小説(ロマン・デュール)〉の作品。ベルギー、オランダの灰色に染められたフランドル地方を舞台に、〈イヤミス〉どころではないイヤな苦味がいつまでも心の中に残る傑作です。『運河の家』『人殺し』の作品選定はあの、「翻訳ミステリー大賞シンジケート」ブログの長期連載「シムノンを読む」で知る人ぞ知る、シムノン研究家の顔をもつ作家の瀬名秀明さんによるもの(瀬名さんの過去の連載記事『運河の家』『人殺し(『殺人者』)』も併せてお読みください』)。翻訳は、シムノンの文芸の師であるアンドレ・ジッドの文学研究者・作家の森井良さん。本書巻末には、森井さんの「訳者あとがき」のほか、シムノンの年譜、80枚以上の力のこもった瀬名さん書き下ろしの「解題」を収録。シムノン入門に絶好の紹介本になっています。
以下に公開するのは、ジョルジュ・シムノン『運河の家 人殺し』の翻訳者・森井良さんによる「訳者あとがき」の一節です。


収録した2篇は1930年代に書かれた、ロマン・デュールの初期作である。いずれも灰色のフランドル地方(オランダ、ベルギー、フランスにまたがる地域)を舞台に、犯罪と謎を基調としつつ、凡庸な人間の凡庸ならざる心のうちに迫った問題作だ。互いに独立した作品でありながら、モティーフや表現のレベルでも相似した点が多く、さながら二面で同じ一幅の「単色画(グリザイユ)」をなしている観すらある。
『運河の家』(1933)は、シムノンの出身地であるベルギーを舞台に、両親に死なれた都会育ちの少女エドメが、田舎のまだ見ぬおじの家に赴くところからはじまる。おじとおばの他に、六人のいとこを擁するヴァン・エルスト家は、運河に囲まれた広大な〈灌漑地〉を所有する豪農だった。が、エドメが家に到着したとたん、大黒柱のおじが急死。その後、遺されたおばといとこたちの狼狽をよそに、運命が数々の不幸を一家に課してくる。「雄の匂い」を盛んに放つもつねに空回りがちな跡継ぎのフレッド、巨頭を揺らしつつ黙々と仕事に打ちこむ「村一番の馬鹿者」ジェフ、陽気で屈託のないたちながら「女」としてどこか未成熟なミア、彼らの母親にして「牝猫」さながら部外者に警戒の目を光らせる不気味なおば、そして一家を絶えず監視しにくる「話を聞かれることに慣れた男」ルイおじ──こうした異形の家族との暮らしに息を詰めていたエドメだったが、やがて寡黙なジェフを手なずけ、強引なフレッドを逆に籠絡するにいたる。いったい何が彼女をそうさせたのか? 生来の魔性か、身裡の熱の導きか? 人間の根源に迫るような謎を宙吊りにしたまま、ついには未曾有の犯罪が出来(しゅったい)してしまう。
つづく『人殺し』(1937)のほうが少しく喜劇的かもしれない。舞台はオランダ、運河も凍るフリースラント地方。自分だけの「しきたり」にしたがい、折り目正しい「日常」を送ってきた中年医師ハンス・クペルスは、雪積もる冬のある日、前代未聞の「冒険」に打って出る。皆勤賞の学会を欠席し、馴染みの親戚の家にも寄らず、挙げ句の果てに武器屋で一丁のピストルを購入──それもこれも、不倫中の妻と友人のシュッテルをこの世から抹殺するためだった。彼らの密会場所で無事計画を遂げたクペルスだが、予定どおりの後始末ができず、ひきつづき「日常」と「冒険」の奇妙な混淆に身を委ねていくことに。殺しから帰るその足で行きつけのカフェに立ち寄り、ビリヤードクラブの同志たちと球突きに興じ、家に帰ると若い女中のネールを思い切ってベッドに誘い──道を踏み外した新しい自分の人生に酔いしれる一方、なぜか胸の痛みは晴れず、気がかりの種もいっこうに減らない。世間の人々はいったい何を考えて生きているのだろう? クラブの男たちは? 愛する女中は? 匿名の手紙の差出人は? 他人どころか自分の「頭のなか」さえ摑めぬ医師はやがて、どこか懐かしい、自分だけの狂気の世界へ深く沈んでいく。
以上、つらつら要約を試みてみたものの、要約だけでも陰々滅々たるものだ。シムノンは自らの全集に『人々のさまざまな病い Maladies des gens』という総題をつけたかったそうだが、『運河の家』と『人殺し』もまたそのコンセプトから外れてはいない。エドメの夢遊病、ジェフの水頭症、ミアの湿疹、クペルスの狭心症といった落とし所のある「病い」から、火への執心、些事に対するこだわり、名づけられぬ欲望、幻視といった灰色の領域(グレー・ゾーン)まで──そして当然ながら、それらの延長上に犯罪ないし殺人という行為が控えていることになろう。作者はそうした「病い」を特殊な症例として囲いこむのでは決してなく、あくまで人間に普遍的な問題として外にひらき、よき社会に属する正しい人々、あるいはそう自分を呑気に見積もっている我々のもとに鋭く突きつけてくる。人間であることじたいが「病い」なら、誰しもそこから免れることはできない。そのことは、エドメ殺しの犯人が最後に放つ「あなたならどうしてました? あなたなら」という台詞、進退きわまったクペルスが群衆のうちに「自分自身」すなわち「事件が起こる前の人間の姿」を見てしまう場面に端的に表されているだろう。「病い」の普遍化は、言うまでもなく、「正しい(コンヴナーブル)」という価値観に対する異議申し立てでもある(「常軌にかなう」「きちんとした」「然るべき」などの訳語も当てられるconvenableという語は、シムノン作品に頻出するキータームである)。
もう一つ、今回訳していてアクチュアルに思ったのは、シムノンにおけるジェンダー/セクシュアリティの主題である。『運河の家』であれ『人殺し』であれ、フェミニスト小説とまでは言わないが、少なくとも当時の「男らしさ」の規範、男根主義的な価値観へのアイロニーが多分に含まれているだろう。じっさいフレッド、ジェフ、ルイおじ、クペルス、ビリヤードクラブの殿方連といった男性の登場人物たちは、「男性゠主人゠英雄゠所有者」のいわば典型であり、典型であろうとするあまりに「ずれ」や「弛み」を露呈し、その間隙から今度は「女性゠家内゠淑女゠所有物」の典型を装う女たちの突き上げをくらって、見事な戯画になりおおせている。むろん、女たちはそういった男たちと「男らしさ」の批判者であると同時に共犯者でもあるわけだが──「何か危ないこと、なかなかやれないことをやってほしい」と男に頼むエドメ、「男の人の涙を見るのは初めてで、そのことに恥ずかしくなった」ネール、「編み物を膝の上に置き、男たちの会話を邪魔しないよう小声で喋る」アリス──、他方で「男らしさ」の反転である「女らしさ」から逸脱した「はしたない(パ・コンヴナーブル)」女とされていることを思えば、彼女らそれぞれの復讐にも義があると言わねばならない。
また男どうしの絆、いわゆるホモソーシャルな集団のさても戯画的な描き方がおもしろい。「ホモソーシャル」とは、アメリカの文学研究者イヴ・K・セジウィックが提唱したジェンダー論の概念だが、同性どうしの排他的な交際、単性だけで構成される同質的な社会を形容する言葉だ。とくにジェンダー論やフェミニズムの文脈では、異性愛者の男性のホモーシャルが問題にされ、この場合否定的に言われることが多い。ヘテロ男性のホモソは男性性の誇示゠女性性の否定を結合原理とし、それゆえミソジニーとゲイフォビアが症候的に現れるとされるが、シムノンの描く男たちの社会゠交際(ソサイエティ)はまさしくその例示であり、とりわけ『人殺し』に登場する「一部の男たち、正確にいうならスネーク在住の真のブルジョワ男性のためだけに作られたこのカフェ」は格好のトポスと言っていいだろう。
たとえば、同じく男どうしのホモソーシャルな絆を描いた作家にパトリシア・ハイスミスがいるが──ヨーロッパとアメリカの往還、純文学とミステリのハイブリッド、また当人は前者への志向が強かったという点で、シムノンと立ち位置が近い作家かもしれない─、『見知らぬ乗客』(1950)や『太陽がいっぱい』(1955)といった作品において、ホモソーシャルがホモセクシュアルにぎらっと翻る瞬間、あるいはそのあわいの艶っぽい危うさまで活写する彼女に対し、シムノンの小説はホモソの沼底をどこまでも這いまわる執拗さが持ち味だ。それは自身も女たらしで男色への偏狭な軽蔑を隠さなかったという彼の限界かもしれないが、それでも自己を投影しながら女を愛する男たちの在りようをごまかしなく暴露し、そこに何重ものアイロニーを綾なして批評的な距離をとるところに、純文学の資格を要求する作家の面目があるにちがいない。
次に、シムノンの文体についても一言。とりわけ目につく特徴として言えるのは、直説法半過去と句読法(パンクチュエーション)であろう。直説法半過去はフランス語の過去時制の一つで、主に継続的な過去(「~していた」)と過去の習慣(「~したものだった」)を表し、物語においては状況・背景の説明を担って、「描写の過去」とも称される。半過去の文をたたみかけ、その場の情景や心象風景をムーヴィーのように撮影しているところに、突如として瞬間の絵を切り取るようなカメラのシャッターが下される─後者がまさに複合過去や単純過去といった点で捉えられるような過去の事件・行為を表す時制の役割なのだが、こうした一連の半過去から点的過去への流れ、何かが起こりそうな気配を醸成したところにぱちんと突発的な変事を生じさせるという叙述の呼吸を学ぶのに、シムノンのテクストは最適かもしれない。じっさい筆者も学生時代にフランス語の半過去と複合過去の違いを理解するのに、シムノンの推理小説を原文で読んだものだった。今回翻訳にあたってそのことを思い出し、二つの時制の使い分け、ムーヴィーとカメラを巧みに切り替えるサスペンスの語りを日本語に再現しようと試みたつもりである。
二つ目の特徴の句読法については、文節をぷつぷつと切り、短い一文をたたみかけることをいう。とくに日本語の読点にあたるヴィルギュールが頻繁に打たれ、ある種独特のリズムをなしているのだが、そこに規則性がないところを見ると、どうやら無作為に打たれているものらしい。既訳では再現されてこなかったシムノンの文体的個性であるし、今回訳出するのが芸術的野心の強い作品ということもあって、当初この句読法を訳文に反映しようと考えていた。が、いざやってみるといたずらにリーダビリティを損ねるだけで、かえってロマン・デュールの内容・主題上の斬新さを伝える妨げになる気がしたため、最低限の反映に留めたことをお断りしておく。ちなみにシムノンの短くスピード感のある文体にかんしては、時に指摘されるところのもので、たとえば作家の丸谷才一がこのことに言及して、原因を作家の病弱さに帰したりしている(「ああいう持たなくなる感じは作者にもあるんじゃないのかしら。だから、シムノンの小説はみんな短いんです。〔…〕シムノンは、血圧が上がって一週間とか十日しか持たない。ドクターストップがかかるんだそうですね」、『座談会・昭和文学史』第四巻、集英社、2003)。たしかに体質の問題もあるのだろうが、言い換えるなら、そうした体質に応じて彼自身が築きあげた量産型・早書きの執筆スタイルの結果ということでもある。物語・作中人物に没入し、自己を一種の「トランス状態」に追いこんだのち、直接タイプライターで、余計な推敲をすることなく、一気呵成(かせい)に書いていく──プレイヤッド版の注釈によれば、シムノンはこうしたシステムに則って作品の量産を可能にしたとのことだが、文体への影響も多分にあるにちがいない。それは頻繁な句読法だけでなく、同語反復を厭(いと)わず、中断符を多用し、口語的表現を地の語りに混ぜこむという点にも現れているように思う(フランス文学研究者のブノワ・ドニのように、こうした文体的特徴と「庶民」の凡庸な人生をありのままに描く作風から、シムノンを同時代の異端作家ルイ゠フェルディナン・セリーヌに比する論者もいる)。
最後に、シムノンとその理解者で友人であったジッドとの関係について少し触れておこう。ジッドがシムノンを「このうえなく強い関心をもって」読み出したのは、一九三四年五月のことだった。ジッドの親友で、彼の言行をひそかに記録していたマリア・ヴァン・リセルベルグ(ベルギー新印象派の画家テオ・ヴァン・リセルベルグの妻)は次のように証言している─「彼はこの作家〔シムノン〕によって引き起こされた賞賛の入り混じった驚きをふたたび私に伝えてきた。この作家は、文学的な配慮とはまったく関係のないところで、ありきたりの、まったく知られていないものを量産したのち、信じられぬほど心理学的な高尚さと価値をもった作品群をものしはじめているというのだ」(『プチット・ダームの手帳 Les Cahiers de la Petite Dame』第2巻、ガリマール社、1975)。
三面記事事件(フェ・ディヴェール)に絶えず関心を寄せ、人間心理の未解明の部分を注視しつづけてきた文学者が、そうした領域を密かに開拓していた生成中の小説家に惹かれたのは故なきことではあるまい。翌年、ジッドが創立に関わったガリマール社のカクテル・パーティで二人は邂逅、やがて書簡のやりとりがはじまり、「彼を最初に称賛した者の一人」を自認する文壇の大御所はこう宣言するにいたる─「私はシムノンを偉大な小説家と見なしている─おそらく今日我々がフランス文学のなかで持ちえた最大の、最も真に小説家らしい小説家である」(『北方手帳 Cahiers du Nord』第2・3号〔ジョルジュ・シムノン特集号〕、シャルルロワ社、1939)。
【目次】
運河の家
人殺し
ジョルジュ・シムノン[1903–89]年譜
訳者あとがき
解説(瀬名秀明)
【訳者略歴】
森井良[もりい・りょう]
1984年、千葉県生まれ。パリ第七大学博士課程修了(博士)。獨協大学フランス語学科専任講師。訳書にエリック・マルティ『サドと二十世紀』(水声社)、ロジェ・ペールフィット他『特別な友情――フランスBL小説セレクション』(編纂・共訳、新潮社)、小説に「ミックスルーム」(第119九回文學界新人賞佳作)がある。
【解説者略歴】
瀬名秀明(せな・ひであき)
1968年、静岡県生まれ。東北大学大学院薬学研究科(博士課程)修了、薬学博士。作家。1995年、『パラサイト・イヴ』で第二回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。一九九八年に『BRAIN VALLEY』で第19回日本SF大賞、2021年に『NHK 100分de名著 アーサー・C・クラークスペシャル これは「空想」ではない』で第52回星雲賞ノンフィクション部門を受賞。他の著書に『パンデミックとたたかう(共著)』などがある。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『運河の家 人殺し』をご覧ください。
#ルリユール叢書 #ルリユール #幻戯書房 #運河の家 #人殺し #シムノン #ジョルジュシムノン #森井良 #瀬名秀明 #ベルギー文学 #硬い小説 #ロマンデュール #イヤミス #メグレ警視
