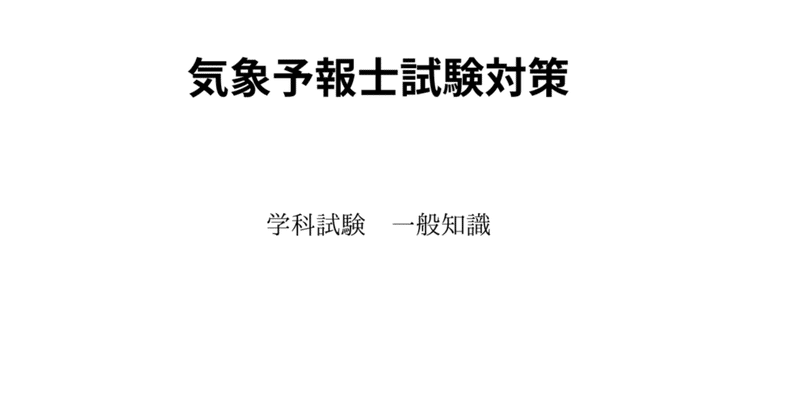
気象予報士試験対策 過去問 学科 一般知識
本日も、大気の鉛直方向に関する過去問を見ていきましょう。
今のところ計算問題がなく暗記勝負!のところから抑えていきましょう。
平成30年度第1回(第50回)問1
正誤問題でした。
(1)対流圏では、気温の平均的な鉛直分布は対流による熱輸送によりほぼ決まっている。❌
👉対流圏の平均的な鉛直分布ですが、上空に向かって気温が低くなります。この時の高度上昇に伴う気温減率は約6.5℃/kmです。この数字も復習です。覚えておきましょう。
そして対流圏では『太陽放射による加熱に地球放射による冷却』や『対流による熱輸送』が気温の変化に関与しているので、問題文の「対流による熱輸送によりほぼ決まっている」のところが誤りとなります。
(2)成層圏では、酸素分子が紫外線を吸収し光解離により酸素原子となり、この酸素原子が別の酸素分子と結合してオゾンが生成されている。⭕️
👉成層圏でのオゾンの生成過程が記述されています。このまま覚えましょう。
(類題)次の文は正しいですか?
『成層圏では強力な紫外線により酸素分子が光電離を起こして別の酸素分子と結合してオゾン層が生成されている。』
さあ、どうでしたか?「光電離」が間違いです。
【こんなに違う光解離と光電離】
漢字で書くと1字違いですが、光解離と光電離では次の点で異なります。
(場所の違い)
光解離・・・成層圏で発生
光電離・・・熱圏で発生
(現象の違い)
光解離・・・酸素分子が紫外線によって分子結合が離されて酸素原子ができる
光電離・・・紫外線によって原子が電子を放出してイオン化する
(3)中間圏では、気温は高度とともに低下し、中間圏界面で極小となる。⭕️
👉正しい記述です。中間圏と対流圏では気温は高度とともに低下します。
(4)熱圏では、窒素や酸素などの原子や分子が波長の短い紫外線やX線等を吸収し、光電離により電子を放出してイオン化している。⭕️
👉上記(2)の解説で記述したとおり、熱圏では「光電離」が発生しています。
無線通信のための「電離層」や、オーロラ現象など復習しておきましょう。
平成30年度第2回(第51回)問1
経度方向に年平均した対流圏内の気温と風の緯度・高度分布について述べた文の
太文字部分に関する正誤問題でした。
(問題文)
気温は、熱帯地方の対流圏下層で最も高く、①熱帯地方の対流圏界面付近で最も低い。
一方、対流圏内の同じ高度における気温は、対流圏界面付近を除き極側ほど低く、
その南北傾度の大きさは、②中緯度地方で大きい。
このことと温度風の関係より、中緯度地方の西風の風速は高度とともに③減少する。
①熱帯地方・・・正しい記述です。
②中緯度地方・・正しい記述です。
③減少する・・・間違いです。正しくは「増加する」です。
👉①対流圏下層の気温は熱帯地方が一番高くなり、高度上昇に伴い気温は低下します。
そして、対流圏界面付近では赤道付近上空では210K(−65℃)と低い。両極上空の対流圏界面付近の気温が230K(−45℃)ですから、20℃近くも赤道上空の方が寒いということになります。正しい知識を持っていれば間違えないのですが、なんとなく雰囲気で解答すると間違えてしまいます。
ハドレー循環により上昇した空気塊が断熱膨張によって温度が下がります。赤道上空の方が寒い!という意外性は頻出項目なので、ここでしっかり得点しましょう。
②南北温度傾度が大きいのは中緯度帯です。赤道付近ではほぼ水平です。両極付近の温度傾度は小さい傾きです。反面中緯度は大きくなっています。ここは覚えるしかありません。中緯度帯は南北の気温傾度が大きい傾圧大気であるため温帯低気圧が発生するので、これと関連付けて覚えておくのも良いと思います。
③中緯度の西風の風速(寒帯前線ジェット気流のこと)は高度とともに大きくなります。
平成28年度第1回(第46回)問1
正誤問題。
(1)成層圏では高度が高いほどオゾンの数密度が大きく、気温が極大となる成層圏界面付近でオゾンの数密度が最大になる。❌
👉オゾンの数密度が一番大きいところは高度約25km付近のオゾン層があるところ。気温が極大となる成層圏界面ではオゾンの数密度はそこまで大きくないが、成層圏界面付近の上空で紫外線を吸収するために気温が極大となっています。
(2)高度約100km以上では紫外線による窒素や酸素の電離により電離層が形成されるが、夜間には日射がないために電離層は消滅する。
👉これには引っかかりました。低層の一部の電離層は夜間に消滅することがあります。日中は下層の電離層で電波が減衰するために遠くまで飛んでいきませんが、夜間になると低層の電離層が消滅または薄くなるために電波が減衰せずに遠くまで飛んでいきます。ラジオ放送(AM波)が夜間になると遠くの放送局のものが受信できるのはこの原理です。また、上層の電離層は消滅しません。
(3)熱圏では太陽放射が安定しているため、年平均気温は、10年程度の期間内では年毎にほぼ一定である。
👉熱圏は太陽活動の影響を最も受け、日変化も大きい。太陽フレアの影響も受けます。問題文で誤りの場所は上記に明記しているところです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
