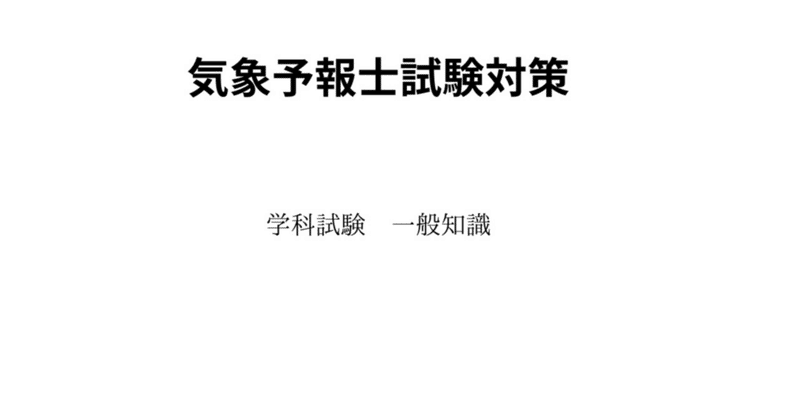
気象予報士試験 学科 一般知識 熱力学
高等学校の物理の教科書をお持ちの方は、そちらをご参照ください。
理科系の知識が必要な部門です。
PV=nRT でお馴染みの式。n:物質量(mol)
密度ρは空気の重さnを体積Vで割ったものなので、上式は
P=ρRTと書けます。 P:圧力、ρ:密度、R:気体定数、T:絶対温度
↑この式を使って解答する問題が出題されています。
🔵ボイルの法則
PV=nRTを見てみましょう。気体の温度を一定として、
閉じた空間の空気塊に外から力を加えて2倍の圧力にすると、体積は2分の1になります。
注射器に閉じ込めた空気をシリンダーで押すイメージです。
上式の右辺は温度一定であるので定数となりますから、体積は加えた圧力に反比例します。圧力と体積の関係をグラフにすると双曲線になります。
これがボイルの法則です。
🔵シャルルの法則
圧力を一定に保った場合に閉じ込められた気体の温度を上げていくと体積が大きくなる(比例する)という法則です。
萎んだゴム風船を日当たりの良いところに出しておくと風船が大きくなる現象はこのシャルルの法則で説明できます。
ボイルの法則もシャルルの法則も日常目にする光景と関連付けて覚えれば忘れないでしょう。そして、気体定数は気象予報士試験では、これを用いて計算しなければならない場合には、条件として与えられるので覚えておく必要はありません。
🟢静水圧平衡 静力学平衡
「一般気象学」では静水圧平衡という見出しでした。どちらでも良いようです。
空気塊自身の重さによる下向きの重力と、その空気塊の下側にある空気からの上への力が釣り合っている状態を静力学平衡と言います。
Δp = −ρgΔz
上式を用いる必要がある問題が過去問において出題されています。
また、この静力学平衡による計算で、地上天気図の等圧線が描かれています。
学科専門科目等で学習しますが、各地で観測した気圧は海面上での気圧になるように補正されています。
また、9時と21時に観測しているラジオゾンデによる高層気象観測では、この静力学平衡の式を用いて高度を計算しています。
静力学平衡の式による計算の結果、エマグラムなどの資料が作成されて、現象の予測ができるようになっています。エマグラムも後日掲載します。
ワイオミング大学のウェブサイトには世界各地の高層気象データが公開されています。https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
🟢熱力学第一法則
熱力学には、①第一法則、②第二法則、③第三法則 があります。
気象学の教科書では熱力学第一法則が紹介されています。
熱力学第一法則はエネルギー保存法則を熱力学に適用させたものです。
Q = ΔU + W です。
Q:加えた熱量 ΔU:内部エネルギーの増加量 W:仕事量
(Ref.)熱力学第二法則 熱を低温から高温へ移すことはできません。熱を全ての力学的な仕事に変換することはできません。不可逆断熱変化ではエントロピーは増大する。
(Ref.)熱力学第三法則 絶対温度が0ケルビンの極限では物質のエントロピーも0になるという法則。
熱力学第一法則により、空気塊がΔT℃上昇した時の内部エネルギーの増加量は
ΔU=Cv✖️ΔT と表すことができます。
この時の係数であるCvは定積比熱と呼ばれるものです。「一般気象学」では定容比熱と書かれていますが、同じものです。
定圧比熱を Cp とすると、
(定圧比熱)ー(定積比熱)=(気体定数)という式があります。
Cp − Cv = R
この式も合わせて覚えておくと良いです。過去問で問われたことがあります。
次回は乾燥断熱減率についてのお話です。
乾燥空気が100m上昇すると気温が1度下がるということを説明したものです。
以前、対流圏では100m上昇すると約0.6℃気温が下がると書いていました。これは乾燥空気と湿潤空気で減率が異なるためで、平均的な値です。それでは、また。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
