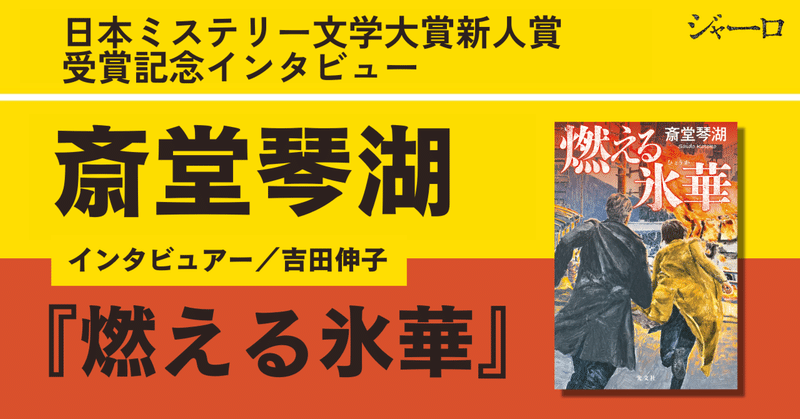
【日本ミステリー文学大賞新人賞受賞記念インタビュー】斎堂琴湖 『燃える氷華』|聞き手:吉田伸子
「受賞を知った友人たちから、いくつになってもなんでもできるんだね、と言ってもらえました」
第27回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞したのは、『燃える氷華』(応募時のタイトルは「警察官の君へ」)。作者の斎堂琴湖さんは、受賞の言葉でこんなふうに述べている。「投稿作はいつも受賞には一歩も二歩も及ばず。正直、今まで書いた作品だけで一大コレクションができそうです」。
私自身、日本ミステリー文学大賞新人賞の予選委員として、斎堂さんのその〝コレクション〟の軌跡を見てきたこともあり、今回のインタビューでは、そのあたりのお話もうかがってみた。
受賞インタビュー
「ずっと作家になりたかった」
――受賞、おめでとうございます。
斎堂 ありがとうございます。
――長い道のりでした。
斎堂 本当ですね(笑)。実は私、30歳くらいの時にも某新人賞に応募していて、それが最終候補に残ったんです。もう、天にも昇る心地でしたね。このまま私は有名作家になるぞ! くらいの勢いだったのですが、その後は候補に残ることがなくなってしまって、あれれ? と(笑)。もう20年以上も前のことです。
――それが初めての応募作ですか。
斎堂 最終候補に残った初めての作品でした。公募への応募は、大学生の頃からやっていたんです。高校生の頃、学生コンクールのようなものに応募して、賞をいただいたこともありました。
――その頃から作家志望だった。
斎堂 そうですね。受賞の言葉にも書いたのですが、「なれるといいな」が「なりたい」、「なる」と移りかわっていった感じでしょうか。
――作家になりたいという思いはあっても、その思いを持続するのは大変なことだと思いますが、モチベーションはどのように保たれていたのでしょうか。
斎堂 40代の頃は応募しても最終候補に残らないし、その当時は5~6年で二作くらいしか書かなかった時期もあったんです。でも、私、周りに作家になりたいってずっと言ってるし、これで作家にならなかったら、ちょっと恰好がつかないぞ、と思ったりもして(笑)。ちょうどその頃、ネットに小説をアップするのが流行り始めていたこともあり、そういうサイトを運営されている方に、(自分の作品を)載せてください! みたいなメールを出して、作品を送ったんです。そしたら、「物語がちゃんと終わっているし、なんか凄い!」という反応をいただけたんです。そこで、少しだけ自分に自信がついたというか、やっぱりまた書いてみようかな、と。
――自ら道を開いたのですね。
斎堂 そこからモチベーションがちょっと上がり、Kindleのダイレクト・パブリッシングを出したりしました。そうしたら、その界隈の方たちから評価をいただけたりしたこともあり、今までの(執筆の)やり方をちょっと変えてみるのもいいのかなと思い、小説講座に通ってみたり。そんな感じで、自分でどんどんモチベーションを上げていく、みたいなやり方にしました。
――小説講座はどちらに。
斎堂 (作家の)鈴木輝一郎先生の講座です。その講座を受講して、新人賞に応募しました。その時からお世話になっています。その後、コロナ禍でオンラインになった山形の小説講座にも参加させていただいていました。(小説講座を主催している)池上(冬ふゆき)先生との面識はなくて、作品を読んでいただいたこともなく、私が一方的にオンライン講座を受講している感じです。輝一郎先生には、色々と見ていただいて、ダメ出しをいただいたりしていました。
――応募し続けるなか、気持ちが挫けそうになったことは。
斎堂 応募する時は、その作品がベストだと思って出すのですが、なかなか届かない。私は、大概のことは落ち込んでも三日くらいで立ち直るタイプなんですが、それでも、(落ちるのは)辛いです。また一から始めなければいけないので。
――ふりだしに戻る、みたいな感じですよね。
斎堂 そうですね。だから、私はどうして書き続けて応募できていたのだろう、と自分でも思います。ただ言えるのは、私は書くことが趣味というか、好きなんですね。自分の生活と書くことが直結している、というか。たとえば、友人から何処かに行こうよ、と誘われたら、なんかネタになるかも、とぱっと思ってしまう。だから、行く、行く! と(笑)。書くことが生活の中に入っている感じです。朝起きて、書いて、ということが日々のリズムになってしまっている。
――朝に執筆を。
斎堂 はい。私、早起きなんですよ。朝の方が頭がすっきりしているので書きやすいんです。とはいえ、5時に起きたからといって、5時から書き始めるわけではなくて、30分くらいは朝ごはんを食べたり、ネットをチェックしたり。今は在宅勤務が主なので、そこから7時くらいまで書いて、その後、気分転換にちょっとゲームをしてから始業、というスタイルです。
――完全な朝型なんですね。
斎堂 そうなんです。だから、夜は早く寝たいタイプです(笑)。
――始業ということは、会社にお勤めされているんですね。
斎堂 マーケティングの会社に勤めています。私、30代半ばまでは、色んな会社を転々としていまして。本当に小さな出版社さんや、出版とは全く関係のない会社に勤めたり、派遣でちょっと働いたり。そういう感じでずっとやっていました。今の会社は二十年ちょっとかな。
「やっぱりミステリーが好き」
――斎堂さんの応募作は、二次選考委員の間で、地の文のドラマには定評がありました。だから逆に、敢えてミステリーにしなくても、という意見もあがっていたのですが、ミステリーにこだわられた理由は。
斎堂 やっぱりミステリーが好きなんだと思います。自分が読む本はミステリーが多かったですし。ただ、いわゆるミステリー作家の方がよくおっしゃるような、小学生の頃から江戸川乱歩を読んでいました、というようなレベルではなくて。小学生の頃は、乱歩なんて怖くて読めなかったです(笑)。
――ミステリーに興味を持たれたのは。
斎堂 私の中学・高校時代が、ちょうど角川映画が流行り出した頃だったんです。それで、映画の原作である赤川次郎先生の作品を読み始めました。あと、新井素子先生が好きでハマりました。高校時代はSFとかラノベ、栗本薫先生や田中芳樹先生がブームになっていて、お二人の作品も読んでいました。高校時代は文芸部にいたので、周りもその辺りの作品を読んだり、自分たちも書いたりしていました。
――その頃から(物語を)書きたいという思いがあったのですね。
斎堂 一番最初に書いたのは、中学受験の頃だと思います。新井素子先生の影響を受けて、ちょっとSF要素のあるものを書きました。
――文芸部ではどんな作品を。
斎堂 文芸部にいたメンバーは、みんな違う(ジャンルの)ものを書いていたので、そのなかで、どうやって(物語に)自分の個性を出していくかの競争みたいになっていました。当時のメンバーの中には漫画家になったり、某大手印刷会社に就職したりとか、そういう方面に進んだ友人もいます。
――文芸部では同人誌を作られていたのですか。
斎堂 そうです、そうです。生徒会室の印刷機を使いすぎて、怒られたりしました(笑)。
――高校卒業後の進路は。
斎堂 大学に進学しました。文芸学科だったんです。その頃は純文学を集中して読みました。夏目漱石が好きでしたね。
――卒論も漱石で書かれたのですか。
斎堂 卒論というか、うちの学科は卒業制作といって、自分で小説を書くんです。明治・大正期の文学が好きだったので、明治の頃を舞台にしたものを書いたことは覚えているのですが、内容はもはやうろ覚えです。
――卒業後、社会人に。
斎堂 はい。一旦は就職したんです。ただ、直後にバブルがはじけていろいろあり、会社を辞めました。私は割と浮かれている人間なので、ま、いっか、と(笑)。ミステリーに本格的にハマったのは、就職してすぐくらいですね。当時読んだミステリーがきっかけです。
――どなたの作品だったのですか。
斎堂 山崎洋子先生の『香港迷宮行』です。夏のフェアの一冊だったと記憶しています。書店でたまたま手に取ったんですが、読み始めたら、すごく面白くて、夢中で読みました。
――斎堂さんの応募作は、映像的だという声も二次選考会でよくあがっていました。2021年の応募作である「荊姫は電気兎の夢を見る」のペットロボットの行進とか、今でも印象に残っています。
斎堂 私には、物語の中に印象的なシーンを入れたいという思いがすごくあるんですね。見たこともないような、と言ったら大げさすぎるんですが、何かポイントになるような〝絵〟が欲しいな、ということは割と意識して書いています。そういう〝絵〟があると、物語が動きやすくなるイメージがあるんです。
――今回の受賞作ですが、過去の応募作と比べて、書き上げた時の手応えとかは違っていたのでしょうか。
斎堂 それが、手応えは全然なかったんです(笑)。次に応募する作品を書き始めていたくらいで。
――えっ?(笑)
斎堂 そうなんです。今回もダメだろうな、と(笑)。
斎堂さんはこう話すものの、受賞作は各選考委員から高い評価を得ることに。「ミステリとして構成をひねったものに見せようという気概」「何より魅力を感じたのは、この著者だからこそ書ける危うさや歪さのような部分」(辻村深月氏)、「主人公が乗り越えなければならない過去を背負っていること、物語に牽引力があるところがよかった」(湊かなえ氏)、「テンポのいい作品で、ドラマチックな要素もあり、個人的に好きな作品だった」(薬丸岳氏)。
受賞作『燃える氷華』には、3人の警察官が登場する。とある事件で息子を失い、刑事の仕事から離れ、今は大宮西署の交通課に勤務する隼人(はやと)、隼人の妻で大宮署の刑事である未希(みき)、埼玉県警の刑事である宇月(うづき)。隼人と未希は別居中であり、警察学校で隼人と同期だった宇月は、なにかにつけて未希を口説いているものの、その度に未希は躱している。
序盤、大宮駅前で車が爆発する場面から、物語は一気にトップギアに入る。爆発で粉々になった遺体は、十七年前に亡くなった、隼人と未希の息子・遥希(はるき)の葬儀を執り行った男のものだったのだ――
――『燃える氷華』は、どういうきっかけで書かれたのですか。
斎堂 私、今日のインタビューの準備にと、当時の資料とか自分のメモを見返してみたんですけど、なんか、「もえる話を書く」、みたいなことをメモしていたんです。
――もえる……。
斎堂 ものが燃えるの燃えると、萌え、の両方ですね。でも、実際に書いた内容は全然違っていました(笑)。
――物語の序盤、車が派手に燃えます。
斎堂 そうなんです、そこくらい(笑)。前回の締切が5月に終わって、それから一ヶ月後くらいに、翌年の5月に向けてまた新作を書き始める、というのが毎年のパターンだったのですが、父が6月に亡くなったこともあり、忙しかったんですね。父のお葬式を経験したこともあり、なにかお葬式にかかわる話にしよう、と。それで葬儀屋さんを出しました。
――あぁ、なるほど。
斎堂 同時期に引っ越しもしたのですが、引っ越した先の近所に、廃墟があったんです。それで廃墟も出しました。あと、最近、自分自身が50代になって、足腰の衰えを実感していたこともあって、同世代で足腰が弱っている刑事、って面白いかも、と。でも、実際に書いてみたら、未希は全然足腰が弱いキャラではなかった(笑)。
――弱いどころか、むしろ強い(笑)。
斎堂 そうなんです。ただ、50代の女性刑事、というのはあまりいないキャラかな、と。だったら、50代、女性、ちょっとやつれた感じにしようか、とか。そのあたりから入っていきました。
――斎堂さんの作品は、埼玉を舞台にした作品が多いですよね。
斎堂 はい、埼玉県民なので(笑)。
――どこを切り取ってもネタバレになってしまいそうなので、詳しくはお聞きできないのですが、物語の最終盤に明かされる〝秘密〟は、最初から決められていたのですか?
斎堂 それが、よく覚えていないんです。
――なんと!(笑)
斎堂 なんと、なんとです(笑)。でも、あとから付け足したわけではないので、最初からここに着地する感じだったと思います。
――『燃える氷華』の隼人と未希は警察官夫婦ですが、7年前に応募された「レンタル探偵と雪の街」も警察官夫婦の物語でした。
斎堂 そうなんです。あちらは片方が警察官を辞めて探偵になっていましたが。あの時は、第一線の警察官が夫婦、という設定が面白いかな、と思っていて。ただ、その時に選評で「男女関係に寄りかかった作りで、作品がミニチュア化しているのが最大の難点」と篠田(節子)先生からご指摘いただいて、そこから動機そのものに重きを置くとか、そういうふうに話をもっていってみようと思うようになりました。私は(物語を)作りすぎる、という指摘をよくいただいていて、その辺りの塩梅が、自分ではまだよく分かっていない。そこはこれからもっと勉強していかなければいけない部分だと自覚しています。
――今回の受賞に関して、高校の文芸部や大学の友人の方たちからリアクションは。
斎堂 おめでとう、と祝ってくれました。あと、意外と多くの友人から言われたのが、このぐらい(斎堂さんは50代)の年になっても、まだなんでもできるんだね、と。会社にも同年代の人が多いですし。なので、三つくらい先には、いくつになってもなんでもできる、みたいなテーマで書きたいな、と思っています。
――それ、読みたいです!
斎堂 ありがとうございます。自分が書きたいものをこのまま書いていければいいな、と。私は「好き」が自分の原動力になっていると思っているんです。色々な「好き」があって、それが物語に繋がっていく感じですね。
何度も挑戦を繰り返し、ついに辿り着いた頂点。そんな斎堂さんだからこそ、(落選しても)「頑張り続ければ手が届く。だから諦めずに書くしかないんだと思います」という言葉が響く。「(落選しても)引きずらないのは大事。私が落ち慣れしちゃってた、ということもあるんですが」と笑う斎堂さん。次作がどんな作品になるのか、楽しみだ。
《ジャーロ 93号 掲載》
著者プロフィール
斎堂琴湖(さいどう・ことこ)
1968 年、埼玉県生まれ。所沢市在住。会社員。「警察官の君へ」で第27 回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞しデビュー。
『燃える氷華』あらすじ

大宮署の刑事・蝶野未希は17年前に息子の遥希を亡くした。雪の日に、廃工場の冷蔵庫に閉じこめられて死んだのだ。犯人は捕まっていない。
ある日、非番で大宮駅を訪れていた未希は、駅前で発生した車の爆破事件に遭遇。被害者の三上は、遥希の葬儀を執り行なった葬儀社の社員だった。さらに数日後、三上の同僚だった男もまた、大宮駅前で刺殺される。17年前の事件が、時を超えて動き出した――未希は捜査にのめり込むが、思いがけない出来事が彼女を襲う。
■ ■ ■
★文芸編集部noteがパワーアップしました!
「みなさまにもっともっと小説の楽しさを届けたい」一心で、日々情報をお届けしています!!「スキ」や拡散、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
