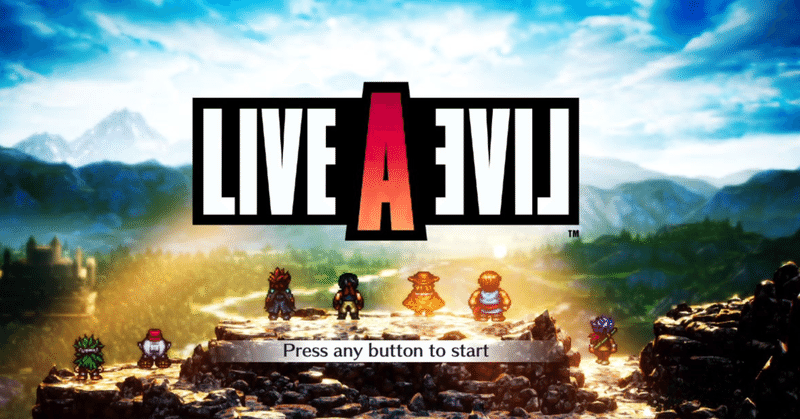
ライブアライブを遊んだカジュアルな感想
Nintendo Switchで発売された「ライブアライブ」を遊んだ。
1994年に発売されたオリジナルのSFC版は遊んだことない。当時の自分は、RPGというジャンルの存在すらもしらず、スーパーマリオコレクションやロックマンXなどアクションゲーム一筋だった。当然、ライブアライブというゲームの存在も知らなかった。後に、電撃ウラワザ王とかで見て、そういう名前のゲームが存在するってことくらいは知ってたけど、RPGであるということ以外はどんなゲームなのかすら全く知らなかった。
その後もライブアライブには触れることもなく生きてきて、今回急に買った。特に思い入れもない人間が書く、ネタバレとか考察とか何もない、カジュアルな感想。とりあえず30時間くらい遊んでクリアした程度で、隠し要素探すとか、やりこみ的なことは何もしていない。
まずは、原始編・西部編・功夫編・幕末編・現代編・近未来編・SF編の7つから遊ぶシナリオを選ぶ。時代の流れ順に選んでクリアしていこうと思ったけど、どういう順が正しいのかわからなかった。遊ぶ順番とか関係ないしむしろ各プレイヤに好きなように遊んで欲しいから、わざと順番がわかりにくくなるようにシナリオを作ったみたいな開発秘話あるんかな、って思った(適当に言ってます)。ロマサガが「ディステニィストーンが全部手に入れられるように作ってしまうと、遊び手は、手に入れることだけが目的のゲームになってしまうから、わざと全部は手に入らないようにした」的な。全然違うか。
◎原始編

主人公は「ウホウホ」。
RPGの主人公に直観で名をつける癖がある。原始編の特徴は、言葉が無いこと。とにかくキャラが動き回って、ストーリを表現していく。言葉にならない声を発してるんだけど、「ウホウホ!」みたいなこと言いまくってたから、「ウホウホ」っていう名は、結果的にめちゃくちゃ普通だったと思う。
で、個人的な思いとしては、このゲームを遊ぶのに最初に原始編を選んだのは良くなかったと思った。散々おもしろいゲームを遊んできた自分には、いまさら、この編をおもしろいと感じられる感性は無かった。おいおい、ライブアライブ大丈夫か~?この時は、そう思ってた。
各編、バトルBGMが違うんだけど、原始編のバトルBGMって、アウトランの「マジカルサウンドシャワー」にめちゃくちゃ似てると思った。
◎功夫編

主人公は「爺尿拳老師」。
功夫編はシナリオが感動ものだったので、こんな名にしたことを後悔した。
功夫なだけあって、バトルが多めだった。このあたりでやばいことに気づいてしまったんだけど、バトルがおもしろくない・・。あまりにも楽すぎて、負けるわけない。ただ一番強い技を選んでいれば終わり。数で攻められても全部同じ。SFC版のことはわからないけど、switch版は遊びやすいように難易度下げたりしているのだろうか。
おもしろすぎたのは、ボスが普通の人間なのに、あまりにもでかいこと。主人公より10倍以上でかい。こういうのを見ると、見たこともないSFC版の画面が、なんとなくどんな感じだったのかが想像できる。でかいことはおもしろい。
シナリオも感動的だし、かっこよかった。まさかこんな展開になるとは。正直、分岐方法もすぐに察して、やりなおしたかったけど、運命受け入れてそのまま進めたのも感動につながったと思う。変な名前にしてしまった運命だけは受け入れたくなかった。
◎幕末編

主人公は「ストライダー忍(にん)」。
隠密行動をしてバトルを避けつつ、迷路のような城を進み、ボスを目指す。自分の場合、最初の隠密行動を失敗してバトルになってしまったんだけど、特に敵が強いわけでもなかった。では、なぜ隠密行動が必要?バトルが多すぎるから?
シナリオ選択のときに「なるか100人斬り」って書いてあったので、全部倒すと100になるんだろうということはわかった。100人斬りを達成すると何かもらえるんだろうと思い、目指してみることに。これにより、隠密という要素はなくなり、敵を探して倒しまくるだけのゲームになった。
で、めちゃくちゃ歩き回って全員倒したと思ったんだけど、結果は81人斬り。隠し要素を見つけないといけないっぽい。解けなかった仕掛けもいくつかあった。心残りは、絶対に勝てないであろう強さの裏ボスみたいなやつを倒せなかったこと。
◎西部編

主人公は「アレーツ」。
正直、一番印象に残ってない。ボスとの一戦にすべてが賭かっている男らしい編。戦いに備えてした行動によって、ボス戦の難易度が変わるっぽい。やり方よくわかんなくて、結果的にボス戦の難易度あまり下がらなかったと思うんだけど、全くむずかしくなくてあっさりとクリアできてしまった。おそらく、西部編を全く楽しむことができずにクリアしてしまったと思う。
◎現代編

主人公は「勉強」。
勉強することが最強であることを証明するために戦うという設定を勝手に付け加えた。
ひたすら最強を求めて格闘をする。どこが現代なんだ!現代(1994年) = ストリートファイター2が流行っているから、みたいなことなのだろうか。
ひたすらバトルしかない、あっさりとした編だった。あっさりと流されがちだけど、よく考えると最悪なストーリだった。唯一この編だけバトルの仕様が他と違って、ただ強い技を使っているだけでは駄目だったので少しバトルを楽しめたんだけど、急なストーリ展開で地獄に突き落とされた感じ。ボスも相変わらずでかい。ここまででかいんだからさすがに最強でしょ、と思ったけど、ボス戦は相変わらず、同じ技ばかり使っていてクリアできてしまった。
格闘ゲが好きな自分には楽しめたかな。楽しんだっていうか、「最強」っていう言葉自体をただおもしろがったり、でかいものはおもしろい、みたいな低い次元で笑ってただけだと思う。この演出は、SFC版ではどうだったんだろう、みたいなことばかり考えてて、皆とおもしろがっているポイントが違う気がする・・
キャラ選択した時の「OK!」の言い方がテリーボガードみたいなのは何!
◎SF編

主人公は「おもしろいロボット」。
「爺尿拳老師」「ストライダー忍」につづき、つまんなすぎる名前に後悔した。
ひたすらストーリを追う、ほぼバトルが無い編。さらにBGMも無い。人間たちのストーリを遠くから静かに見守るだけ。気付いたら、プレイ中に何度も寝てた。おいおい、まじで何だこれ。退屈すぎる・・
・・って思ってたんだけど、途中から、SFっていうかホラーゲームになり、気が抜けなくなった。バトルが無いのも、BGMが無いのも、演出だった。船長のセリフには本当に寒気がした。
最後の最後には、どこに行っていいのかわからず、かなり長いこと彷徨ってしまった。まじでどうしたら良いのかわからなくて全部屋をしらみつぶしに巡っていて、ある部屋に入った時・・。あのBGMが聞こえてきて、うおおおおおおおおおおおおお、これかああああああああああああ!!って言った。
真相は、当時のSFとしてはありがちな気はする。日常の何気なかったものから異世界に突入する、自分の好きな展開。自分が超昔に書いた長編漫画にちょっと似たような展開があった。冒頭に何の意味もなさそうな日常的なコマがあって、それが最終的にキーになる的な。圧倒的に自分の感覚にあっていたからこういうのが好きなのだろう。
◎近未来編

主人公は「デョウニアーツ」。
どこが近未来なんだ。1994年の日本に超能力者がいるだけ?でしょ。近未来 = 超能力が使える っていう謎の思想自体に時代を感じる。1994年当時からしたら近未来である2022年に、このゲームがリメイク発売することになるなんて予想できなかったと思うし、その時代には暴走族やプロレスネタが伝わりにくくなっているとは思わなかったのでは。リメイク版の20代若手スタッフも「これってどういう意味ですか?」とか言いながら作ってたら面白い。
このゲームの全ストーリの中で、近未来編が一番おもしろかった。ベタな?馬鹿らしい?ヒーロもののストーリで、夜露死苦みたいな世界観やキャラに時代を感じるし、今見るとダサいんだけど、こういう時に流れるBGMが一番好き。バトルBGMといい、テーマ曲といい、聞いてると意味わからないけどなぜか涙が出る。ストーリも馬鹿らしいんだけど、終盤はめちゃくちゃ泣かせに来る。一番ノっている時に、主人公が「やめろおおおッ!!」って叫ぶところが一番つらかった。
ボス戦は、SFC版ではどんな感じだったんだろ、っていうのが一番気になった。後にSFC版の動画を見たら、さすがにちっちゃくて、おとなしくて、地味だと感じるけど、これはこれでおもしろいなあ。switch版の良いところは、ボス戦の時、下の方に超ちっちゃい敵3人がいるところ。
◎中世編

主人公は「ゼリター」。
7つの編をクリアすることでアンロックされた。よくありがちな王道のRPGで、逆に「何だこれ。なぜ今更こんなことをやらせる?」って思ったら、途中で無茶苦茶な展開に捻じ曲がって、ぶっ壊れた。これを見て、「誰が普通のRPGなんて作ってやるか!バーカ!」っていうスタッフの思いがはっきりした。
・・ここまでかな!このゲームのこれ以降の話は、とても大切に守られているものだと思う。平気でネタバレして良いものではない感じがする。
この編以降がこのゲームの集大成であり、おそらくこのゲームを人気ゲームに伸し上げた要因であると思う。しかし、正直なところ、個人的にはそこまで心に響かなかった。この編以降だけで、これまでのプレイ時間を超えるほど長い。それは、敵が固い、広いマップからノーヒントでキャラやダンジョンを見つけなければならない、パーティ入れ替えのために広いマップを行き来する、迷っている間もずっと敵とエンカウントする、といった、面倒な要素のせいで間延びしてしまっているせいだと感じた。なんか、ストーリがその疲れを超えてこなかったというか・・。シナリオお気に入りは、「近未来編」「SF編」「現代編」。
◎その他
・バトル
「バトル、もうちょっと何とかならなかったのか・・」と、どうしても感じてしまう。いままで、バトルがおもしろいRPGをたくさん遊んできて、それらと比べて、いまさら1994年のゲームに文句言ってるのもおかしいけど。
幕末編で、知らずに隠しボス的な奴に挑んでしまった時以外、ゲームオーバになっていない。それくらい難易度が低く、負けるわけがない。強い技をつかうことにデメリットがなさすぎるから、それだけしていれば良いというものになってしまっている。装備も適当で、数字がでかいのをただ付けてただけで一回も工夫しなかったけど、あっさり全クリできてしまった。
switch版は、今の子供でも遊びやすいように、SFC版よりも難易度を下げたみたいなことがあるのではないかと感じたんだけどどうなんだろう。
・MEGALOMANIA
各編のボス戦で流れる「MEGALOMANIA」という曲。ストーリ的にも全てがこの一曲にかかっている。しかしそのプレッシャをいとも簡単に押し返すほどの最強曲。ここまでこの曲を知らずに生きて来たのが不思議なくらい、語り継がれてもっと広く知られるべき名曲だと思った。いや、たぶん普通に語り継がれてたんだろうけど、自分がなぜか気付かなかった。聞いて1秒でサントラ買った。
switch版で新しくGIGALOMANIAという曲が増えたけど、MEGAの方が圧倒的にインパクトあった。
◎総評
きれいだったと思った。
今見ても、なかなかこんなゲーム見当たらないほど、尖っている設定だと思う。それでいて、あまりにもしっかりと作られているという印象。
同じく、尖っているロマサガとなんとなく比べてしまうんだけど、ロマサガはボコボコにぶっ壊れていて、おかしな世界にツッコんだり、バグらせて楽しむものなのに対して、ライブアライブはそういう感じではなく、変ではあるけど、しっかりと正統に楽しませてくれるクリーンな印象を受けた。自分が知らないだけで、SFC版はもっとボコボコだったのかもしれないけれど。
総評を一番勘で書いた。
#ゲーム #ライブアライブ #LIVE_A_LIVE
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
