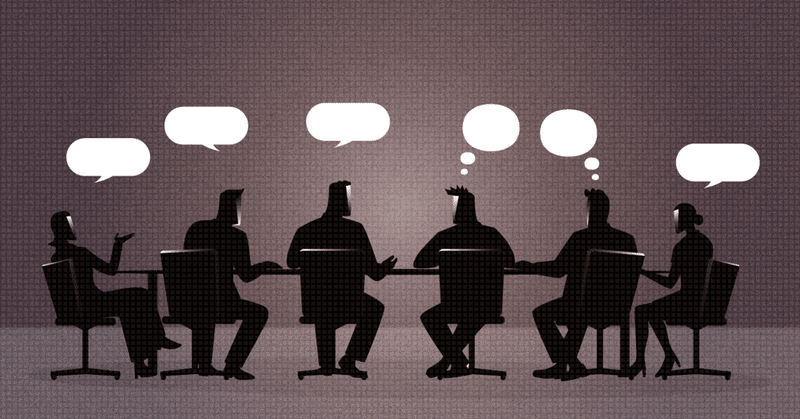
正しい会議の準備、進め方、クロージングについて
こんなこと聞いたことないでしょうか?
物事は準備が8割で実行は2割みたいな言葉です。
極端な言い方ではありますが、どんなことでも準備段階が大切ということを伝えているわけですが、これは古来からの人類の歩みの中で編み出された考え方だと思います。
孫氏の兵法の有名な一説ですが
故日、知彼知己者、百戦不始。
不知彼而知己、一勝一負。
不知彼不知己、毎戦必敗。
これも準備が大事ということを説いているようなものですね。
会議も準備が大切です。
よくあるあるなのは、何かあったらすぐMtgをする病です。
Mtgすると疲れますし、仕事をした気にもなるのでこの病は結構手強いです。
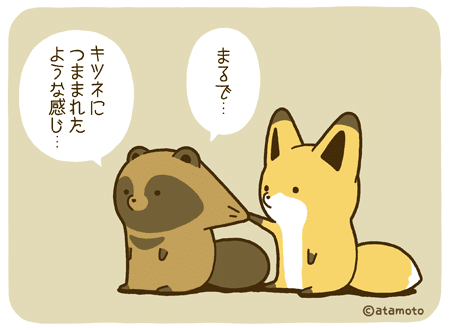
多くの場合、準備も無しに行われるMtgは時間を浪費し、終わった後も
「で、なにが解決したのだろう?」
「何か決まったっけ?」
「何も解決していないからまた来週Mtgすることになった…」
「何も解決してないけど、解決するためにまた別のMtgが設定された」
といったことありませんか?
しかも
・会議時間になっても人が揃わないので始められない
・長々と話して演説してしまう人
・端的に言えることを長々と話す人
・時間配分ができてないし、管理されていないので予定終了時間になっても本題にも入れていない

こういう無駄な会議を減らしたいと私は思います。
みんなで相談というのは仕事ごっことしては都合が良いですが、生産性が低すぎるとか無駄な会議だけどなぜか決まってるからやるというのが、日本の会社の生産性を下げている一因だと思っています。
そんなグダグダな会議にしないための方法について書きます。
原則はシンプルなのでまずは列挙しますね。
・アジェンダを事前に展開する(ゴールを明確にして開催する)
・最初にゴールの合意をする
・必須メンバーのみで行う
・決めたこと、宿題をデブブリーフィングで全員で確認して終わる
・議事録を必ず残して開示する。
・積極的に参加する
・思ったことはすかさず言う 不安やモヤモヤを溜めない
・職位や年次は一切気にせずコミュニケーションを!フリーズ禁止!
・時間厳守!
・言葉の定義を丁寧に
・資料送付は会議の2時間前まで
・時間配分を全員意識し時間内完結!
▼開始前
(1)アジェンダ(話し合う議題)は事前に決めて周知すること
議題を事前参加者へ連絡しておくことで、会議冒頭の説明時間などを省くことができます。
(2)会議を開始前に会議終了の条件(ゴール)を握ること
○○を決めたら終わりといった形で会議終了の条件についても予め、参加者に伝達しましょう!
そうするとことで、雑談でダラダラ終了時間まで会議をしてしまったり、会議終了時刻になっても何も決まっていないといったことが無くなります。
(3)無駄に出席者を増やさず、必須参加者のみで開くこと
情報共有で齟齬をなくすためとか、いろんな理由をつけて会議参加者を多くして、結果的には話してるのは数人みたいな会議はハッキリ言って無駄です。
共有できない組織で参加させたからといって情報伝達の問題が解決されたりはしません。
会議もコストが発生してますから参加者を無駄に増やすのはお金の無駄でもあります。
(4)資料送付は遅くとも会議の2時間前までにすること
資料が必要な会議もありますから、それを会議の中で読んでもらったり書いてあることを説明するのに時間を使うのは、もったいないです。
十分に会議参加者が読み込める時間的余裕をもったタイミングまでに、資料は展開しておきましょう。
(5)最終意思決定者とファシリテーター、タイムキーパーを決めておくこと
会議のオーナー(最終意思決定者)でもあり、最終的に意思決定するのは誰なのかを決めましょう。
また、オーナーとは別に司会進行をする役割と、時間を管理するタイムキーパー役も決めて実施しましょう。
▼会議中
(6)開始時間厳守、時間配分は全員意識し、終了時間厳守
よく会議時間になっても参加者が揃わないということがありますが、それは本来的には待たされている人たちのコストを無駄にしているわけですから、迷惑行為です。
厳に開始時間を守るように注意しましょう。
また、終了時間も同様です。
だいたい人間の集中力の限界は90分程度と言われてますから、2時間、3時間の会議などというものは生産性は期待できません。
(7)使う言葉の定義は明確にすること
○○ということを△△と表現する人がいたり、□□と表現する人がいるとなんの話をしているのか分からなくなってしまったり、誤解の元になるので使用する言葉の定義を明確にしましょう。
(8)議事録を書き、記録に残すこと
必ず議事録を取る人を決めて、記録を残しましょう。
一言一句すべて筆記するスタイルと、要点のみを簡潔にまとめるスタイルに大きくは分かれますが、とにかく議事録のない会議とかは最低です。
人の記憶は相当、曖昧で会議後の不確実性を増幅させ、誤解を助長して新たなトラブルに繋がりかねないからです。
(9)積極的に会議へ参加すること
参加者は積極的に会議へ参加し、傾聴し、考え、自らも発言をしましょう。
決して傍観者やただの聴衆になるのはNGです。
緊張感を持たせることでこれを実現する方法もあります。
例えば参加者にランダムに意見、発言を求めるといったテクニックです。
(10)会議後に後出し禁止なので思ったことは思ったことはすかさず言うこと(不安やモヤモヤを溜めない)
よくあるのが、会議の席で実は○○と思っていたという形で、事案が起きた時にさも予測していたかのように、後出ししてマウントしようとする人です。
その人は気持ち良いかもしれませんが、組織にとっては最悪です。
必ず思うことや懸念点があったら発言しましょう!
また、ファシリテーターは怪訝な顔をしている人を見つけたら発言を促しましょう。
(11)会議中は職位などは一切気にせずにコミュニケーションをすること
会議の目的にもよりますが、ブレインストーミングなど活発な意見交換、意見だし、議論を必要としている会議体においてはこれを原則としないと、効果は望めません。
(12)決めたこと、宿題をデブブリーフィングで全員で確認して終わること
決まったこと、宿題などについては会議の終わりに必ず参加者で確認をして終わりましょう。
こうすることで、会議後に実行されないといったことやそんなこと頼まれましたっけ?といったことを回避できます。
(13)次回が必要な場合は、会議終わりに日程と議題を決めて終わること
会議が一回では終わらずにさらにという場合には、会議の席上で最後に次回開催日も決めてしまいましょう。
持ち越すと日時の調整などがまた時間がかかったり、口実を作って忌避する人もいるからです。
▼会議後
(14)議事録を参加者へ配布すること
議事録は必ず参加者や、必要な人たちへ共有しましょう。
また、共有する前に筆記者の誤解がないかオーナーは目を通して、内容を担保しましょう。
さて、これらは私がビジネスパーソンとして生きてきた中でまとめたものになります。
もちろん失敗や反省からというものもあれば、上司や先輩から学んだことも含まれています。
みなさんも仕事で無為に苦労しないようにするために役立てば幸いです!
私については下記をご覧頂ければ幸いです。
今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。
記事を読んで頂きましてありがとうございます😃 サポート頂けましたら嬉しいです!頂いたサポートは新たな記事を書くための活動費に充て、より有益な情報発信のための糧にします🙇🏻♂️
