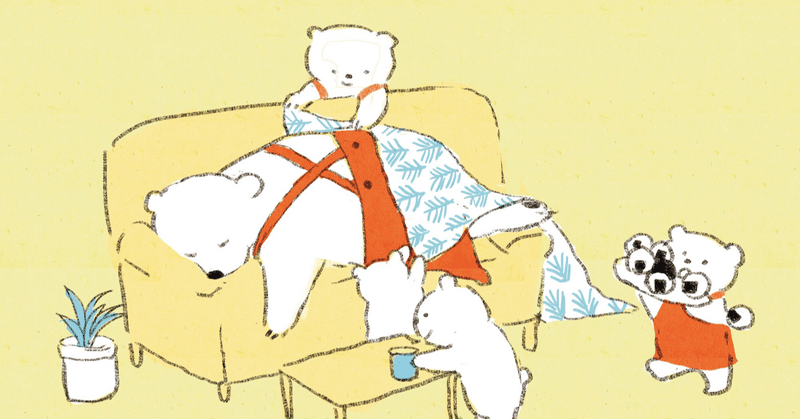
僕が小学五年生の時に母はガンで死んだ。最後のお見舞からその後の生活まで。
母親は僕が小学五年生のときにガンで死んだ。僕は母が死んだ前後の記憶はそれなりに覚えているのだが、それ以外の日常生活はほとんど覚えていない。
僕は、自分が小学四年生のときに、何組だったかも覚えていないし、友達と何をして遊んでいたかも覚えていない。もう、まったく覚えていない。
皆は自分が小学生の頃の事を覚えているものなのだろうか。
母は2年近く入院していた
当時はなんの病気かわからないが、ずいぶん長く入院するんだなぁ、よくなるのかなぁ、と思っていた。たまに退院してくると、少し家のことをしたり、友達とあったりしていた。この頃から、キリスト教の友達が出来たようで、クリスマス会にも連れて行かれたりした。うちは別にキリスト教徒ではない。母は何かにすがりたかったんだろう。
今では、変な宗教ではなくて、ちゃんとしたキリスト教でよかったと思う。僕はキリスト教を信じているわけではないが、聖書くらいは読んで理解しようと思い、ちゃんとした聖書を持っているのも、母との思い出を少しでも残しておきたいからだろう。
母の入院先に最後の御見舞に行ったときのことだけ、鮮明に覚えている
その日は夏休みにはいる直前の火曜だった。兄弟みんなでサンダーバードを見ていた。テレビ東京だ。いつもは6時前に帰ってくる父が、何故か今日は帰ってこない、電気もつけずにサンダーバードを見ていたのだが、全く楽しくない。そこに、おばが来て僕ら兄弟全員を車に乗せて病院に向かった。
すでに何十回も、毎週土曜日にお見舞いに来ていた病院だが、夜に行くのは初めてだった。いつもと違う時間、いつもと違う病院。もう何かとんでもないことになっていると感じざるを得なかった。その時初めて、母が死んでしまうかもしれないと感じたのだ。
「いい子にするからお母さんを助けてくれ」
病院の前で僕は本心からそう願った。真っ暗な病院を見上げて、声に出して願った。そのとき、いままでそこまで切迫した思いを持っていなかったのも同時に理解して、とても悲しくなった。僕は、もうだめだという時になり、ようやく初めて母のために祈ったのだ。なんて薄情なヤツなんだと、他人事のように感じていたのを覚えている。いつもと違う病院の姿に、ビビりながら母の病室に向かう。
その時の母は、酸素マスクをつけ、何本もの点滴をつけていた。白目を向いて苦しそうな呼吸を繰り返す。もう意識はなく、ただただ苦しそうだった。怖くて仕方なかった。
その後、僕は怖くて逃げてしまったのだろう。病院の待合室でテレビを見ていたのを覚えている。テレビではボクシングを中継していて、多くの入院患者がテレビの前に集まってボクシングを見ていた。僕のお母さんはあんなに苦しそうなのに、テレビの中では殴り合いのスポーツをしていた。僕はボクシングも見ていられなかったが、他にできることも、行けるところもなく、ずっとボクシングを見ていた。
夜の何時だったかは覚えていないが、兄弟全員が車で家に戻された。父親や祖母、おばは病院に残り、僕や兄弟は家で寝ることになった。すごく怖かったはずだが、眠れなかったわけではなく、いつの間にか寝ていたんだ。
そして翌朝、母が死んだと聞かされた。
多分おばから聞いたと思う。父は病院から帰ってこなかった。ぼーっとしている内に、いつの間にか母は棺桶に入って帰ってきて、その日のうちにお通夜、翌日の告別式。告別式は雨だった。
いつもは広々としているおばあちゃんちの庭に、たくさんの弔問客が並び、口々にお悔やみを述べて涙を流してくれていた。僕のクラスメイトも来てくれたし、近所の方々が色々と手伝ってくれた。
火葬場で火葬されて、骨だけになった母。母の遺骨は手分けして箸で骨壷に入れられていった。僕は最後の方に頭蓋骨と思われる骨を入れた。骨はボロボロでスカスカだった。
覚えているのはここまでだ。
そして、告別式の翌日に学校の遠足(臨海学校という1泊2日の遠足みたいな行事)に予定通り参加していた。僕はなんで休まなかったんだろう、休ませなかったんだろう。楽しめるはずがないだろう。周りも気を使うに違いない。
でも、僕は臨海学校に行き、なんと、おそらくそれなりに遊んで楽しんだのだと思う。ただ、今では全く記憶がない。僕が臨海学校で新潟の海に浮かんでいるとき、妹と弟は何をしていたんだろう。父は何をしていたんだろう。家では何が起きていたんだろう。今考えると、少し疎外感がある。あそこで家に残り、一緒に生活をしていたら、今とは少し違う家族関係になっていたかもしれないと思う。
臨海学校から帰ってきて、父と兄弟3人の生活が始まった。もともと母は入院していて自宅にいなかったので、死んだあとも生活はそれまでと全く変わらない。父が大体の家事をする、食事を用意する。でも、母が死んだあと、父の料理はしばらく適当で、あんまり美味しくなかったことはよく覚えている。兄弟全員が文句を言わず黙って食べていたが、おいしくなかった。
すでに母のことはほとんど覚えていない
覚えているのは最後のお見舞の日のことだけだ。母は兄弟全員を心から愛していたはずだし、死ぬ直前まで子育ての本を読んだりしていたようだ。でも、僕には母の記憶は殆ど無い。母の記憶はこの最後のお見舞いくらいしかない。だから、母のことを思い出すのは母の死に際を思い出すことと同じで、とても悲しくなる。
僕は今でも母のことを思い出すと泣きたくなる。それは悲しいのと、申し訳ないという気持ちだ。死に際の思い出しかなくて、母は死のイメージと直結してしまった。
母という単語は、僕の中では一番「死」にちかい言葉だ。それが悲しく、申し訳ないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
