「読んでいない本について堂々と語る方法」
「読んでいない本について堂々と語る方法」
ピエール・バイヤール
“本は読んでいなくても批評できる。いや、むしろ読んでいないほうがいいくらいだ。テクストの細部にひきずられて自分を見失うことなく、その書物の位置づけを大づかみに捉える力こそ、「教養」の正体なのだ。”
読書感想文でこの本を紹介する勇気をまず褒めて欲しい(笑)
言っていることはだいぶ極論ですが、
知識全体の中の一冊の書物の位置を把握するためには個々にとらわれる読み方はかえって危険であり、その本に対して適当な距離を保つことでかえって真の意味を掴め批評ができる、という本書の主張は大変重要だと思います。
でもでも!ちゃんと読まなくちゃ話にならないじゃないか!という人々に、著者はカウンター気味にこう問いかけます。
「完全な読書って何?」
精読すること?原文で読むこと?読み終わった後に一語一句忘れないこと?
、、そう、著者曰く、完全な読書というものは幻想であり、読書は我々自身の「内なる図書館」を充実させる遊戯であって、絶対無二の真理探求ではありません。
我々自身がそこに蓄積してきた書物の総体とも言える。この内なる図書館は、各人が新しいテクストの受容の仕方や解釈の仕方、読書観や現実と想像の境界を左右する無意識のフィルターです。共通の内なる書物があるということは愛し合う条件、信頼の礎となり、その反響が個人間の親和性となります。
ちょうど夏目漱石も文学問題F+f(フォーカスとフィーリング)にて同様の指摘をしています。
私たちが本について語り合う時は、それぞれがこの内なる図書館から持ち寄った全く別の本を比べているに過ぎないのです。これが唯一の同一物を指して議論していると錯覚するがため、それぞれがそれぞれの“真実“を確信して相手の読みの深さを貶し合う“競争”が生まれてしまうのです。自分自身に向けた真実は、教養人に見られたいという欲求から解放されて初めて向き合えるものです。そうして初めてお互いの内なる図書館を響かせ合うという”遊戯”としての批評が可能となります。
この変化してやまない批評空間においては本自身の絶対的な姿よりも、それがどう変化していくのかを何よりもまず掴まなくてはならない。テクストそのものより、テクスト間、テクストと人間の諸関係が重要となる、、、、というところで冒頭の極論(テクスト間の関係を掴めなくなるくらいならテクスト自体を読まないほうがいいくらいだ)に繋がって行きます。完全に読まなきゃ批評できない、という後ろめたさを取り除くために著者は本書を書いたようです。
メディアがマスから細分化されてきた一億総発信者社会の現在、こうした読書批評へのリテラシーはますます重要になっていくと感じながら、
一応俺はこの本を読み終えてから感想書いてるということを添えて結びとさせていただきます(笑)
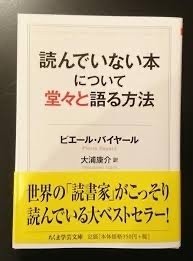
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
