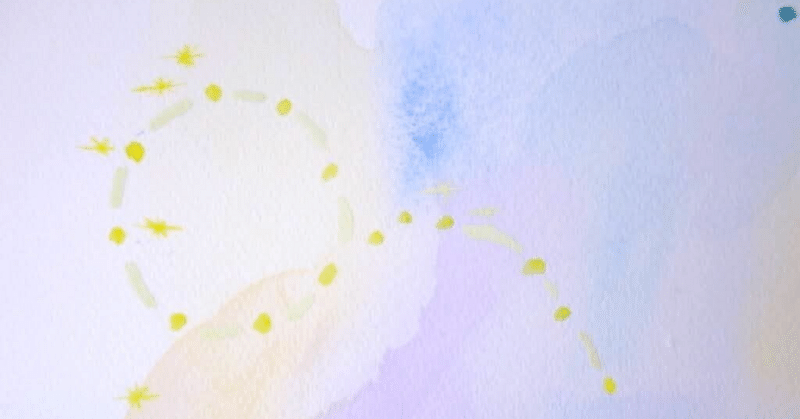
森田修史Quatet Jazz Live Over The Rainbow IIDA森田修史(ts) 魚返明未(p) 安東昇(b) 小松伸之(ds)
家に戻った私は、迫りくる睡眠の発作と戦った。いつもの表現衝動、内面との対話が形を成してこない。けっきょくその夜はやむをえず眠りをとったのだが、いま一夜以上を経て、かすかな睡眠欲求は消えない。実際、このメンバーの名前たちと、素晴らしいライブだったという一行があれば、私のモノ書きとしての仕事は終わったようなものなのだが、それは私の矜持が許さない。この「現実」から逃れようとするものに違いない睡眠への強力な誘いは何だったのだろうか。
いつものように、リハーサルなどはじまるはずのない時間にハコに到着した私の耳に達者なバッハの演奏が入った。あとで確認したら、平均律クラヴィーア曲集の第一巻A-dur19番、そしてC-dur21番だったそうだ。魚返の手によって、極めてしっかりと弾けていたバッハだったが、どこか古典をはみ出したものにも聴こえた。形式が、とかではない。そこにソウルがあった。やがてiPadを使った各種テンポによる細かなスケール練習に移っていったのだが、「機械的」な練習はまったくなかった。魚返がアップにバッハを使うという話は聞いていたが、このような「有機的」というか、有意味な練習とは思っていなかった私は、アップの邪魔をしないようにハコの外へ出て、聴き入っていた。このピアニストは想像していた以上にただものではない。私は早くも涙ぐんでいたのだから。音楽性もスタイルも何もかもまったく異なるけれど、たとえばチックが世に出始めたときはこんな風だったのではないか、そんなことを想像した。そうして魚返のスタイルは確立されている。
やがてバンドのメンバーが全員揃う。小松に「こんなのが(フレーズ)本番で出てきたら大泣きしちゃうよ」と告げると、「これ、何でも出てきますよ。」あれ、初めてですか?とかえって怪訝な顔をされたものだ。なんといってもピアニスティックに完璧なのだ。
リハーサルは何曲かの森田のオリジナルの中にスタンダードのバラードがあった。すっきりと声部が整っているがゆえの一種の「何か」を思わせるシンプルなさびしさ。強烈な郷愁を伴うのだが、それが何なのかはいまだに言葉にできない。この不思議な懐かしさを言葉にできたら、私はジャズライターを超えられるかもしれない。
いつものような細かなレビューをかけるメモは持っている。だが私は、曲名をかけない曲があることだけでなく、いつものスタイルを捨てようと思う。ソロやバース交換のコーラス数も数えた。だが、そういったテクニカルなレビューに私(たち)の感動はない。私が森田節と呼ぶバラードでの森田のフェイク、安東のしっかりしたバックアップだけにとどまらない、ソロだけに出たものでない、黒い歌心、小松のシビアなリズム感だけでない歌心、魚返の精密極まりないタッチと多彩な歌。これは会場にいた誰もが感じ取れたものだし、会場に来られなかった人々には、ぜひ会場へとしか言いようがない。
そうして言葉使いである私は、感じてしまった音楽と、自分の言葉のギャップに、睡眠発作に襲われることになったのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
