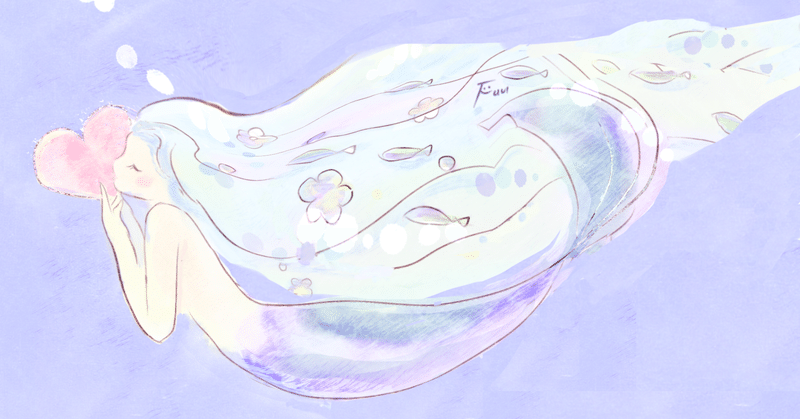
Queen of mermaid
わたしの名前はうさくま。
わたしたちの村の真ん中には、大きな樹がある。
その樹は果てしなく高く、一番上まで登ったものはひとりもいない。
樹のてっぺんは天につながっているとか、精霊が住んでいるとか、色々噂はあるけれど、真実は誰も知らない。
そして、その樹の下には、深い青をたたえる湖があり、記憶の湖と呼ばれている。
いろいろなものを映す湖は、宇宙なのか太古の昔なのか人の心理なのかわからないけれど、どこにでもつながれるらしい。
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
あらためまして。
自己紹介をさせていただきますね。
わたしうさくまは、その村で ” Only One ” というお店を営んでいる。
地球で使うぬいぐるみというか着ぐるみのような「NINGEN★SUITS」を作るのがわたしのお仕事で、” Only One ” は村で唯一のスーツ屋さんだ。
わたしの仕事について説明する前に、まずは「NINGEN★SUITS」について説明しなくちゃね。
「NINGEN★SUITS」は、地球語でいういわゆる ” 身体 ” のこと。
最近、天使や宇宙人の間で、地球を旅するのが流行しているんだけど、その旅を濃厚に五感で味わうには、「NINGEN★SUITS」は欠かせない装備だ。
「NINGEN★SUITS」は、完全オーダーメイドで、一つとして同じものはないから、わたしたちのお店は毎日大忙しっていうわけです。
この村は、” Earth School Project ” と題されたいわば「地球旅行」をするための村だ。
地球で過ごすための全てが揃う。
だから、村で生活するみんなは「NINGEN★SUITS」をはじめとした「地球旅行」に関わる仕事に携わっていて、” Only One ” 以外にも色々なお店がある。
村にやってきたお客さまが最初にまず向かうのは、” No Design No Life ” という人生の設計書を作るお店だ。
そこでは、人生のテーマ、名前、行きたい国や時代、性別、寿命、家族、職業、年齢ごとのイベントや出会いたい人を決める。
ここのやぎじいはこの道一筋のベテランで、ボツになった設計書はやぎじいのおやつになるらしい。
設計書ができたら、” Past & Future is up to you ” という記憶銀行へ向かう。
そこでは、今世に紐付ける過去世のアーカイブNo.を確認したり、今世で持ち帰る記憶の預け先アドレスを設定したり、家族になる人の登録No.のリストをもらったりして、設計書に必要な情報を追記する。
ここでは、バクさんとヒツジさんが働いているのだけれど、ふたりとも一日の半分以上寝ているから、仕事の進みがたいへんに遅い。
それに、膨大な情報の中から必要なものを探し出すにはそれなりに時間がかかるので、待つのを覚悟しなくてはならない。
そんなこんなでやっとのことで設計書はできあがる。
それを持って、お客さまが ” Only One ”、つまりうさくまの店にスーツを作りにやってくるというわけだ。
「NINGEN★SUITS」を作る間、お客さまは " Honey Moon Hotel " に滞在して、旅の準備をする。月は記憶との関わりが強いんだって、支配人のKAGUYAちゃんから聞いたことがある。
設計書に載せるような基本デザイン以外にも、こだわりを詰め込みたい存在のためのお店もある。
"SOTODURA" はスーツの外側をデザインする。
肌や目の色にはじまり、顔や髪型、体型、体質に至るまですべてを自分で選ぶことができる。国や時代によって制限が出るから、お客さまに的確なアドバイスをするときにプロとしてのスキルが問われるのよって烏のマリアさんが威張ってた。
他にも、記録編集屋さんの ” Dream Quilt ” や、環流された NINGEN★SUITS を湖から回収して記録・修復を行う ” God bless you ! ” 、スーツを洗濯する ” The-boo-boon ” なんかがある。
わたしは、いつもはお店の中で作業してばかりで、お客様に会うことはない。ほとんど表に出てくることすらない。
けれど、今日は少し違う。
特別な「NINGEN★SUITS」が返ってくる日なのだ。
見に行かなくてはいけない。
スーツが耐久年数を迎えてここにかえってくることを、” 環流 ” と呼ぶ。
スーツは湖に還ってくる。
お店に配達される村の新聞には、環流欄というのがあり、翌日環流予定のスーツが記載されているので、それを日々確認するのはわたしたちの日課だ。
昨日の新聞の環流欄に人魚姫の 氷魚ちゃんが載った。
彼女の記事が載るのは、たしか11回目だと思う。
氷魚ちゃんはわたしの初めての友だちだけれど、特別な理由はそこじゃない。
わたしが初めて作ったNINGEN★SUITS、それが氷魚ちゃんの初めてのスーツだったからだ。
彼女と出会った千年近く前のことが鮮明にわたしの脳裏に蘇る。
人魚のお姫さまがニンゲンとして地球に降りるつもりらしい。
そんな衝撃的なニュースで、村は揺れていた。
お姫さまはまだ幼く、地球という過酷な星で生きていけるような力がない。けれど、どうしてもそのお姫さまは地球に降りるといってきかない。
そんな話だったように記憶している。
村中の皆が噂し、ことの行く末を固唾を呑んで見守っていたけれど、当時まだ見習いだったわたしには、他人事でしかなかった。
とってもとっても忙しかったのだ。
設計書の内容を理解してスーツという形にするためには膨大な知識が必要で、さらにはそれに合う素材の選び方ひとつとってもセンスが要求される。
頭をフル回転し、手をくまなく動かして縫い合わせては、足りない素材を探すために遠くまで足を運んだ。
昼も夜もなく、それどころではなかったというのが正直なところだったし、「お姫さま」なんてワード、わたしには天ほどに遠いと思っていた。
けれど、わたしは噂の張本人に相対することになる。
数日後、彼女を見かけたのは、お客様にスーツを納品した後のことだった。
最終のフィッティングを済ませて、地球へ送り出す日程を決め、最後の手配を済ませた帰り道、ふと湖に立ち寄りたくなった。
疲れていて少しだけ息抜きをしたかったわたしは、木陰になっている湖畔の野原にいつものように向かった。
わたしのいつもの場所を占有していたのが、彼女だった。
あどけない顔立ち、それなのに湖を見つめる横顔はひどく大人びて見える。
けれど、彼女からは純粋さが立ち昇っている。
周囲を取り巻く空気の清浄さに戸惑い、そこに向かおうとしていた足が止まる。
近づくことは、できない。
仕方なしに休憩をあきらめ、踵を返そうとした次の瞬間、その子と目が合ってしまったのは、完全なる誤算ではなく、後から思えば運命だった。
彼女の視線にとらえられたわたしは、もう引き返すこともできなくなった。
見つめあったわたしたちは、動けない。
先に沈黙を破ったのは彼女の方だった。
「ねぇ、わたしのこと知ってるわよね?」
ストレートでくるらしい。
わたしはあきらめて、頷いた。
「みんな、わたしを止める。それって、地球へ行くなってことなの?」
伝えてよいのか迷ったけれど、嘘はつけなかった。
これを初対面のわたしに聞くほどに、彼女はひとりなのだ。
「いいえ、あなたが地球へ行くってことは決まってるわ。」
そう答えた。
彼女は少しだけ驚いたような顔をした。
それは想定の範囲内で、話を続けた。
「あなたは村に入れた。村に入れた人で地球へ行かなかった人はいない。」
そう、ゲートは開いたのだ。
ゲートは資格のないものを通さない。
彼女は地球に降り立つことになる、それは村で働く全員の共通認識だ。
「そう、じゃあ準備が整ってないってことなのね。」
頷いた。
けれど、その先に進むために必要な答えをわたしは持っていない。
人生の設計書を担当するひとの業務範囲だからだ。
「困ってるのは、デザインが決まらないっていうことなの。」
どういう意味なのかわからない。
そんなこと聞いたことがなかった。
わたしの表情を見て、彼女は必要な説明を加えてくれる。
「つまりね、わたし持ってないの、何も。
普通なら、こういうことを体験したいとか、こういう学びを得たいとか、そういう動機があって、それに合わせてデザインをするんでしょう?
あるいは過去世でやり残したことがあるとか、会いたい人がいるとか。
わたしには、そういうものが何もないの。
ない、というのは正しくないわね。
正しくは、それを忘れてしまったみたいなの。」
ベテランであるはずのやぎじいが頭を抱えていた理由がやっとわかった。
「覚えていることは、たった一つ。
” 地球に行かなくちゃいけない ” ただそれだけなの。
どうやってここにたどり着いたのかすら、覚えてない。
みんながわたしを人魚だって言うけれど、人魚だった記憶も、お姫様だった記憶もない。地球で何をすべきなのかもわからない。」
彼女が困っていることは明白だった。
けれど、” Only One ” というスーツを作製するお店で働くわたしが、設計図に関して彼女にアドバイスをするのは、村の禁忌に触れてしまう。
けれど、力になりたいと思った。
目の前にいる彼女には吸引力があって、何かをしてあげたい気持ちに駆られてしまう。
もしわたしにできることがあるとしたら、と思いを巡らせる。
思いついたのは、ひとつだけだった。
わたしは、彼女を知らない。
だから、彼女について知ること、それが必要だと思った。
「そうだ、泳いでみたら?」
ふと浮かんだアイディアが口をついた。
まだピンと来ていなそうな彼女に言い募る。
「泳いでみたら、人魚だったことを思い出すかもしれないじゃない?」
彼女はじっと考え込んでいたけれど、泳いでみることにしたようだった。
おもむろにドレスを脱いで裸になると、止める間もなく湖に飛び込む。
じゃぼん、と広がった波紋がゆっくりと広がり、湖面が静寂を取り戻すまで、それはそれは長い沈黙だった。
彼女は泡にかえってしまったのか、と不安になりかけた瞬間、ぐいんと大きく水面がうねって持ち上がった。
濡れ髪の彼女が水をまとって浮き上がる。
時が止まったように感じた次の瞬間には、すごい速さで音もなく消えていた。いつの間にか湖に光が降り注いでいる。
それから、ひとしきり彼女に魅入った。
彼女の動きは、泳ぐ、という言葉で表現されるものとは違っていた。
湖すべてが彼女と一体化しているように見えるほど、水は圧倒的に彼女の味方だった。
彼女自身がわからなくても、彼女は紛れもなく人魚のお姫様だ。
圧倒的な存在感、このとき初めて目にしたそれを今も忘れられない。
純粋で無垢で、それが形になって目の前にある。
半ば呆然としているわたしに、湖から上がった彼女が言った。
「ありがとう。わたし、人魚だったみたい。」
そう微笑む彼女があまりにも愛らしくて、思わずわたしにも笑みがこぼれる。
わたしと彼女が友だちになった瞬間だった。
それから数日後のことだった。
” No Design No Life ” のやぎじいに呼び出され、わたしはお店に向かった。
着いた途端にやぎじいに頭を下げられて面食らう。
まだ見習いのわたしに、この村一番のベテランであるやぎじいが頭を下げている。
「うさくま、お願いだから手伝ってくれんか。」
やぎじいの目の下にできたクマを見て、ことわれるはずもない。
事情はなんとなく察していたし、もう結論は出ている。
けれど、一応話を聞いておくことにした。
やはり、人魚の氷魚ちゃんの設計図がどうしても進まないらしい。
氷魚ちゃんの話は聞き終わってしまって手詰まりであること、にも関わらずその話から設計図を起こすことが全くできていないこと、そしてそんなことは初めてだということ。
そんな中、氷魚ちゃんからわたしの話を聞いて、ワラをも掴む気持ちでわたしに連絡をしたこと。
けれど、わたしはまだ見習いの身で、自分ひとりで決めることはできない。
それを話すと、頷いたやぎじいがすぐにわたしが働く ” Only One ” に電話をかけてくれて、わたしは ” No Design No Life ” で研修を受けるという形をとって働くことになった。
働くとはいっても、することは何も決まっていなくて、ただ氷魚ちゃんと一緒にいてほしいとやぎじいは言った。
わたしは、やっぱり強く思っていた。
氷魚ちゃんのことを、わたしは知りたい。
氷魚ちゃんとほとんどの時間を過ごす日々が始まった。
何かをしようとしてするのではなく、気分でそのときどきやりたいことをすること、それが大事だという直感があった。
最初に氷魚ちゃんが自分のことを思い出したのは、それから10日くらい経った雨の日だった。
毛がうねるしスーツが湿気るのでわたしは雨が嫌いだったのだけれど、氷魚ちゃんは雨が大好きだった。
最初に出会った湖で、氷魚ちゃんはいつものように泳いでいて、わたしもいつものようにそれを眺めていた。
湖みたいな淡いブルーのお洋服が似合いそうだな、と思った。
空腹のあまり湖から上がった彼女と、ここでお昼にすることにした。
まだ、シトシトと雨は降り続いていた。
ホテルのひとに作ってもらった昆布のおにぎりをふたりで頬張る。
氷魚ちゃん用のおにぎりは塩多めの特別仕様で、間違って食べると口の中がジョリジョリで大変なことになる。
彼女は塩辛い物が好きで、特に湖で泳いだ後は塩分を欲しがった。お肉とかお魚は苦手で、貝や海藻が一番食べやすいと言っていた。
「氷魚ちゃんのお母さんはどんなひとだったんだろうねぇ。」
すごく綺麗な人に違いないと思った。
「うさくまちゃんのおかあさんはどんなひと?」
微笑んでこっちを見る氷魚ちゃんは本当に綺麗だった。
「わたしのおかあさんはね、まぁるくて明るくて優しかった。」
思い出しただけで、涙が出そうになる。
でも、ここに来るときに離れて以来会っていなかった。
表情に出てしまったのかもしれない、氷魚ちゃんの顔が曇った。
「ここに来るって決めたとき、おかあさんが『もう戻ってこないつもりで行きなさい』って言ったの。」
だから、わたしはあれから必死で働いてきた。
一人前になったら、いつかおかあさんに会いに行くんだと思っていた。
涙がこぼれないように必死でおさえて、やっとのことで顔を上げたとき、氷魚ちゃんの異変に気付いた。
氷魚ちゃんが泣いている。
「どうしたの?」
「『もう、戻ってこないで。』
最後の日、おかあさんがそう言ったの。
小さなわたしをカプセルに入れて、宇宙に放流したの。」
氷魚ちゃんの目は虚ろで、目がキョロキョロ動いている。
何か思い出しかけているみたい。
少しだけ、そうっとしていようと思った。
「わたしが住んでいた惑星、なくなっちゃった。」
びっくりしたけれど、顔に出しちゃいけないと思ったから頷くだけにした。
目は逸らさない。
「よくわからなかった。
ある日、世界が壊れるって誰かが言いだした。
本当かどうかわからないのに、毎日ひとりずついなくなって、惑星もすり減って少しずつ軽くなっていった。
おかあさんはだいじょうぶだよってずっと言っていたけど、ある日とうとうおとうさんまで行かなくちゃって言い出したの。
もっと純粋になって、もう一度君に出会いたいから。
今度こそ、ひとつになれる。
おかあさんにそう言うの。
わたしには意味がわからなかったけど、おかあさんはわかっていたみたい。
そして、いつの間にかおとうさんが消えていた。
それからは、わたしの周りにいた魚たちも少しずつ減っていった。
わたし自身も減っていって、少しずつ薄く小さくなっていった。
そして、限りなく小さくなったわたしを、おかあさんがカプセルに入れて宇宙に放した。
あの惑星に残ったのがおかあさんだけになった瞬間、星ははじけ飛んで散り散りになった。
その星屑が光の道になって、わたしはそれに乗ってここまできた。
わたしには、もう何もない。
帰る場所も家族も何もかも、失ってしまったの。」
目が虚ろなまま、氷魚ちゃんが喋り続ける。
わたしはというと、感情のスイッチを切って、モードを切り替えていた。
泣きそうだったけれど、ここで呑まれてはいけない。
必死だった。
目の前の女の子は、わたしの友だちではなく、大切なお客さまだ。
そしてわたしの仕事は、この子のスーツをつくることだ。
そのために、わたしはここにいる。
「全部忘れなさい。
今までのことは全部忘れて、もう一度探すのよ。
おかあさんはそう言ってた。
けど、あのままでよかった。
どうしてあのままじゃだめだったの。」
そのとき、何かが、頭に引っかかった。
何もない、そう氷魚ちゃんは言った。
けれど、違うのではないか。
彼女がいる、だから何もないわけではない。
少なくとも、彼女自身つまり ” 器 ” はある。
あるいは、何もないという状態がある。
「他に、おかあさんに言われたこと、ない?」
あとちょっとでわかりそうな気がする。
「あなたは " 核 " になるって。」
まさに、雷に打たれたような衝撃だった。
頭の中の霧が晴れていく。
” 器 ” じゃなく、 ” 核 ” 。
彼女がいれば、集まってくるのだ。
彼女が中心となって、その周りに世界が創られていく。
降りてきたインスピレーションには確信があった。
その日はそこまでだった。
氷魚ちゃんはすでに疲労困憊だったし、ひとりになりたいというので、ホテルの部屋まで送っていった。
わたしも疲れていたけれど、それより興奮が優っていた。
早く、やぎじいと話したい。
息急き切って走ってきたわたしを見て、やぎじいが言う。
「思い出したのか。」
頷いて、答えた。
「うん、でも揃ってない、何か足りない。だから教えて欲しいの。」
「デザインしないスーツって作ったことある?」
詳細は省いた。
おかあさんのエピソードは、氷魚ちゃんからやぎじいに直接話してもらった方がいい気がしたし、明日になればもっとわかるはずだ。
「デザインしない?基本のスーツのことか?」
やぎじいが不思議そうにこっちを見ている。
「うん、基本っていうより、氷魚ちゃんそのままっていうか…」
うまく伝えられない。
「つまりね、氷魚ちゃんには何にもないけど、それでいいの。
彼女は、何もないっていうことが計画されていて、それがアイデンティティーなの。
たぶんだけど…」
最後自信がなくなってしまったわたしに、やぎじいが補足してくれる。
「だから、今の姫さんのまま、地球に降りるってことを実現するスーツ。
なるほど、理屈は通るな。」
ひとつだけ、とやぎじいが言う。
「姫さんの惑星は滅んだのか?」
わたしは、たぶん、と頷いた。
氷魚ちゃんもたぶんわかっている。
「姫さんのおっかさんは、もういないんだな。」
やぎじいがポツリといって、机の上の本を開いてわたしに見せてくれた。
それは、ある人魚の生態についての調査記録だった。
群れには女王がひとりいて、周囲の存在はすべて雄である。
周囲は魚がほとんどで、稀に人魚の形をしているものもいるが、すべて雄であり、どれも女王の子どもあるいは女王から派生した一部である。
女王以外の存在の寿命は数百年であるが、女王は数千年から数万年生きると言われている。
数千年〜数万年に一度の代替わりは、雌の人魚の子がうまれることからはじまる。
生誕から数十年後、その惑星は徐々に力を失い、女王とともに消滅する。
理由は定かではないが、惑星の消滅は死と再生を意味しており、その消滅と同時に、宇宙には星屑が降り注ぎ、0の祝福が起こると言われている。
雌の人魚の子については、未だ記録がなく、その後の生態については不明であるものの、女王の一部は子に継承されているという説が有力である。
読んでいて、泣きそうになったので、これが真実なんだと思った。
やぎじいはたどり着いていたけど、氷魚ちゃんに言えなかったんだ。
「いや、確信がもてなくてよ。
それなのに、記憶もねぇ姫さんにおっかさんのことなんて聞けねぇだろ?
それに、この記録にもある通りで、このときどういうスーツを用意したかはわからねぇしな。」
遠くを見つめるやぎじいの目が優しいので、わたしは、思う存分泣くことに決めた。
今だけ、明日になったら仕事に戻るから。
「お前さんがいてくれて、本当によかったよ。」
やぎじいはおぅおぅ泣き続けるわたしを呆れたように見ていたけれど、姿を消したかと思うとホットミルクを持ってきてくれた。
優しく頭を撫ぜてくれる。
数千年前、氷魚ちゃんのおかあさんもここにきたんだろうか。
頭の中に氷魚ちゃんそっくりの小さな人魚姫が思い浮かぶ。
どうか、この子の側にも誰かいてくれますように。
最初のスーツが出来上がったのは、それから約1ヶ月後の晴れた日だった。
あの次の日に氷魚ちゃんとやぎじいとわたしで、もう一度確認して、どんなスーツを作るのか決めた。
「氷魚ちゃん、どうしたい?」
わたしとやぎじいから、氷魚ちゃんへの何度目かの質問だった。
「わたしは、わたしを知りたい。」
氷魚ちゃんの目はもう揺らいでいなかった。
「氷魚ちゃんが今わかってる氷魚ちゃんはどんな感じ?」
少しヒヤリとした。
「わたしは、今 0 と 1 の間くらい。持っているのは、わたしだけ。
そして、わたしは、あの惑星の最後の人魚で、生き残り。」
氷魚ちゃんが思ったよりしっかりしているので少しだけ安心した。
「氷魚ちゃんは、その惑星での生活や一緒にいた存在たちのことを覚えてる?」
少しずつ、近づいていく。
「それが、思い出せないの。昨日思い出した、最後の方の記憶だけしか。」
それは予想通りだった。
「誰か、会いたいひとはいる?」
聞きながら、怖くて目をつぶってしまいそうだった。
「ううん、一番会いたいひとはもういないから。」
氷魚ちゃんが優しい目でわたしを見ている。
わたしに気を使っているのだ。
だいじょうぶだよって伝わってくる。
「おかあさんに会いたい。
もう一度、会いたい。それに、聞きたいこともいっぱいある。
けど、おかあさんはもういない。
でも残ってる。
おかあさんもその願いもすべてわたしの中にある。」
それは、わたしとやぎじいと考えた仮説とまったく同じだった。
「だから、わたしなるべくこのままで、ニンゲンになりたい。
わたしの知りたい答えは、ぜんぶ地球にある。」
それも、わたしとやぎじいの出した結論とまったく同じだった。
いつもと同じ、すべては地球にあるのだ。
それから1週間、やぎじいは氷魚ちゃんの設計図にかかりきりだった。氷魚ちゃんが氷魚ちゃんらしくそのまま地球で生きていけるように、必要な装備と不必要な装備が次々と判別され、書き込まれる。
わたしにも、仕事があった。
" SOTODURA" に氷魚ちゃんを連れていくことだ。
0才、5才、10才それぞれの時点での氷魚ちゃんを設定していく。
その後、間をつなげるように調整したイメージを描画してもらう。
瞳と髪の毛の色は、今の氷魚ちゃんになるべく近くして、肌の透明感にもこだわりたかった。
会ったひと誰もが、氷魚ちゃんだってわかるように。
ちゃんと、氷魚ちゃんのもとにみんながかえってこられるように。
できあがった詳細な設計書をもとに、プログラムを組んでスーツを縫い上げるのはわたしの仕事だった。
素材選びもすべて含めて、最初から最後まで、わたしひとりで仕上げた。
これは、天から授かったわたしの仕事だと思った。
丸々三週間かかった。
そして、ある晴れた日に、氷魚ちゃんのスーツは出来上がった。
ホテルの部屋で、最終フィッティングを行う。
部屋の窓からは、晴れ渡った空とキラキラひかる湖面が見えている。
スーツを身にまとった氷魚ちゃんはいつも以上に清廉なオーラを放っていた。
純粋無垢、それが氷魚ちゃんなのだ。
ほんのりペールブルーをまとった、ピュアでシンプルでクリーンな魂。
それから、氷魚ちゃんは還ってきて、再び地球へ降りるということを繰り返した。
” 獲得 ” しないと、といって何度も何度も地球へと向かう、氷魚ちゃんは勇敢で無謀な魂だった。
1回目に還ってきたとき、おかあさんを思い出したよと言った。
わたしも女王になる。
いつかわたしの惑星をつくるんだ。
そういった氷魚ちゃんの横顔は美しかった。
2回目は、仲間の記憶を持って還ってきた。
幾千もの魚たちとともに暮らした故郷の記憶。
けれどそれは、少しずつ自分から彼らが剥がれて落ちていく悲しみや、彼らと一緒に生きていたときの安心感に包まれていた感覚を同時に連れてきた。
還ってきたばかりの氷魚ちゃんは少し疲れているように見えた。
けれど、先に地球に向かった魚たちがいるかもしれないこと、その魚たちと地球と再会するって約束をしたことは彼女の支えになった。
少し強くなった氷魚ちゃんがいた。
3回目の地球では「仲間と出会いたい」と氷魚ちゃんは言った。
今回は、前回より情報充填率を上げて、寿命も長くしたりと、設計に変更をかなり入れる必要があるとやぎじいがいう。
情報充填率は、基本魂の割合で、本来の魂に近しいかどうかだ。それぞれ、40〜80%くらいを選択するのだけれど、氷魚ちゃんは1回目 95%に設定していた。それを少しずつ下げていく。
"SOTODURA" のスタッフが腕によりをかけてデザインを加えたスーツは、前回より少しだけ人間っぽさが加わっている。
「行ってくるね」
そう言って、また地球に深く潜っていった。
けれど、そのとき出会えた魚たちはそのままの姿ではなかったらしい。
氷魚ちゃんの故郷である惑星から地球までは遠かった。
地球へ向かう旅路で起こるトラブルや少しの悪意と生まれる誤解に、慣れない魚たちは傷つき削られていく。
放浪した魂は疲れていた。
にも関わらず、やっとのことでたどり着いた地球には愛した姫の姿はなく、その事実に絶望し心折れてしまった魚たちもいたという。
その後地球で暮らしだした魚たちも、楽園のような惑星で暮らしていた身に地球という環境は過酷すぎた。
こうして、幾千もの魚たちは約束を忘れ、姿を消していった。
だから出会えた魚たちはごく僅かだった、と悲しそうに氷魚ちゃんはいった。
それでも、彼女は傷ついた魚たちを連れて、還ってきた。
魚たちと一緒に、彼女は魂トリートメントを受けた。
癒された彼らは、氷魚ちゃんに吸収されて溶けていった。
このときぐらいから、氷魚ちゃんはわたしが知っている氷魚ちゃんから少しずつ変わっていった。
たぶん、姫から女王になっていった。
それでも、純粋さと愛らしさはそのままに、柔らかくなっていった。
4回目は、ニンゲンの体と心を思う存分味わいたいと言った。
でも、このとき還ってきたスーツは本当にボロボロだった。
悲しみと痛みがたっぷりと染み込んでいて、何度クリーニングしても落ちなくて、シミ抜きまでやったのは久しぶりだと ” The-boo-boon ” のぶーちゃんがぼやいていた。
このときのスーツは、かなりスーツを薄くして、シンクロ率もあげた。
ハードな人生のときは、致命傷を負わないようにスーツを分厚くするけれど、その分感覚は鈍る。
” 味わいたい ” 氷魚ちゃんのスーツは薄くするべきだと思った。
シンクロ率をあげると、魂本体も傷つきやすくなるけれど、氷魚ちゃんは怯まなかった。
オプションの「他人との境界線」の部分も薄くするよう、やぎじいと相談した。今までは危ないからキッチリ線を引いてのだけれど、氷魚ちゃんが成熟してきたこともあり、そこを一旦あえて薄くすることにしたのだ。
わたしは、還ってきたスーツの軽さに驚いて「よく還ってきたねぇ」と声をかけずにはいられなかった。
氷魚ちゃんは、ギリギリまで闘っているのだ。
人の裏側にある、嫉妬とか執着とかに触れた部分が火傷のようにあちこち薄くなっていた。
還ってきた 氷魚ちゃんの本体は、長く長く眠っていた。
目覚めた 氷魚ちゃんは、故郷の惑星が滅びた理由を再び語り始めた。
嫉妬。執着。怒り。後悔。恨み。不遜。強欲。虚勢。
いつしか、そんなものを持ち込む魚たちが増え始めた。
そして、純粋な魚たちはその毒にあたり、惑星から離れていくものもいた。
バランスが崩れ、マイナス側にふれた惑星には、ドロドロした何かが入りこみ溢れかえるようになった。
惑星が呑み込まれる前に、と母は浄化に力を入れ、すべて手放していった。
かくして惑星は綺麗になり、けれど同時に薄くなりアイデンティティーも喪われ、宇宙との境目が消えていった。
そして、母とわたしという純粋な存在、源となる核だけが残った。
そのあとは、前回の通りだった。
このあと、氷魚ちゃんは、使命がわかったよ、と絶望したようにいった。
わたしは、全部の意味を知った後に、その上でもう一度純粋さを獲得する。
何度でも地球に潜って、精神を磨く。
実際のところ、彼女は地球に潜り続け、ハートの真ん中に宿る石を磨き続けた。その度に純度が高まっていったのは事実だ。
けれど、このときの彼女はまたその旅の途中にいた。
旅を終えるたびに、苦しそうに呑み込み、咀嚼して、一部を受け入れて、消化して、自分ではないものを吐き出す彼女を、わたしは見てきた。
苦いものが内側にピッタリと張り付いていて取れないの、そういっていた。
実は、長い眠りから目覚めたばかりの氷魚ちゃんは、 氷魚ちゃんじゃないみたいに、生気がなかった。
透明感を通り越して、透明に近くて氷みたいに溶けてしまいそうだった。
「よく、還ってきたねぇ。」
わたしは、氷魚ちゃんを抱きしめた。
泣きじゃくる氷魚ちゃんは昔のままなのに。
時々、還ってこないNINGEN★SUITSがある。
実際、地球は危険なのだ。
自分が自分だってことを忘れてしまう魂とか、他人を傷つけた分だけ自分を傷つけてしまう魂とか、地球で懸命に生きていこうとして自分を亡くしてしまう魂とか、スーツにはある程度のゆらぎが設定されていて、そのゆらぎが思いも寄らない未来を連れてくることがある。
スーツには、保険としてこの村につながるコードが付いている。
それでも、それを自ら切ってしまう魂はあるのだ。
氷魚ちゃんはここに還ってきた。
それが彼女の意志だった。
それからも、氷魚ちゃんは果敢に地球に潜り続け、わたしは環流されてきた氷魚ちゃんを受け止め、送り出し続けた。
9回目のテーマは、「性」になった。
久しぶりの設計書の更新になる。
4回目からニンゲンの体と心を味わい尽くした氷魚ちゃんは、しなやかで女性らしくなってきていた。
それを村中に知らしめたのが、前回の環流だった。
氷魚ちゃんから放たれたお花みたいなかぐわしい匂いが辺りに満ち、その妖艶な姿に誰もが目を奪われる。
村中が恋に落ちた瞬間だった。
以来、氷魚ちゃんの蕾は開き、強く馨るようになった。
そして、そんな彼女が「恋に落ちたい」と言い出したのだ。
一方、このころのわたしは不安でいっぱいだった。
ここ数回の環流で、氷魚ちゃんの純粋無垢なオーラが曇ったような気がしていた。
氷魚ちゃんが女王と人間の間でグラグラしている。
今回の設計書には、「運命」をセットする。
久しぶりにやぎじいと氷魚ちゃんと打ち合わせすることになった。
鍵と鍵穴を設定する必要があった。
鍵穴は、癒えない傷とか致命的な欠損を設定する場合が多い。
パスワードとなる鍵は、鍵穴に合わせるので、あまり決まっていない。
言葉やシチュエーション、イベントそのものなど流動的になるそうだ。
そうやぎじいが説明してくれたけれど、わたしにはピンとこなかったので、どうコードを書くかを考えることに集中することにした。
それ以外に運命を裏打ちするオプションとして、声の耳へ伝わる甘さとか視線の持続時間とか匂いの肌への浸透度とか、ふたりを接着する特別な磁石を仕込んでおくらしい。
わかりやすく体に印をつけておくこともある。
メモをしながら、全体をどう書くか、どういう素材を使うかイメージを膨らませる。
氷魚ちゃんは静かに説明を聞いていた。
そして一通り聞き終えた後、消え入りそうな声で言った。
真魚に会いたいの。
真魚というのは、故郷の惑星で一番強かった魚だそうだ。
物心ついた頃からずっと一緒だった彼と、地球でもう一度出会う約束をしていたのを思い出したのは、7回目のときらしい。
彼によく似た魂に出会ったのだそうだ。
このときの氷魚ちゃんの目は潤んでいて、甘酸っぱい匂いがして、全身が真っ赤に染まっていた。
発情、という状態だとあとからやぎじいに聞いたけど、未だわたしには意味がわからない。
できうる限り細かく「運命」をセットしたスーツを身に纏い、8回目の地球へ氷魚ちゃんは旅立った。
8回目の環流では、氷魚ちゃんの泣き声がなりひびいた。
「わーーーん」
その声が村を貫いたと同時に、「好き」その純粋な気持ちが湖の真ん中から漣のように広がっていく。
霧雨が降り注ぎ、空には虹がかかった。
結局のところ、彼女は美しいのだ。
命が、息づいている。
泣き声が空気を清浄にしていくのがわかった。
純粋無垢、はやはり彼女そのものだった。
わたしは一瞬でもそれが喪われたかもしれないと疑ったことを恥じた。
氷魚ちゃんが無事にホテルで寝入ったのを見届けてから、わたしは湖を取り囲む森の端に向かった。
そこに大きな大きな赤銅色の鍋があることを知っているのは、村でも数人しかいない。
「スーツの作製において、2つ以上の工程に関わってはいけない」
この村の禁忌は、リスクヘッジのためにある。
わたしは、氷魚ちゃんのスーツを作った時、この禁忌に触れた。
仕事の定年がなくなった。
つまり、わたしはこの惑星から数千年は出られない。
禁忌を侵したものにより、この鍋は守られている。
わたしをここに連れてきてくれたのはやぎじいだった。
この鍋には数億年分の愛が溜まっている。
少しずつ雨のように降り注いでは、鍋にくべられた火に炊かれ、濃密さを増してこっくりとしている。
蒸発した愛は空気を溶かし、ゆらりと舞い上がる。
わたしは、ぐらりと鍋の上を揺るがす熱を見るのが好きだった。
それはいつかの氷魚ちゃんにも似ている。
この鍋には、わたしの母の愛も氷魚ちゃんの母の愛も、氷魚ちゃんの真魚を思う心も溶けているのだろうか。
あの時氷魚ちゃんと出会えたことに心から感謝した。
わたしは、今を愛している。
「今日は、8つだったっけ。」
今日も忙しくなりそうだ。
ボクは、” God bless you ! ” で働いている。
まだ半人前のボクには修復や記録の仕事はできない。
環流したスーツのNo.と数が予定とあっているか確認して受付するのがボクの仕事だ。
もうすぐ10時半になる。
還ってきたスーツが湖畔に到着する時間だ。
湖畔は、ざわざわしていた。
伝説の人魚が還ってくるらしいのだから、当然といえば当然のことだった。
今回は11回目の環流だと聞いたけれど、本当だろうか。
「おつかれさま〜。」
うさくまさんは、” Only One ” というお店で「NINGEN★SUITS」をつくっている人で、千年もここにいる大ベテランだ。
「おつかれさまです。」
ボクは気後れしてしまい、小さい声になってしまったけれど、うさくまさんは何も気にしていないようだった。
ふと、思った。
うさくまさんに聞いてもいいだろうか。
その瞬間、口からもうそれは出ていた。
「スーツって結局なんなんですか?」
新人のクシャミくんの問いに、思いを巡らせる。
そうだよね、わたしたちニンゲンになったことも、地球に行ったこともないもんね。わからないよね。
そういえば、わたしも昔そう思っていた。
なんて言えば、この子に伝わるんだろう。
「わたしにとって、スーツはここと地球をつないでくれる架け橋かな。」
還ってきたスーツの傷が教えてくれること。
スーツを縫い合わせるときに込める願い。
すべて、わたしにとっては地球とのコミュニケーションだった。
今日もわたしたちは、願う。
スーツとその持ち主の無事を祈る。
望んで、とはいえ過酷な旅になることがわかっているから、わたしたちは、常に最大限の努力をして、希望とともに送りだす。
どうしても現れる揺らぎ、けれど計算できないそれが美しさをつくりだす。
未来は決まっていない、紡いでいくものだから。
瞬間の命がとても美しいの。
そうクシャミくんに伝えたかったけれど、やめた。
誰かに教えてもらうことに価値はない。
いつか。
そう、決めていることがある。
彼女の惑星が生まれ出ずるとき、そのときには休暇を申請しよう。
許可が下りるかわからないけれど、行くと決めている。
今日も、ゲートは開く。
わたしは、わたしを開く。
全部が開かれていく。
そして、わたしたちはたどり着くはずだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
