
心には君のパズル
無窓居室という言葉を聞いたことがある。
窓がなかったり、必要なだけの採光面積が取れない部屋は住むための部屋として認められない。そういう居室を無窓居室と言うそうだ。
私、伊勢崎芽衣が転がっていた『ここ』がかなり広い無窓居室らしいことに気がついたのは体を起こして三十秒ほど経ってからだった。
(どこだろ、ここ)
大体十畳くらいの天井の高い、窓がない部屋だった。ただ、窓もなく灯りも点いていないのに、ぼんやりと明るく、真の闇ではない。
そもそも今日は校外学習のためにバスで移動中、途中休憩のためにサービスエリアにいたはずだった。みんなトイレを済ませたり、何か飲んだり体を伸ばしたり、友達と話したりしていた。私も酔い止めの薬を車酔いした子に飲ませてあげたり、トイレまで連れていったりして少し疲れたこともあり、展望スペースでぼんやり景色を見ていたはずだった。
少なくともこんな暗い場所に心当たりは全くない。
「えーと」
声を漏らした瞬間、すぐ近くで何か動く気配がした。
「……伊勢崎?」
私とそんなに変わらない年頃の、男の声だ。どうやら私以外にもこの床に転がっている人間がいたらしい。声に聴き憶えはない。でも、私の名前を知っているのなら同級生の可能性がかなり高かった。
今は五月の半ばだ。まだ個別認識していない男子生徒はそれなりにいる。私は同級生男子らしい彼の転がっている方に顔を向けた。
「顔見えないんだけど、起き上がれる?」
「一応」
ややけだるげな声を漏らしつつ、その男子は上半身を起こした。動いた時の影の動きでやっと彼が私の座っている場所から数十センチのところに転がっていたらしいことに気がついた。多分、彼は私が動いた気配で意識を取り戻し、声で個別認識して呼びかけたのだろう。
私はやや顔を近づけ、彼の目鼻立ちを確認した。光はわずかに射しているけれど、相当近寄らないとどんな顔なのか解らないのだ。とりあえず暗がりで見る限り、パーツは小作りだけどバランスのいい顔立ちだった。肌が白い黒いまでは判別できなかった。
全く憶えていない。
「ごめん――思い出せない。まだクラスの半分くらいは憶えてないんだ」
「俺、印象薄いし、いいよ」
クラスメートが顔を憶えていなかったのに、彼はさして気にした様子もなく、かすかに笑ってみせてから明石香積と名乗った。
「展望スペースにいたところまで憶えてるけど、ここ、どこだろ。あのへんにいた子達、どうなったのかな」
ここが地面が崩れて空いた穴などだったら、何らかの事故が起こって展望スペースが崩れてしまい、そこに落ちたのだろうと推測できるけれど、私と明石には怪我もなく、体や服が汚れてもいないままで謎の無窓居室に転がっていたのだ。
明石は困ったように首を振る。距離が近いので、髪がさらさらと動いた音が聞こえた。
「ちょっと前に気がついたから、他の場所は確認してないんだ。伊勢崎が気がつくのを待ってるうちに寝てた」
「寝てたんだ」
明石はずいぶん緊張感のない男らしい。彼は籠もったような、どこかセンシティブな中音域で付け加える。
「何も解らないうちに考えると、嫌なことしか思いつかない気がするから、伊勢崎が起きるのを待ってた」
広くて窓のない部屋なんて、ただでさえ異様だ。思考停止してしまうのは正解なのかも知れない。
「でも、ずっとここに座ってる訳にもいかないし、そろそろ見つけに行こうか――ドア」
ここは室内だ。私達は外から連れてこられたはず。
雨風が吹き込んだり、砂で汚れていたりしない部屋なのだから、多分……まともなドアがあるはずだ。
私達は立ち上がり、周囲を確認した。
ここはホール、広間的な場所か、倉庫にでも使われていたのだろう。ただ何もなくだだっ広い。ドアがない代わりに、どこかへ続く廊下と隣接している。
廊下の向こうに光源はなさそうだ。
ここと同じく暗そうだった。
「行く?」
「うん」
一歩踏み出そうとした瞬間に、私は展望スペースでのあることを思い出した。
景色を見ている時に見つけて、拾おうとした何か。
「そのへんにパズルのピース、落ちてないかな」
「パズル?」
「うん、展望スペースのあたりで拾ったはずなんだ」
生成り色っぽいジグソーパズルのピースがひとつだけあるのを見つけて拾ったのだ。サービスエリアといっても観光用のおみやげなんかはほとんど売っていないので気になってしまったのだ。
明石は身をかがめ、それらしいものが落ちていないか確認する。暗いので地道に探してくれた。いい人だ。
「何もないけど。大事なもの?」
困ったような顔で笑いながら戻ってくる。
「うーん……」
拾った後のことをちゃんと思い出せなかった。ここに連れてこられる途中でどこかに落としたのだろうか。
「どうだろうね」
私は曖昧に微笑んだ。
この不条理な状況で、ここまでが日常だった印として刻まれているような気分だった。だからこそ些細なことが心に残っているのだろう。
「明石、そろそろ行こ」
あのピースを落としたのがここでないのなら、こんな場所に用などありはしないのだ。
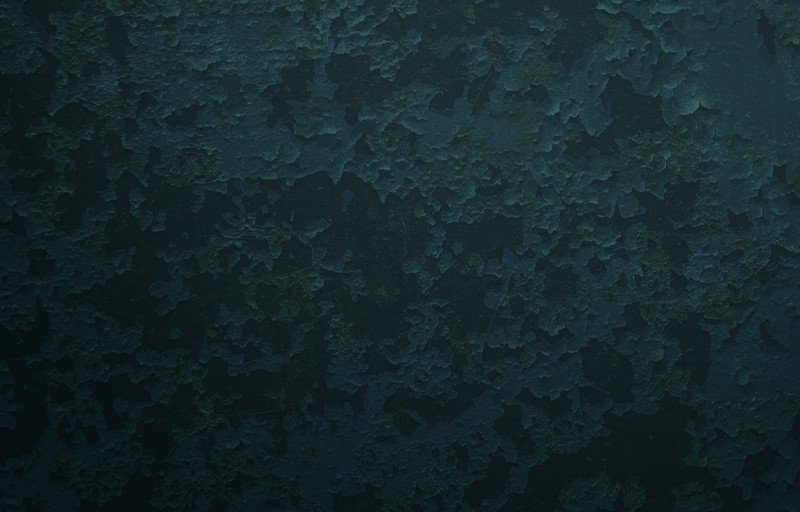
私達はしばらく歩いてみた。
要するに『しばらく』と言える程度に長く歩けるほどこの建物の中は広かった。でも、当座の目的にしていたドアを発見することができなかった。
「ここまでドアがない建物ってどうなってるんだろう。しかも何だかずっと暗い割には真っ暗じゃないし」
眼もそれなりに馴れて、明石の顔を確認するくらいは問題なくできるようになっていたから、こうして歩いていると夜の散歩でもしているような気分になる。明石が口数の多くない、穏やかな感じの男子なので、尚更ゆったりとした、ある意味緊張感のない雰囲気だ。
でも、そんな空気はしばらくまっすぐだった廊下の角を曲がった時に吹き飛んだ。
暗がりの中、『それ』だけが鈍い光を放っていた。
ゲル状の何かの中に蛙の卵みたいな、でも大きなタピオカくらいのつぶつぶが何百と含まれている。そして――その粘液の中に見憶えのある学校の制服がぐしゃりと歪んで落ちていた。
私が今着ているのと同じ制服。ネクタイの布地が少し色あせたように見える独特の薄紫なので暗くてもすぐに解った。
それだけでなく制服の端から靴下や靴、そして乱れた髪の毛が絡みつき、うねったままで固まっている。
猛烈な吐き気がこみ上げた。でも、それに向かって吐瀉物を出すのはひどい冒瀆をしているような気がしたので必死で堪え、もつれた足で後ずさりする。
明石が私の手を引き、かがませてくれた。
他に吐く場所もない。ここで吐くしかないのだ。
『それ』を見ないように眼をそむけ、無様に吐いた。吐瀉物が服にかからないようにするだけで精一杯だった。
「あれ、うちの学校の子だよね。誰か解る?」
「……顔がないから無理」
あの制服のポケットから、生徒手帳を取り出すことができれば解るかも知れないけれど、正体不明の粘液に手を突っ込んで探るなんて絶対嫌だろう。私だって嫌だ。
「でも、あんなのがあるってことは、ここにクラスの子達がいる可能性はそれなりにあるんだよね」
「あんなのばっかり見つかっても伊勢崎がつらいだけのような気がするけど」
「何が起きてるか解らないままだと、もっとつらいよ」
自分がああなるかも知れないと脅えながら、どこへも行けないまま、何もしないでいる訳にはいかない。
「あんな状態になるかも知れない原因もここにあるかも知れないってことだよ。あったとしても私達に解決できるとは思えないけど、それでもああなる前に逃げられるかも知れないし」
明石はしばらく沈黙していた。うつむいて考えている表情は、深刻なようにも眠そうにも見える。考えても仕方がないことは考えないタイプらしいから思考停止したのかも知れない。正直言うと、私もこの状況については思考停止したくなってきていた。
今まで既にキロ単位で歩いているのだ。巨大な工場やビル以外でこんな場所を思いつかない。しかも、その間一度も窓を見ていないのだ。
「でも、どこかにドアはあるはず。そこまでは何とか正気を保てるように頑張らないと」
ドアを見つけさえすれば、この異様な場所をただ歩くような時間は終わるのだと信じなければ、とてもやっていけそうにない。そう思っていた。
でも、私達がドアを見つける前に、次の『それ』を廊下で発見することになった。今度は女子の制服ではなく明石が着ているのと同じ男子の制服だ。そして、体の大きさの問題なのか、今度は髪の毛だけではなく肉や骨の一部も中途半端に粘液の中に混ざっていたのだ。
最初に見つけた女子制服の方は、髪の毛だけしか人間の体がなかったから、どれほど生理的嫌悪をそそる有様でも一縷の望みがあった。あれは制服と髪の毛だけが、気持ちの悪い粘液の中に落ちているのだと、無理に思い込めなくなかった。でも、溶けかけた肉や骨が混ざっている時点でいくら何でも無理だ。
服の中から見えている肉、骨からは誰だか解らない。
でも、あの時間にバスから降りて休憩していたのは1年C組の生徒だけ。憶えている子もいる。明石みたいにまだ憶えていない子もいる。でも、同じクラスの仲間の誰かがあんなことになっているのだ。
ふらついた私の肩を明石が支えて「吐く?」と小声で問いかけた。かすかに首を振る。
「ううん、もう何も出ない」
生々しすぎて、ショックを通り越していた。
明石は黙ってうなずくと、私の肩を支えたままで静かに歩き出す。
こんな時なのに、明石が「いつ私が吐き始めるか」を気にしながら歩いていることだけは伝わってきていた。
私にとっても明石にとってもありがたいことに、吐き気を我慢することができた。
それから数時間。ここで初めて瞼を開いた時には想像もしなかった、深刻な眠気と直面することになった。
移動中、溶けかけた『あれ』を発見することもなく、探していたドアも見つからなかったのだ。
どれだけ歩いたのか考えたくもなかった。
「もう限界。寝たい」
スマホも落としたらしく、今の時間も解らないけれどこの場所の明るさは一定だった。ずっと暗いままの場所を歩いていたから時間の感覚はとっくに摩耗していた。
私は明石の返事を待たず、多少広いスペースのある場所を見つけてふらふらと足を進めてへたり込む。
「ごめん。待っててとは言わない。明石はそのまま行ってもいいから……寝、させて」
話している途中に私の意識がふつふつと途切れる。
そのまま眠ってしまいそうになる直前、遠くから明石が何か言ったのが聞こえたような気がした。
次に起きたら明石はいなくなっているかも知れない。
それに、私自身があのどろどろ粘液になって命を終えている可能性もゼロではない。明石がそうなっているかも知れない。でも、ここまで疲れ果てている時にそんなことを考えている余裕はなかった。
ただ眠りたかった。ここが普通の場所では有り得ない現実から解放されたかった。それが数時間だけでも何かの間違いでこれで人生が終わってしまうのでもいい。
もう限界だった。
だからこそ私は自分の体が訴えている、とても大事なことを思い出すのを怠ってしまったのだ。
「おはよう、伊勢崎」
再び瞼を開いた時、横から明石が声をかけてくれる。視界は暗いままのはずなのに、暗さに馴れてしまえばそれほど気にもならなかった。
明石が上半身を壁にもたれさせ、足を伸ばして座っている。私も体をずらし、明石の隣で壁にもたれた。

「あのままここにいたんだ」
「うん」
「隣で溶けてなくてよかった」
「そうだね」
明石は曖昧に笑う。
「私、溶けてない?」
そう言うと明石は笑うのをやめて、真面目に肌が露出している部分を確認し、首を振った。
「溶けてないよ」
「そりゃどうも」
彼の反応は何だか独特なところがある。彼の言葉には言葉通りの意味しかないのに、腹を割って話しているような気もしない。多分こういうタイプの相手には『適切な答えが返ってくる問い』をする必要があるのだろう。
「あのさあ、明石」
ふと思い立ち、私は問いかけることにする。多分『適切な答えが返ってくる問い』ではないだろうけれど。
「あんなの見ちゃった後で、みんなのこと、心配にならないの?」
もちろん私の問いは言葉通りの意味ではない。
昨日の明石からは他の生徒達への心配なんて欠片ほどにも感じなかったし、それを責め立てるつもりもない。
ただ、彼が本当にそんな気持ちを持っていなかったのか、心配していたものの感情が麻痺してしまって自覚もできなかったのか知りたかったのだ。
明石は少し首を傾げて考えていた。
「俺がちゃんと『見た』と言えるのは伊勢崎だけだよ。あとは個別認識もできない」
「クラスで仲のいい子が溶けてたら?」
「見た時考える」
彼の反応はごく淡々としたものだった。
明石にとって、ここで出逢った人間は私だけ。生きた知人として認識されていないから、クラスメートらしい死体を見つけても平気でいられるのだ。生きているクラスメートを見つけた時に、どんな反応をするのか想像もできなかった。もし明石がこういうタイプだというのを校外学習の前に知っていたら、一緒に行動するのをためらったかも知れない。
ただ、彼のこの言動のおかげて必要以上に動転しなくて済んでいる。少しだけ気が楽だった。
「じゃ――私がこの後いきなり溶けてたら?」
低い声で続ける。
見捨ててほしくないという意味ではなく、単に明石が「溶けたクラスメート全般を人間扱いしない」のか確認したかったのだ。その意味を理解しているのか否か全く摑めなかったけれど、明石は予想外の反応を示した。
笑みを浮かべたのだ。どことなく哀れんでいるようだけれど、やさしそうですらあった。
ごまかしや狼狽は全くなかった。
「ないよ」
私があんな風に溶けることを示しているのか、そんな状況になっても見捨てることはないと言おうとしているのか、どちらとも判断ができなかった。理由を問いかける気力も出なかった。
何とかドアを見つけ、ここから出ることができる時に、明石がどんな人間なのかちゃんと知っているのだろうか。そんな未来のことは全く想像ができなかった。
眼を伏せると、明石が不思議そうに私を見下ろした気配がした。
「私達、ここで目を覚ます……でいいのかな。まあ、覚ますまで一度も話したこともないからさ。そこまで断言される理由が解らない」
そう言うと、明石は今度こそものすごく困ったような表情を浮かべて、しばらくの間言葉をひねり出すために必死で考え込んでいた。
その間、私達は黙って歩く。元々明石はそんなに口数の多いタイプではないらしいので、返事のないまま終わるだろうなと思いつつあった頃。
「……展望スペースで伊勢崎が『あれ』を拾ってるところを見たんだ」
小声でそう返ってきた。
私が拾ったはずのパズルのピース。
明石は私がパズルのピースを拾ったのを目撃し、その後私が意識を取り戻した後に、すぐこの話題が出たから『続き』みたいに感じているのかも知れない。
「明石には私の記憶は『続き』なんだよね。私は明石のことを『ここ』からしか知らないのに」
ここを出た後、ちゃんと日常は戻ってくるのか。
この場所で起こっていることを考えると、ここが現実ですらなく、ただの長い悪夢でしかない可能性も充分にあるのだ。夢が醒めた時、明石はちゃんとクラスにいるのだろうか。
「明石」
「うん?」
「……ごめん。いいや」
問いかけたい言葉はあったけど、口に出したら終わるような内容なんて言わない方がましだ。この一日のうちに彼に対する親しみも湧いていたし、生々しく長く続く暗がりの中、たった一人の同行者がそもそも存在していないかも知れないなんて考えたくなかった。
だからただ、先へ歩いた。
この時点で考えておくべきもうひとつの可能性について、その時の私は思いつきもしなかった。
次の『それ』が視界に入ったのは、体感的には数時間ほど歩いた頃だろうか。
「いせだ……ひ……ぁん!?」
不明瞭な発音ではあったけれど、その声に聴き覚えがあった。
「青木?」
床で必死に腕をついて、上半身を起こそうとしていた女子は、校外学習のバスで隣の席だった青木加奈子。
座席が五十音順の配置なので、一番の青木と二番の私は隣だ。それほど親しくはないけれど同じ中学から進学したので、友達というほど親しくなくても、それなりに見知った相手だ。バスの中でも彼女が吐きそうになっていたので私がビニール袋を口に当てて吐きやすいように手伝ったりもしていた。
そんな青木の下半身が今まで見た『それ』と同じように溶け、既に動かすこともままならない状態だった。
必死で体を起こそうとしていた腕も、有り得ない位置で歪み、たわんでしまい、無様に床に突っ伏すのを見て私は駆け出した。
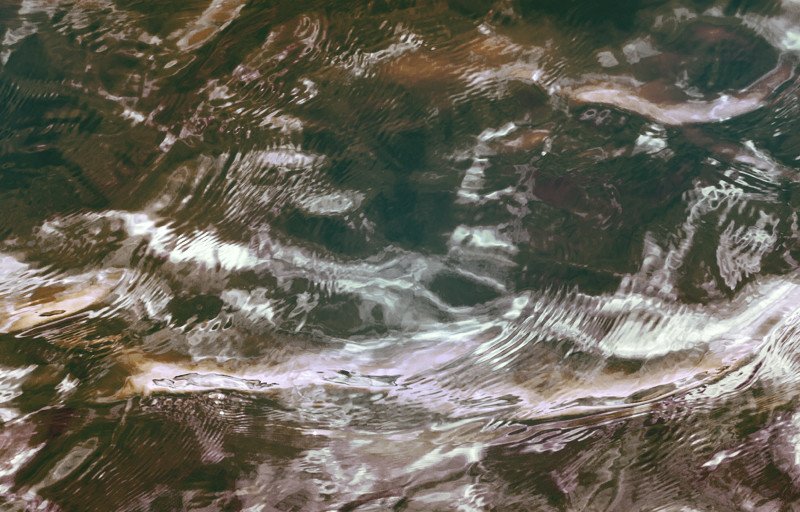
「青木!!」
抱き寄せた青木の体は、本来小太りでがっちりとした体格なのにものすごく小さくなっていた。そして粘液でぐちゃぐちゃになっていて、肋骨のあたりからぽとんぽとんとビー玉大の球が転がり落ちたのが、シャツの布地の中に溜まる。体の形が刻々と崩れ、変わっていく。
「何でこんな……」
溶けていく途中の、個別認識できる知人がこんなことになっているのを見た衝撃のあまり私は半泣きになっていた。
ぬるぬるの粘液のせいで、腕を回した青木の体がずり落ちそうになるのを必死で留める。
床に落としたら青木が痛がる。そんな焦りもあって、肌に絡みつく感触への生理的嫌悪感を忘れていられた。
「明石、ちょっと手伝って。青木のこと、もう少しましな場所に運ぼう?」
暗がりでこの状態の青木が踏まれることも充分有り得るのだ。せめて壁際に運ぶべきだろう。
近づいてくる明石を見て、青木が顔を強張らせる。
「いしぇ……ぁ……ん」
唇の動きから『伊勢崎さん』というのがぎりぎり理解できた。
「そい……ぅ……ぁれ」
そいつ、誰。
粘液で顔の皮膚が溶けかけた青木の顔に浮かんでいたのは、恐怖。眼の周りの粘液が涙のように見えた。
「誰って、明石だよ。同じクラスの――もしかして暗くて見えない?」
「……んぁやうっ、いあいっ!!」
たったそれだけを叫ぶのに、青木が渾身の力を使ったのは間違いなかった。
私の腕の中、青木の体が大きな魚を支えているみたいにしなり、溶けた下半身からあの球がぼとぼと落ちる。
その球が床でぐしゃりとひしゃげる音がした。
聞き取ることが既に困難だった。でも私は青木の唇の動きを見てしまっていた。間違えようがない。
『そんなやつ、いない』
その意味を理解して、私は――今まで見た『それ』や青木の有様を見た時以上の衝撃で、数秒硬直した。
後ろにいる明石を振り返ろうとした時。
「伊勢崎を無駄に脅えさせないでくれ」
明石の、今まで聴いたことのないような、感情が欠落した声が響く。
彼の気配はいきなり消え、突如前に出現する。大体一秒くらい、明石の体は半透明に見えていた気がした。
半透明の明石が青木の胸のあたりに手を当て――そのまま肋骨に指が吸い込まれる。そして青木の姿は水が爆発したように飛び散り、最初から存在していなかったかのように消え失せた。
飛び散った青木のゲル状の飛沫が私の顔や胸、腹部をどろどろと流れていく。肉も骨も感じ取れない、重たい粘液はただあたたかく苦しい。
粘液のせいでまともに視界が効かないでいると、明石がおずおずと私の顔を掌で覆う。青木と同じことをされるかと思ったけれど、顔をそっと拭われただけだった。
その間に、あることを思い出す。
(ああ、五十音順――そうだよ)
もし明石が同じクラスにいるのなら、私は青木と隣の席に座っておらず、通路を挟んで明石と隣。私は市村(いちむら)という女子生徒と隣になっていたはずだ。
明石香積なんて生徒はうちのクラスにいない。憶えていなかったのではなく、そもそもいないのだ。なら、私の顔を困ったように拭ってくれている、眼の前にいる彼は何者なんだろう?
ぼろぼろと、みっともないほど泣いていた。
そして呼吸が苦しいほど涙を流しているうちに、私の体は急に重たくなり、制御を失って崩れ落ちた。

展望スペースに涼しい風が吹いていた。
吐いた後にもつらそうだった青木を、公衆トイレまで案内した後、私はぼんやりと暇をつぶしていた。石畳に落ちていたそれを見つけたのは退屈だったからだろう。
パズルのピース――だと思った。
生成り色で、陽光で色あせたパズルのピース。
私はそれを何の気なしに拾う。
その時、遠くから悲鳴が聞こえたような気がした。
「伊勢崎さんっ!!」
そう叫んだのが誰の声かは解らない。
その直後に耳腔が圧迫され、口や鼻を逆流する何かが私の喉をこじ開ける。これが水なら肺に溜まった空気を吐き出すこともできただろうけれど、自分ごと世界が葛湯で埋め尽くされていくような感じだった。
体が重く、苦しい。
視界が淡く濁り、何も見えない。
それなのに、ものすごく近くから誰かの声がした。
何となくほっとしたような、面映ゆいような響き。
『ああ、あったんだ』
その声は外からではなく、私の体全体がスピーカーになったような感じで肉や骨を震わせていたのだ。
何かが細胞に染み渡っていく。
それはゆるやかに私をまどろみに連れていく。
でも、それが何なのか解らないままだった。
あの時も、今も。
私が瞼を開けた時、ここに来てからお馴染みのやさしい暗がりが広がっていた。完全に眼が馴れてしまったのか、それすら心地よく感じられる。
しばらくの間、私の意識はおぼろげで倒れる前のことをまともに思い出せずにいたけれど、青木がどうなったのか気になって慌てて身を起こした。
「青木っ」
「……あ」
近くで明石の声がする。勢い余ってそれとほぼ同時に前へとつんのめり、ぎりぎりのところで手を引かれて顔面から床に激突せずに済んだ。そのまま明石が私の体を支え、上半身を起こして座らせてくれる。
青木の姿はどこにもなかった。今までのように服すらもなく、最初から存在していないかのようだった。
「もしかして私のことを移動させた?」
「あのままだと伊勢崎の体が不安定になりそうだったから、移動させずに寝かせておいた」
なら、消えたのは青木の方なのだ。服や骨、肉の破片どころか、飛び散った体液ごと消えてしまったのだ。
「青木、もういないの?」
「うん」
「他のみんなは?」
「伊勢崎がショックを受けてつらそうだったから、全部使った」
意識を失っている間に思い出した、展望スペースでのことを鑑みると、人間が『使う』ことのできる用途ではないことくらいは想像できる。
だから、私が問うたのはもっと切実なことだった。
「私、生きてるの?」
「俺が生きてるのと同じ程度には」
「明石は……生きてるの?」
問いかける声がおのずと小さくなった。
どう考えても彼は普通の人間では有り得ないのだ。
そんなことを問うこと自体が、明石を傷つける可能性もなくはなかった。
でも、明石はさして気を悪くした様子もなく続ける。
「人間の体を持ってるのかと訊かれたら、違うと答えるしかないだろうけど、生きてる」
明石は半透明で流動することが可能な体で、溶けかけた相手に対してではあるものの、人間の体を爆散させることができたのだ。
思い出してみれば、私自身も目覚めてから一度も食欲も感じず、トイレに行きたいとも思わなかった。水すら欲しくならなかったのだ。今もそうだった。
「じゃ、私は今までの、人間の体を持った私じゃないんだね。明石も人間の体を持ってないんだね」
掌で自分の腕や顔、胴体を撫でてみても、以前と全く変わらない体のように思える。問題なく動かせるし体感も変わらない。でも『これ』は人間の体ではないのだ。
ついさっき私を起こしてくれた明石の体も、人間とは違う何かなのだ。
ものすごく変な気分だった。溜息をつく私を見て、明石は少し困ったように考え込んでいる。多分、私に説明する内容を真面目に考えているのだろう。
少なくともその様子からは、明石が推測することもできないほどかけ離れた存在のような気はしなかった。
ややあってから、明石は私に向き直る。
「何も残ってない訳じゃない。俺も、伊勢崎も」
そう言うと明石は私の右手を摑んで、おもむろに私の胸の合間に――埋め込んだ。
肋骨のところではね返されもせず、二人分の手はさしたる抵抗もなく体内に呑み込まれていく。表面に触れた時とは全く違う、あたたかくてぷるぷるのゼリーみたいで、何だか不思議だった。でもちょうど心臓のあるはずの位置で、指が触感の違うものに当たる。小さくて硬い何か。この位置からは見えないのに、私が展望スペースで握ったパズルのピースなのだと理解した。
「それは明石香積の欠片。展望スペースから落とされた時に欠けた頭蓋骨」
なくしたのではなかった。こんな形ではあるけれど、ずっと持っていたのだ。
本当なら、そんなものが自分の体に入れ込まれていることをおぞましく思うべきだった。そしてそれ以上に、今の自分の体に対してもっと衝撃を受けるべきだった。『俺の欠片』ではなく『明石香積の欠片』と言ったのがどんな意味なのか考えれば号泣してもいいくらいだ。
でも彼の声が少しだけ寂しそうに、淡々と響くのを聞いていたら、そんな感情に成長する何かは消え失せる。
「私の体の、残ってる部分は?」
「こっち」
空いている左手を、今度は明石の胸に潜り込ませる。
同じようにぷるぷるとしたゲル状の中で指を導かれ、あるものに触れた。どこにも繋がっていないだろう私の心臓が収縮している。自分の心臓をつぶしてしまいそうな気がして、指先をそっと這わせるしかできなかった。
そして、その鼓動が指先に伝わるのが妙に気恥ずかしくて、ちょうどいい言葉が出てこない。
「動いてる」
「動いてなかったら嫌かなと思って」
嫌かどうかとは関係ない、何となくあたたかい気持ちで、明石の体内で脈打つ、本来自分のものである心臓に触れている。そんな気持ちを悟られたらものすごく間が悪い気がして話をそらす。
「そう言えば……全部『使った』って、何に」
「伊勢崎に」
たった一言で理解できた。
この、互いに内蔵を触れ合える、人ではない組成の体をもう一人分作るために、あんな風にクラスのみんなが溶かされたのだ。明石が私のことを、こんな形で留めておこうと思った理由は解らないけれど、クラスのみんなは私の『この』体を作るために死んだのだ。本来ならここに連れてこられた全員に土下座し、何度死んでも足りないくらいの状況だったけれど、ここにはもう私と明石しかいない。詫びるべきみんなはいない。
この居心地のよい暗がりの中、存在していた痕跡すら消えてしまったクラスメート達のことを忘れないでいられる自信は全くなかった。
別に元の生活に戻らなくてもいい。
日常に戻るためのドアなんて要らない。
もちろん明石と一緒に向こうに戻れる未来があったら学校で何でもないことを話したり、一緒に遊びに出かけたりして、少しずつ彼を知っていくことができる可能性だってなくはない。でも、今の私にはそんな未来なんて想像もできないほどかけ離れた絵空事でしかない。
明石が作った私の体は、この暗がり以外の世界なんて知らない。明石以外のみんな消えてしまったこの場所が今の『私』の唯一知っている世界なのだ。
だったらそんな場所は要らない。明石と私の日常は、この暗がりの中でも手に入る。
明石の欠片が私の心臓のあるべき部分にある。
私の心臓が明石の心臓のあるべき部分にある。
こうして二人で交わし合ったものに触れ合える。
それだけで、かつてあった世界なんてまとめて架空の世界に追いやってもいい。そんな気持ちで今この暗がりの中、互いの生きていた痕跡をどこへも行けないままで触れ合えている。
それなら私達以外の全てが溶かされて消えても、他の誰に逢えなくても、私達の時間が多すぎる屍の上に築かれているとしても問題なんてない。
私の欲しい『続き』はこの暗がりの中にあるのだ。
館山の物語を気に入ってくださった方、投げ銭的な風情でサポートすることができます。よろしかったらお願いします。
