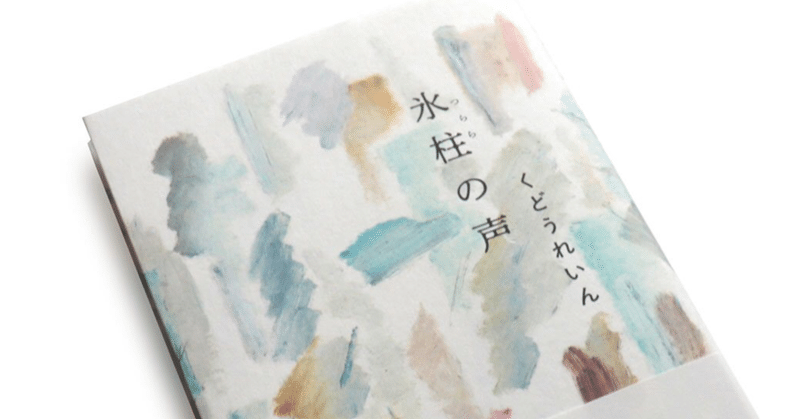
『氷柱の声』
2021/10/26
くどうれいん,2021,講談社.
良い。新鮮…!
『貝に続く場所にて』も震災文学で、あれはもっぱら大きな出来事との距離をめぐる話だと解釈したけど、こちらにも距離とか痛む資格みたいな話が出てくる。わたしもけっこう長らく、正しく傷つくとか、誠実に語るとかいうことを考えている。
そのほかにも、物語として消費されるとか、わすれたくないとか、個人的にぐっとくるテーマがあって、そういうテーマ自体が良いというより、そういうテーマへの触れ方、目の向け方が細やかでいやらしくなくない。そこが良い。水溶液みたいに入ってくる。(単行本の表紙の色味が良すぎるよ。そうそうそうそうってなる。)
物事へのむかつき方とか呆れ方とか違和感の抱き方とかが、なんか、しっくりくる。わかんないけど、作者と私の頭の回し方が似てるような気もする。
人物が次々と登場してきて、そのだれもが魅力的。思ったのは、なんか、みずみずしいんだ。不用意に感傷的じゃなくて、だからといってドライにすさんでもいなくて、欺瞞っぽく輝いてもいなくて、哀しくて、明るい。
登場人物たちの言葉を聞いていて、自分も生きていけそうな気がするよ、仲間を得たような。
部活の後輩にも薦めようと思った。最後の大会とコロナが被った世代で、頑張ろう的なメッセージのある作品が下駄を履かされたというか、そのせいで悔しい思いをしてる子で、その作品はとてもとても良かったから、わたしも悔しかった。
大きな出来事があって芸術の評価基準が曲がったと思う。そんなことも書かれてあって、読んでほしいと思った。
この小説が芥川賞候補に挙がったのは震災10年という時代背景がもちろんあるけれど、だからといって下駄だと言われたくないな。
**
追記しだしたらきりがないので、ひとの言ってたことは胸にしまって、自分の考えたこと多めのリアぺだけ貼っとく。
あっさり読めてしまうことをどう評価するかについて、希望的な結末に批判が向いがちでしたが、授業で得た知見としては、再考すべきは終盤の内容よりも全体の形式であるように思いました。形式だけでなく、良くも悪くも一読して満足できる重量感は、群像劇に似ていると感じます。純文学の領域で評価されるには奥行きが足りないという指摘も頷けました。
一方で私はこの作品が持つみずみずしさを高く評価しています。不用意に感傷的でなく、だからといってドライにすさんでもいなくて、欺瞞っぽく輝いてもおらず、違和感や哀しみに目を向けながらも、明るい。
綺麗事であることを恐れずに語っていく姿勢は新鮮な印象さえ受けました。重いテーマにどう向き合うかについて、重いテーマを重く扱うほかに、重いテーマにユーモアを添えるといった戦略はよく見られますが、それとは違うやり方で希望を示していく姿勢に好感を覚えます。いくつかの選評に対して、文壇のほうがむしろ希望的な結末に過剰に怯えすぎなのでははないかという疑問を抱きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
