夜、12時ごろ、昔の自分の部屋で (1905字)
 最初の部屋にいた頃、私は現実のリハーサルをしていたのかもしれません。極度に反復的な構造を持ち、高密度で、官能的で、血肉に明らかな変容を強いる長い儀礼です。自分を洗脳するための正統な手続きと言い換えてもよいでしょう。
最初の部屋にいた頃、私は現実のリハーサルをしていたのかもしれません。極度に反復的な構造を持ち、高密度で、官能的で、血肉に明らかな変容を強いる長い儀礼です。自分を洗脳するための正統な手続きと言い換えてもよいでしょう。 しかしそれに対応するはずの現実は、とても奇妙で、毒性があり、最初から最後まで謎と偶然に満ちていて、最初から最後まで全貌が隠されたままの迷宮です。誰にとっても平等に。
しかしそれに対応するはずの現実は、とても奇妙で、毒性があり、最初から最後まで謎と偶然に満ちていて、最初から最後まで全貌が隠されたままの迷宮です。誰にとっても平等に。 私は物語の中で育ちました。具体的な脅威はすべて空想の領域に押し込められ、混乱や競争や暴力といったものはすべて想像上のものでした。編集された誰かの記憶と自分の人生を明確に区別することは事実上不可能で、どこかの誰かが成し遂げた偉業はすべて私にも実現可能なはずでした。むやみに巨大で荒唐無稽な物語の中を目的もなくさまよう魂、それが当時の私です。ごく幼い頃から郷愁めいたものを感じ続けていたのもそのためでしょう。
私は物語の中で育ちました。具体的な脅威はすべて空想の領域に押し込められ、混乱や競争や暴力といったものはすべて想像上のものでした。編集された誰かの記憶と自分の人生を明確に区別することは事実上不可能で、どこかの誰かが成し遂げた偉業はすべて私にも実現可能なはずでした。むやみに巨大で荒唐無稽な物語の中を目的もなくさまよう魂、それが当時の私です。ごく幼い頃から郷愁めいたものを感じ続けていたのもそのためでしょう。 やむなく最初の部屋を捨てることになったとき、私の半分は夢見たままになり、残りの半分は永遠に冷たくなりました。
やむなく最初の部屋を捨てることになったとき、私の半分は夢見たままになり、残りの半分は永遠に冷たくなりました。 生き残った半分の私はさらに分裂して2人になりましたが、複雑に混じりあって結局は1人のように観測されます。私はいつもメランコリックで穏やかです。半分の私がもう半分に向かって言います。「誰かに似てるね。少しも思い出せないけれど」。もう半分はこう言います。「何かが消えたね。少しも惜しくないけれど」
生き残った半分の私はさらに分裂して2人になりましたが、複雑に混じりあって結局は1人のように観測されます。私はいつもメランコリックで穏やかです。半分の私がもう半分に向かって言います。「誰かに似てるね。少しも思い出せないけれど」。もう半分はこう言います。「何かが消えたね。少しも惜しくないけれど」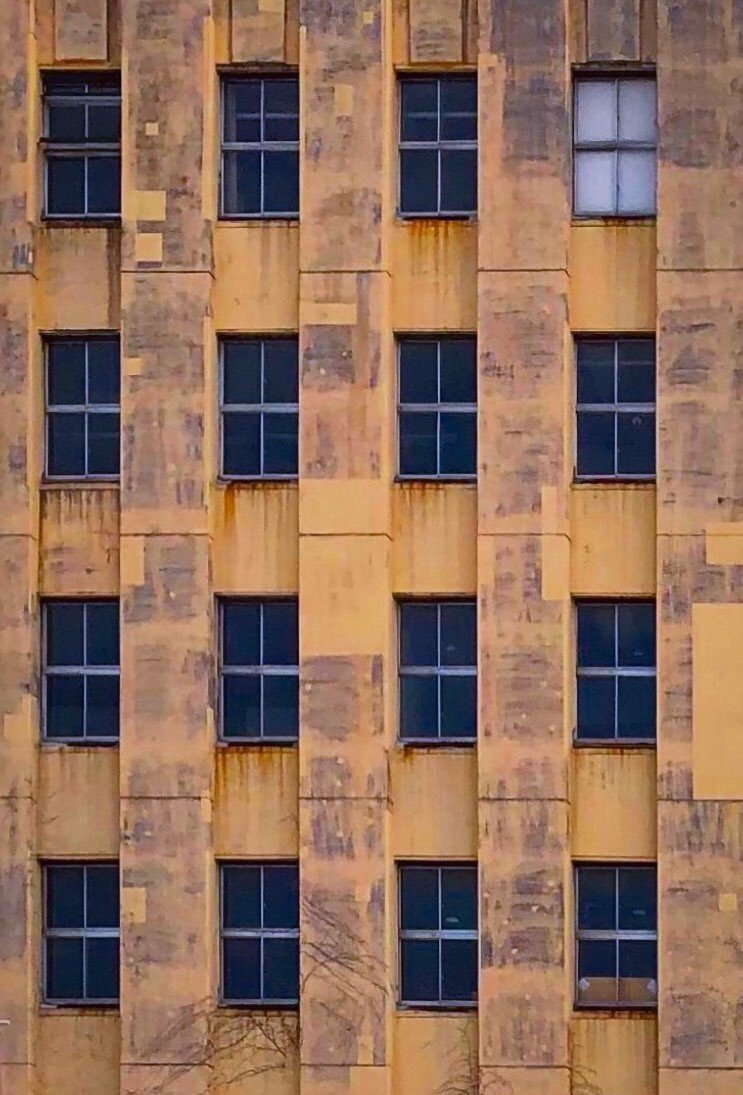 部屋を捨てたあとの私は、完璧にランダムな数字を打ち続けるダイスの目にとても従順でした。完璧なランダムなどというものが本当にこの世に存在するのであれば。いずれにしろ、結果としてそれはたいして無節操ではありません。むしろほとんど動きがない。たいていの場所で私は居心地の良さを感じていましたが、それは私がどこにいても、誰にとってもよそ者だったからです。私は何かの抜け殻にしか見えなかったことでしょう。私の半分はたしかに空虚でしたし、もう半分には現実と架空の境界線が見えていませんでした。
部屋を捨てたあとの私は、完璧にランダムな数字を打ち続けるダイスの目にとても従順でした。完璧なランダムなどというものが本当にこの世に存在するのであれば。いずれにしろ、結果としてそれはたいして無節操ではありません。むしろほとんど動きがない。たいていの場所で私は居心地の良さを感じていましたが、それは私がどこにいても、誰にとってもよそ者だったからです。私は何かの抜け殻にしか見えなかったことでしょう。私の半分はたしかに空虚でしたし、もう半分には現実と架空の境界線が見えていませんでした。 「最もピュアな音楽とは、金のために再結成した、まともに動けないほど太り切ったロックバンドが鳴らす雑音のことだ」私の半分が皮肉っぽい調子で言い、振りかぶって、第1球を投じます。凄まじい轟音とともにボールがミットに叩き込まれると、もう半分が言い返すのです。「ところが最も素晴らしい球は、たったいま初めて野球のボールを握った、ルールも知らない女が偶然投げたスプリットだ」
「最もピュアな音楽とは、金のために再結成した、まともに動けないほど太り切ったロックバンドが鳴らす雑音のことだ」私の半分が皮肉っぽい調子で言い、振りかぶって、第1球を投じます。凄まじい轟音とともにボールがミットに叩き込まれると、もう半分が言い返すのです。「ところが最も素晴らしい球は、たったいま初めて野球のボールを握った、ルールも知らない女が偶然投げたスプリットだ」 最高の瞬間は過去にしか存在しない。思い出以外のどの場所を探しても結局は徒労に終わる。最初の部屋にいた頃に血を吐くほど会いたかったあの人には、現実の世界ではついに出会えなかった。私の推進力にもう科学的な根拠はありません。おそらく他人の自己陶酔に自分を重ねてしまえるような無邪気さを、私は最初の部屋で使い切ってしまったのです。それは夢見たままで生きていこうとする人間には致命的な欠陥だったかもしれません。
最高の瞬間は過去にしか存在しない。思い出以外のどの場所を探しても結局は徒労に終わる。最初の部屋にいた頃に血を吐くほど会いたかったあの人には、現実の世界ではついに出会えなかった。私の推進力にもう科学的な根拠はありません。おそらく他人の自己陶酔に自分を重ねてしまえるような無邪気さを、私は最初の部屋で使い切ってしまったのです。それは夢見たままで生きていこうとする人間には致命的な欠陥だったかもしれません。 ときどきあの部屋のことを思い出します。そこにあった大量の物語を。精密な青写真を。生々しい幻覚を。ほとんどが私の生まれる前から存在した物語で、それは私自身が生み出した物語と完璧に不可分です。圧縮された膨大な時間のどこかで、誰かが私にささやいた言葉を今も忘れることができません。「とてもおきれいですね」。それで私は本当にきれいになろうと思ったのです。
ときどきあの部屋のことを思い出します。そこにあった大量の物語を。精密な青写真を。生々しい幻覚を。ほとんどが私の生まれる前から存在した物語で、それは私自身が生み出した物語と完璧に不可分です。圧縮された膨大な時間のどこかで、誰かが私にささやいた言葉を今も忘れることができません。「とてもおきれいですね」。それで私は本当にきれいになろうと思ったのです。 みるみるうちに何もかもが終わってしまいました。どうしようもない気分ですべてが砂になるのを見つめてきました。すべての愛は排水溝に流れてしまって二度と取り戻すことはできません。ですが、それだけがせめてもの救いです。
みるみるうちに何もかもが終わってしまいました。どうしようもない気分ですべてが砂になるのを見つめてきました。すべての愛は排水溝に流れてしまって二度と取り戻すことはできません。ですが、それだけがせめてもの救いです。 思い出は都合の良い嘘ばかりです。思い出は選択しなかった分岐のシミュレートばかりです。思い出は私を殺す真実ばかりです。永遠に冷たくなった私の半分は、今も律儀に私のもう半分を冷やし続けています。だけど残りの半分は夢見ることをひとときも忘れていなかったのです。浮かぬ顔で。悲劇的なやり方で。電気信号のような祈りとともに。
思い出は都合の良い嘘ばかりです。思い出は選択しなかった分岐のシミュレートばかりです。思い出は私を殺す真実ばかりです。永遠に冷たくなった私の半分は、今も律儀に私のもう半分を冷やし続けています。だけど残りの半分は夢見ることをひとときも忘れていなかったのです。浮かぬ顔で。悲劇的なやり方で。電気信号のような祈りとともに。 耳を澄ますと聖歌が聞こえる。いつでも。どこからか。どこかの校庭で子供たちが歌っているのだ。いつでも。どこかの校庭で。世界が大きくなる前に小さな服で踊っていられた可愛らしい時代。ファミリーレストランのちょっとしたおもちゃのショーケースが輝いて見えた。今はもうどこにもない、昔の自分の部屋で今夜は眠ろう。幽霊のように透けて見える過去。全てがはりぼてのように微笑ましくて安らかだ。「だけど現実はもっと恐ろしく、もっと美しいのです」「きっと、誰にとっても平等に」。憂鬱なフロウで。性懲りもなく。排水溝に向かって。祈ろう
耳を澄ますと聖歌が聞こえる。いつでも。どこからか。どこかの校庭で子供たちが歌っているのだ。いつでも。どこかの校庭で。世界が大きくなる前に小さな服で踊っていられた可愛らしい時代。ファミリーレストランのちょっとしたおもちゃのショーケースが輝いて見えた。今はもうどこにもない、昔の自分の部屋で今夜は眠ろう。幽霊のように透けて見える過去。全てがはりぼてのように微笑ましくて安らかだ。「だけど現実はもっと恐ろしく、もっと美しいのです」「きっと、誰にとっても平等に」。憂鬱なフロウで。性懲りもなく。排水溝に向かって。祈ろう