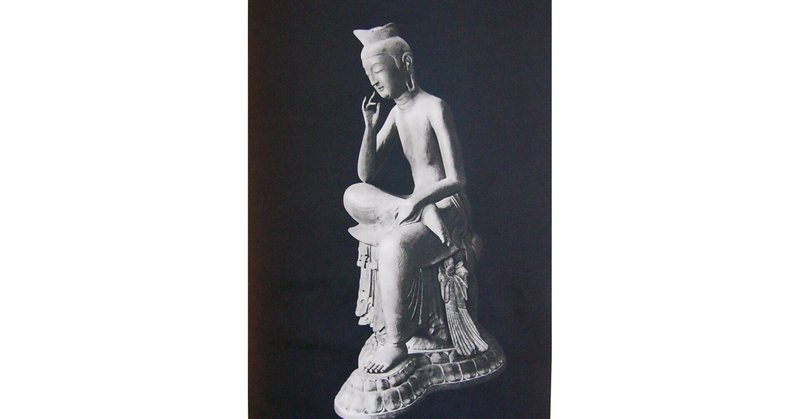
十二支縁起
はじめに
仏教には十二支縁起という考え方がある。これは仏教の本質であり、非常に重要な考え方なので、ここで説明したい。簡単に言えば、カテゴリーを横断する思考法である。
十二支とは次のようなものである。
無明によりて行があり、
行によりて識があり、
識によりて名色があり、
名色によりて六処があり、
六処によりて触があり、
触によりて受があり、
受によりて愛があり、
愛によりて取があり、
取によりて有があり、
有によりて生があり、
生によりて老病死がある。
これら十二支が因果関係によって結ばれているのだが、十二支はそれぞれ異なるカテゴリーに属している。
識→名色→六処
まず識から見てゆこう。ここがおそらく十二支の起点である。識とは認識である。識から名色が生じるということは、認識から名前が生じるということである。というのも、我々がものを名付けることができるのは、それを認識することができるからである。もしも、ウサギとニワトリを区別できない人がいたならば、ウサギという言葉もニワトリという言葉も使うことはできないだろう。我々は、それぞれのものを識別できるから、それらを別々の名前で呼ぶことができる。石を石と呼び、木を木と呼べるのは、それぞれのものを区別できるからである。これが、識から名が生じるということである。
では、名色の色とは何か。それは、それぞれの名前に対応する実体があるということである。ウサギという言葉には、現実に存在するウサギという生き物が対応している。名前には対象があり、それを色と呼ぶ。このように、認識から名前が生じ、名前に対応する実体が生じる。
では、名色から六処が生じるとはどういうことか。我々は先ほど、認識から名前と実体が生じると言った。では、我々はどうやって物を認識したのか。それは感覚器官を通してである。ウサギを見るためには目が必要であり、ウサギに触るためには手が必要であり、ウサギの肉を味わうためには舌が必要である。そのように、対象を認識するためには感覚器官が必要である。
この考察から分かることは、我々は、認識される対象の存在を通して、認識を可能にする感官の存在に到達する、ということである。我々が感官を認識するのは、必ず認識される対象を認識した後のことである。ものを見ることを知る前に、目の存在を知ることはできない。それが、名色から六処が生じるということである。
取→有→生
この先、六処から触、触から受、受から愛、愛から取はそれほど難しくないだろう。だが、取から有、有から生は少し分かりにくいかもしれない。取は執着のことである。有はおそらく常見に近いものだろう。対象を愛し執着することから、それが永遠に続くものだという思いが生じる。それは強迫観念に近いものであり、自分の依存する対象が存在しなくなってしまうことに対する怖れである。その怖れを打ち消すために、それが永遠に存在し続けると思い込もうとする。それが有である。
そして、有によって生の世界が生じる。それは存在するものの世界であり、いわゆる世間である。おそらくこの生は、自分自身の生ではない。そうではなく、我々が生きているこの世界を生と呼んでいるのであろう。それは、識から始まる認識と名前とによって、我々が作り上げた対象の世界である。我々が生きるために作らざるをえなかった、概念と存在の集合である。
識←行←無明
では、そもそもどうして識が存在したのか。どうして我々はものを認識してしまったのか。そこには意志があったからである。それは生への意志であり、生きることへの欲求である。我々は生きるために食べなければならない。食べるためには認識しなければならない。どんな生き物でも、生きてゆくためには認識が必要である。アメーバも餌の存在を認識し、その方向へ動いてゆく。生きるために認識が生じる。その生への意志を行と呼ぶ。ゆえに、行から識が生じると言う。
では、行はどこから生じるのか。生への意志はどこから生じるのか。それは無知そのものである。我々の生の世界は認識から生じる。認識から名前と実体が生じ、名前と実体から感官が生じ、感官から感受が生じ、感受から快・不快が生じ、快・不快から執着が生じ、執着から存在が生じ、存在から世界が生じる。この因果関係について無知であることから生の世界への欲求が生じ、さらに認識が生じるのである。
老病死
このように十二支の連続によって不断に生の世界が生じ、無知が生じる。その慌ただしさに翻弄されるうちに、人は老いて死ぬ。これが十二縁起の全てである。カテゴリー云々という最初の話とは結び付かなくなってしまったが、因果関係の複雑さについては、何となく感じとってもらえたのではないか。
ギリシャ哲学との関係
十二支の中で最も劇的なのは、取から有が生じる部分であろう。ここには仏教の神髄が表現されている。十二支の十番目で、初めて存在が現れるのである。何かが存在するということを、これほど明確に表現した思想はないだろう。そして、それが幻想に過ぎないことも余すことなく示されている。十二縁起が示しているのは、存在によらない思考法であるとも言える。
また名色については、心と体という解釈もなされている。それも間違いではないが、ここで述べたような解釈をすると、ギリシャ哲学との比較が容易になる。アリストテレスの術語を用いれば、名は形相であり、色は質料である。ここに、インド=ヨーロッパ語族に特有の思考の型を見出すこともできる。詳しくは「空の論証」を参照のこと。
名色が心身という解釈が成り立つのは、心が名前だけのものだからである。心には実体がなく、名前としてしか認識されない。その名前の器として身体があると考えれば、心身を名色ととらえることができる。
因果関係について
歴史と科学は似ている。なぜならば、どちらも事実を扱うからである。一方で、哲学や経済学、法学などは一種のフィクションである。
歴史においても科学においても、最も重要なことは因果関係を把握することである。ある出来事がどうして起きたかを説明するということは、その出来事が生じた原因を明らかにするということである。
因果関係は必ずしも時間的な前後関係を意味しない。なぜならば、時間は名前だけのものだからである。時間は十二因縁によって作り出された有の一種であり、それ自体因果関係の中にある。一方で、因果律は現実そのものである。それは作られたものでもなく、作られないものでもなく、存在するものでもなく、存在しないものでもない。それは存在を作り出すものであり、存在よりも前にあるものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
