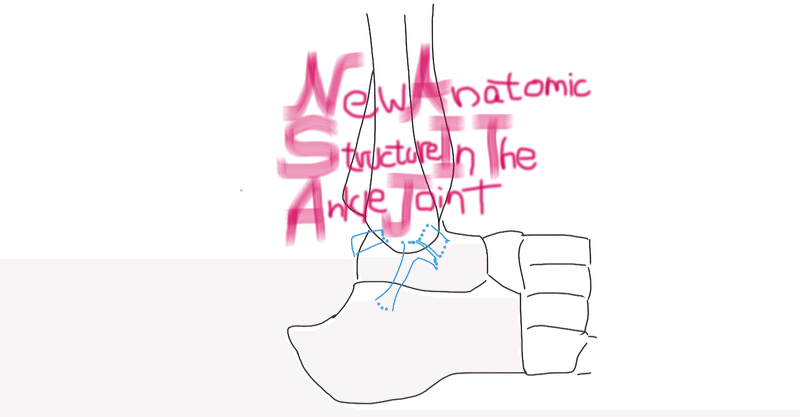
New anatomic structure in the ankle joint
どうも、あやです。
どんな一日を過ごしましたか?
岡山は天気も良く最高の一日でした。
私は日曜日に同僚がくれたサンマルクの飲み物半額券を使いたくて、20%還元のpaypay沼にまんまとハマりたくて普段はいかないサンマルクカフェに約5時間滞在しました。使用したお金は180円です。ありがとうございました。
さて、今日は件名にある研究論文を再度読み直したのでここにアウトプットさせていただきます。
画像は使っていいのか分からなかったので、手書きです。
ではスタート。
足関節外側側副靭帯にあたる前距腓靭帯は上部線維と下部線維が存在。前距腓靭帯上部線維は関節内にあり、非等尺性構造で、背屈で弛緩し、底屈で緊張する。前距腓靭帯下部線維は踵骨靭帯と共に弓状線維で統一化され、外側腓骨踵骨複合体を形成する。これらは関節外にあり、等尺性構造で常に緊張し足関節のどのようなポジションでも安定性を保たれている。解剖学の教科書によれば、足関節の靭帯は外側側副靭帯と内側側副(三角)靭帯からなる。しかし新たな靭帯結合であるLFTCLをUB(UB: University Barcelona) 研究チームが定義した。この結果はKnee surgery, Sport traumatology, Arthroscopy, で公表された。この仕事はUB Jordi Vega, Francesc Malagelada, M Cristina Manzanares とMiquel Dalmau Pastorにより発見され、私が思うことはただ一言、感謝!!
1つの構造として2つの靭帯の線維結合
足関節外側側副靭帯は捻挫で損傷する靭帯の1つです。多くの人は捻挫後の慢性的な痛みとそれに伴い発生する他の捻挫に苦しんでおり、これらがなぜ起こるのかはまだ明らかにされていません。しかし「この欠落があったからこそ解剖室で靭帯解剖するという変化のカギとなり、私たちは靭帯間の結合が靭帯ではなく線維であったため解剖書から取り除かれていたことをみた。」とMiquel Dalmau pastor, 発生学と解剖学ユニット研究者、UBの病理学・実験治療学専攻らにより唱えられました。この線維は外側靭帯の3つの構造の内2つの靭帯である、前距腓靭帯下部線維と踵腓靭帯を結合している。Dalmau pastorは「この結合は両方の靭帯が機能的なユニットになっているのに反して今まで1度も説明されたことがなかった。私たちはこれらの2つの結合された靭帯を解剖学的構造として外側腓骨踵骨複合体と呼ぶ。」といった。この記述で前距腓靭帯と踵腓靭帯の損傷症例の前距腓靭帯単独損傷に対する良好な結果が得られたことがいくつかの臨床論文と一致した。Jordi Vagaは「これは前距腓靭帯修復中に踵腓靭帯の修復も可能であるかもしれないことと、これが靭帯間に何らかの繋がりがあった時のみ可能かもしれないことを私たちに考えさせた。」とnoteした。
足関節捻挫の発展と治療の関係性
足関節の念入りな解剖は前距腓靭帯が関節内構造であることを明らかにした。この研究によると前距腓靭帯は上部線維と下部線維の2つの線維膜を形成しており、上部は関節内、下部は関節外に存在する。下部線維は踵腓靭帯と共に外側腓骨踵骨複合体を形成し関節外構造になる。前距腓靭帯の1部が関節内構造であることを記述することはこの種の損傷に対する進展と治療の関係性があることを持つ。Miquel Dalmau-Pastorは「これらの発見は関節内靭帯損傷後の反応(作用)と類似していて、ツイル(あや織り)のようで、瘢痕組織修復ができず、関節の不安定感を残存させるため患者は他の捻挫や関節痛を引き起こす可能性が高くなる。」と供述している。解剖学的観察とは別に靭帯の作用の研究がUBの研究院により行われた。Maria Cristina Manzanaresにより「前距腓靭帯の上部線維は関節内であることを除けば、等尺性構造ではなく背屈で弛緩し底屈で緊張する。しかしながら、前距腓靭帯の下部線維は弓状線維で踵腓靭帯と結合しており、関節外にあり等尺性構造であるため常に緊張を保っている。」と締めくくられている。
↓URL
等尺性であるか非等尺性であるか、連結しているか否か、関節内か外かによって評価による損傷の仮定や施術プロセスに変化が出てきますね。解剖も不変的で常に新しく発見されるということを知れるいい機会になりました♬ とても面白い記述でした。丁寧に靭帯解剖をしてくれた方々に感謝感謝です。しかし、どれくらいの期間いくつの足関節を解剖したのか知れると尚、信憑性が出てくるのになぁなんてつぶやいておきます。施術に関しては可動域をどれくらいの期間で出すのがベストなのか、圧痛部位により前距腓靭帯の単独損傷といえるのか複合損傷といえるのか評価判断に役立てそうな部分が多々ありより一層仕事が楽しくなりそうです。またエコーの見方も変わりますね!
このような靭帯構造から、テーピングを施す際に靭帯を守るために制限をかけたい動作、動きを出すためにかけたくない動作を試行錯誤できそうです。
次回も何か学術論文を読んで発信しようと思います。
Thank you for reading
Have a nice day! See you soon!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
