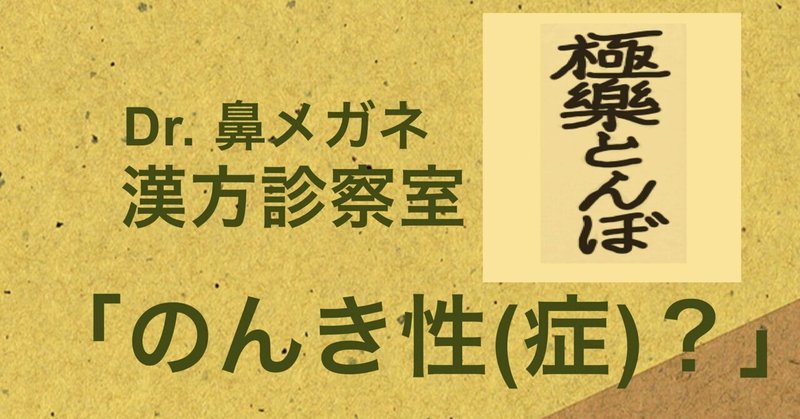
のんき性(症)?
私は学生のころ母親から、極楽とんぼといわれたことがある。と言っても漫才の話ではありませんが。まあ、それほど気楽にやっているつもりもなかったのだが、母の眼にはのんきにやっているように見えたのだろう。こののんきを漢字でかくと「呑気」となる。もともとは暖気と書いて、中国では温かい気候を意味していたそうだけど、日本では暖かい季節には外でゆっくりする人が多かったのか、遊山のいみや、気晴らしの意味が入り、そのうちのんびりした人の性格を表すようになったらしいですね。気を呑みこむとかいた呑気はどうやら当て字らしいです。
医療分野では呑気と書けば、まさに空気を呑みこむことを表しており、やたらと空気を呑みこんでしまいお腹が張ったり、げっぷが出たり、おならが多かったりという場合、呑気症という病名がついたりします。この場合は、のんきではなくどんきと読むわけです。
呑気症の方の胃や腸の中のガスを減らしてあげようとして、整腸剤や消化管ガスを吸収させるようなお薬を使ってもなかなか効き目は出ません。検査で異常がない場合、ストレスが原因になっていることが多いといわれ、心療内科での診察が一般的には勧められます。もちろん、ストレス解消を図ったり、歯をかみしめる癖のある人は歯医者さんで相談するのも良いと思います。また、早食いの癖があるのなら、改めたほうが良いでしょうね。
もし漢方を使うのであれば、空気が入ってお腹が張るような状態は、気のめぐりが悪いと考えて処方薬を考えるのが良いと思います。気をめぐらせる、理気剤の出番です。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)や香蘇散(こうそさん)といった理気剤が第一選択になると思います。ただし、お腹が冷えているような人には大建中湯(だいけんちゅうとう)を合わせたほうが良いこともあるでしょうし、元気がなくなっているような人なら補中益気湯(ほちゅうえっきとう)を使うのもよいかもしれません。また当帰湯(とうきとう)などは今あげた、半夏厚朴湯、大建中湯、補中益気湯の意味合いを持つ生薬が含まれていますから、利用できると思います。いっぽうストレスを軽減してあげる方が良いのならそのような漢方薬も検討対象となるでしょう。
呑気症の人は、決して呑気(のんき)なわけではないという、少しややこしい話でしたが、いろいろな症状に漢方薬を利用することができる、ということを知っておいてほしいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
