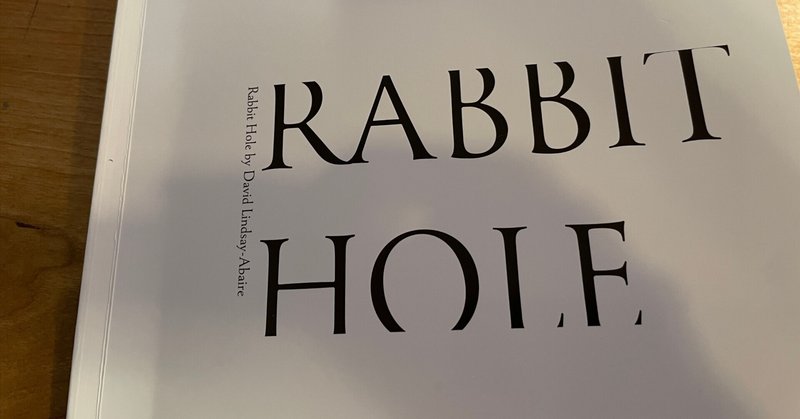
【劇評298】幼い子を亡くす。いつの世も変わらぬ痛みを掘り下げた『ラビット・ホール』。
幼い子供を事故で亡くした夫婦は、日常を取り戻すことはできるのか。
『ラビット・ホール』(デヴィッド・リンゼイ=アベアー作、小田島創志訳、藤田俊太郎演出)は、このおよそ不可能な問いに対して、微かではあるけれども、希望を語った。それは、この世界には出口がない、ただ断崖だけが待っている。そんな未来への絶望に捉えられている私たちへの力強い励ましとなった。
ニューヨーク郊外にある住宅街。瀟洒な家に住むベッカ(宮澤エマ)と妹のイジー(土井ケイト)の奇妙な会話からこの舞台は始まる。何か落ち着きがないベッカに、パンクなイジーがいたわりを見せる。イジーが妊娠したことを姉に告げると、空気が一変する。
夫ハウイー(成河)とベッカは、三歳の長男ダニーを事故で失っていたと、やがて明らかになる。ベッカとイジーの母ナット(シルビア・グラブ)もまた、かつて長男を失った。いたわりや慰めが、かえって傷口を広げる関係が周到な台詞で描かれていく。事故を起こした青年ジェイソン(阿部顕嵐、山﨑光のWキャスト。私は阿部の回を観た)の強引なまでの誠実さもまた、夫婦を別の次元に連れて行く結果となる。
藤田俊太郎は、これまでの演出作品の特徴であった映像の挿入をほぼ、控えている。そのため俳優の微細な表現がよく見えてくる。
年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

