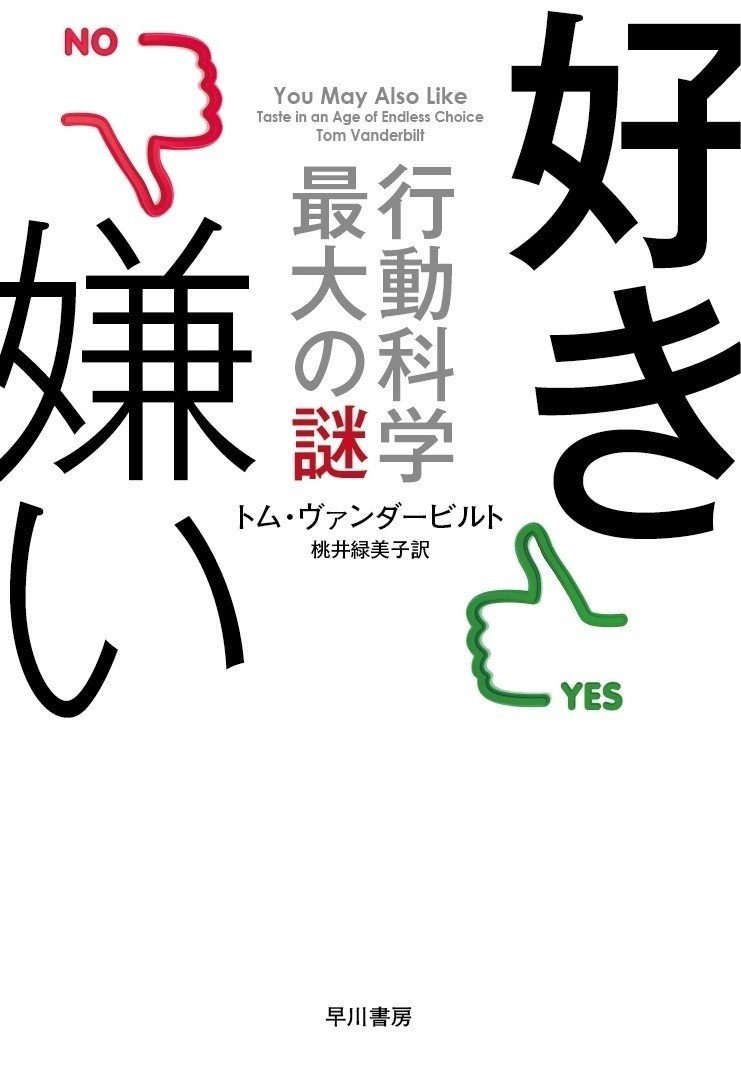あなたはトイレットペーパーの端は「ロールの手前」派、それとも「奥」派? 『好き嫌い―行動科学最大の謎―』抜粋掲載
色の好みからトイレットペーパーのセットの仕方まで、すべてにかかわるものの「好み」が気になるあなたには、「こちらもおすすめです」。『好き嫌い―行動科学最大の謎―』(桃井緑美子訳)の冒頭をお試しください。
はじめに 好きな色は何色?(そもそもなぜ好きな色があるのか)
そして友よ、君たちは私に、趣味や嗜好をめぐる論争はできないというのだね? だが、およそ人生とは、趣味や嗜好をめぐる争いではないか!
──フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラはかく語りき』
「パパは何色が好き?」
ある朝、学校まで歩いてゆく道すがら、五歳の娘がそう聞いてきた。娘は近ごろ「お気に入り」に凝っていて、私の好きなものを聞いては、自分のお気に入りを教えてくれる。
「青だよ」と、私はいかにも欧米男性らしく答えた(欧米では青が好まれ、男性は女性よりも青が好きだ)。
一瞬黙って、また聞く。「じゃあ、どうしてうちの車は青くないの?」
「それはね、パパは青が好きだけど、車は青じゃないのがいいんだ」
それなりに納得したのか、次に進む。「あたしが好きなのは、赤」。答えは変わっている。先週はピンクだった。そのうち緑も出てきそうだ。
「それで今日は赤いズボンなの?」
娘はニコっと笑った。「パパは赤いズボンもってる?」
「もってないよ」。私もスペインに住んでいたときは一着買ってはいていた。スペインの男たちの赤いズボンが目にとまったからだ。ニューヨークにもどってからは赤いズボンの男などほとんどいないので、買ったズボンは引き出しにしまったままだった。マドリードではあたりまえだったものが一九九一年ごろのアメリカでは、私には目立ちすぎに思えた。ただし、そういうことは娘には説明しない。
「パパも赤いズボンを買えばいいのに」
「そう?」
娘はうなずく。「パパの好きな数字はなに?」
これには答えに詰まった。「うーん、好きな数字ってあるかなあ」。それからこう答えた。「8かな」。私はそういいながら理由を探ろうとした。子供のころ、書くのが一番おもしろいと思っていたからだろうか。
「あたしはね、6」と娘。
「どうして?」
娘は眉間にしわを寄せ、肩をすくめた。「わかんない。ただ好きなだけ」
私たちは好きなものをなぜ好きなのだろうか。娘と私はたったこれだけの会話のなかで、好みの科学の重要な原則を少なくとも五つは提起していた。第一に、好みは分類で把握される。私は青が好きだが、青い車は好きではない(いったいなぜ?)。オレンジジュースが好きな人でも、オレンジジュースの入ったカクテルはきらいかもしれない。第二に、好みは状況に左右される。スペインではすてきだったズボンが、ニューヨークでは着映えがしなかった。旅先ではうきうきして買った旅行土産(エスパドリーユとか、カラフルな毛布とか)が、いまではクロゼットに放り込まれたままというのは誰にでも覚えがあるだろう。気温が上がってくると黒い車を買う人が減り、夏のあいだはプールつきの家を買う人が増える。第三に、好みはつくり上げられる。好きな数字を聞かれたとき、私はまず頭に数字が一つ浮かび、そのあとで考えられる理由を探った。第四に、好みは本来的に相対的なものである。まだ言葉を話せない赤ん坊でさえ、好みの違う人よりも好みの同じ人が好きなようだ。非常にうまく構成されたある実験では(見るのもたのしそうだ)、赤ん坊はまず二つの食べものから一つを選ばされた。次に二つのぬいぐるみがその二つの食べものを「好き」か「きらい」か表現してみせた。そしてぬいぐるみをあたえられると、幼い被験者たちは自分の好きなほうの食べものを「好んだ」ぬいぐるみに手を伸ばす傾向が見られた。ただし、親子の好みは頭にくるくらい一致しない。いくら親が教え込もうとしても、いくら遺伝物質を共有していても、子供は何事につけても親の好みと違うものを好きになる。
娘と私の会話は、趣味や好みに関して非常によく出くわす現実で幕を閉じた。好みは理由を説明するのがひどく難しいということだ。三世紀近く前、哲学者のエドマンド・バークは好みを初めて深く考察した著作でこう嘆いている。「この非常に微妙でとらえにくい心のはたらきは、定義という鎖で縛ろうとしてもすり抜けてしまい、どんなに確証しようとしても受けつけず、いかなる基準によっても規定できない」
なんとかして好みというものを理解しようとしている人々も、説明すべきものは何もないと結論したりもする。ノーベル賞受賞経済学者のジョージ・スティグラーとゲイリー・ベッカーは、「人々の重要な行動のうち、好みの違いがあると想定することで解明されたものはない」と主張して議論を呼んだ。どんな行動も──私の娘が6という数字が好きなことも──たんに個人の選好に帰すことができ、それがために選好は「あらゆるものを説明でき、したがって何一つ説明できない」のである。スティグラーとベッカーは、好みについて議論するのは、ロッキー山脈について議論するようなものだと述べている。「どちらもそこにあり、来年もあり、すべての人にとって同じままだ」
だが、ある経済学者が指摘するとおり、ロッキー山脈は変化している。変化の速度が遅いのでわからないだけだ。心理学者がしだいに神経科学のたすけを借りつつ繰り返し示しているとおり、好みは一回の実験中にも変わることがよくある。たとえば、ある音楽を流すとその食べものがいっそう好きになったり、作曲家に関する不健全な事実を知ると好きな気持ちがうすらいだりする。
私たちの好みは、影響力のあるノルウェーの政治理論家ヤン・エルスターが好んだ言葉でいうと、どこまでも「適応的」なようだ。食べたくてたまらないブドウの房に手がとどかないキツネがブドウはどうせ「すっぱい」のだと負け惜しみをいう、あのすっぱいブドウの寓話を引いて、エルスターはキツネはただ次の望ましい選択肢を選ぶのではなく──「合理的選択」の理論家はそういいそうだが──初めにもどってブドウを「格下げする」のだと指摘する。ブドウはすっぱくないし、キツネがブドウをほしい気持ちに変わりはない。好みは「反適応的」な場合もあるとエルスターは考えた。状況が違えば、キツネはブドウを手に入れられないためにブドウを食べたいという欲求が増すばかりだったかもしれないというのである。どちらの場合も、好みはそのときの制約によって形成されたわけだが、そこで疑問が浮かぶ。キツネは本当はブドウが好きなのか、そうでないのか。
経済学者は選択は好みを「示している」と考えるが、心理学者は逆に選択が好みを生むのではないかと考える。キツネがブドウとサクランボから「自由選択」でどちらかを選び、選んだもののほうが好きだといったとする。キツネは食べたいものを選んだのだろうか、それとも選ぶものを食べたいと思っているのだろうか。どちらも正しいだろう。「好み」そのものを探究しようとすることは、つかみどころのない作業だからだ。あなたはいま頭をかしげているかもしれない。「好み(テイスト)」というのは味覚のことか、それとも衣服などの好みのことか。あるいは「よい趣味をしている」というときの趣味のことだろうか。これらはみな微妙に関連しあっている。キツネは「ブドウの味」をたのしんだかもしれないが、ブドウをたのしめるのは自分だけだという感覚も好きだったかもしれない。
さしあたって、「好み(テイスト)」とは好きなものすべて(理由はなんであれ)だと考えていただきたい。とはいえ、すべきことは多い。まずは好みとはどういうものかを知らなくてはならない。その好みは誰のものか、その理由はどう説明できるのか、好みが違う人(ほかの変数はかなりの部分が共通する人)の違う理由はどこにあるのか。それらを考えたうえで、さらに好みはなぜ変わるのか、好みはなんのためにあるのか等々を解明していきたい。デザインライターのスティーヴン・ベイリーは白旗を掲げてこう述べている。「好みを学問的に解明しようとしても、それは難しいを通り越して不可能だ」。それでも私は説明できると思っている。なぜ、どのようにして、それを好きになるのか、言い換えれば、多くのもののなかからどれかを選ぶときに何が起こっているのか。それらを見極めること
はできる。
あなたの好きな数字はなんだろうか。大半の人と同じなら、答えは「7」だろう。7は色でいう青、これまた欧米で好まれる数字なのである。7と青は一九七〇年代の一連の研究で好きなものとして選ばれることが非常に多かったので、心理学者は二つに何か関連があるかのように「青7現象」を論じはじめた。青のことはここではおくとして、7はいったいなぜ好まれるのだろうか。
ほとんどの好みと同じで、文化的学習と心理的バイアスと精神的資質が絡みあい、そこに選択するときの状況が影響したもの、それがその答えである。7が好きな最も単純な理由は、文化的に人気が高いことが挙げられる。7は「ラッキーナンバー」だ。7が幸運な数字とされているのは、ある学者が述べているように「聖書やラビ文学に」目立って出てくる「とりわけ神聖な数字」だからだと考えられる。そしてたぶんそれは、情報をワーキングメモリに保持する私たちの能力が、情報数が「魔法の」7のときに低下するからだろう(だから電話番号は7桁になっているのだ)。
あるいは、ことによると7そのものに何かがあるのだろう。1から10までの数字のうち最初に頭に浮かぶのはどれかとたずねられると、7と答える人が最も多い(次に多いのは3)。一番「無作為」な感じがするものを選びたい、それならなんとなく「数学的」だから7にしようということかもしれない。その思考の過程は想像できる。「1か10? 単純すぎる。5? 5はど真ん中だ。2は? 偶数よりも奇数のほうが無作為な感じがするのでは? 0? 0は数字といえるか?」。素数の7はほかの数字とのつながりがなさそうで、だから無作為に見える。独立しているし、なんらかのパターンもない。ところが、7はこれだけの力がありながら、状況が変われば──6から22までの数にした場合──急に一番ではなくなる。それでもその影響力は健在で、今度は17が首位に躍り出る。
私たちは日々さまざまな場面で、あるものが別のものよりも好きな理由の判断を求められる。その曲がかかったときに、なぜラジオのチャンネルを変えたのか。フェイスブックのその投稿に「いいね」をつけて、もう一つの投稿にはしなかったのはなぜか。ダイエットコークではなくレモネードにしたのはなぜか。こうした選択は私たちが自分の世界を規定するささやかな日常的な方法で、それは「卵はどうやって食べるか。パンは精白粉のか全粒粉のか。ソーセージかベーコンか」というふうに朝食を「規定する」のと同じことだ。たいしたことではなさそうに思えるが、選択を誤ったときの不愉快さは目に見えている。その一方で、こうした選択がちょっとやそっとでは変えられないはっきりした好みに姿を変え、自分がどういう人間であるかを浮かび上がらせることにもなるかもしれない。「私はカントリーミュージックが大好きだ」、「私はフランス語の響きに憧れる」、「私はSF映画が好きではない」というように。
娘がお気に入りに凝っていた理由については、そのことを主題にした研究がわずかながら行なわれている。その科学文献の「好きな数字」に言及した希少な記述の一つに私がやや警戒しつつ着目したのは、それが強迫神経症に関連づけられていたからだった。「好きなもの」は理解しやすく獲得しやすい自分らしさのしるしとして、この世の中で自分を主張し、他者を理解する方法であり、また自分がほかの人々と似ていると同時に似ていないことを示す方法であることは、大理論がなくても想像に難くない。娘が私に新しい友だちの情報を伝えるときに、誕生日の次にくる最初の一つがその子のお気に入りの色であることは多くを物語っている。
人間は好みが風のように絶えず移り変わる状態をいずれ卒業し、心変わりなどしない確固とした好みをもつ理性ある人になるものだと考える人もいるかもしれない。だが、つねにそうとはかぎらない。たとえば私たちは、本質的にほかのものよりすぐれているわけではないものをまるで迷信に頼るかのように好むことも決して少なくはないのだ。
例を挙げよう。あなたは公衆トイレを利用するときに、使う個室に好みがあるだろうか。全部が空いているとして、端の個室がよいだろうか、それとも真ん中あたりの個室がよいだろうか。少なくとも「カリフォルニアの州立ビーチの公衆トイレ」で行なわれた研究によると(明らかに社会学の最先端からの報告だった)、人々は端よりも真ん中の個室を好んだ。理由はたずねられなかったが、数字を選ぶ場合と同じように、なんらかの理由があったと考えられる。最初の個室は入口に近すぎるし、一番奥の個室は遠すぎる気がするのかもしれない。だから真ん中が「ちょうどよい」。それが最良の選択かどうかは、何を基準に判断するかによる(細菌の数を測定した微生物学者によれば、最も好まれる真ん中の個室は皮肉にも最も不潔らしい)。
もう一つトイレの例で、トイレットペーパーをホルダーに取りつけるときに、紙の端を「手前に」下げるか「うしろに」下げるかは、機能的にはどちらがよいという強力な根拠はない。どちらかの取りつけ方で紙がうまく繰り出せなかったことがあるだろうか。どちらが好みでもたいした問題ではなさそうだが、人生相談のコラムニストのアン・ランダーズが、妊娠中絶や銃規制など、自分が取り組んできたどんな問題についてよりも寄せられた手紙の数が多かったと述べたことは有名だ。
この問題がここまで人の心をつかんで離さないのはおそらく、トイレのプライベートな性質がそうさせるのだろう。だが、執着の度の強くない好みもあり、心理学では「動機のない選好」と呼ばれている。これという理由のない好みである。ある研究はこれを「系統立った理学理論がまだ掃き集めていない実験の残滓」と表現している。この場合、目に見えず、おもてに表われない選択の規則、それによって選択せずして選択できるような規則があるのだろう。それでも大半の人が同じ選択に落ち着くというのは、どんなにでたらめに見える選択にもなんらかの根拠がある(したがって本当に動機がないわけではない)ことを暗に示している。
では、それはどこからくるのか。言語学には、一連の単語のなかでどれが最も英語の単語にありそうかをたずねる古典的な手法がある。たとえば「blick」か「bnick」なら、「blick」のほうがありそうだと推測するのに、単語ならべゲームのスクラブルが得意である必要はない。「bl」ではじまる英単語はあるが、「bn」ではじまる英単語はないからで、事情は単純だ。しかしマサチューセッツ工科大学の言語学者アダム・オルブライトは、どれも実際にはなさそうな単語ばかりのなかから──たとえば「bnick」「bdick」「bzick」──好きなものを選ばせたらどうなるかを問う。はっきりした根拠がなくても選択肢のなかから選ばなくてはならない場合(いわゆる「強制選択」の問い)、人はなぜ、どのようにその一つを選ぶのだろうか。その一つが「bnick」だったとして、それはなんとなく英語の単語に最も似ていそうだからだろうか(似てはいなくても)。あるいは「音韻バイアス」のせい、つまり単語を口にしたときに「頭子音連結」──「bnick」や「bzick」で二つの子音がつづいているのを言語学でこう呼ぶ──の響きが別のものよりもなんとなく好きだからだろうか。その答えは、学習したことともとからもっている好みとがいわく言い難く組みあわさった結果のようだ。好みの学習はふつう無意識になされるため、この二つを区別するのは困難なのである。
ここで話は青色にもどる。娘が好きな色を教えてくれてまもなく、私はカリフォルニア大学バークリー校の心理学教授スティーヴン・パーマーを訪ねた。パーマーは普段はパーマー研究室と簡単に呼ばれている視覚認知・美学研究所の所長である。パーマーの研究チームは好きな色を好む理由に関して、より説得力のある理論を打ち出している。
地下階の雑然としたパーマーのオフィスは、彼の模写したファン・ゴッホの『星月夜』が飾られているおかげで、殺風景な研究室の環境にも安らぎが感じられる。その部屋で腰を落ち着けるとまずパーマーは、美的感覚に関心をもつようになったのは趣味の写真撮影がはじまりだったと話してくれた(絵画の技巧について理解しようと参加した美術教室でその『星月夜』を描いた)。芸術がみなそうであるように、写真撮影にも一連の選好がある。何を撮影したいのか。どのアングルなら最もよい写真が撮れるのか。被写体はどこに配置するべきか。パーマーのように写真を志す者は、ふつうは有名な「三分割法」を用いるように教えられる。構図を決めるときに、画面を縦横それぞれ三等分に区切る線上のどこかに主対象を配置するという原則である。ところがパーマーが被験者に写真を好みによってランクづけしてもらったり、カメラをわたして最も満足できる写真を撮ってもらったりすると、被写体が構図の中央にあるものが圧倒的に好まれる。
ここでまた疑問が生じる。それではなぜ芸術家は人が好みそうにない構図にするよう教えられるのだろう? なぜ芸術家の好みは一般人の好みと一致しないのか。パーマーは美術と音楽を学ぶ学生に(対照群として心理学の学生も加えた)、「調和を好む傾向」に関する質問をした。学生たちはさまざまな作曲家の音楽を聴いたり、色の組みあわせを見たり、長方形のなかに配置された円を見たりして、どれが調和がとれているかをたずねられた。彼らの意見はおおよそ一致した(モーリス・ラヴェルは無調音楽の巨匠アルノルト・シェーンベルクよりも調和があると考えられた)。だが、美術と音楽の学生が好むものは、彼らが調和があると考えるものからそれていったのだ。
彼らはスノッブになりかけていただけなのだろうか。芸術の修練は調和への関心を失わせるのか、あるいは調和を好まない者が芸術家になるのか。パーマーにも確かなところはわかっていない。芸術を学ぶほど、芸術への関心を維持するために「より強い」刺激が必要になるということかもしれない。パーマーはこういった。「一つには、たんに過剰接触のようなことだと思います。同じものには誰でも飽きるでしょう。初めは重要なものを全体の中央に置く空間構成を試みても、そのうちに少し退屈になってきます。それに教師は新しさを奨励しますし、実際、構図の中央に被写体を置かないようにいったりします」
芸術家もそうでない人も、みな美に反応する。意識するしないにかかわらず、それが好きかきらいかを考えずにいられない。赤ん坊は生まれてしばらくは、自分を見ている顔を見るのがとても好きだ。それでは青色の何が多くの人を引きつけるのだろうか。先駆的な研究をしたジョゼフ・ジャストロウが一八九三年のシカゴ万国博覧会で大勢の来場者に色見本を手わたして質問をした心理学の黎明期から、青色が最も好まれているのである。
たんに青が色彩のスイートスポットである、ということなのだろうか。だが、もしも私たちが生まれながらに青が好きなら、乳児も青が好きだと考えてもおかしくない。ある実験で、パーマーは乳児(とりあえず「いつものぐずり」で失格にならなかった乳児)に一対の色の円を見せた。赤ん坊が円を「見ている時間」が好みの指標とされた。見ている時間が長いほど、それが好きだということだ(大人は乳児ほどはっきりした相関がない)。大人の被験者にも同じことをしてもらった。予想どおり、大人は青を見ている時間が最も長い傾向にあったが、乳児は青に対して明らかな好みを示さなかったばかりでなく、とくに「暗黄色」を好んだのである。この色は大人がふつうきらう色の一つだ(この茶色がかった黄系統の色をパーマーは研究のなかで「気持ち悪い色」と呼んでいる)。
どういうことなのだろう。パーマーと共同研究者のカレン・シュロスは、大人と乳児の両方の選好を説明する生態学的誘発理論という考え方を提唱している。私たちは最も好きなものの色を好むというものだ。実験の手順はうまく簡潔にまとめられていた。まず、被験者の一グループに三二色を好みにしたがってランクづけさせた。次に別のグループに、各色についてその色をしているものを二〇秒でできるだけ多く挙げさせた。最後のグループにはそれらのものがどの程度好きかをランクづけさせた。その結果、好きなものの色は八〇パーセントの割合で好きな色と一致した。最も好まれたのは予想どおり青だった。青から連想されるものを思い浮かべればわかる。たとえば澄みきった空、清らかな水。それらをきらいな人が──生きていくのにそれらを必要としない人が──いるだろうか。男性のワードローブに青いシャツとカーキ色のズボンが多いのは、大自然と何か関係があるのだろうか。ジャーナリストのピーター・カプランは、淡青色のワイシャツとベージュ色のズボンという彼の好みのスタイルについて、「浜辺の色だ。海が陸に出会う」と語っている。海辺がきらいな人がいるだろうか。
対照的に、パーマーの実験で不人気だった茶色がかった黄系統の色は、不快なものがぞろぞろと連想される。色の濃い粘液、嘔吐物、膿汁、一九七〇年代に流行ってすたれた乗用車のAMCペーサー。しかし、それならなぜ乳児は暗黄色が好きなのだろうか。
生態学的誘発理論のよいところは、色の好みは食べものの嗜好と同じで、進化的に脳に組み込まれている(私たちは自分にとってよいものを好む)と同時に、適応的な学習の機能をもつ(私たちは自分を心地よくさせるものを学習する)としていることである。結局のところ、乳児はまだ糞便のたぐいを嫌悪感と結びつけることを学習していない。おむつの交換台で奮闘している親なら誰でも立証できるだろう。進化論で考えれば、乳児が暗黄褐色系統の色を「好む」のは母親の乳首の色に似ていることに関係があって、最終的には背を向けたりきらいになったりする、などといった「それらしい説明もその気になればつけられますが」とパーマーはいった。
生態学的誘発理論はほかにもいろいろな方法で検証されている。パーマーの研究チームがカリフォルニア大学バークリー校とスタンフォード大学の学生に色について質問したところ、学生たちはライバル校のスクールカラーよりも自校のスクールカラーを好んでいるのがわかった。また、自分の大学を気に入っているほど、その色がより好きだった。パーマーからすれば、このことは色の好みは色そのものよりもその色から連想するもので決まる度合いが大きいことを示唆している。たまたま青と金色が好きだからという理由でバークリー校に行くとは考えにくい。赤い色の好ましいもの(イチゴやトマト)の画像を人に見せると、彼らの赤への好みは強まる。開いた傷口やかさぶたの写真を見せれば、赤が好きな気持ちはやや弱まる。大統領選挙の日に民主党支持者と共和党支持者に質問すると、選挙を目前にしてそれぞれの党の色である青と赤への好みがわずかに強まる。
色彩業界の人々と話せば、彼らは生態学的誘発理論にかなり似た一種の適応的な学習の話をするだろう。著名なカラーコンサルタントのリアトリス・アイズマン(彼女がヒューレット・パッカードに青緑色のコンピューターを発売するよう熱心に勧めたのは、アップルがあの革新的なアイマックを発売する数カ月前だった)は、シャトルーズグリーン(明るい黄緑色)――おしゃれな色とされる時期がときどきある──のような色は初めはきらわれるかもしれないが、しだいに見直されると指摘している。「私は周辺視野の色と呼んでいます」とアイズマンは私にいった。「おや、あそこにも黄緑、あそこにも黄緑。なるほど、そんなに悪い色じゃない。黄緑色のシャツも悪くはないな」。そう感じるころには、黄緑色がきらいだった理由は急にどこかへ消えてしまっている。ライフタイム・ブランズ(キッチンに白色でない調理器具をいち早く持ち込んだ企業)の取締役トム・ミラビルと話したときには、彼はこんな言い方をした。「充分に目にすると、目にしたいものだと思いはじめるんですよ」
どんな選択もつくり上げられるとするのは行き過ぎだと指摘し、消費財のようなものの好みは「備わっているもの」であって、抑圧された記憶のように埋もれていて解放されるのを待っていると考える人もいる。彼らの主張によると、私たちはアイフォーンの登場によってスマートフォンのメカニカルキーボードを(多くの人は好きだといっていたが)好きではないことに気づかされたという。だがその一方で、「生来の」好みとされるものの陰には、往々にして文化がひそんでいる。ピンク色は「本来」女の子の色だという考え方があるが、前世紀の初めには男の子の色とされていたという事実を知るとそれもあやしくなる。女の子がピンク色を好きなのはほかの女の子たちがピンク色の服を着ているのを見ているからだというのが、最も考えられそうな理由だ。というのも、いくつかの研究からわかったように、女性に「赤みの」色を好む傾向がやや強く見られても、そのことは、男の子の自転車にピンクはふさわしくないと思われたり、赤い女の子用自転車がめずらしかったりする理由にはほとんどならないし、それこそピンク色の女性向け大人用自転車をめったに見かけない理由にもならないからだ。
こうして一種のフィードバックループがはじまる。ある色を見る機会が多いほど、またその機会がよい出来事に関連するほど(女の子の誕生会のピンク色のケーキとか男性の紫色のシャツとか)、その色がいっそう好きになるだろう。そしてその色が好きになるほど、ほかの機会にその色に一役買ってもらうようになるだろう。赤のフェラーリはかっこいいから、ミキサーも赤くていいよね、という具合に。パーマーはこう述べる。「私たちは自分の好きなものときらいなものに関連する色のデータを蓄積しながら暮らしています。そのデータを絶えず更新しているといってよい」。私の娘がお気に入りの色を絶えず見直しているように、私たちは「その場その場で経験を差し引きして好きな色を決めているのです」とパーマーはいう。好きな色とは、それまでに心地よく感じたすべてのものの色彩記録のようなものなのだ。
数年前のある日、私はふと気づいた。いつもと同じ一日に、どれほど頻繁に好ききらいをたずねられ(自問もし)、どれほど答えが曖昧なことか。具体的にいうと、
「その映画、見たよ」「おもしろかった?」「ああ、まあね」
あるいは、
「あの新しいタイ料理店に行ったよ」「おいしかった?」「おいしかったけど、期待してたほどじゃなかった」
そして、判で押したように、
「ご意見を参考にさせていただきます。あなたのお考えを1から5の五段階でお答えください(1は非常にきらい、5は非常に好き)」
これらは本当はどういうことなのだろう? 気持ちのよい経験、愉快な経験は何段階あるのだろうか──五段階で充分なのだろうか。私がインスタグラムの投稿に「いいね」をつけたとして、それはどういう意味だろう? 画像の内容が気に入ったのか、写真の撮り方か、あるいは投稿した人に好感をもったのか。私はほかの人の「いいね」の数につられなかっただろうか。もし「いいね」をつけなければ、気に入らないといっているに等しいのか。神経インパルスが脳から親指に伝わるときに、私は自分の頭のなかで何が起こっているのかに気づいていただろうか。インスタグラムの写真に顔が写っているだけで、その写真を好ましく思う気持ちが約三〇パーセント高くなることが研究によって示されている(年配でも若者でも、男性でも女性でも、一人でも一〇人でも関係なく、ただ顔ならよい)。このことは私が「いいね」をつけようと決めたときに意識されていただろうか。
好ききらいを判断すべきものは増える一方だが、判断をたすけてくれる大原則や基準は少ない。私たちはインターネットで大量の他人の意見を見てまわるが──イェルプの星四つのレビューやユーチューブのサムズダウン──注目に値する意見はどれだろう? 世界中のほぼどんな曲も聴くことができる現在、どれを聴くか、それを気に入ったか気に入らないかを私たちはどうやって決めているのだろうか。世の中は逆さまになった。以前はめったに手に入らなかった食べものやファッションがあたりまえのものになる一方で、あたりまえだったものが目利きや通の評価するものに昇格している。「まったくけっこう」なことだとしても、どこかに不都合はないだろうか。
快楽と美にものすごい速さで反応している私たちがふだん考えているひまなどなさそうなことを、ここで問いたい。好きときらいは同じものの裏表なのか、それとも別のものなのか。以前はきらいだったものをどのようにして好きになるのか。好みは数値で表わせるのか。専門家と素人の好みはなぜこうもたびたび食い違うのか。好きなつもりでいるものは、絶対に好きなもののかわりになるか。私たちは好きなものを知るのか、それとも知っているものが好きなのか。
二〇〇〇年にイタリアの神経科学者のチームが、前頭側頭型認知症の高齢の男性に関するめずらしい事例を報告した。その男性は、以前は「ただの騒音」だとけなしていたイタリアのポップミュージックが突然好きになった(以前はおもにクラシックが好きだった)。以前の好みを「忘れた」わけではなさそうだった。たとえばアルツハイマー型認知症の患者は、ほかの記憶がうすれていっても美的なものへの好みは残るらしいからである。それよりも治療が神経系に影響をおよぼして、男性のなかで新しいものへの欲求が目覚めたのかもしれないと研究者らは考えている。
このように好みが急にがらりと変わるとなると、たくさんの疑問が頭に浮かんでくる。好みはたびたび変わるものなのだろうか。きらいだったものがきらいでなくなったとき、つまり「ただの騒音」が本当はたのしい音楽かもしれないと判断したとき、脳内では何が起こっているのか。神経の構築のされ方によって、新しいものを受け入れやすかったり、ピッチとリズムの特定の組みあわせを好きになりやすかったりする人がいるのだろうか。
この男性の状態の変化が彼のなかに眠っていた──だが抑圧されていた──ポップミュージックへの好みを解放したのだとしよう。それはどうも考えにくいことだ。しかし、私たちは自分自身の好みをどれだけ知っているだろう? 山ほどの趣味や嗜好や傾向をどれだけわかっているだろう?
ドイツの見本市で行なわれた実験では、来場者に二種類のケチャップを味見してもらった。どちらもクラフトの同じケチャップだったが、片方にはバニリン(バニラビーンズのフレーバーの主成分である化合物)が少量加えられていた。なぜこうしたかというと、ドイツでは乳児用の粉ミルクはふつう少量のバニリンが入っているからである。食べものの嗜好についての質問表には、ミルクと母乳のどちらで育ったかをたずねる質問が紛れ込んでいた。母乳で育った人は「自然の」ケチャップのほうを好む人が圧倒的に多かったが、ミルクで育った人はバニリンが入ったほうを好む人が多かった。彼らはこれらの事実を結びあわせて解答したわけではない。ただ好きなものが好きなだけだった。
よく「好みは説明がつかない」とか「蓼食う虫も好き好き」といわれる。あなたも首をふりながらそういったことがあるだろう。だいたいは他人の趣味や嗜好に呆れたときにいう言葉だ。自分の好みが自分でも説明できないという意味でいうことはめったにない。なにしろ自分の好きなものなのだから、明々白々ではないか。ところが、好みに関する実験をすると、その結果に本人が驚き、動揺さえすることがある。フランスの社会学者クローディア・フリッツは、ストラディバリウスなどむかしのイタリアの名工が製作したバイオリンに関するプロのバイオリニストの好みをさまざまな環境で調べている。そのようなバイオリンがいまは失われたむかしの不思議な魅力を備えているかのように美しくゆたかな音を響かせるにちがいないとは、タクシーの後部座席に非常に高価なバイオリンが置き忘れられていたというニュースを通じてだけにしろ、誰もが考えることだ。ましてやバイオリニストなら、そんな名器を弾きたいと思わないわけがない、と。ところがフリッツがこれまでに調べたプロ演奏家は、楽器が見えない実験環境で選ばされると新作のバイオリンの音色のほうを好む者が多かったのである。
ティモシー・ウィルソンは著書『自分を知り、自分を変える──適応的無意識の心理学』で、私たちは自分の物事に対する反応の理由を知らない場合が多いと主張している。そのような行動の多くは、彼が「適応的無意識」と呼ぶ状態で起こっているという。ところが私たちはいわば自己確信の錯覚に陥っていて、自分の感情の理由は何にせよ自分の感情なのだからわかっていると思い込んでいる。ウィルソンの挙げた例にならっておたずねしよう。あなたは本書の表紙をどう思うだろうか。好きだろうか。もし二種類の表紙から選べるとしたら──読者が選べることはめったにないが──どちらを選んだだろう? それを選んだ理由を考えてみただろうか。あるいは好きかどうかなど、いま問われて初めて考えただろうか。では、知らない人がこの表紙をどう思うかを想像してみてほしい。それはなぜだろう? この表紙が何か特別にあなたの心に訴える──好きだった別の本を思い出すとか、あなたがグラフィックデザインの学生だとか──のでなければ、いま思いついた理由(たとえば目にとまりやすいとか、色の感じがよいとか)はこの表紙へのあなた自身の反応の理由とあまり違わないプロセスで生じたにちがいないだろう。いろいろなことが推測できると思う。
要するに、私たちは自分の好みのことを何もわかっていない。そろそろ知ってもよいころだ。「すべての好みの原型」である食べものからはじめるのがよいのは当然だろう。
『好き嫌い―行動科学最大の謎―』(トム・ヴァンダービルト、桃井緑美子訳、46判並製、定価2100円)は早川書房より刊行中。