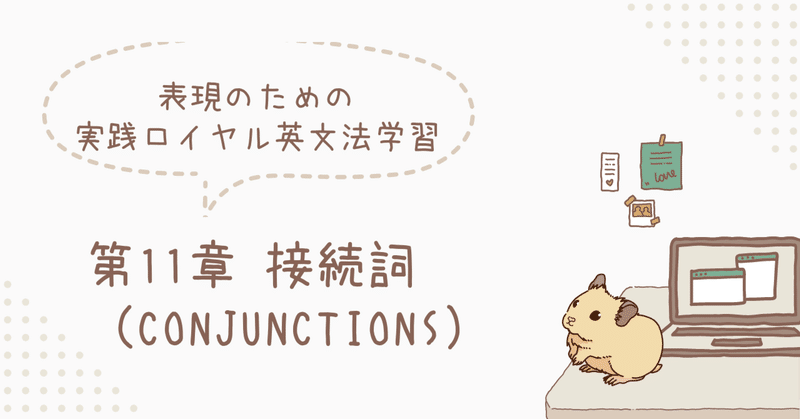
【表現のための実践ロイヤル英文法学習】第11章 接続詞(CONJUNCTIONS)
この記事は、ランサーズが運用する新しい働き方LAB内で立ち上がった、英語学習コミュニティにおける学習記録です。
主宰の堂本さんの指定文法書「表現のための実践ロイヤル英文法」をもとに、毎週1章ずつ学習を進めていきます。
例文は主に別冊の「英作文のための暗記用例文」に記載の文章と、確認・実践問題から引用します。
接続詞=語と語、句と句や節と節などを結びつける語
等位接続詞
文法上対等の関係にある語と語、句と句、節と節を結びつけるもの
145.I read the book / and found it very humorous.(私は読んだ、その本を/そして見つけた、とてもユーモラスなこと⇒その本を読んで見たが、とてもユーモラスだった)
※「〜したが」という日本語をみると逆接のbutを使いたくなるが、「読んでみたら(その結果)〜だった」という意味でandを使う
147.One more click, / and you'll get the details.(もう一度クリックすれば/あなたは手に入れるだろう、詳細を⇒もう一度クリックすれば、詳細が表示されます)
※Click once more,and you'll get the details.やIf you click one more time,you'll get the details.などにしてよい
148.The noise grew louder and louder.(その音はだんだん大きくなった)
※連続や多様さを表し、意味を強めるのに、同じ語をandで重ねて表現することができる。だんだん〜というときは「比較級+比較級」で表す
149.He doesn't like nor trust anyone.(彼はだれをも好きにならないし、信用もしない)
※「AもBも〜ない」というときには「neither A nor Bがふつうだが、前にneitherでなく、norの代わりにorでもよい。この文の場合もnorをorにしていい。norの次に節を続ける時は、主語と動詞は倒置する
150.Salmon can live / in both fresh and salt water.(サケは住むことができる/どちらも、淡水も海水も⇒サケは淡水でも海水でも生きられる)
※freshとsaltはどちらもwaterにかかる
146.He tried to climb the tree, / but failed.(彼は挑戦した、その木を登ることを/だが失敗した⇒彼はその木に登ろうとしたが、失敗した)
※その木に登ろうとした結果「しかし失敗した」というのだから、これはbutになる
151.Buy it, / or you'll be sorry.(買いなさい、さもないと後悔しますよ)
※命令文+or…は「〜しなさい、さもないと」の意味になる
接続副詞
本来副詞だが、意味嬢明らかに接続詞的に機能している言葉。
文や後続する節の先頭や中間、あるいは末尾に置ける。ただし、soやyetなどのように、先頭の位置に限られるものもある
152.I don't feel like douing this ; besaides, I am very tired.(私はこれをやる気はないし、それにとても疲れている)
※「その上」はbesidesとsがつくのに注意。このように等位接続詞を使わずにbesidesなどを用いるときにはセミコロンを書く
従位接続詞
「〜だから…」「〜したときに…」「もし〜したら…」の…の部分(主節)に、〜の部分(従位節)を結びつける
153.It doesn't matter / that he is Japanese.(それは問題ではない/彼=日本人であること⇒彼が日本人であるということは問題ではない)
※That he is Japanese doesn't matter.でもいいが、It~that…の形のほうが多い
154.I think / (that) this limitation is too restrictive.(私は思う/この制限は厳しすぎる⇒私はこの制限は厳しすぎると思う)
※会話の場合、thatは普通省略する
155.I hope (that) / you find the enclosed information to be useful.(私は望む/あなたが見つけた同封の情報が役に立つ⇒同封のお知らせがお役に立つとよいのですが)
※hopeに続くthat節中の動詞は未来形にしないことが多い
156.Whether the two incidents are related is unknown.(2つの出来事=関係されるかどうか=わからない⇒2つの出来事が関係あるかどうかはわからない)
※It is unknown whether…としてもよい。It is〜の形ならwhetherの代わりにifを使えるが、文頭にwhetherを出すとifは使えない
157.He worried (that) / she might tell someone / what had happened.(彼は心配した/彼女は話すかもしれない、誰かに/何が起きたかを⇒彼は、彼女がだれかに何が起きたかを話はしないかと心配していた)
※lest she(should)tell…とも言えるが、文語調になる
158.I was about to leave / when they started to argue again.(私は立ち去ろうとした/その時、彼らは始めた、議論を再び⇒私が立ち去ろうとした時、彼らはまた議論をし始めた)
※be about to~when…という語順に注意
159.We got there / before it started raining.(私達は着いた、そこに/降り始める前に⇒私達は雨が降り出す前にそこに着いた)
※beforeで時の前後関係がわかるから、過去完了を用いなくていい
160.Order now / before you forget.(注文しなさい、今/忘れる前に⇒忘れないうちに今注文しなさい)
※「〜しないうちに」に引っ張られて、notを入れない
161.Ten years have passed / since he won the Nobel Peace Prize.(10年が過ぎた/彼がノーベル平和賞と受賞してから⇒彼がノーベル平和賞を受賞してから10年になる)
※It has been ten years since he won the Nobel Peace Prize.としてもよい
162.As soon as I get home, / I'll send it to you.(家に着いたらすぐに/私はそれを送ります、あなたに⇒家に着いたらすぐにそれをお送りします)
※「〜するとすぐに」はas soon as~を使うのが無難
163.Since he is so busy, / he doesn't have time to eat breakfast most mornings.(彼はすごく忙しかったので/彼はない、朝、ほとんど朝食を食べる時間が⇒彼はすごく忙しくて、朝はほとんど食事をする暇がない)
※聞き手もわかっているだろうと思われる理由はsinceやasを使って前に出す。asよりsinceのほうが多い。理由を特に新しい情報として意識しているときにはbecauseを使って後ろに置くことが多い
164.I'll give you my e-mail address / so (that) you can easily contact me.(私はあなたに、Eメールアドレスを教えましょう/あなたが簡単に私と連絡がとれるために⇒容易に連絡が取れるように、私のEメールアドレスを教えておきましょう)
※so that A can…のthatは省略することが多い
165.I'll take an umbrella / in case it rains.(私は傘を持っていくつもりです/雨が降る場合に備えて⇒雨が降るかもしれないので、傘を持っていきます)
※「〜する場合に備えて」の意味ではin caseを用いる
166.The explosion was so small / that no one even noticed it.(その爆発はあまりに小さかったので/ 誰も気づかなかった⇒爆発はあまりにも小さくて、だれ一人気づきもしなかった)
※「あまり〜なので…」にはso~that…の構文を用いる
167.Unless you check this box, / you will not be allowed to proceed.(あなたがこのボックスをチェックしない限り/あなたは先に進めない⇒このボックスをチェックしなければ先へ進めません)
※「〜しない限り」という意味があればunlessが使える
168.It is a useful guide, / even if it is somewhat out of date.(これは役に立つ案内書だ/たとえ時代遅れだとしても⇒たとえ時代遅れだとしても、それは役に立つ案内書だ)
※evenを使わない、ただのifにもこうした用法があるが、even ifにすることによって「たとえ〜だとしても」の意味が強まる。guideだけで「案内書」の意味がある
169.Any paper will do / as long as it is acid free.(どんな紙でも結構です/中性紙である限り⇒中性紙でさえあれば、どんな紙でも結構です)
※「〜である限り」はas long asを使う。Any A will doで「どんなAでも結構です」という言い方になる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
